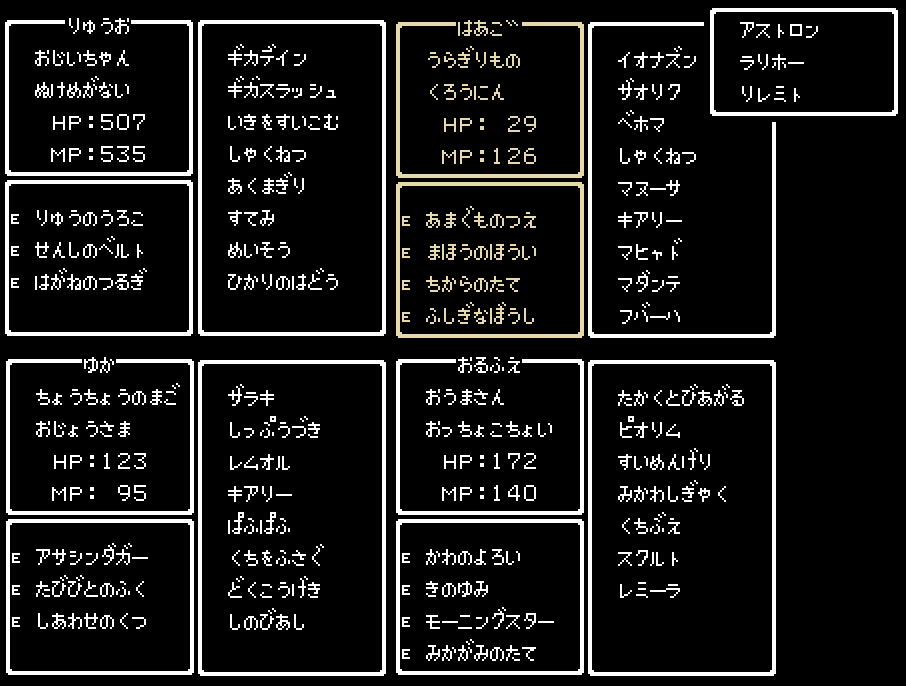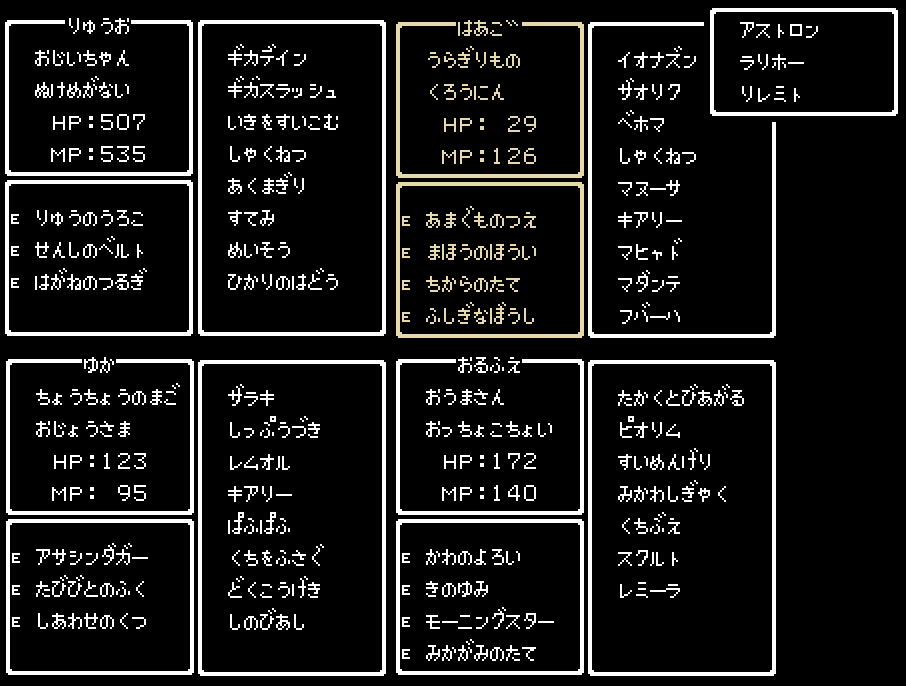第VI章 アレフガルド 〜Return of the troublemakers〜
「おお ****!すべてはふるいいいつたえのままであった!
すなわち そなたこそは ゆうしゃロトの ちをひくもの!
そなたこそ このせかいをおさめるに ふさわしい おかたなのじゃ!
わしにかわって このせかいを おさめてくれるな?」
しかし ****は いいました。
「いいえ。わたしの おさめるくにが あるなら それは わたしじしんでさがしたいのです」
――――――――――――――ドラゴンクエストⅠ(ファミリーコンピューター版) エンディング〜
死者の塔最上階の一室で、巨怪な異形の神像に向かって静かに祈りを捧げる一人の男。
蒼白い肌、痩せた体躯。竜のそれに似た、横に拡がる皮膜を伴った耳。色鮮やかな異教の法衣を身にまとい、唇から紡ぎ出される古代語の祈祷には、第三者の侵入による如何なる乱れもない。
祈念の言葉が止み、伏せられた瞼から、金の瞳が僅かに覗いた。
「誰ぞ、我が祈りを妨げし者は……」
誰、と口にはしたが、男には解っていた。
彼等は、聖地を血で穢しに来た者達。
彼等は、世界を救うと称して、世界を腐らせた連中に荷担する者達。
偽りの勇者。
一度は、己の弱さ故に要らぬ情けをかけ、故に却って傷付け、要らぬ苦しみを与えてしまった。
だから。
再び過ちは繰り返すまい。
「愚か者め。私を大神官ハーゴンと知っての行いか?」
世界を守る為に。
世界を救う為に。
双方の肩に世界の命運を賭けた戦いが、今火蓋を切って落とされた。
勇者達が身構える前に、神官の口から、短い、しかし力強い呪句が迸る。彼の姿は背景に溶け込むように揺らぐと、そのまま煙の如く拡散する。大気に融けたかと思われた彼の幻は幾つもの元の姿となって現れると、勇者達に向かってすかさず呪文を唱え始めた。ローレシアの王子がそのうちの一体に切り付けるが、刃は空を切り何の手応えも残さない。言霊は呪力となって三人を焼き尽くさんと襲いかかり、極限まで圧縮された爆炎が解き放たれて3人を包み込み吹き飛ばした。並の生き物であれば、瞬時にして灰さえ残さず焼き尽くされたであろう。
「これはまやかしなんだ! くそ、本体はどいつなんだ…」
男には時間が無かった。その体は病に蝕まれ、異界への門を開く呪法は未だ完成していない。ましてや、此処で己が凶刃に斃るる事あらば、我らの『想い』が無に帰してしまう。彼と、その想いを信じ従ってくれたが故に犠牲となった多くの部下の為にも、敗北は人の上に立つ者として許されざる結末であった。
時間が必要だ、そして…
我が身は滅びの神に魂までも捧げし身。命など、今更何が惜しかろう。元々病弱に生まれついたお陰で死は常に身近にあり、死への覚悟は既に幼き頃より否応なしに植え付けられて来た。生への執着などとうの昔に捨ててしまっていた。せめて術の完成までの間で良い。どうか、どうか、我がまやかしの術甚だ稚拙なれど、汝の加護にて彼らに我が幻術を見破られしその時を遅らせたまえ。世界の為に、どうか…
世界を滅ぼそうなどと大それた望みを抱く者にしては、あまりにもささやかな、願いであった。
突如、胸を締め付けられる苦しみが、抑え難く男を襲った。肉体を蝕んで来た胸の病が、今となって発作となり彼を苛んだのだ。黒ずんだ血が口から、口元を押さえる骨ばんだ手から溢れ出て、聖なる祈りの場を汚す。
「幻が消えたわ!」ムーンブルクの王女が叫ぶ。
男は問うた。自らに、そして神に。
「……血?」サマルトリアの王子が床に伝う血を見付けて、指で拭う。流れる血に、一同の視線が注がれる。
私如きの祈りでは、貴方の慈悲は我が身には届かないのですか、と。
「僕らの目を欺く事は出来ても、流れる血を誤魔化す事は出来無いぜ!」集中が途切れて、血を吐いて蹲る男の痩躯が徐々に浮かび上がった。その姿を見付けて、ローレシアの王子が稲妻まといし破邪の魔剣を振りかぶって駆け寄る。
私の信仰が足りなかったせいなのですか? それとも…。
視界の端に、彼を見付けた勇者達の姿が映り込んでも、避ける事も無く異教の法衣を刃が貫いたその時もなお、彼は神に、己自身に問い続けていた。
その身を床に這い蹲らせ、地を舐めてもなお問い続けていた男の脳裏に、或る思考が侵入した。
「この場に及んでなお慈悲を乞い、己の生を望むとは笑止なり。汝自身を捧げよ」
彼の想いが刹那、揺すぶられた。己が内よりの問いに、思い当たる所があった様に思えたのだ。
正しき世の理が妨げられんとするこの際にさえ、私は保身を図っているのではないか? 本来ならば、上に立つ者こそが真っ先に己を捨てるべきだったのではなかったか? いや、死は別に、今更恐ろしくはない。
ならば、最初から、こうするべきであったのだ。我が身を贄と捧ぐ事によって皆の想いが叶うのならば、何を躊躇う事があろうか?
薄れ行く意識の中で、男は最期の意思を振り絞った。
滅び行く世界の浄化と再生の為、この魂を捧げる事に如何なる躊躇があろう? 真に遠ざけねばならぬのは、仮初めの死よりも腐敗と堕落。腐り切ったこの世は滅ぼさねばならぬ、そして、必然の時は今まさにこの時より他に無い、と。
滅び行く肉体が、この想いすらも支えられなくなる前に。
破壊の神よ、我が祈りの言葉聞き届け給え!
滅び行く世界の破壊と再生の為に!
新たなる世界の礎となる為に!
「我が破壊の神シドーよ、今ここに生け贄を捧ぐ!」
若者の手の中で、彼の心臓が脈打った。
顕在意識の揺らぎが彼を覆い、慈悲深き脳内麻薬物質が彼を自らの心臓を抉り出す苦痛から救った。抉り出された心臓がなお脈打つ様に戦く勇者達が視界の端から消え、心臓から淡い霞のような気が、宙の一点に吸い込まれて行く。そこだけが盲いたか如き「点」は急激に範囲を拡大し、自らの命を神に捧げた男に気を取られていた勇者達は、辺りの空間の変化に気付いて愕然とした。
「しまった!」
サマルトリアの王子の叫びも、もはや彼の者の耳には届いていなかった。塔は重力の歪みによって震え出し、破片が雨霰と降り注ぐ。その埃すらも、もはや点とは呼べぬまでに拡大した点−異界への門−に吸い込まれ、不可視の神に形を与えた。
「我…は、滅びの神………破壊神…シ…ドー………」
気の揺らぎが形を取って、余命幾許も無い若き神官の金の双眸に映し出された。それは、彼が、そして世界が待ち望んでいる筈の、滅びの神の姿であった。
「よくぞ…我…を甦らせてくれた…礼を…言おう…ぞ………」
神の姿が、また少し揺らいだ。揺らいで、拡散した「姿」が、再び緩やかに収斂して、見慣れぬシルエットを描き出す。陰影が纏う気の僅かな歪さに気付いて、男は顔を曇らせた。その「歪さ」は、世界を浄化する神が背負うにはあまりにも禍々しく、寧ろ、世界を絶望に包む闇の魔王にこそ相応しく想われた。彼が生まれる遥か昔に、勇者の手によって滅ぼされたと幼い頃枕元で語られていた、ごく遠い伝説の彼方の存在でしかなかった筈の。
「な、この様な…、汝如きを呼び出す為に、我は命を捧げたに非ず。去るが良い」
若き神官は戸惑いを飲み込んだ。世界を滅ぼす為、己自身は言うに及ばず、腹心の部下から無辜の民草に到るまでのあまたの命を捧げてまで招来したのは、絶対にこの様な存在であってはならない。破壊神召喚の為の儀式手法は何ヶ月もかけて練りに練り上げられ、その祭儀は寸分の間違いも無く執り行われた筈であった。
禍々しい影の姿が、また少し揺らぐ。頭の中に響く『声』は、急速に生命力を失って行く神官のそれとは対照的に、実に明瞭で生気に溢れていた。
「何を申すか。…おお、そうか、そうであったな。青人草は言うに及ばず、汝の様な賢者すらも知る由も無い故、詮無き事であったな。そう、この余こそが、汝が呼び覚ませし、世界を破滅に導く滅びの神。…だが、汝にもはや、何の関わりがあろう?」
「そんな…馬鹿な事…が……いいや、あ、ある筈が、あって良い筈が…ぐふっ!」
飲み下した筈の惑いを内臓ごと揺すぶられて、神官は吐血した。
「信じられぬか、…さもありなん。余をこの世界に呼び出す為に汝が捧げた贄の数、汝が重ねた罪の重さ、良心の痛みが、如何に苛烈にして深甚であったことか…無論、その事は汝自身が一番良く知っておろう? お陰で、随分と愉しませて貰うた」
神よ、男は問うた。
「絶望の涙こそが我が喉を潤し、破滅を迎える者の断末魔の叫びこそが我が魂を悦ばせるのだ。さあ、嘆くが良い、自らの過ちが招いた滅びの時を。そして、余を愉しませよ、汝の手が無辜の民草によって血塗るられる様を以て…」
神よ、神よ、何故貴男は私を見捨てたのですか?
脆弱な肉体を灼熱の冷気が駈け巡り、彼の肉体は、もはや自身のものではなくなった。
世界を憂えた若者の涙は、崩れ落ちた死者の塔の中に埋もれ、劫の雨に流されて、消えた。
「トンヌラ様、リムルダールのムツヘタ預言所から使者が参りました」
近衛兵の一人が、執務室にて作業をする、若い僧形の青年に呼び掛けた。青年は立ち上がると、衛兵に下がるよう申し付けてから執務室に使者を通させた。通常ならばこのような会見は謁見室で行なわれるべきものである事を思えば、使者の所用がただならぬものであろう事は容易に伺い知れた。
「で、本日はどのような」
「大変な事になりました」
「何事か」
「実は」遥かアレフガルドはリムルダールからの使者は、息を切らせて語った。
「勇者ロトとその一族…つまり陛下とその御先祖様の事ですな…が闇に葬った筈の、悪魔の化身竜王と、世界を滅ぼそうとしたあの悪魔神官ハーゴンとが、罪ある死者の世界ニヴルヘイムから脱走し、いくつもの世界を経てこの世界、アレフガルドに現れるとのお告げが」
「……ふうむ」トンヌラ、と呼ばれた青年は、使者に背を向けしばし黙り込んだ。
「解った。よろしい、この件に関しては、ラルス21世にはくれぐれも内密に」
「は、はあ……し、しかし」
使者が戸惑うのを見てか、僧形の若者は使者の耳元で囁いた。
「この件に関しては、こちらの方から王の耳にお入れする。心配せずともよい。ところで、そなたも疲れたであろう、しばし休むが良い。……ザキ!」
「有り難きお言……う、ぐっ!」
使者は死者となり、床に転がってそのまま動かなくなった。青年の僧帽から覗く角が、黄昏に照り映えていた。
「悪いねー、余計な事に疑問を抱くと長生きできないよ。……フフフ、こんな日がいつか来ると思ってたさ。さーて、二人に連絡取らなくちゃ。チャンス到来っ☆」
若者は改めて帽子を深く被り直す。衛兵を呼び付け死体を片付けさせると、謁見室に誰も通さないように言い含めて、扉の内側に鍵を掛けた。
「うちの妹もいーかげん、ヨメにやらんとね…はあ…」
「ね、マイラ温泉行こうぜ。竜王が生きてたら行くって約束じゃん!」
「温泉は懲り懲りです…」
「わはははは、パノンのダジャレでも思い出したか」
「うわあん、止めて下さいって! ホントに」
「パノンダジャレ百選、キングスライムはキングすら忌む。ちゃんちゃん」
「うわ、マヒャド斬り食らった位寒いギャグ。オルフェ、お前パノンに弟子入りしたらどうだ」
「あの…今日はあったかいですよ?」
「そういうユカのセリフが一番寒いな」
久々のアレフガルド。私の世界。何もかも全てが懐かしく、馴染み深い世界。そして、一度は滅ぼそうとした世界。再びこの地を踏む事があるとは思っても見なかった。
で、私達は今マイラの村名物の温泉に向かっている。その理由は冒頭のやりとりにあった通り。私は温泉というとどうしてもダジャレ芸人パノンの顔がちらついてダメなのだが、皆は温泉がいたく気に入ったらしく、当初の目的であるところの旅の扉探索をおっぽり出して温泉に浸かりに来ているという次第なのである。まあ、今回は優勝賞金の20000ゴールドとトトカルチョの賭け金で儲けた分が充分にあるので、よほどの贅沢をしない限りはゆっくりくつろげる程の余裕はある。
だが、私には一抹の不安があった。この世界はタイジュ国やグランバニアの様には魔物達と人々は共存していない。そして、決してこの世界の人々から私の名が忘れ去られる事はないだろう。
「温泉に行くのなら、私は待ってますよ」
「何だハーゴン、お前は行かないのか」
「流石に、あれから未だ8年しか経っていませんからね」
「まだ昔の事を気にしておるのか? 神経質に過ぎるぞ。そんなに心配ならマイラの町中に行かなければ良い。あの辺の山ならいくらでも温泉があるしな。これから行くところも山奥だから、その辺は気にしなくて良いぞ」竜王は何だそんな事かと言わんばかりにばしばし肩を叩く。
「はあ…」
「だいじょーぶだよハーゴンさん! 山ん中ならパノンも出て来ないからさ! ぎゃははっ!」オルフェは事情を知らない所為か、ノー天気に呵々大笑。
「わはははは、そりゃそうだな。よし、じゃあ行くか。な、待ってるなんて言わずに一緒に来い」
「わーい、温泉、温泉!」
「温泉…ですか。いいですね」
ユカにまで言われては逆らう道理もなく、結局、私は皆に押し切られ、半ば強引に温泉に付き合わされる羽目になってしまったのだった。
マイラの村を遥か下に望む山中に、温泉は紅葉を映し出し、溢れんばかりの湯を湛えていた。
「うわー! すっげー! めちゃめちゃ綺麗だぜー! それに、村中どころかグランバニ…もとい、アレフガルドだったよね…全部見渡せるじゃん!」
「だろう? こら、ユカ。温泉だからっていきなり脱ぎ出すな。ちっとは恥らえ」
言われてユークァルは脱いだ上着をもぞもぞと着出した。
「うう、寒いなー。それにしても外の世界ってこんな寒いんだなー」
「なんだ、前の世界には冬は無いのか」
「何だ冬って?」オルフェは剥き出しの腕を擦る手を止めて瞬きした。「それ、ウマい?」
「冗談じゃない、良いか、冬になったらもっともっと寒くなるんだぞ。そうしたら雪が降って来て、湖は凍るし辺りは真っ白になるんだ。何時までもそんな格好で居たら凍えて死ぬぞ」
「うわあ、大変だ。じゃ、オイラの服も買って」
「着れる服があればな。とっとと温泉に入るぞ。ん?」
「どうしたんですか?」
「いや、人の話し声がしたような…おお、いたいた」
我々が崖を下りて行くと、どうやら先客がいたらしく、恰幅のいい頭の禿げ上がった男といかつい男の二人組が温泉に浸かって呑気に鼻歌を歌っている。先客の面々は人っけのない露天風呂で紅葉狩りを決め込むつもりだったらしいが、我々が彼らに気付いたのと殆ど同時に我々を発見した。
「ギャーッ! でででで出たぁーっ!」
「出たんじゃないです、来たんです」
ユークァルが冷静に突っ込むが、オヤジ二人は無論聞いていない。二人組は見てはいけないものでも見たように…いや実際見ているのだが…口をパクパク目を白黒させている。その様子と来たら、さながら空気不足で喘ぐ金魚の様だ。その内湯の上で腹を出して引っ繰り返るんじゃ無かろうか。
「うひゃーっ! ああびっくらこいた。おっさん達、いきなりでかい声出すなよ」オルフェの声に振り向いた二人組は、その異形を見て余計に慌てふためいた。
「そ、そっちはばばばば化け物ー!」二人組はもう一度揃って叫んだ。バスとテナーの見事なハーモニーだ。
「化け物って何だよー。失礼だなあ。ねえハーゴンさん」
「ばっばか、それはまずい!」竜王はようやく事態を把握したのか、あわててオルフェの口を塞ぐ。
「や、やっぱり、あれは本当だったんだ!」
「冗談かと…」
「ん? 待て、貴様等。あの話とは一体?」だが怯え切った村人を相手に、まともな答えが返って来ると期待する方が無理というものだ。村人二人組の裸が更に二メートル後ろに下がる。
「お、お命ばかりはお助けを…わしたちゃ美味しくないで…なんまんだぶなんまんだぶ」
「待て、誰も取って食うとは…」
「ヒャ〜!」
「か、かあちゃん助けてーっ!」
ハゲ頭とがたいのいい男は、二人してすっぽんぽんのまま逃げ出してしまった。
結局、二人組が去っていく姿を、一同は温泉の事も忘れて見届けていたのだった。
「なんだ、驚かせおって…しかしまた、何でこんな山奥のへんぴな場所にまで人間が来る? 私が居た頃はこんな所にまで温泉に来る物好きはおらなんだぞ」竜王は二人組が姿を消した後も、その方向を瞬きしながら見つめ、合点が行かぬとばかりに首を傾げる。
「当たり前です! その頃は魔物が溢れていて、普通は危なくてこんな所まで来れませんよ」
「あ、そうであったのか!」
竜王は、さもありなんと言わんばかりに拳で掌を打った。私にはたまに、この人が狡猾なのかボケているのかどうも判別しかねる時がある。
「しかし何故顔が割れておったのか…お前はともかく何で私が……ん? あんな所に小屋があるぞ」
「あ、ホントだ。あの人達ここから温泉に入りに来たんだね」
私達が来た方からは木陰になって見えなかったが、崖の上には温泉を利用する人の為に小屋が立てられていた。村人が逃げて行った小屋の中を、遠慮無しに覗き込む。
「あーらら、あのおじさん達、服持ってかないで逃げちゃった。しーらないっと。あれ、何だこれ」オルフェは村人の服を漁ると、そこから折り畳んだハンカチ大の紙切れを取り出した。
その紙は、我々の人相書きを書き立てた、指名手配のポスターだった。御丁寧な事に賞金まで付いている。
「ありゃりゃ、こんなものが出回ってたんだ。ふうん、どうりで有名人な訳だ…わっ! おいちゃん返せよ!」
「おいちゃんと言うな!」竜王はオルフェが摘み上げたポスターを素早くひったくって、一瞥するなり私に向かってくしゃくしゃに丸めたポスターを放って寄越した。「何じゃこれは、全然似ておらんではないか。もっと良い男に描いてくれねば割に合わぬ!」
私は余りにおバカな反応に呆れかえった。この人の現状認識は一体何を基準にしてるんだ?
「あのねえ、この期に及んでまだそんな呑気な事を! そういう問題じゃないでしょう! これだけ人相書きが出回ってしまったら、何処の街や村にも寄れませんよ。食料の調達や情報収集はどうするんですか!」
「しかも、生死不問って書いてあるよ。ヤバいんじゃないの? これ」
「ふん、自分達が生死不問だろうが身の程知らず共め。奴ら、この私と戦って勝てる奴が居るとでも思っておるのか? しかも何じゃこれは、たったの20000ゴールドか私の首は? あん?」竜王はそう言って自分の首を手の平で叩く仕草をする。
「ばかっ! 賞金が高ければ人相書きが出回ってもいいんですかっ!」
「おいおい、顔をそこまで赤くして言う事でも無かろうよ。冗談に決まっておろうが。…うむ、しかし確かに弱ったな。人相書きが出回っていないのはユカとオルフェだけだが、この世界は他の世界と違って人と魔物が共存している世界ではないからな。かといってユカ一人でお使いに行かせる訳にはいかんし…」
「…どうしてダメなんですか?」
「うるさい、色々ダメなんだ」竜王は真顔で問うユークァルを、うざったそうに言い除ける。
「うっわー、すげー強引な言い方」
「じゃお前ならユカを行かすのか?」竜王は仕返しとばかりに今度は真顔でオルフェに問うた。
「う、ちょっとその件に関してはノーコメント」
「とにかく、困りましたね。これでは買い出しも出来無い」私は人相書き相手ににらめっこする。
「それにしても、いつの間に人相書きまで出回っちゃったのかなぁ。オレ達今この世界に来たばっかりなのにさ」訝しがるオルフェに、竜王はさも解りきった事の様に返した。
「この国のリムルダールという街にはな、ムツヘタ預言所という施設がある。おおかたそこで預言を聞いてきたんだろうよ。けっ、仕方あるまい。うちでも行くか」
「うちって?」
「私の城だ。今は廃墟だろうがな。来るか?」竜王はアレフガルドの内海に浮かぶ島にそびえる古城を指差した。
ラダトーム城を内海を挟んで正面に、かつては魔の島と呼ばれた島の切り立った崖に守られて、その城は立っていた。
尤も、人々に恐怖を与え続けたその面影も今は無く、主を失った館の例に漏れず朽ちた姿を曝している。とはいえ、この城にまつわる幾多の伝説が人足を遠ざけているのは疑い無く、それが証拠に未だ取り壊されもせず、ロザリーヒルの様に人の手が加えられた形跡も無い。
「うへぇ、こんな所に住んでたのかよ。すげえじゃん。針の城より断然すごいよ」
「当然だ」竜王は素っ気なく返す。
「どこにも階段が見当たりませんね」
「それはそうだ。侵入者を防ぐ為に、ゾーマの奴が階段を判らぬ様に隠蔽したのだ。おまけにそこから降りると中は迷宮になっていて、普通の人間なら到底玉座までは辿りつけんだろうな」
「じゃあ、我々はどこから出入りすればいいんですか?」
竜王は、黙って尖塔の一つを指差した。
朽ちかけた尖塔から見渡す海は半ば沈みかかった夕日に照らされ、波頭は晩秋の消えゆく太陽を惜しむかのように煌めいている。空に浮かぶ鱗雲は血の赤から青、紺青そして射干玉の闇色に溶けて行く。さっさと行ってしまった竜王を追って我々が息を継ぎ継ぎ尖塔の上に辿り着くと、竜王は水平線の彼方に僅かに残された光を双眸に湛え、水平線の彼方を独り見つめていた。声をかけ難く見守っていると、視線だけは水面から逸らさずに語り出す。
「ここはあの当時、孤独になれる数少ない場所だった。ここだけは、ちっとも変わらぬ。…独りになりたい時には、いつもここでこうして風に当たっておったものだ。苦しい時も、辛い時もあった。だが、弱音は吐けん。そういう時、ここに来て水平線の彼方を眺めていた。もっとも、あのころは太陽も星も無い、全くの闇だったがな」
「今は…?」
「今は…昼と夜の区別が付くだけ良しとしよう。…いかん、妙に感傷的になってしまうな」
海から吹く一陣の風が、冬支度の済んでいない私達には酷く堪えた。
「早く降りましょう」
「うむ。少し待っておれ、ええと…あったあった」
鉄製の扉の上方を探ると、蝶番の辺りのひび割れた煉瓦が丁度外れるようになっていて、中に隠されていた鍵束を引張り出す。その鍵で尖塔の扉を開けて梯子を下り、螺旋階段を辿ってその更に地下へと潜って行く。アレフガルドの地下深く広がる闇の迷宮は音一つ無い死の世界。明かり取りの窓さえも無い死の闇の中、我々の足音だけがこだまする。
「レミーラ」
オルフェが魔法の灯りを点した。死の世界が馴染みある、いつもの世界に変わる。魔法の光に照らされた迷宮が妙に小綺麗なのに私は気が付いた。これは、主の無い館の部屋ではない。
「もしかすると」
「何だ?」
「まるっきりの廃墟でもないみたいですよ。埃も積もっていませんし」
三つ目の角を曲がった先、広間の奥にある鉄製の両開きの扉に手をかけようとした時、扉が突然内側からゆっくりと開いた。
奥には更に広間が続いており、魔法の松明がか細い明かりを提供する。正面には玉座が設えられており、そこに座している城の主を一目見て、我々は唖然とした。
「何者じゃ」
玉座には、もし子供時代の竜王に会っていたら、きっとこんな感じに違いないという少年が腰掛けていた。というよりは寧ろ、玉座に乗せられていた。
「何時の間に、こんなに小さくなって…おいたわしや」
「待て待て、私は此処にいるぞ。…や、それは置いといて、誰じゃお前は? 何処のマネマネだ?」
「そなたこそ何者じゃ。勝手に我が住居に忍び入った上、余のひい爺様の姿を騙りおって。事と場合によっては許さぬぞ」
「ひい爺様?私がか?」
竜王の問いに、少年は無言で頷いた。
「も、もしや…貴男は竜王の子孫では?」
「そうじゃ。余は王の中の王、竜王のひ孫じゃ」
「そうだったのか……なあ、聞いても良いか? お前、何でこいつが私のひ孫だと解った?」
突っ込まれるには痛い処を突っ込まれ、私は言葉に詰まる。「う…ぐっ……ん、んなことはどうでもいいんですっ。ンな事言ってるとハゲますよ! それより貴男、いつの間にどこで子供作ってたんですかっ!」
「待て、ハゲる毛はないぞ。…何を人聞きの悪い。私にだって妻子の一つくらいおったわ」
「あれ? じゃルビス様は? ねえおいちゃん?」
「おいちゃんというなっ! あれはあれ、これはこれ。そうか、あれの子孫は生きておったのか…」
竜王は適当にオルフェのツッコミをかわすと、半ば感慨深げに、残り半分は愉快そうに自分の子孫を観察する。
「こっ、こら! 余を無視するでない! この無礼者っ!」
「無視はしてないぞ、無視は。なあ?」竜王は回りに同意を求めつつ気軽に近付いて行く。「ふふん、面白い。やいチビスケ、私がお前の正真正銘のひい爺さんだ」
「やっぱりおっさんじゃないかー。おっさんどころかじじいじゃん」
「ええうるさい、当て馬は黙っとれ」
「フン!」ひ孫は距離を詰める曾祖父を胡散臭げに睨め回す。「余のひい爺様は100年も前にロトの生まれ変わりの勇者とやらの手にかかって死んでおるわ。でたらめ申すでない」
「うっわー、強情そうなとことかひね曲がった所までそっくり!」
「こらオルフェ、誰がひね曲がっておるのだ誰が」竜王はオルフェのほっぺたをうにうにつねりあげる。「ところでチビ、もしも私が本物のお前のひい爺さんだとしたらどうするね」
「どうすると言われても…」ひ孫は言い澱んだ。「そんな事在る訳が無い」
「それがあるのだ」玉座に手を掛け、実に嬉しそうに身を乗り出す。「私が、お前の正真正銘のひい爺さんだ」
「やーいジジイ! …う、前言撤回」
オルフェは無言の威圧に負けて野次るのをやめた。
「信じられぬか?」竜王はあの魅入るような、しかし、血の通った優しさを笑みに滲ませて迫る。
「ひい爺様…もし、ほんに、ほんにそうならば…」ひ孫は突然現れた己の先祖を前に、もどかしげに、湧き上がって来た感情を溜め込んでは弄んでいた。が、少年は、これ以上押し込めておくのをやめ、意を決して、口を開いた。
「ひい爺様、余は…お恨み申し上げますぞ…」
「恨む、だと? 何故に私を恨む? 我が血を引くが為の、自らの不遇の故にか?」竜王は向けられた好意がすげなくはね除けられたのも大して気にしてはいないようだった。睨み返す気の強さが気に入ったらしく、気安げに手を伸ばす。
「く、来るな! 近付くなっ! 無礼者めがっ! 帰れっ! ここの今の主は余じゃ。これ以上近付くと、例えひい爺様とて容赦はせぬぞ!」
「こらチビスケ、どちらが無礼者だ? 年長者に対する口の利き方を教えてやろうか? ん?」
「そうだよ、ひい御爺様に対して『帰れ』だなんてさ。何だったら、僕は帰ってもいいよ」
聞き覚えのない第三者に割り込まれ、竜王の顔から気安さが消えた。緊迫が辺りを支配する。
「…出てこい、後にいる奴」
「これはどうも失敬。身内同士の事だったようなんで、遠慮した方がいいかな? と」
玉座の裏から、もう一つの影が音もなく現れた。その手には鍔に隼の姿を模した一振りの細身の剣が握られており、その切っ先は違う事無くひ孫の喉先に突き付けられていた。影の正体は我々に向かって一歩踏み込むと、辺り全ての者達を侮蔑する笑みを口元に浮かべたまま、切っ先の向きを変える事無く我々に対して一礼した。作法が完璧なだけに、余計に慇懃無礼、傲慢不遜である。
「久しぶりだね。いやァ、流石にキミらが根の国から脱出したと聞かされた時は驚いたけど」
「あ、貴男は、さ、サマルトリアの王子、トンヌラ!」
「と、トンヌラ? …何だそれは。もしかして、それがこ奴の名前なのか?」
「ええ」
オルフェと竜王は、顔を見合わせて二、三度瞬きした。
「ぷっ、ぎゃはははははは! なんだそりゃー!ダサダサじゃん! うひゃひゃひゃ、へ〜んな名前! パノンのギャグよりおかちー!」
「うぷぷぷ、貴様の名付親はグランバニアの国王か?」
「何かおかしな事でもあったんですか?」ユークァルだけが相変わらず真顔だ。
「う、わ、笑うなぁー! これでも気にしてるんだぞっ! 笑うとお前のひ孫がどうなっても知らないからなっ!」
トンヌラの過敏な反応に、一同はぴたっと黙りこくる。どうやら、トラウマど真ん中を突いてしまったらしい。
「オホン。と、とにかく。王子とは失礼だな、あれから8年経ってるんだぞ。僕はもう、父上から王位を受け継いだ立派な国王陛下なのさ」
影の正体は、誰あろう、8年前のサマルトリア王子、現サマルトリア国王トンヌラであった。
が、トンヌラは相手を間違えていた。並の人間ならともかく、かつては魔王と呼ばれた神の御子に自我を無くした殺人機械、序でにダジャレ好きのお気楽妖魔が相手では、人間の王族の権威などに気圧されよう筈もない。
「貴様が誰であろうとどうでも良い。が、うちのひ孫が関わってるとなれば話しは別だ。ぼうずを離せ」
「いやだなぁ、まるで僕を人攫いみたいに言わないでくれるかな。なあ? ボク達親友同士だし〜」
トンヌラは威圧にも動じず、切っ先を突き付けたまま親しげにひ孫の肩に手をやった。ひ孫は憮然としたまま頷く。刃を向けられて怯えている、と言った感じでは無さそうに見受けられる。
「チビスケ、どう言う事だ?」
ひ孫は返事をしなかった。
「言った通りの意味さ。な? 我々同じ高貴な血を引きし者同士、交流があってもおかしくないっしょ? あっそーだ! どう? せっかくだからさ、今日うちに遊びに来いよ。こんな穴ぐらに一人で篭っててもつまんないだろ? 明るい日差しの下、テラスでお茶しながらカードでもしようぜ。アインやマリアも待ってるし。な、いいだろ? …OK? よし、決定! っと…」トンヌラは切っ先を鞘に収めると、懐から金無垢の時計を取り出した。「おっと、もうこんな時間だ。僕らそろそろ城に帰らないと。執務もまだ一杯残してあるし。あ、保護者の皆様方、また会う事があったらヨロシク! 今日はうちにお泊まりだからさあ、待ってなくていーすよ。じゃ! リレミトッ!」
「ま、待って下さいっ!」
私は必死で二人を引き留めようとしたが、声をかけた時には既に城から一緒に脱出した後だった。
我々は、後に残された空位の玉座をただ呆然と見つめているしかなかった。
辺りに再び緊張が走った。袋に入った何かが、床にぶちまけられた鈍い、音。第三の気配。
振り返れば、そこには買物袋を落とした老リカントが口あんぐりで突っ立っていた。
「坊ちゃんは、坊ちゃんは? ………! 旦那様じゃございませんか!」
「おお、リカルドではないか! 貴様まだ生きておったのか!」
「旦那様ぁっ! よくぞ御無事で! お亡くなりあそばしたのではなかったのですか?」
「えーと…あの、あなた、彼を御存じなので?」目の前で繰り広げられているらしい感動的な再開劇に、私達は完全に乗り遅れていた。唯解る事と言ったら、二人が知り合い同士、らしい、というくらいで。
「御存じも何も、生きていた時は妻の世話を任せていた。前の世では唯一、全面的に信頼を置いていた。そうか、生きておったか…細君は元気か?」
「旦那様ああ…よよよ…お帰りあそばしたんで御座いますね。どうやって黄泉の国よりお帰りになられたので御座いますか?」
「色々あって、逃げ出して来た。何だ、貴様は知らんのか。アレフガルド中そこら辺に我らの賞金付き人相書きが出回っておるらしいぞ」竜王は先程自らくしゃくしゃに丸めた人相書きを、リカルドに放って投げる。人相書きを一別するなり、老リカントは目を丸くしてひっくり返らんばかりであった。
「ひゃあ! 何と言うことでございましょう! 全く存じ上げませんでしたで御座いますよ! …それより、坊ちゃんは?」
「ああ、チビか。ええと、サマルトリアとか言う国の…ええい、何と言っておったかな。トンカチとかトンチキとか」
「トンヌラです」また間違えていたので訂正しておく。ひょっとすると、竜王はいちいち私にツッコミをいれて欲しくてわざとボケているのではなかろうか。
「おおトンヌラか。そ奴が遊びに行こうとか何とか言って連れて行ってしまったわ」
「ギャ〜! だ、旦那様あ! な、なんで止めてくださらなかったんですかっ!」リカルドが顔を強張らせて詰め寄ったので、さすがの竜王も一歩も二歩も腰が引ける。取りも直さずリカルドを両手で制する。
「まあまあ落ち着け、リカルド。何じゃ、トンヌラとやらは貴様がぼうずと遊ばせるのも厭う程の穀潰しなのか? 貴様のその口振りでは、あ奴らがしょっちゅう顔を出していたようだが?」
「穀潰しどころか、一国潰しの王ですよ!」ここまで言い切ってから、リカルドは慌てて周りを見回した。
「こんな事を聞かれたら、どんな事をされたもんか解ったもんじゃあ御座いませんですよ、旦那様。ああくわばらくわばら」
「もう来るものか。あ奴、あんなガキを連れて何をしようと言うのだ? 私を挑発するつもりか? フン、昨日今日会ったばかりの赤の他人も同然のガキを人質に取られたくらいで、奴らの挑発に応じてのこのこ計略にはまりに行く程お人好しでもないというに、随分と舐められたものだ」
リカルドの顔が、親に捨てられた子みたいに情けなく崩れていく。突然、老リカントは、主人にしがみついてベア・ハッグを噛ませた!
「坊ちゃんを助けて下さらないんですかぁ! いくら何でもそりゃあんまりですよ! このリカルド、竜王様の為ならばと身を粉にして百年以上もお仕えしてきたというのに、この仕打ちがこれですか! よよよ…見損ないましたぞ!」
「こらっ! な、泣くな! 泣くなと言うておろうが! …あー、解った解った。だから泣くなって。うちのチビは必ず助けてやるから。こらっ、人の袖口で涙を拭くなっ!」流石の竜王も、昨日今日の身内には冷たくとも、百年も献身的に仕えて来た僕を見捨てる程冷酷ではなかったようだ。
「ホントでございますね?」
竜王ははくどいくらい何度も頭を縦に振る。老リカントの目が鋭く光った。
「ああ良かった。これでお坊ちゃまから今月のお給金が戴けるというものです」
「リカルド……貴様という奴わぁぁぁぁっ!」
「ほ、ほんのじょ、冗談でございます…ギ、ギブアップギブアップ!」
竜王にスリーパーホールドをかけられて、リカルドは苦しそうに床をバシバシ叩いた。
最後にリカルドが床を思いっきり叩くと、丁度古城が地上から、不自然な振動を伝えた。
「これ、床を叩き過ぎだぞ」竜王は愉快そうに笑うが、手を叩くのを止めたところで揺れは収まりそうになかった。
「ち、違いますで御座いますよ旦那様。私が叩いたくらいでお城が揺れたら、この城はもう百回くらいは崩れておりますです」
「真面目に切り返すなリカルド。…しかし、今のは随分揺れたな」
「まだ、ちょっと揺れてます」ユークァルが言った途端、再び大きな揺れが城を襲った。
「じ、地震?!」
「違う、こいつは上からだ。う、わっ!」
天井から、土煙に交じって粗い石壁の欠片が落ちてくる。
「逃げましょう、ここに居ては危険です! 早く!」
「そんなこた解っておる、何が起きたんだっ!」
そんな事を言っているうちに、本格的に建物が崩れる音が上の方から響いて来た。
「きゃーっ! 助けてー!」混乱して飛び跳ねるオルフェの横でユークァルが土煙を吸い込んで咳き込んでいる。
「知りませんよそんなの。とにかく逃げましょう、リレミトッ!」
私達が脱出すると、城も地下迷宮も尖塔も、それを支えてきた土台もろとも土煙の中に沈んでしまった。あれだけ長い間、人々の心に恐怖を植え付け、負の歴史を刻み付けてきたこの城も、これでやがては伝説の一つとして、遠い日の記憶としてしか存在を誇示出来なくなる日が訪れるのだろう。
「ああ、とうとうこの城も廃墟になってしまったんでございますね。奥様の形見の品やら沢山の大切な物を置いてきてしまって、どうしてもっと早く運びだしておかなかったんでございましょう。ううう…」埃まみれになったリカルドが、これまた埃まみれのハンケチーフを取り出してぐずぐず啜り泣いた。
「まぁた嘘泣きか? この老いぼれめが!」
「その仰りようはいくらなんでもあまりにもひどうございますっ! よよよっ」リカルドは主人に対して抗弁する。
「まあまあ、それにしてもおっさんどうすんの?」
「だからおっさんって言うなっ! 貴様そのうちさい干しの刑にするぞ…しかし、ここを拠点にするつもりだったのだが、とんだ災難だったな」
「これは人災でしょう」ユークァルが辺りの空気を嗅いでいる。「火薬の匂いがします」
「やってくれるな、あのガキ」竜王は忌ま忌ましげに舌打ちする。「とにかく、ここでじっとしている訳にはいかん。そろそろ夜は冷える」
「おお、それでしたら、是非このリカルドめの家にいらして下さいまし!」リカルドが嬉しそうに平手を打った。「メルキドの南西の方に越しまして。孫が5人もおりますので賑やかですが、皆さんが寝るくらいの場所はございますから。ね? 旦那様」
「ぅやったー! こんな埃まみれのまんま外で寝るのオレやだったんだー! ありがとリカルドさん! オイラ大感謝だよ! キスしちゃう」オルフェは無理矢理老リカントの手にキスをして、四本足で嬉しそうにスキップした。リカルドはチューされた手の甲を迷惑そうに見つめている。
「おお、お前の細君のシチューが食えるなら大歓迎だ。喜んで世話になろうぞ」
「いいんですか? あんな事言っちゃって」私はリカルドにそっと耳打ちする。「あの人メチャクチャ食べますよ」
「知っておりますよ」リカルドは平気な顔をしていた。「タダとは言ってません」
リカルド一家の住むメルキド高原周辺は、北の険しい山岳地帯と南の湿地帯に囲まれた天然の要塞とでも言うべき地域である。土地は豊かとは言い難いが、地の利より、アレフガルドの中では半ば独立の自治区として中央からは一目置かれてきた地域であり、その中心都市メルキドは、その独立心旺盛な気質から、商業、特に貿易の盛んな街として、多くの商人を世に送り出している事でつとに知られている。しかしながら、この都市が世界に名を知らしめたのは、他ならぬ、街の周りに二重に巡らされた堅固な城塞に尽きるであろう。この城塞と、正門を護り続ける街の守護者ゴーレムこそが、この街をロト3国からもアレフガルド王家からも一目置かれる存在にして来たのだ。
「ふふん、懐かしいな。ここを攻めるのには苦労したものだ」
「じゃあ旦那様、買い出しに行きましょうか」リカルドは皆を見回すと、タダより高いものはない、と言う顔でにこやかにのたまう。
「はあ? 買い出しだと? ちょっと待て。リカルド貴様主人に買い出しに付き合えと言うのか? そもそも我々はもう正体ばれておるのだぞ!」
「旦那様、まさかタダメシにありつこうなんて思っちゃあいらっしゃいませんよね?」どうやらこの老リカント、見た目以上に老獪な人物の様だ。尤も、そうでもなければあの主人相手にまともに仕えてはおれまい。
「ぐ、ぐむう…わーったわーった、買い出しでも何でも付き合ってやるわ。だが、我々皆面が割れておるからな、オルフェはこの通り馬だし、こ奴の耳くらいならマントで誤魔化しようもあるが…」
「旦那様、そうビクビクなさらなくても大丈夫でございますよ♪」
「誰も人間共相手にびくびくなどしてはおらんわ。だが、見付かって騒がれてはことだ。今後の動きがやりにくくなる」
リカルドは何処か聞き分けのない子供をあやすように人差し指を立てて左右に振って見せた。「メルキドは人口も経済も、ラダトーム王家からも一目置かれるほどの自治都市でございます。ですから、メルキドは他の町なんかよりずっと自由な空気を吸えますよ。リムルダール南部から魔物狩りを避けてこっちに移住してきた仲間も少なくありませんから」
「魔物狩り…?」
「ええそうでございますよ」訝る私にリカルドは、僅かに肩を竦めた。「今じゃあ、人間じゃないって言う理由だけで、今まで友好関係にあった種族をも魔物扱いして追い立てるようになったのでございます。まったくもってせちがらい世の中になったものでございますね。さ、それより今夜はどうしましょう。クリームシチューなんかいかがです?」
大分前に購入して袋の肥やしにしていたフード付きマントを取り出して羽織り、リカルドの先導でメルキドに潜入する。こんな取り合わせは端から見ても怪しいに違いないのだが、土地柄のせいかどうかは知らないが、兵士達に怪しまれることもなくすんなりと城門を通してもらう。
流石は商売の街メルキドと言うべきか、街は活気に溢れており、人々に混じってちらほらと亜人種の姿を垣間見る事が出来た。町の様子に、私は少しだけ、破壊の神に身を捧げる為捨てて来た同胞を想って安堵した。
リカルドはシチュー用の材料だけでなく、ここぞとばかりに何やらかんやら雑貨の類を大量に買い込みまくり、おかげで我々は全員にわか人足と化して、蹌踉めきながらメルキドを後にする羽目となった。食事が出来るまでの間、慣れない仕事をさせられたオルフェは随分しんどそうに座り込んでいたが、食事に呼ばれるといの一番に食卓に飛んで行って一同の笑いを誘った。リカルドの家で食卓を囲みながら、百年余りの歳月を、私は8年の歳月を埋めるべく昔話に花を咲かせた。
「旦那様と奥様の間のお子様は、奥様に似て病弱でございました。奥様を娶られ、お子が出来て2年もしない内に、病に斃れておしまいになりました。坊ちゃんの父君、つまり旦那様のお孫様にあたるんですが、あの方は本当に立派なお方でしたねえ。自らの出自を恥じる事無く、いつも堂々としておられました」
リカルドは妻のクリームシチューをすすった。
「うちの亭主はいつもこの話ばっかりなんでございますよ、済みませんねえ、年寄りの愚痴でして」
「いえ、かまいませんよ」
「アレフガルド王家に固い忠誠を誓い、騎士として叙任さえ受けておられたのです」
「人間の配下になったのか!」
「これというのも旦那様が生前に無茶をなさったからじゃありませんか!」リカルドは百年ぶりに再会する主人を、我が侭な子供の様にたしなめる。
「旦那様はお子様達がどれほど苦労なさったか御存じないからそんな事を仰るのでございます。お子様達は人間の奥方を貰っていたので、随分と血も薄まりましたし…でも、良かったんでございしょうかねえ」
「何がだ。お前は良かったと思っておったのではないのか」
「それが元で、坊ちゃんの父君は亡くなられたんでございます。しかも、何者かの手によって……。魔物狩りと言い、今の御時世、人間で無い者には何かと暮らしにくい世の中なんでございますよ」
「こ奴のせいだと言うのか?」私の顔をちらりと見る。
「ん、まあ」リカルドは遠慮がちに応えた。こんな事は当の本人を目の前にしては、はっきりとは言いにくいものだ。「半分はそうでございましょうね。でもそればかりとも言えないんでございますよ」
「何だ、はっきり言うが良い」
「それがですね旦那様。教団の残党狩りやら魔物狩りと言うのも、本当の所はロトの三国が他国に対して影響力を強める為に、裏で連中を支援して人々を攻撃させていると言う専らのウワサで」
「は? 何だと?」
「こんな事、みんな陰では判ってる事でございますよ。もっとも、こんな事を堂々と言えるのは、この国じゃあメルキドくらいでしょうがねえ」
「なんだそりゃ、そんなのアリなのかよ!」オルフェがイスから立ち上がった。「あ、ゴメンいいんだ。ちょっとコーフンしちゃって」
「いや、オルフェさん、いいんでございますよ。確かに、伝説の勇者の子孫がそんな事をしてるだなんて言ったら、誰だって驚くものでございます」
「私どもも住みにくくなりましてねえ」でっぷり太ったリカルドの妻が台所で食後のお茶を入れていた。薫りからするに、カモミールであろう。「魔物狩りの影響で、リムルダールじゃあ町で買い物も出来なくなっちまいまして、娘が嫁いだメルキドのほうに引っ越したんですよ。メルキドなら、今の王様みたいにサマルトリアべったりのやり方じゃないから安心して住めるってもんです。街の人達もみーんな解ってくれてるからねぇ」
「サマルトリアべったり?」つい先程再会を果たしたばかりのサマルトリア王の姿が瞼を掠める。
「8年前の破壊神の教団と言うのがアレフガルドをめちゃめちゃにしたものですから、アレフガルドはすっかり国力も衰えましてね。復興するのに友好国のサマルトリアの援助を受けたのですよ。それに、今のラダトーム王家は例の件以降半ば臣民から信頼を失っていて、経済だけじゃなく、政治的にもサマルトリアからの援助に頼っている有様です。経済を立て直す為と称して、現国王のラルス21世は重い関税を課して経済的統制を強めたのですが、経済的に友好関係にあるデルコンダル・ベラヌール・ペルポイ・ルプガナの4都市経済同盟を潰そうとしているサマルトリアの圧力が見え隠れするものですから、王家とメルキドの議会は緊迫状態にあるんでございます」
「サマルトリアの何が友好国なもんかね」リカルドの妻が窯から焼き立てのスコーンを取り出した。「今年でやっと十になる王太子に倍の年の行き遅れ妹君を嫁にやろってんだからめちゃくちゃな話さね。連中、アレフガルドを乗っ取ろうってんだよ。まるっきり自分の国のつもりでいるのさ」
「相変わらずお前の細君は歯に布着せずに物を言うな」竜王は食後のお手入れ爪楊枝をしーしーやっている。
「あら。でも旦那様こそ、随分お人が変わってしまって、別人みたいじゃありませんか。百年前なんか、とてもじゃないけどこんな口きける雰囲気じゃあなかったじゃないですよ。はい、焼き立ての特製スコーン。でこっちが木苺のジャム。旦那様はクリームがお好きでしたね。はい」
「ん、そうだっだか」竜王はクリーム山盛りのスコーンを横目にハーブティを口に含む。「あの頃の事は余り思い出したくないのでな」
「あの…」私は百年前の邂逅から、時間を一世紀引き戻す事にした。百年前の私はまだ年端もいかぬ子供だったのだ。
「何でございますか?」
「ムーンブルクのロト廟の話はどうなったんでしょうか」
結局、この事件をきっかけに、総てが始まったのだった。ムーンブルクの先代国王が特に強く、勇者ロトを神と奉る廟を聖地ロンダルキアに造ろうなどと言い出さねば、その為に、ムーンブルク王が不可侵の筈であった聖地ロンダルキアに軍隊を送り込むという愚挙さえ犯さなければ、恐らくはこんなに多くの人々の血を流す事も、そして私が人間達に絶望し、この魂を滅びの神に捧げる事も無かっただろうに。
「ん、あ〜あ〜、そう言えば! ごく数年まではムーンブルクは復興に全力を傾けてたお陰でそれどころじゃなかったようでございますねえ。しかしまあ、今のマリア女王陛下が、先代国王時代以上の強国にムーンブルクを復興してしまってからは、ロト廟を建造しようって話がまた蒸し返されてきたんで御座いますよ。まあ今度は反対勢力も無いことですし」
「反対勢力を片っ端から消していきましたからね、先代ムーンブルク王は…我々はもとより、ムーンペタの前町長を街から追い出したと風の噂に知った時、余りの容赦の無さに我々は怖れ戦いたものです」
「ロンダルキアには既に、去年の夏あたりから物資が運び込まれて準備が始まってるようでございますね…旦那様、これは世間のウワサでございますがね」リカルドは食後のハーブティを一口すする。
「何だ、声をひそめて」
「ロトの三王家は、勇者ロトが魔の島に渡る際に用いた三種の神器を血眼になって探し求めてるんだそうでございます。話によると、そのうちの1つが行方不明になってしまったんだそうで…そして、もう一つ。大地母神ルビス様が、行方不明になってしまわれたっていう話なんでございますよ」
「何だと?」
「そして、ロトの三王家では、そのルビス様の行方を八方手を尽くして探し回ってるそうなんでございます」
私達は顔を見合わせ、入口に立て掛けておいた雨雲の杖に目をやった。
「そう言う事だったのか…」
「ルビスの奴、えらいものを託していったな。…どちらにしろ、あの女には会わねばならんな」竜王はスコーンにたっぷりクリームを付けて頬張る。
「でもルビス様、どこに居るのかなあ…おいちゃん、ジャム取って」
「どっかの海のど真ん中に、ルビスを祀った祠があるらしい。そこに居るんじゃないのか? ほれ、ジャムだ」竜王は瓶に慣性を付けて良く磨かれたテーブルの上を滑らせる。オルフェは瓶を受け取って、木苺ジャムを山盛りに盛りつけた。
「まさか。そんな場所ならあの3人組がチェックしてない筈ないです。事によると罠が張られているかも知れません。オルフェ、みんなの使う分も考えなさい」私はさっきから、ハーブティに砂糖を一匙入れてくるくるかき混ぜながら、一口も口を付けていない。
「だとしたら、どこに?」
「順を追って考えましょう。ルビス様がこの世界に居るという仮定で、ですが」
「むぐむぐ…天界には帰ってないと思うけどな、あんなに嫌がってたしさ」
「雨雲の杖を持ち出したことからしても、まず有り得ないでしょうね。恐らく自分の祠にはお戻りになってはいないでしょう。同じ理由で、他の神殿や祠に身を寄せている可能性も無さそうです。貴男なら、どうします」
「ふむ…」竜王はしばしクリームを塗る手を止めた。「ああ見えても、あれは決して愚かな女ではないからな。そうだな、私なら、か…髪を切って人込みに紛れるな。いや、だめだ。あ奴は確か供を連れておった筈。あの容貌ではどう足掻いても目立ちすぎるし、身を隠す為とはいえ、あの女には独りで暗黒街に足を踏み入れる勇気はないだろう。話を聞く限りでは、表の世界ではロト一族の目が届かない所に逃れるのは難しかろう」
「彼らの勢力外に逃れても、敵対勢力に利用される可能性があります」
「ユカ、口の周りくらい拭け。ヒゲが出来とるぞ」竜王がユカに向けてナプキンをひょいと放ると、ユカはナプキンを受け取って、早速口端を拭った。「ユカの言う通りだな。結局はどこか人気の無い場所に身を潜め、供の片割れに人々の様子を探らせていると見た。多分それはギズモ娘の方だ」
「あのねーちゃんじゃあ無理だよな。目立ちすぎるもん」
「あ奴、技は切れるがおつむの方はてんで当てにならんからな……」竜王はキューリ(以下略)嬢の事を思い出して、ため息をついた。
「話を元に戻しましょう。ルビス様が、どこに身を潜めているのか」
「神殿や祠でなく、人が訪れない場所、そして、大地と言う自分のテリトリーからは離れずに居たいだろうから、塔なんかの地上の建物にはおらんだろう」
「それから」オルフェが口を挟む。「意外な所だね。きっと、ルビス様がこんな所に居る、なんて事考えもつかないような」
「うーむ」私達は額を寄せて唸ったまま黙り込んだ。冷め切ったハーブティの表面にランプの光が反射して、見覚えのある像が形を結んだ。私はハーブティを啜りつつその像に思いを巡らすと、ふとある考えに思い至って口を開いた。
「思い当たる所があります。確証はありませんが」
「何処だそれは。言ってみろ」
「海底洞窟です。私達が昔、儀式に使用していました」
そう言って私は残りの冷めたハーブティを飲み干した。砂糖入りのハーブティは、やはり不味くて飲めたものではなかった。
「では、行ってくる。世話になったな、リカルド」
リカルドは皆に弁当を渡すと、巨大な竜に変化した主人の姿を眩しそうに見上げた。そう言えば、私はこの姿を今初めて目にしたのだった。
「いいえ、とんでもない。旦那様のお元気な姿を再び見られただけでこのリカルド、三国一の幸せ者でございます。それより、くれぐれも坊っちゃんの事はお願い致しますですよ」
「そうさな、4日もしたら一旦帰ってくる。その時には、お前の細君にタンシチューを作っておいてくれるように言ってくれ、楽しみにしておるとな。お茶請けはパウンドケーキが良いな、木の実とバターをたっぷり入れるんだぞ」
「旦那様」
飛び立たんとする主人に向かって、リカルドは最後に呼び掛けた。
「ん、何だ?」
「優しく、おなりあそばしましたね」
竜王は顔を背けると、返事もせずに飛び立った。
背中に乗せられて丸2日、絶海の孤島とでも言うべき場所に、海底洞窟はあった。
最後にこの洞窟に足を踏み入れてから、既に8年の歳月が経っていた。根の国に送られて来た時、私は、もうここに戻ってくる事は二度とないと信じていたというのに、今こうしてここに立っている己がいる事に、運命の皮肉を感ぜずにはおれぬ。
「う〜、熱いよ〜」
「良くもまあ…こんな所に祭壇を作ろうなどと思ったものだな」竜王は額の汗を拭いつつ不平を垂れる。皆、熱そうに手で仰いでみたり汗を拭ったりしている。
「当時は魔法で冷却していましたから、もう少しましでしたよ。こんな洞窟ですから、カモフラージュにも防御にも最適の場所でした。無論、彼ら…ロトの勇者達には破られましたがね」
竜王は聞かない振りをした。「お前達の使っていたという祭壇は何処にある? まさか、このだだっ広い洞窟を歩いていったわけでもあるまい?」
「入口の近くに隠し扉があるんです。その奥には魔法陣があって、私達は地下の祭祀場にそれを使って移動していました」
ユークァルが早速壁に手を当てて、それらしい隠し扉を見付け出す。扉を開けて中に入ると、小さな部屋はめちゃめちゃに荒らされている。
「うわぁ…こりゃダメだね」魔法陣は誰かの手で、既に粉々に破壊されていた後だった。
「直しようがないな…これでは使いものにならん」
「仕方ありませんね」
「おい、まさかこの溶岩地帯を歩いて渡るのか」
「無理ですそんなの」私はあっさり答える。「そもそも、この足で行ったら靴底が熱で焼けます」
「竜王ならいけんじゃないの?口から火ぃ吐いちゃうしさ、熱いの平気そうじゃん」
「お前のひづめでもいけそうだな、オルフェ、渡るか?」竜王はオルフェの耳を思いっきり引っ張る。
「ギャー、やめてやめてっ!」
「何やってるんですか、ホントに。子供の遠足じゃないんですから……そんな事しなくてもいけますよ。これがあるでしょう」雨雲の杖を取り出して、目の前で振ってみせる。
「おお、すっかり忘れていた」
「皆さん、入口近くに退避して下さい。火を消しても、大量の水蒸気が発生して危険ですから」
一同が一旦洞窟の外に避難したのを確認し、私はルビス様よりお預かりした雨雲の杖を握り締め、杖を天に掲げて祈念する。5分ほど祈っただろうか。天に掲げた雨雲の杖が黒雲を呼び寄せ、雨を誘う。最初はぱらぱらと、やがて大粒の雨が滝の如く降り注ぎ、それは小さな川となって海底洞窟に流れ込んで行く。洞窟の入口からは水蒸気が天に向かって噴き出し、ますます激しい雨を呼んだ。雨が止むまでにおよそ一時を過ぎてから、ようやく辺りの空気が夜気と混ざり合ってひんやりと辺りを包み込んだので、我々はずぶぬれの体をおして海底洞窟へと踏み込んだ。
「なあんか、生暖かいなー」
「さっきまで溶岩ぐつぐつだったんだからしょうがないだろう。しかしどこまで探せばいいんだ? おーい! 誰かおらぬかー!」
「絶対にいるとは言ってませんよ。だから、ここに隠れているかどうかも、何処にいるかも断定は出来ません。隅々まで探してみないことには…」
「ルビス様ーっ! おーい! やっほっほーい! ……あ、すげ、反響しまくってる! やほほーい! うわ、おもしれー! ユカもやってみなよ!」
「何て言ったらいいですか?」
「んー何でもいいよ。何か思い付いた事言ってみなよ」
「うん…じゃあ…おんせーん!」
「ぷっ…温泉って叫んだらルビスが見付かるのか? それとも、ずぶ濡れになったんで温泉にもう一度入りたくなったか。マイラでは入り損ねたからな…しかし全く、この洞窟は何処まであるんだ。こんなに広くては探しようがないぞ。何とかならぬのか?」
「祭祀場へ行きますか。魔法陣が壊されているというのが少し…気になりますね」
我々は洞窟内をひたすら歩き回った。当時は祭壇への移動は魔法陣を使っていたので大して苦では無かったのだが、こうやって歩いて行くのは、祭祀場への正しい道のりを知っており一時的に溶岩の熱気が治まっているとはいえ、流石に骨の折れることではあった。熱気がまとわりついて皆の体力を徐々に奪い、しかもろくに休んでいないのだ。自分で言い出した事とはいえ、本当に、こんな所にルビス様が身を潜めておられるのであろうか?
上へ下へと随分歩き回った後、ようやく私達は祭祀場の入口にまで辿り着いた。
「おーい、誰かおらんかあ」
「おいちゃん…あのさあ…」
「おいちゃんではない! …何じゃ、申してみよ」
「オレ、思うんだけど…ルビス様隠れてるのにさあ、声かけたって出てこないんじゃない?」
「…そうだったな」
「とにかく、奥に行ってみましょうか」
祭祀場の中に近付くと、更に押し寄せる熱気に気圧される。踏み入るのに躊躇していると、熱に紛れて殺気が絡み付く。
「下がれっ!」
殺気に気付いたのは私だけではなかった。下段の構えよりの鋭い踏み込み、相当の手練れに違いない。 刃の欠けた鋼の剣で殺気を何とか受け止め、相手の正体を見定める。
殺気の主は、やや疲労の色を濃くした天空人の女戦士だった。
「キューリさん!」
「何と、この程の騒ぎ、全て汝等の仕業であったか!」
キューリさんは肩をおろし、剣で、洞窟の奥を指した。
「付いて来るが良い、ルビス様はこの奥に居られる」
祭壇の後に腰掛けているルビス様の横顔は、やつれて疲れ切って見えた。私達がキューリ嬢に連れられて室内に入るとルビス様ははっと顔を上げられたが、私達の姿を見て緊張が解けたのか、抱き付いて泣きじゃくった。
「ああ…まさか、来て下さるなんて…わたくし、不安で、ずっと…」
「ああ、泣くな泣くな。判ったから抱き付くな」竜王はオルフェに笑われながらルビス様を引き剥がす。「しかしルビス、そなた、何故」
「ルビス様はな、三種の神器がロトの一族の手に渡るのを怖れておられるのじゃ」キューリ嬢が代わりに答える。
「またロトか」竜王は半ば投げやりに、力なくため息を付いた。「皆、どうして奴らをそんなに怖れているのだ? 我が血を引く者とはいえど、所詮は人の子ではないか。一体奴らに何の義理があって力を貸してやらねばならんのだ? 嫌なら嫌とはっきり言ってやるが良い」
「それは…」
「何じゃ? 申してみよ」
ルビス様の深い瞼が伏せられ、淡い薔薇色の唇が僅かに震えた。「古の契約ですわ。私が、あの子の…ロトの子孫に加護を与えると約束したからですわ…」
「…そう、あれは今から500年以上前に遡りますわ。あの子がわたくしを、貴男の手で石柱にされていた姿から救ってくれた時の事です。わたくしはあの時まだ、あの子が我が子とは知らずに、わたくしを救ってくれた礼にと、わたくしの加護をあの子の子々孫々にわたって及ぼすと、そしてその証を、印として残すと、そう約束したのですわ。その印が、ロトの一族に伝わる、翼を広げた黄金の鳥のシンボルなのです。ロトの印と人々は呼んでおりますわ」
「なーんだ、全部おいちゃんの自爆じゃん!」
「う、うるさい! …とにかく、奴らがその印を持つ限り、奴らには加護を及ぼさねばならない、とそういう訳だな」
ルビス様は頷かれた。
「つまり…お前は奴らが何を企んでいるか知っているのだな? だからこそ、お前は我々に雨雲の杖を預けた。奴らのやり方に危惧を憶え、その野望を、結果として後押しする羽目になったのを悔いておったからだ。違うか? 奴らは何を企んでおる」
「! ……まさか」ルビス様は暫し考え込んでいたが、突然面を上げた。何か触れてはならない禁忌に触れてしまったかの様に、動揺が押し隠しようもなく溢れ出す。「あり得ませんわ、そんなこと…馬鹿げてます…でも…そんな…」
ルビス様が啜り泣かれたので、我々もこれ以上強くは聞き出せなかった。竜王はそっと肩を抱き、いずれ戻るからと慰めの言葉をかけたが、ルビス様はかぶりを振って、いいのです、彼等の暴走を止めて下さい、後悔はしません、と、涙ながらにもはっきり言い切った。
あの印は、大地母神の加護を表す物なのか? だとしたら…
形にならない思考が、頭の片隅で僅かに渦巻き、形にならぬまま蠢き脈打っていた。
海底洞窟からアレフガルドまで空の旅を約2日、そろそろメルキド高原が見えてくる頃である。溶岩の熱気にあてられ、夜気に身を震わせた事もあったが、ようやくリカルドの妻の温かいシチューとふかふかのベッドの恩恵にあずかる事も叶うのだ。朝焼けを背に空を翔んで一時、水平線の遥か先に、朝靄に煙るメルキド高原が姿を現わした。
「おっ、右前方10キロメートル先にメルキド高原が見えました、隊長!」
オルフェが手の平を望遠鏡に見立てて覗き込む。
「いい加減な事を言うな、幾ら何でもそんなに近い訳無かろう」
「隊長、ひどいであります」
「まあよろしい、では二等兵、観察に戻れ」
「勝手に二等兵にしないで欲しいであります。せめて上等兵がいいであります」
「馬鹿、お前がそんな上等なものか。そうさな、我らが竜王軍の階級を決めよう。当然私が元帥で軍隊長、ハーゴンは中佐に任命してやる。ユカは鬼軍曹だ。ユカ、部下を可愛がってやれよ」
そんなもの勝手に決めないで戴きたい。
「はい。あの…」
「どうした軍曹、人に命令するのはお前にゃ無理か?」
「煙が……」
「煙?」
「あれです」ユカが指差した先で、城塞都市メルキドが煙を上げていた。
城塞都市メルキドの有様は、それは惨憺たるものであった。二重に巡らされ、その存在故に世界にメルキドの名を知らしめる事になった城壁は半壊状態のまま放置され、焼き討ちを受けた痕が街のあちこちに点々と黒ずんだ侵略の印を残している。街頭では兵士達が巡回し、教会の神父が家を失った人々の為に炊き出しを行なっていた。ゴーレムは街の修理に駆り出されて木材やら石材やらを運んでおり、被害の甚大さを裏付けていた。
「何が起こったんだ? …ありゃ、ラダトームの正規軍だな」
「まさか…国王が兵を差し向けてメルキドを攻めたなんて事はないですよね?」
「何でそんな事するんだよ、自分の国の街だろ。アレフガルドといいグランバニアといい、王様のゲレゲレと言い、この世界メチャクチャじゃないかぁ!」
「ゲレゲレじゃないです、トンヌラ王。それに国の名前はグランバニアじゃなくてサマルトリアです。いい加減憶えて下さい」
「まあまあ…良いではないか。だが、リカルドの話からするに、アレフガルドにそれほどの国力の余裕はない筈なのだが…しかも、偉く動きが早いではないか」
で、私達はというと、街の様子を探るべく、城塞正門近くの植え込みから遠巻きに人々の様子を観察しているのであった。人々は恐怖故に憔悴しきっていて、数日前の活気は跡形もない。作物を運びこむ農夫やメルキド自治議会の義勇軍の代わりに、軍事物資を搬入する正規軍の兵士達が否応なしに目に付く。
「隊長、大変なものを見付けましたであります!」手で望遠鏡を作ったまま、オルフェが軍隊調で叫んだ。余程気に入ったらしい。
「し、声がでかいわ馬鹿者。でどうした、オルフェ二等兵」
「鳥のマークであります。ええと、ロトの鎧に付いてたあのマーク」
「何? 本当かそれは!」
「しーっ!」人差し指で静かに、のポーズを作る。「そう言ってる本人が一番大きい声を出しているでしょうが」
「済まん済まん。ふむ、しかし何やらきな臭い匂いがしてきたな」
「…もう少し、メルキドの様子を探りますか?」
我々は消え去り草で姿を消し、メルキドに侵入する事にした。
メルキドの街中は火が消えた様に静まり返っていて、数日前の活気を考えると廃墟と見まごう程だ。朝市に出向いて行ったが、店もなければ客も来ないので、皆早々に店を畳んでしまったのか誰もいない。
「かなり規模の大きい戦闘が行われた様子があります。しかも、一方的に攻撃されたみたいです」ユークァルが辺りを見回して、言った。
「でしょうね」
「しかも、市の中心部も相当攻撃を受けてます」
「空から、か。人間じゃあないな」
「魔物が、ですか? これだけ大規模な攻撃を仕掛けられる程の?」
「まさか、な」魔物狩りが横行し、ロト3国の影響が馬鹿にならないこの世界で、これだけ統率された魔物達を率いる勢力が、白昼堂々威力を奮う事など、あろう筈もなかった。まともに考えれば。
町中を歩き回り、下町の路地に入った所で、私達はようやく兵士と土木作業員以外の人間に出会う事が出来た。それは、ちょうど子供が表に遊びに行こうとして母親に止められている姿だった。
「かあちゃん、なんで遊びに行っちゃいけないんだよぉっ! 今日で三日目じゃないかぁ!」
喚く子供を母親は平手でぶった。
「また魔物達に街が襲われた時に、逃げられなくて隣のキムちゃんみたいに魔物に食われちゃったらどうするんだい! とにかく、今日は家で大人しくしておおき!」母親は子供をぴしゃりと叩くと、子供を無理矢理ドアに引きずっていこうとした。
「魔物達が街を襲った? ふむ、やはりユカの指摘は正しかったと言う事か」
「何処の魔族がそんな事を…またどこぞの魔王が現れたのでしょうか」
身体がドアまであと半身、というところで、先程までいやいやして母親に逆らっていた子供が、ついに観念したのか悔しそうに壊された石畳の欠片を蹴っ飛ばした。
「くっそー、竜王とハーゴンの奴っ! 勇者ロトの三人組が早くやっつけてくれないかなあ…そうしたら、また外で遊べるのに」
「ぼうやおやめっ、もし魔物達が聞いてたらどうするんだい!」
私達は顔を見合わせた。見合わせて、己の甘さを心底呪った。
「くそ、何てこった! トンヌラの奴にまたしてもやられた!」
「こんな見え透いた謀略を仕組むとは…どういうつもりなのでしょう?」
「人間どもにはその辺りの事情など解るまいよ。…それにしても、どうやって魔物達に町を襲撃させたのだ? この世界にはもう魔物など数える程もおらぬ筈。闇の影響も大して感じられん」
「でも、おいちゃん達ハメられたんだろ? ヤバイよ、早くズラかろうぜ」
「ズラかるって…??」ふと、私は、親子連れの視線がこちらに注がれているのに気が付いた。
「キャァーッ!ま、ま、魔物よっ!」
慌てて自分達の姿を見ると、既に消え去り草の効力は、半透明ながらお互いを十分視認出来る程に消えかかっていた。
「おい、ハーゴン、見えてるぞ!」
「わーっ! だー! やべーよこれ!」
「お母ちゃーんっ!」
「魔物だーっ! 魔物が現れたぞーっ!」
「こっちです、逃げましょう」
町中を巻き込んだ大捕物の末、我々は這々の体でメルキドより退散した。
リカルドの妻の温かいシチューの代わりに、リカルドの家に戻るしかなくなった我々を待っていたのは、変わり果てたリカルド一家の姿であった。
私にはしばらくの間、ここで何が起こったのかを考える事すら出来なかった。状況を把握する事を脳が拒否していた。リカルドの一家は、女子供に至るまで無惨な屍を晒していた。ほんの数日前まではこの辺りを走り回っていたのに。同じ宅を囲んで昔を懐かしんでいたというのに。
こんな事があって良いのか。
感情移入したら自分が壊れてしまう、という無意識の危機感が、私を何も感じない木偶のように立ち尽くさせていた。
「リカルド、リカルド! しっかりしろ! 目を覚まさんか!」
眼の前では、竜王が動かないリカルドの肩を揺すぶっている。現実を認めたくないのだ。痛い程、解り過ぎる程解る。解らない方がましな位。だけれども。誰かが、何時かは現実を認めなければならなくなる。
私はそっと肩に手を置いた。
「リカルドは、リカルドは死んでいます」
「ザオリクだ」竜王の声は震えていた。「ザオリクをかけろ」
「無理です」私は努めて冷静である様に振舞った。そうしなければ私の心の均衡が崩れてしまいそうだった。「蘇生しないように内臓を抜かれています。それに、死んでから日が経ち過ぎています」
イッソノコト、ソンナ物ハカナグリ捨テテシマエバイイノニ。
「リカルド! リカルドォォォッ!」
竜王はリカルドの骸にしがみつき、吼え猛り狂った。想いを何一つ、後生大事に抱え込んで押し込めておこうなどとはしなかった。
「……見せしめの為にリカルドの様な善良な者まで殺しおって…! 虫螻共が、神の代行者でも気取っている心算か? 人の子の分際で、他の生き物を裁く権利が何処にある! ……その血筋、この手で根絶やしにしてくれる! 例え我が血を引きし者とて容赦はせぬ!」
羨ましい。偽らざる、私の気持ちだった。
リカルド達を出来る限り手厚く葬った後、私達は仕方なく惨劇の跡で一晩をすごす事にした。
辺りは血に汚れていて、とうてい心安らかに、という訳には行かなかった。だが、眠らねばならぬ。そうしなければ、次はいつ屋根の下で体を休められるか解らない。無理矢理目を閉じると、血の匂いが鼻を突き、いやがおうでも覚醒を促す。
どうしても、リカルド一家の死に顔が瞼の裏から離れないのだ。
“魔物狩り”だ。彼ら…サマルトリア王家が何らかの工作によって、ラダトーム王家の正規軍を動かして、魔物狩りをするようし向けたのだ。魔物達にメルキドを攻めさせ、メルキドを守るという目的でメルキドをラダトーム王家の監視下に置く事によってアレフガルド国内の反対勢力を抑え、その罪を我々に着せて我々を追い詰め、亜人種を魔物として排斥する事で…。いや、やめだ。こんな事が何になるのだ。原因が解れば、我々の状況が少しでも良くなるとでも? これでリカルドが蘇るとでも言うのか?
リカルドの子や孫の姿が浮かんでは消え、涙が止まらなかった。涙などもう流さないと、あの時…そう、滅びの神にこの身を捧げる時誓ったというのに、星降る夜からだろうか? すっかり涙もろくなってしまったように思う。
私は再び目を閉じ、努めて心を平静に保とうと呼吸を整え、やがて眠りに入った。
私は真闇の中を立ち尽くしていた。
如何なる深淵に嵌まっているのであろうか。三歩先にある物が見えない、絶対の暗闇。不安が胸中を掻き立てる。が、不安に駆られた所でどうなろう? この闇は、我が心の闇。逃げ回った所で逃れる術などあろう筈もない。私は再び闇に意識を向けた。
眼前に、光が満ち始めた。それは、太陽の様に全てに恩恵を与えるような輝きではなく、闇夜の遠い空に輝く星の様な、強くも明るくもないが、しかし心安らぎ、勇気づけられるような光。観想の中で、その光を受け止め、少しずつ大きく輝かせて行く。
光が辺りを見渡せる程に満ちて来ると、私は湖岸に立っている事に気付いた。あの光は、月光を反射して輝いているのだ。頭上を見上げる。
満月であった。今まで厚い黒雲のヴェイルに覆われてその姿を隠していたが、それは突如生まれ落ちたかの如く顔を覗かせ光を放ち始めた。その光が、深淵を照らし出す。
木々のざわめき。
漣は一陣の風に沸き立ち、映し出された月はその姿を水鏡に散らす。
そして、湖の向こうに、街の姿が浮かび上がった。
これが夢の中である事は承知していたので、軽く地面を蹴って宙に浮く。そうでなかったとしても、私の体は星幽体のそれなので、普通の人間に私の姿を見る事は出来ない。緩やかな空気の元素に動きを任せ、街に向かう。
街の空気は冷ややかで、どこか懐かしさと痛みを思い起こさせる匂いがあった。街の中央には広間があったが、昼間はともかくもう随分と月が西に傾く今の時間に、人が歩いている気配などあろう筈も無い。その広間の正面には、個人のものと思われる立派な屋敷の佇まいがあった。屋敷は月光をたっぷり浴びて、あたかもそれが独りで、太古の昔より存在するかの如く光を放っていた。
上空より屋敷を眺むれば、庭に咲くレンギョウの黄色い花が出迎えてくれた。屋敷の脇には淡い紅色の木蓮が花を付けている。花々は月光を受けて、我が世の春を謳歌する。
私はベランダの手摺に腰掛けて、花々の命を燃やす様を愉しんでいた。ああやって咲き誇る花も、いずれは枯れて散る。だが、その後に、もっと沢山の美しい花と、緑と、新しい命をもたらすのだ。緩やかな風が頬を撫で、春の花の香りを運ぶ。
「あの…」
ある筈の無い呼び声と気配に、はっと振り返った。
誰もいない筈の、いや、さっきまで誰も居なかった筈のベランダに、年端も行かぬ少女が、その手をレンギョウの花で一杯にして立っていた。
私と少女は目が合ってしまった。
姿を見られて、私は驚愕に竦んでしまった。
少女は、私に微笑みかけた。
私は、声を上げ、布団をはね除けた。
月の光に照らし出されて、私は目が醒めた。
「…お前も、起きておったのか…」
竜王がもぞもぞと布団の中から顔を出した。眠れなかったのだろう。
「いえ、うたた寝はしておりました」
「無理してでも、眠れよ」私を労る声に、僅かな掠れが混じるのが聞き取れた。私などより余程、ショックは大きかったに違いないのに。
「私にお気遣いなさらずとも、貴男こそ休まれなければ」
「いや…今夜だけは眠れそうにない。…それより、良い月夜だな…満ちて行く月か」
「ええ…」
ベッドから這い出して、二人で月を見た。
「まだ、夢の中のようです」
「夢だとしたら、悪夢の中だな…もしこの世が全て夢なら、悪夢で無い夢など見た試しが無い」
「先程、夢を見ました」あの夢の事が、頭から離れなかった。
「深淵の真っ直中に取り残されて、怯えていました。すると目の前に光が満ち始め、空を見上げると月があったのです。ちょうど今みたいな…いえ、あれは満月でした…。私は湖岸に立っていて、目の前には街が月光に照らされて、いにしえの時代よりずっと変わらぬ佇まいを見せていました。街に入ると、広間の正面に大きな屋敷があり、庭には木蓮とレンギョウが咲いていて、私はベランダからそれらの花を愉しんでいました。月は随分西に傾いていて、夜の静寂に頬をなぜる春風が心地好く、そこは私の為だけに用意された古代の遺跡の様でした。そこに、ふと人の気配がしたのです」
私は夢に浮かされて、独り饒舌になっていた。
「そこには人など居なかった筈でした。もう皆寝入っている時間だからです。もし人がいたとしても、その姿は誰にも見えない筈でした。なのに、そこには少女が立っていました。レンギョウの黄色い花を一杯付けた枝を抱えて、少女は私に微笑みかけたのです」
「…だから、それがどうしたというのだ?」
「すいません…つい…」
「まあよい。お前の饒舌を咎め立てするつもりはない」竜王は僅かに目を細める。その眼差しは逢魔が時に見た、あの目に何処か似ていた。「あの月を見ていれば、そういう気分になることもあるだろうよ」
「……この夢にも、何か意味があるのでしょうか…」
「ふむ…」何気ない呟き故に軽く受け流されると思っていたのだが、竜王は真面目に受け取ったようだった。「そなた、確か夢占であったな。もし、意味があるとするなら、そなたならどう解釈する?」
「そうですね…月が、我々を導く鍵になると思います。月…あの街は、見たことがあるような気がします。そして、あの少女…少し待って下さい」私は懐から、タイジュで買ってきた小さな水晶のお守りを取り出した。「この世界の地図は何処にありますか?」
「待っておれ。きっと何処かにしまい込んであるに違いない…これか? 違うな…これだな」
血の跡が付いた羊皮紙を広げさせ、メルキドの上空に鎖を垂らして、水晶のペンダントヘッドを吊す。意識を集中させると、水晶は円を描きながら揺れ始め、やがて、ある一方を指して揺れるようになった。
「これは…ムーンブルクか?」
「確かに、月と関連があります…しかし…」水晶が描く軌道の先には、ムーンペタの街があった。夢に出てきたあの街は、ムーンペタだったのだろうか?
「行こう、ムーンペタへ」竜王にぽんと肩を叩かれて、水晶が軌道を不規則に変えた。「こういうのは、閃きが大事なんだ、自分を信じろ」
「しかし…我々は、顔が割れています。どうやって?」
「面が割れていようがいまいが、堂々と歩けば良い。もう面を隠してびくつくのは沢山だし、第一性に合わん。明日は早いぞ、無理にでも寝ておけ」そう言うや否や、竜王は再び毛布の中に潜り込んでしまった。
朝日が薄明るく闇夜に染み渡るや、問答無用で一同を叩き起こしてムーンペタに向け翼を広げる。ユークァルは相変わらず黙々と従ったが、オルフェは眠い目を擦って不平を零した。無論その不平に耳を貸す者など誰も居なかったが。
「私はな、涙を流した事が無い」不意に、冷たい風に混じって呟きが届いた。私は風に逆らって身を乗り出していた。
「不思議か? だがな、もう涙など、とうの昔に涸れ果ててしまった。だから…あ奴が、リカルドが足許で冷たくなっている時でさえ、そこにあったのは悲しみなどではなく、己の運命を呪う憤りに過ぎなかった。直ぐにでも、奴らの元へ舞い戻って、一人残らず皆殺しにしてやるつもりだった。だが…」
巨竜の口元が僅かに歪んで、象牙色の牙が覗いた。
「リカルドの奴、枕元に出てきおってな。『わたくしめのことはどうでも良いので御座います、だからぼっちゃまを助けて下さいませ、旦那様』だと。気が抜けたわ。…まったく、死んでまでも口うるさい奴だ」
「悪くない、夢でしたね」
「そうかもしれんな」それっきり風鳴りにノイズが混じる事は無かった。
月が沈み、太陽が昇り、太陽が沈んで二度目に月が昇る頃、ムーンブルクが姿を現わした。
夜の湖にはムーンブルクの名に相応しく月の光が映っていた。森に囲まれた美しい国。そして、あの忌まわしい過去の記憶。様々な想いが交差し錯綜する。ムーンペタの近くに降り立った、土の感触さえもが馴染みの物に感じられる。
私は、とうとうここに戻って来たのだ。
過去への憧憬に浸る間もなく、我々はムーンペタにその歩を向けた。
ムーンペタの門は、我々異形の者には頑なにその門を開こうとはしなかった。我々が正門の前に立つと、門を守る兵士達が一斉に槍を向けた。が、我々は大して怯みもせず、衛兵達へ適当に睨みを効かせながら門へと歩みを進める。
「門を壊したくはない。開けよ」
兵士達は射竦められ、かといって言うなりにもなれずに身を硬くする。
と、殺気が走った。一人の兵士が畏れを振り切り、襲いかかって来たのだ。竜王は突き込んで来た槍を跳ね上げて切っ先を躱すと、懐に入って兵士の首をつかみ素手で易々とねじ切った。地面に転がった兵士の首をつかみ上げ、衛兵の中に投げ返す。返り血にまみれた姿が、月明かりに晒される。
「門を開けろ。二度は言わん」
衛兵達は黙って街の正門を開けた。我々が後について行く。
「ところで、聞きたい事があるのだが」竜王が不意に立ち止まったので、衛兵達の動きが面白い程見事に凍り付いた。冷ややかな夜気が彼等の唾を飲む音さえも伝え来る、そんな錯覚を呼び起こす。
「この街で一番偉い奴は誰だ?」
「ち、町長です」
「町長はどこにおる」
「街の真ん中の、大きな家です」
「宜しい」竜王は振り返りもせずに言った。「引き続き、任務に戻れ」
町長の家の前に立った時、私は未だ、自分がリカルドの家で見た夢の続きの中にいるのではないかという錯覚に囚われた。あの建物は、まさしくここに違いなかった。秋も深く木蓮もレンギョウも花を付けては無かったが、春ともなれば木蓮が屋敷周りを彩り、レンギョウの黄色い花が庭を美しく染めるのだろう。もしかするとあの少女がこの中で待っているかも知れない、とも思ったが、当然の如くベランダにそれらしき少女の影は見当たらなかった。
町長の家の扉をノックすると、召使らしき女が迎え出た。女は我々の顔を見るなり、声もあげずに屋敷の奥に走り去った。恐らくはここにも例の指名手配のポスターが出回っているのだろう。遠慮無しに屋敷の中を進んで行くと、さっきの召使の女がリビングでくつろぐ町長に我々の到来をちょうど告げている所であった。
「その女の言った通りだ。お前がこの町の町長だな?」
町長は禿げ上がった頭を必死に前後に振った。
「よろしい。では、要件を告げよう。お前達一家は荷物をまとめて早々にこの家から出て行け。そうさな…タイムリミットは15分だ。何なら後で荷物を送ってやるから、越した先を後で知らせるが良い」
勿論、町長一家はそれっきり屋敷に遣いを寄越さなかった。
「ちょいとあんた達」町長一家が逃げる様に屋敷を後にした後で、台所の方から老婆が、その手に蝋燭を持って、ナイトキャップにピンクのネグリジェ姿で現れた。色っぽいとはお世辞にも言えない。
「あたしもこのお屋敷から出て行かなくちゃならないのかい?」
「何だ、このばあさんは?」
「さあ…住み込みの賄いさんじゃないでしょうか」
「何だとは何だい! あんた達こそ勝手にこの家を占拠して町長さん一家を追い出しちまうなんて、何て酷い連中なんだろう! 町長さん達可哀想に、これからどうするんだろうねえ」
「いちいちうるさいばばあだな。お前も出て行け!」
「ばばあとは何だいばばあとは! あんた、年寄りを敬うという気持ちはこれっぽっちも無いのかい? いいかい? あたしゃこのお屋敷に、もう四十年は奉公してるんだよ? あたしがこのお屋敷で奉公する間に4人の町長がこの屋敷に住んだんだ。それをうるさいばばあだから出て行けとは何だい! おふざけじゃないよ!」
竜王は老婆の説教を神妙に最後まで聞き終わると、噴き出した。噴き出して、大いに笑った。
「何がおかしいんだい」
「ばあさん、気に入ったぞ!」
「何だって?」
「よろしい、私がお前の5人目の主人だ。お前さん給金いくら貰ってた?」
「アー、ええっと…」老婆は突然の事に対応しかねている様だった。「17ゴールド。月に17ゴールド」
「ふむ。安いな、二倍の34ゴールド出そう。いや、40でどうだ」
「え、いいのかい? ちょっとそりゃあ貰い過ぎだよ。うちの孫より多いじゃないか」
竜王は嬉しそうににやりと笑った。
「いやなあに、気にするな。私ももう五百年は生きておるからな」
さて、我々が件の屋敷を占拠した事実は、誰が伝え広めたのやら、日が明ける頃にはムーンペタ中の人々に周知となっていた。
私はオルフェとユークァルには絶対に庭にも表にも出ないように厳命し、対外的には取りあえず平穏を保っておく事にした。人々を怯えさす必要はないし、下手に外に出て、二人が危険な目に遭わないとも限らない。
「こ〜んないい天気なのに、誰も出て来ないね〜。静かで何だか気持ち悪いや」オルフェは双眼鏡で広間をのんびり眺めていた。
「しょうがないですよ、我々が居る事が解っているのですから、人々も心落ち着かないのでしょう。…それにしても、私達、まるでブレーメンの音楽隊みたいですね…」
「それ何?」
「そういう物語があったのですよ…4人の田舎者が大それた夢を持って都会に行く途中、強盗の屋敷を乗っ取ってそこに居着いてしまう話です」
「あ、ほんとだそれそっくり。オレらみたいじゃない? いっそのことそうしちゃえばいいのに」オルフェは双眼鏡から目を離した。「ダメなの?」
「ここの人々の様子を見たら、そうしてはいけないのは解るでしょう? 私達は…いや、少なくとも私と竜王には、一所に腰を落ち着けて余生を過ごすような生き方は、もはや望むべくもないんです。それを望むには、二人とも、余りにも大きな物を背負い、背負わされ過ぎて居るのですから。…オルフェは、そうしたいんですか?」
「いつかはそれでもいっかな」オルフェは双眼鏡を持ったまま私の顔を見た。「でも、当分はゴメンだね。だってまだ見てないもの聞いてないもの、たくさんあるんだもん。それに…ひとりぼっちはヤダな」
「一人にはしませんよ」私はオルフェが一人で居るのに気が付いた。「ところで、後の二人は?」
「お腹すいたって言ってたから、台所じゃない? オイラもお腹空いちゃったなあ」
で、当の張本人はというと、オルフェの予想通り台所に忍び込み、料理をつまみ食いしようとして老婆に手を叩かれているという体たらくであった。
「つまみ食いしようだなんて何て行儀の悪い! 夕飯まで待てないのかい? 呆れてものも言えないよ」
「良いではないか。ちゃんと毎月の給金を払ってやっておるのだ。文句言うな。った! また叩いたな! 頭をフライパンで叩く奴があるか!」
「400年だか何だか知らないけどね、今まで40年仕えてきた中で、主人自らつまみ食いしようなんて馬鹿な事をしたのはお前さんが初めてだよ! 全く、お里が知れるってもんだよ!」
「お前に行儀を云々される筋合いは無いわ、なあユークァル。ほれ、ポテトフライだ、食え」
ユークァルは竜王に貰った揚げたてのフライを、息を吹きかけながら大して旨くもなさそうにもそもそと食べた。
「子供にそんなお行儀の悪いこと教え込むんじゃないよ! …ユークァル? 今、ユークァルって言いなすったね?」
「ああ。この娘、ユークァルと言うが?」
ばあさんはしげしげとユークァルを眺めていたが、突然、手をぱちんと叩いた。
「…もしかして、もしかして嬢ちゃん、ムォノーさんの孫娘のユカ嬢ちゃんじゃないかね?」
「なんだ、ばあさんこの娘の事を知っておるのか?」
「知ってるも何も、ムォノーさんはこの街の町長だったのさね!」言うなり老婆はユークァルの頬に愛おしげに触れる。「ユークァルなんて名前はそうそうこの辺にはないからね。ああ、ユカ嬢ちゃん、生きてなさったんだねぇ! こうやって見ると、どことなく面影が残ってるねえ! あたしゃ人生で、こんなに嬉しかった事はないよ! ムォノーさん一家がここを出て行かなくちゃならなくなった時、あたしゃこの人生七十余年で一番悲しかったんだよ。ムォノーさんが今までの町長さんではあたしに一番良くしてくれたんでねえ。嬢ちゃんはあたしのこさえたブルーベリーパイが大好きだったじゃないか。憶えてないかい?」嬉しそうに涙ぐむ老婆にユークァルが放ったのは、しかし、余りにも冷淡な彼女自身の現実だった。
「あなた、誰ですか?」
「すまんな、この娘に向かって詫びる」狼狽える老婆に向かって、竜王はユークァルの代わりに応えた。「この娘が昔ここに住んでいたというのは本当の事かも知れぬ。だが、もうそれを思い出す事が出来ない程、この娘は変わり果ててしまったのだ。何がこの娘の身に起こったか、それは言うまい。知らぬ方が良い」
「…そうかい…。ユカ嬢ちゃん、辛い思いをなさったんだねぇ…」
涙ぐむ老婆に、ユークァルはただ戸惑うだけだった。
「どうして、泣くんですか?」
「人は悲しいから涙を流す」その答えには、何処かに哀れみの響きが入り交じっていた。「婆さんが泣くのは、どうして婆さんが泣くのかも解らなくなる程に、お前が変わり果ててしまったからだ。変わってしまう前のお前さんを私は知らんが、婆さんの様子から大体想像は付くさ」
夜更け、扉をノックする音に導かれ、私達は――とはいえ、オルフェとユークァルはもう寝入ってしまったので二人だけで――玄関に立っていた。我々を怖れている筈の人々が、こんな夜更けに町長宅を訪れて来るとは思えない。町長の遣いか、さもなくばムーンブルクの罠やも知れぬ。
三度目に扉をノックした時、私はドアを開けた。
「おお…」月明かりの影に隠された顔から、感嘆の声が漏れた。
「本当に、戻って来られたのですね。お待ち申し上げておりました、ハーゴン様」
「? そなたらは…もしや…」
夜更けの訪問者は、嘗て志を同じくし、私に仕えていた破壊神の神官達であった。
「こいつら何者だ? 知り合いか?」
「知り合いも何も」私は驚愕のあまりに振り向く事すら出来ずにいた。「私と共に破壊神に仕えていた神官達です」
「おい、だったら、こいつらに言っとけ。悪趣味な色使いのローブに妙なマスク、人の家を訪問するつもりならもう少しマシな格好をして来いってな…」お約束の悪態が放って置かれて、竜王はつまらなさそうに突っ立って頬を掻いていた。
「おお、お懐かしや。我々の事、忘れずに憶えておられたのですね」
「風の噂にこの世界に戻られたと聞き、何かお役に立てる事はないかと馳せ参じたのでございます」
「ハーゴン様が亡くなられてからというもの、ロト3国による魔物狩り、残党狩りは熾烈を極め、殆どの者がその命を…」
「我々、ハーゴン様の為ならばこの命も惜しくは御座いません」
口々に協力を申し出るかつての部下達に、私はしかし、語る言葉が思い付かなかった。
だが、私は伝えねばならぬ。8年の歳月を耐えて来た彼等には、余りにも残酷な事実を。
「済まないが、今の私には、お前達の申し出に応える資格はない」
「何故です?」
ああ、彼らは、私に決別を申し渡される為に、危険を冒してまでここに来た訳では無かろうに。
しかし私は、これ以上それを引き延ばす訳には行かなかった。お互いの為に。
「私はもう、破壊神シドーの神官ではないからだ。私は、信仰を捨ててしまったのだ」
言い終えて、皆の顔を見回した。誰も口を開こうとはしなかった。
刹那、激痛が私を襲った。
悪魔神官の手元に閃くナイフ。法衣が血で染まり、二度、三度と追撃が己が身を貫く。辺りが返り血で朱に染まる。周りで、裏切り者! という叫びと悲鳴、怒声が交錯する。
乱闘の様子を映す目の前が真っ赤になり、意識が途切れかけた。
「こら、起きんかバカモン。まだくたばるのは早いわ。全く、虚を突かれたとはいえ、こんな傍若無人を許すとはな。ちょっとは進歩しろ!」
頭を叩かれて目を開けると、私を刺した悪魔神官の一人は既に他の神官達に取り押さえられていた。傷のあった辺りに触れると、傷は完全に塞がれていた。肩を借りて起き上がる。
「貴様、覚悟は出来ておろうな?」
私を刺した悪魔神官はそれには応えずに、恨みがましく私を睨め付けた。「…裏切り者め」
「フン。愚かしい、何時まで過去のしがらみに囚われておるのか知らんが勝手にするが良い。おい、ハーゴンよ。例え貴様にとってこ奴が嘗ての子飼いの部下であろうと、今の我々にとっては敵でしかない。貴様が許すつもりでも、私はこ奴を生かしておくつもりはないからな。良いな?」竜王は私に顎をしゃくって同意を求める。が、立場上、彼等の前で承知したと頷く訳にも、許してやってくれと命乞いをする訳にも行かず、唯気まずそうに下を向くばかりであった。
「ん? まさか、貴様こ奴らにその貧弱な命をくれてやるつもりだったのではあるまいな? いいか。例え貴様がそのつもりだったとしても、この私が許さん」
「な、何と! どういう事だ!」
「黙れ!」
竜王はざわつく悪魔神官達に一喝する。
「良いか、神官共。例えこ奴が過去の下らん負い目の為に、貴様等に生命をくれてやっても良いと覚悟を決めていようが、こ奴の生命は貴様等の物ではない。ましてやこ奴自身の物ですらないのだ。何故だか教えてやろうか? それはな、こ奴は根の国で、私に忠誠を誓ったからだ。なあ?」
「ほ、本当なのですか? ハーゴン様っ」
悪魔神官達の前で、私は頷かざるを得なかった。頷いた途端、勢い良く後頭部を叩かれる。
「ばか、そんな辛そうな顔をして頷く奴があるか。良いか腐れ坊主共、どんなに信仰があった所で、信ずる物がイワシの頭だと判れば坊主やめたくなる事もあるだろうが」
「うぬぬ…貴様、我々の神をイワシの頭だと言うのかっ!」私を刺した悪魔神官の一人が食ってかかる。
「そうでなかったら…いや、私は神なんぞ信じやせぬから知らぬが、少なくとも、奴がそう思わなかったら、この生真面目な頭でっかちが転向なんぞすると思うか?」
神官達は一斉に口を閉ざしてしまった。
「こ奴の事情は知らぬ。別段知りたいとも思わぬ。だが、それがこ奴の決断だと言うのならそれで良いではないか。それとも、お前達の崇拝するのはその何とか言う破壊の神ではなかったのか? 何時から貴様らはこ奴を崇拝する様になったのだ?」
神官達は半ば諦め、観念したようだった。だが、それでも納得など出来ようもないでいる。
「我等は貴男の釈明が聞きたいのではありません」悪魔神官は最後の抵抗を試みた。
「ハーゴン様、貴男の口から理由を、聞きたいのです」
竜王は匙を投げたようだった。「ふん、筋金入りの狂信者だな。好きにしろ」
私は彼等一人一人の顔を見た。彼等は文字通り身を削り、8年の歳月を血を吐く思いで耐えて来たのだ。私がこうやって戻って来なければ、このまま己の信仰に殉じて行ったのだろう。私を刺した神官も、彼を止めた神官達も、私に裏切られたという思いは皆一緒に違いなかった。
そうまでして私を信じて来た、彼らの想いに応えねばならぬ。
だが、私には彼らに応える言葉がなかった。彼等に示すべき『何故』を未だ見付けられていない、というあまりにも貧弱な現実。
「私には解らぬ…思い出す事が出来ぬのだ。何処の忘却の川の水を口にしたのかは解らぬが、何故に信仰を捨ててしまったのか、何故に己の成した事を過ちであると知ったのか、どうしても…。だが、やはり私は誤っていた。たかだかこの世に生を享けた人の子の分際で、どうして世界を裁く事が出来ようか」
こんなにも世界は美しいのに。
「私はその答えを探す為に戻って来た。その答えを探すまでは、私を信じて付いて来てくれたお前達にさえ、この貧弱な命を預ける訳には行かないのだ」
私が失ってしまったあの『何故』を取り戻すまでは。
「今まで良くぞ仕えてくれた。だが、それに報いる事は、今の私にはもう出来ない」
神官達はじっと私を見ていた。これ以上私が言葉を継ぐ様子がないのを見て取って、言った。
「待ちましょう」
「え?」
「待つのは慣れております故。ハーゴン様、貴男がその答えを見付けるまでは。そして、貴男が答えを見付けたその時、我々も、その答えを受け入れるか否かを決める事に致します」
「フン、そう来たか。こ奴らもどうやら、がちがちの教条主義者という訳でもないようだな。おい、貴様はどうする?」
「どうする、と?」私を刺した悪魔神官は訝しげに顔を上げた。
「許す、と言っているのですよ。私の裁量に任せると」私は悪魔神官の手を取った。「もしまだ私を刺して自決しようとしなければ、ですが。ああいうお人ですからね、人に情けをかけたと思われるのはお嫌いなのです」
捨てる神あれば拾う神ありとはよく言ったもので、思わぬ援助が得られる事となった。
地獄の遣い達に情報を収拾させ、我々は市長の屋敷で悪魔神官達と連日対策を練り、また三種の神器に関する謎解きに頭を悩ませ一日を過ごした。
世界の情勢ははどれも芳しいものとは言い難かった。ロトの3国が予想以上の軍を集結させている事。ローレシアが海軍を動かしてデルコンダルに圧力をかけている事。ベラヌール・ルプガナ・ペルポイ・メルキド・デルコンダルを中心とした対ロト3国包囲網とも言える経済同盟が、この間のメルキド制圧とロト3国の妨害工作によって破綻しかかっている事。
だが状況の悪さを思い悩んで過ごすのは馬鹿げている。今の私達には、今の私達にしか出来ぬ事がある。例え四面楚歌でも、必ずどこかに打開策はある筈だ、五体満足で生きている限りは。
「太陽の石はラダトーム王家が所有し、ロトの印はローレシアにあったという話ですから、これら2つの宝は既に3国の手に渡っていると考えて差し支えないでしょう」
「うむ、おそらくはな」
「そして、雨雲の杖もまた、時を経て、再びアレフガルドの雨の祠に封印されていたと思われます。それをルビス様がこっそり持ち出したという事は、それ相応の意味があったと考えるのが筋ではないでしょうか」
「そう言えば」オルフェも口を挟む。「ルビス様がロトの一族に加護を与えたのを悔やんでるような事言ってたよな。雨雲の杖を奴らに渡したくなかったって言ってたし」
「しかし、奴ら、何で今更そんなものを欲しがるのか…」
「雨と太陽が合わさる時、虹の橋が出来る。アレフガルドの古い言い伝えにありました」
「そして魔の島に橋を架けた、と」
「ただの島では無かった。ただ橋を架けるだけなら、幾らでも出来ただろう。確かにあの島は天然の要塞としても超一級だ。辺りの海流は激しいから船では到底近づく事は出来まいし、船を着ける場所も無いほど切り立った崖に囲まれていたからな。しかし」
「結界を張っていたのですね」
「うむ。恐らくは、それを破る為の神器だったのだ、あれは」
「しかしながら、それならば、雨雲の杖と太陽の石だけで充分だったのでは?」
「何故ロトの印が必要だったのだろう」
「そこがどうも引っ掛かる所なのです。…三種の神器には、もう一つの謎が隠されているかも知れません。が…もう少し資料をそろえたい所ですね。今日はこの話題はお開きにしましょう」
とりあえずこれ以上この件について話しても、新たな材料が出て来なければ事態の進展は無いだろうという所に落ち着いて、我々は次の議題に移る事にした。
「ハーゴン様、来客が」
地獄の遣いが会議の最中に私を呼びに来た。
「来客?」
「お前、悪魔神官ども以外に心当たりでもあるのか」
「…いえ」
何やら玄関の方が騒がしい。階段を下りると、玄関で誰かが悪魔神官達ともみ合っている。
「どけ! 貴様等邪教の輩に用はない!」
「い、いけません、困ります!」
「お引取りを!」
「お願いです、兄に、兄に会わせて下さい」
悪魔神官達を押し退けて、二人の人影が乱入してきた。何処か懐かしい…見覚えのある顔。
その二人は、私には馴染みの深い、竜人族の若い男二人であった。
「あ、ああっ、アーロンにザーゴンっ」
「ん、何だ、お前の連れか?」
青いローブに身を纏った、こうもり耳の竜人族がつかつかと歩み寄ってきた。彼らに会うのは何年ぶりになるだろう。私は懐かしさが堪え切れずに、階段を下りて駆け寄った。
「あ…アーロン……」
「一族の恥さらしが、良くもおめおめと帰って来れたものだな!」
蒼白い肌の従弟は眉間に皺を寄せ、再会の挨拶の代わりに細い拳で私を殴り付けた。
「貴様、何をする!」
「止めて下さい!」
寄ってたかってアーロンを押さえ付ける悪魔神官達に向かって、必死に訴え。
「彼は、アーロンは私の従弟です」
「……なるほどな、しかし、お前らも難儀な親戚を持ったものだ」
「…貴男に言われたくはないです。寧ろ、難儀な親戚なのは私でしょうね」
我々は会議室で、椅子に縛り付けられた従兄弟と十数年ぶりの邂逅を果たしていた。
「ああ。皆元気そうで…」
「まさか兄さんと、生きて再び出会えるなんて……」
「その御陰で、こっちは偉い迷惑を被って居るんだ」従弟の口振りは悪意に満ちていた。
「解ってる」解り過ぎる程解っている。
「解っているものか」アーロンは噛み付いた。「いいか、我々の一族が、お前一人の御陰で迫害を受け、どれだけ形見を狭くして暮らしている事か、お前には解るまい」
「まあまあ…アーロン、そんな事を言う為に来たんじゃないだろう? とにかく、私は兄さんが戻って来てくれて、素直に嬉しいと思ってます」話す時に相手の目を真っ直ぐに見つめ返す処は、ちっとも変わっていない。聞きたい事言いたい事多々あろうに、触れずにおいてくれる弟の気持ちが私には嬉しかった。
「兄さんって、お前、ハーゴンの弟なのか? 確かに良く似ておるが」
「ええ。生憎と似ているのは顔だけで、兄には遠く及びませんが。兄は昔から頭脳明晰でしたから。私は随分と誇りに思っていたものです」
「へぇ〜、兄弟がいたんだ。オレ、初めて聞いた」
「ええ、私は破壊の神に身を捧げると誓った時、一切の現世の縁を切ると誓いを立てたのです」
「ふーん、そっか。坊さんって大変なんだねー。なんかオレっちには出来そうにないや」
「いや、そう言うわけでは…」
「ああ、お前みたいな悩みの無い奴には一生無理だな」
竜王の悪態を真に受けて、オルフェはふてくされて「じゃあガキは会議に参加しちゃジャマだよな!」と会議場から出て行ってしまった。と思いきや、オルフェはすぐに誰かに押される格好で会議場に戻ってきた。
「なんだ戻って来たのかガキ」
「ち、違うよ。出て行こうと思ったらさあ…わ!」オルフェは全てを言い終わる前にあっさり押し退けられ、デルコンダルに情報収集に出していた筈の地獄の遣いBが入れ替わりに部屋へ押し入った。
「ハーゴン様、大変です!」
「何事だ、騒がしい」
「またか。今日は色んな連中が来るな。今度は何だ?」
「実は…その、デルコンダル国王が崩御しました!」
「何と!!」
地獄の遣いの乱入に、会議の場は騒然となった。軍事的に匹敵しないまでも、三国に対抗しうる数少ない国であるデルコンダル。その国の王が崩御したとなれば、我々のみならず世界的にも大ニュースだ。
デルコンダル先王といえば、ローレシアの度重なる軍事的圧力に対して、常にのらりくらりとどっちつかずの態度を取って来た。即位する新王に、各国が態度を表明するよう求めるは火を見るより明らか。新王が果たして、親・ロト三国派なのか、それとも反・三国派であるのかによって、世界の勢力図は大幅に塗り替えられてしまう。どう転んでも世界の情勢が大きく動き出す事には違いない。
「新国王にはナリーノ王太子が即位しました」
「喪にも服せずにか!」
「国の情勢が情勢だそうですので、この際そんなヒマはないそうで…」
そこまで言い終えると、地獄の遣いは声のトーンを一段階落とした。
「世間では、先代国王は何者かに暗殺されたという専らのウワサです……」
「どうした、地獄の遣いB」
私が次の言辞を促すと、地獄の遣いは更に声のトーンを一段階落とした。
「…実は、私…新国王からの信書を受け取っておりまして……これを…」
「新国王からの信書? 私宛てにか?」余りに突然の事で、俄かには信じ難い。いいや、もし地獄の遣いが言う『ウワサ』が事実であるとすれば、そして、その黒幕が…いや、よそう。これも邪推に過ぎぬ。だがしかし、何の為に…?
「は、はい……」
「どうした、覇気が無いな」
「そのう…」地獄の遣いは、もぞもぞと決まり悪そうに口篭もった。
「信書と共に、新国王も……」
「は? …!」
地獄の遣いの背後には、その背中にボウガンを突き付けた若い青年の姿があった。
「どうも〜。ボクが皆のアイドル、デルコンダル新国王、勇者ナリーノだ。よろしく☆」
「何もんだ? 貴様、おつむ大丈夫か?」
竜王があきれ返って言った。ナリーノの格好は、自称勇者で国王を名乗るにはあまりにも奇天烈な代物だったのだ。
肩まで伸ばした金髪をくりんっくりんの縦ロールに巻き、小脇には、長い牙を伸ばしたピンクのネコ科動物の剥製を抱えている。戦うにはあまりにも意味無くヒールの高いブーツは、白の、イミテーションの宝石を
鏤めたエナメルの靴部に透明のビニール部を組み合わせ、そこからは何重にも重ねられた銀糸の刺繍入りレースの靴下が透けて見える凝った造りだ。金糸で刺繍を施した黄緑色のシルクのスーツの上にこれまた鮮やかなグリーンのベストを着込み、その胸元には「ナリーノ」と書かれた名札を付けている。スーツは後ろを燕尾形にカットし、ポケットには黄色のニコチャンカンバッチ。前はバックルが見えるようにわざとボタンを外し、腰には細身のサーベルと鞭が下げてある。そのベルトから更に皮製のガーターベルトを装着し、小型のナイフを何本も仕込むという具合だ。これで全身黒ならまるで暗殺者だが、どちらかというとチンドン屋、というのが彼の出で立ちを一言で言い表すのに相応しかろう。
更に、スーツの下には筋肉質の下半身を誇示するかのように黒皮のボディスーツを装着し、それだけ着込んだ上になお、鳥の翼を模した鮮やかな空色のマントを羽織る。マントを固定する為の留め具には、無数のメレダイアに囲まれた拳大のイミテーションルビーに意味の無い金のモールがごてごてと取り付けられ、広い額にはそれを誤魔化す様に勇者定番グッズのゴーグルを装着していた。背後には薔薇を持って待機する黒子が二人付き従っている。くんと鼻を鳴らすと、オリエンタル系オー・デ・パルファンのきついミドルノートの匂いが鼻を突く。はっきり言って付け過ぎだ。
「…この方が、本物の、デルコンダル国王、ナリーノ様です…」
「ううっ、嫌過ぎる…」
地獄の遣いBの言葉に、私は眩暈を覚えた。
「あんまりカッコ良すぎて目が潰れそうだった? オッケーオッケー。サインは後でね」
ナリーノは愛想良く笑って、周りに手を振った。
「ゆ、勇者と言うよりはむしろチンドン屋…」
「やだなあ、伊達者って言ってよ。今年のベストドレッサー賞狙ってるんだから。ポイントは右耳のスライムピアスね。左につけるとモーホーになっちゃうから注意☆」
「逆だ」竜王が呟いた。
「え!」
「逆だと言ったのだ。勇者の印は左のピアスだ」
「え?! ホントホント? ねえ、それホント??」
その意味を知っている者達は、皆無言で頷いた。ナリーノは顔を真っ赤にし、慌ててピアスを付け直す。
「チクショー、城の連中知ってて黙ってて影で笑い者にしてやがったんだな…。城に帰ったらお仕置きしてやる〜! っと、そんな訳で、改めて自己紹介。ボクは勇者ナリーノ、コンゴトモヨロシク」
ナリーノの差し出した左手を見て、竜王は、手を差し出す代わりに、億劫そうにその手を指差した。
「人に握手を求めるなら、手袋くらい外せ。それと、握手は右手だ」
「…んまあ、社交辞令はおいといて、単刀直入に行きましょうや」ナリーノは何事も無かったかのように指し出した手を引っ込める。「今日、自らこちらに出向いた用向きをば」
ナリーノ王は、掘り出し物を探してウィンドウに並べられた商品を品定めする目利きのように、正しく舐めるように我々の顔を見回した。その様子から察するに、ウィンドウの中は宝の山らしい。
「貴男達ムーンペタで孤立してるんでしょ? ボクの助けが必要なんじゃないですか?」
「は? 何を申しておる。見てくれ同様頭の方も相当キておるようだなこのトンチキが。そもそも貴様如きと組んで、我々に何のメリットがあるんだ?」
「心配御無用!」ナリーノは竜王の嫌味を無かった事みたいに無視して、自信たっぷりに答えた。
「おつむも大事だけど、勇者を自称するからにはそれに見合う実力が無くてはね。この世界じゃ、ボクの事は、力はローレシア王の次に強く、素早さではサマルトリア王の次に素早く、魔力ではムーンブルク女王の次に長けていると専らの評判で…」
「なぁんだ、みーんな中途半端なんじゃん」
痛い所を突かれて、ナリーノはオルフェを睨み付けた。
「うぉ、うぉっほん! ボクの国デルコンダルは、その地理的関係から、常にローレシアの武力に脅かされてきた歴史があるんですよ。貴男達が世界を滅ぼすとか何とかやってる内は、まだ奴らも大人しかったんです。でも、ムーンブルクが復興してからはとうとう本性を現わして…。奴ら野蛮人です! 僕らは由緒正しい代々の王家ですけど、奴らたかだか百年あまりの成り上がり勇者の王族じゃないですかっ。武力を以て我が国を脅かしたのはいうまでもないですけど、奴らはボクの、ボクのただ一人の友達、キラータイガーのジョンを、ジョンを、月の紋章欲しさにいたぶり殺したんだぁーっ! クソーッ! 奴らも奴らならオヤジもオヤジだーっ! ジョーーーーーーーーーーーーーン!!! インマイハアアアアァッ!」ナリーノは目に涙を浮かべると、小脇に抱えていた剥製を固く抱き締め、空いた手で天に向かって拳を振り上げた。
「貴様…」
「何です?」
「キラーパンサーのゲレゲレしか友達がいなかったのか…」
「キラータイガーのジョンですぅっ!」
「トンヌラにゲレゲレかー、まるで動物園みたいだね」オルフェがカラカラと笑う。
「チクショー! ボクのジョンをあんなマヌケ野郎と一緒にするなーっ!」
二度までも人前で取り乱した所を見られて、ナリーノは慌てて話を戻した。
「と、とにかく…ボクは保障が欲しいんですよ。今のままではロト3国連合プラスアレフガルドに対抗しようという国はデルコンダル一国だけ、ベラヌール・ルプガナ・ペルポイとの経済同盟も奴らの撹乱戦術のお陰で破綻仕掛かっていて、メルキドが落ちた今、このままでは奴らもロト一族に屈してしまいかねません。確かにボクは最強勇者ですけど、ボク一人の力だけでは人々の心を動かすには不十分です。例え巧く立ち回ったとしても、後からぶすっ、てやられちゃお仕舞いですからねー」
「人望なさそうだもんなー」オルフェが聞こえないように私に囁く。
「と、言う訳で、ボク達と貴男方の利害は一致する筈だ。どうです、貴男達、最強勇者のボクと組んで、あのムカつくロトの一族を一緒に滅ぼしませんか?」
「なんだそりゃ。魔王と手を組む勇者など、見た事も聞いた事もないわ」
「チッチッチッ、やだなあ。これからの時代、勇者も魔王もビジネスですよビ・ジ・ネ・ス☆」
ナリーノは人差し指を振った。
「これからのトレンドは、人と魔物が共存する世界ですよ? これからはポスト構造主義、脱二元論の時代です。人間vs.魔物、勇者vs.魔王、光vs.闇、ブルジョアvs.労働者、共産主義vs.資本主義。そんな出来合いの対立構造なんてノンセンス、時代錯誤、お笑い草でしかありません。そうでしょ? …ところで、あの、お願いなんですけど、このお嬢さん何とかして戴けませんかね?」ナリーノの背後で、ユークァルが首筋に黒曜石のナイフを突き付けていた。
「ユカ、やめろ。こ奴が敵と判断したら、何時でも合図する。それまでは手を出すな」
「ほう、貴男子飼いの暗殺者という訳ですか、流石魔王と称されるだけの事はある」ナリーノはナイフを引いたユークァルを眺めやり、酷く感心を装ってみせる。
「魔王魔王言うな。自分で言ってるのはありゃ自虐的なレトリックだ」
「おっとこいつは気付きませんでした、失礼。ところで」
ナリーノは振り返ると、ユークァルの義眼をじっくりと見つめながら、お気にいりのオルゴールのねじを巻きでもするようにユークァルの前髪を掻き上げる。
「ユカさんって言うんですか。この娘、義眼なんですね。ボク、この娘気に入っちゃったなあ。どうです、この娘をボクにくれません?」
「ゆ、ユカを物みたいにゆうなあっ! 誰がお前なんかにやるもんかっ!」
いきり立つオルフェを仕方なく宥める事にする。オルフェの気持ちは解らないでもない。デルコンダル王の傲慢な態度を不快に思っていない訳でも、政治的判断の為にユークァルを犠牲にする心算も勿論無い。しかし、四面楚歌の今の我々には、彼の提案は状況を打破する格好の突破口たり得る。それを考慮に入れると、デルコンダル王の性格や真意が今一つつかめない今、露骨な拒絶の態度を取る事もまた、あまり賢いやり方とは言えない。まずは相手の目的を知る事だ。
「あの…気に入る、って、何ですか?」
「ありゃー、こいつぁまいったね」ナリーノは半ば戯けて驚いて見せた
「ほら言わんこっちゃ無い、止めておけ。この娘にはまともな人間の感情なんか持ち合わせちゃおらんのだ」
ナリーノはそれには応えずに、しゃがみこんでユークァルに視線を合わせた。
「ますます気に入りました。よろしい。ユカ、ボクが、キミに気に入るって事が何なのか教えてあげますよ。いいかい、今から何をされてもボクを殺そうとしちゃいけないよ」
ユカは素直に頷く。すると、ナリーノはユカを後から肩越しに抱き締めた。
「今ボクがキミの首筋にナイフを突き立てるか首の骨を折るかしたら、キミは死ぬよね」
「うん」
「気に入るって事は、それをしない事さ。解ったかい?」
ナリーノは、ユークァルの生殺与奪をその手に握り、爬虫類じみた笑みをユークァルに向けた。
「フン、気にいらん」
ユカと馴染んでいるナリーノを尻目に、竜王は一人毒づいた。
「何がですか? 助力が得られただけでも良かったじゃないですか」私は気のない返事をした。
「饒舌に過ぎる。あ奴、ぺらぺら喋る割に、結局手の内は一切明かさず終いだ。それに…巧く言葉では言えんが、あ奴の目、何となく気にいらんのだ、何となくな…」
賄いの老婆が地獄の遣い2名を引き連れて、ぴったり三時に紅茶とお茶受けのブルーベリータルトを持ってきた。地獄の遣い達をこき使っていいと申し出たにもかかわらず、この老婆は自分の眼が黒いうちは台所の事に口出しはさせじとばかりに、厨房には終ぞ一歩も連中を通さなかった。今この屋敷に十人は常駐している事を考えると、彼女の負担は何時に増して大変なものであるに違いないのに。
「あらやだね、4人も増えてるのかい」老婆は困った様子で辺りを見回した。「お茶請けの余分が無いんだよ。クッキーでいいかい?」
「あ、おばあさん、お気になさらないで」ナリーノは作り笑いで愛想良く応えた。「ボクはちょっと早いお茶してきたところですし」
「そうかい、悪いねえ。でもまあ、お茶くらいは飲んでお行きよ」給仕を住ませて老婆はさっさと台所に引っ込んだ。ナリーノはお行儀良く他の悪魔神官達と席を並べていたが、隣の地獄の遣いの席に目を向けた。視線の先には老婆がこしらえて切り分けたばかりのブルーベリータルトが鎮座する。
「おや、このタルト美味しそうだな」
「差し上げます…」目だけは笑っていない笑顔で威圧され、地獄の遣いは進んでナリーノにタルトを差し出した。
「ではお茶にするか」竜王は一杯目の茶をとっとと飲み干し、タルトの攻略に取り掛かる。「…うむ、こいつは素晴らしい」
「え、ホント? どれどれ…むぐむぐ…わ! おいちーい♪」
「ま、まあまあ美味しいほうかな。うちの城の料理人の方が上手いけど」
皆は口々にブルーベリータルトを褒めちぎった。酸っぱ過ぎず甘過ぎず、ブルーベリーの旨味を凝縮した具とそのブルーベリーを引き立てるしっかりした台、そしてその程好い焼き加減。これだけのタルトを焼けるとは、確かに40年もの間町長の家に仕えて賄いを取り仕切ってきただけの事はある。これだけのものを作るのだから、地獄の遣い達を台所に入れたくないと言うのも解ろうというものだ。そんな中、唯一人タルトを頬張ったユークァルだけが神妙な顔つきで首を傾げている。
「ユカ、三時のおやつの時間くらいはそんなつまらなそうな顔をするな」
ユークァルは首を僅かに横に振ると、お茶を飲んで、それから意外な事を言った。
「このタルト、昔、食べた事あります」
「何だと? ふむ、となるとやはりバアさんの言った事は本当だったのかな? とにかくもっと喰ってみろ」
竜王は悪魔神官達のタルトを取り上げると、ユークァルの口に次々タルトを放り込む。口一杯にタルトを詰め込まれ、ユークァルは餌を食べ過ぎたハムスターみたいに頬を膨らませてもぐもぐやっている。どうしても喉を通らない分を無理矢理お茶で流し込まされて、ユークァルは大きくげっぷをした。
「思い出したんです。あたし、昔、この家に住んでました」
「何だと? と言うことは、お前、元町長とやらの娘だったという事か?」
ユークァルはそれには答えずに、ベランダへ通じる扉を開けて出ていった。私達もそれに続く。
「あそこの庭にある木は、春になると黄色い花を付けてたんです。それに、この樋。よくお兄ちゃんと一緒に登っては、お母さんに叱られてました」ユークァルはその樋を、毎日登っているかのように器用によじ登った。
「この風景、ちっとも変わってません。お兄ちゃんはもう居ないけど」
ああ、あの夢に出てきた少女は、幼いユークァルだったのか。
ユークァルはいつもと変わらなかったが、私には、初めてユークァルが笑った時の顔が想像できた
「へえ、ユカちゃん、昔この家に住んでたんだってねえ。っていう事はムーンペタ前町長の関係者って事になるのかな?」と、我々がベランダを見下ろしていると、ひょっこりナリーノが顔を出した。ナリーノの地獄耳ぶりには驚きを禁じ得ない。
「さ、さあ」私には思い当たる所があった。もしも彼女が更迭された前ムーンペタ町長の孫娘なりなんなりであるとしたら、これは大変な事になる。そうであったなら、彼女はこの世界の情勢を動かす鍵として、否応なしに表舞台に立たされる事にもなりかねない。
「もしそうだとしたら、貴男達にとっては大変なメリットじゃないですか」ナリーノはにやにやしていた。「だってそうでしょ。彼女がもし前町長の孫娘なら、貴男達は町長の後継者として、自らのムーンペタ居住の正当性を世界に主張できる大義名分が立つんですからね〜。今の…追い出された町長、評判良くなかったらしいですしね〜」
「ど、何処でそんな話を」
「賄いの婆さんが下で愚痴ってましたよ。ユカさんが前の町長のお孫さんだったらどんなに良いだろうってね☆」
「関係があるか」竜王は鼻で笑う。「どう転んだところで、人間共が我々に好意など抱くものか。この娘が昔の町長の孫だか何だかだったとした所で、却って反感を買うだろうよ。この娘をこんな風にしてしまったのさえ我々のせいにされかねん。現に、既に兵士の首をねじ切って一人殺したからな。まあ…ナリーノよ、貴様もせいぜい私を利用しようなどと無駄な試みをしてみるが良い」
そう言い捨てると、竜王はとっとと部屋に戻ってしまった。
「ほほう」ナリーノは獲物を捕らえる際の爬虫類じみたあの視線で竜王の背中を追った。「つまり、取りあえずはボクに協力してくれるって事ですね? いいでしょう、ボクの政治手腕をみせてあげますよ」
ナリーノは振り返りざま、私の手を取って強く握り締めた。
「では、早速ですが、明後日にデルコンダルで経済同盟の会議があるんですよ。是非出席願いますネ☆」
* * *
私達がナリーノに乞われて経済同盟会議の席上に現れた時の第一印象は、しまった、はめられた、だった。我々がこの席上に呼ばれたのは、彼らに無言の圧力をかける為のナリーノ王の策略だったのだ。同盟都市の代表達の強張った表情からも、その事は明らかだ。
「どうします?」私は素早く耳打ちした。
「どうするって、いるしかあるまい」竜王は実にめんどくさそうにいらえを返した。
会議が始まってすぐ、デルコンダルの大臣が、血相変えて会議の席に入って来るなり、ナリーノに駆け寄って素早く耳打ちした。ナリーノはそれを聞き終わるや否や、同盟都市の代表連に向かってしばらく席を外す事を告げて会議室を去った。
ナリーノが席を外した途端、黙していた代表達が陰口を叩き出した。
「デルコンダルのナリーノ王太子と言えばキチガイで有名じゃないか。そんなのが王になった国とこれ以上同盟を続けていくよりは、いっそロト3国に従った方がまだましでは」
「ナリーノ王は魔族と通じているという専らのウワサですし」
「歌姫アンナの追っかけで、王太子としての職務を放棄していたとか」
「マリア王女の等身大人形を、金に糸目を付けずに作らせて部屋に飾っているとも聞きますし」
「あげく若い娘を高値で買って、剥製にして地下室に飾っているらしいですよ!」
「その上魔王と取引をするなんて、正気の沙汰じゃないですよ」最後の一言は、聞こえよがしに。ナリーノ王の戦略は、却って逆効果になってしまった様に思われた。
が、代表達の言いたい放題が一段落するや否や、堅く閉じられていた蒼い瞼が持ち上がり、金の瞳が姿を現わす。眼球だけが油断無くテーブルの端から端まで動いて一同を見回し、一つ瞬きを落した。寝たふりなど決め込んで殆ど無関心を装っていたと思われた竜王が、実は先程まで自分達を監視していた事に気付かされて、代表達は我々を怒らせたのではないかと表情を強張らせた。
「良いかな? 発言しても」代表達は無言で首を縦に振った。
「私は今まで貴様等の言う事に口出しはしなかった。こんな糞退屈な会議なんぞに在席するつもりも無かったからな。貴様等が私に怖れを抱いている事位はよくよく承知。故、見られていると思えば言いたい事も言えなかろうと狸寝入りも決め込んだ。だが、言わせてもらおう。私はあの時から、この世界の覇権などというものに関心はなかったし、今でもそれは変わらん。貴様等が何百人何千人死のうが私の心は痛む事はないし、逆に言えばちっとも嬉しくもない。貴様等がナリーノに付こうがロト一族の支配を甘んじて受け入れようが、知った事ではない。序でに言えば…と言うよりは此方が本筋だが、別にあのバカと取引なんざしちゃおらん。勘違いして貰っちゃ困る」言い終えて、一つ欠伸を零す。大きく開いた口から僅かに覗いた牙は、手を当てて隠しても人々の威圧感を削ぐには至らない。
「そ、そんな事信用できるか」ベラヌール代表が机を叩く。叩いてから、反響の大きさに怖れ戦いて身体をちぢこませる。
「信じようが信じまいが好きにするが良い。だが、ロトの3人組の言う事なら信じられるのか? 人間だからか? 人間だったらナリーノでも信頼に足ると言えるのか? 信用に足らんのはどちらも同じだ。より重要なのは、どちらに付けばより安全に、より多くの利益を得る事が出来るか、一時の利益でなく、より長期にわたって、そして将来的に優位を得る事が出来るか、だ。どちらに付くのか、若しくはどちらにも付かないで漁夫の利を得ようと隙を伺うのか。貴様等も一国の代表なら、もう少し図々しく、私やナリーノを利用する位の事は考えても良いのではないか?」
「り、利用するだと?」ペルポイ代表が口を開いた。「逆に利用されて酷い目に合うのが落ちじゃないのか」
「そうなったら貴様等の才覚が足りないというだけの話だ。あのアホンダラ国王にそれだけの才覚があるかどうかはさておき、あの図々しさ位は見習う余地があるのではないか? 発言は以上だ」
竜王は言い終わるなり、誰もこの場に居ないかのように再び瞑目した。まるで、ここに居る誰にも、自分が決して傷付けられる事も、その存在を脅かされる事も無い、とでも言いたげに。
しばらくして、ナリーノ王子がにこにこしながら会議の席上に戻ってきた。
「お待たせしましたー」
「壁の向こうで盗み聞きか。良い趣味だな」ナリーノはそれには応えずに、議長をしっしと追い払って壇上に立ち、どんと机を叩いて一席ぶち上げた。
「パンパカパーン! 皆さん、大ニュースです。ローレシアの海軍がこの会議に圧力をかける為、デルコンダルの海域に兵を集結しているそうです!」
会議の席がざわついた。当然の事だ、軍事大国ローレシアが初めて本格的な動きを見せたのだ。
「いい機会です、皆さんは安全な所でボクの実力を見ていて下さいね。ウチの国が滅んじゃったら、その時は、幾らでもローレシアに投降してくださいよ。さ、お前達、皆さんを安全な所に送り届けて差し上げろ」
代表連が会議室を退席した後、ナリーノが駈け寄って来た。
「流石は! やはりボクのカンは間違ってなかったですよ! ホントに協力を申し出て良かった。しかし、実に凄い洞察力です。良く解りましたねー、正面の鏡がマジックミラーだって」
「なあに、あてずっぽうさ」竜王は少しだけ肩を竦めた。
デルコンダルの人々は皆、城を捨てて着の身着のままで南の森に避難していた。ナリーノは森に到着すると、お供を傅かせてずんずんと人の間を割って進み、適当な木の切り株を台に見立てて上に登るや一席ぶった。余程演説の類が好きと見える。
「やあやあやあ、遠からん者は音にも聞けってな具合で、親愛なるデルコンダル臣民の皆さん! 今デルコンダル王国は、暴君率いる軍事大国ローレシアの脅威によって、建国以来未曾有の危機を迎えております。ローレシアは、祖国デルコンダルが彼らに屈せず、寧ろ我々の経済同盟を強化して彼らに対抗しようとする様を快く思わず、暴力を以て我々の自由と権利を奪おうと攻め入ってきたのです。何という恥知らず、何という野蛮人でしょうか!」
ナリーノは一息入れて親愛なるデルコンダル臣民を見回したが、突然退去命令を出され追い立てられた人々がそんな演説を白けずに聞いていられる筈も無かった。望んだ反応が得られなかったのを悟ってか、今まで口にした事が何の核心にも触れていないかのような面構えで――いや、実際そうだったのだが――ナリーノは演説の続きに戻った。
「しかし、我々は彼等には屈しません!」
ざわっ、と人々の波が動いた。
「たかだか建国百年あまりの野蛮人の国に、祖国デルコンダルを明け渡すわけには行かないのです! 良いですか皆さん。我々は、彼等に屈して引き下がる訳にはいかない三つの訳があるのです。まず一つは、我々が彼等に対して軍事的圧力をかけられるべき如何なる云われもないという事。次に、我々には十分な勝機があるという事。そして、最後に、ここ、デルコンダルこそが、我々にとって唯一にして最高の祖国だからであります!」
「勝機があるだって?」人々の中では、三つの理由の最初と最後は完全に黙殺されていた。当たり前と言えば当たり前だが。
「おっと、お疑いの方々もいらっしゃるでしょうね、当然です。何せ、ローレシアと言えば世界中にも類を見ない軍事大国。デルコンダルも決して引けを取るとは思いませんが、それでもやはり分は悪い、というのが常識でしょう。普通に戦えば。しかし我々には、知恵と勇気、力強い援助、地の利、そして何より愛国心があるのであります! 優れた戦略と愛国心は、数万の兵に勝るものであります!」
「えん…じょ?」
「援助なんかあるのか?」
「何処の国の軍隊だ?」
「ふっふっふっ…では皆さんに、皆さんを守ってくれる心強い友を紹介します! さあどうぞ」
ナリーノが草むらを指差すと、藪からスライムがぽこぽこ飛び出した。ホイミスライムにスライムつむり、はねスライムにドラゴスライム、珍種のキングスライムやメタルスライムまでいる。一度にここまで揃うと、弱いはずのスライムでも中々壮観だ。
「この魔物さん達は皆さんを傷付ける事はありません。それどころか皆さんを守ってくれるんですよ。ほら、ボウヤスライムさんに触ってご覧」ナリーノはスライムを抱えると、子供の手を握ってスライムを差し出した。が、子供は手を振り解こうと暴れ出す。
「さわるなよナリーノ! キチガイが感染るだろッ!」
「…イケナイなあ、一国の王に向かってそんな事言っちゃあ」
口元だけ笑った様な形を作って、ナリーノは子供の頬を酷く抓った。子供は泣き、母親は睨み付けたがナリーノは涼しい顔を決め込む。
「スライムばっかり居たってどうするんだよ!」
「向こうはロトの勇者だぞ! かなう訳ないじゃないか!」
「まあまあ」ナリーノは次々に飛ぶ野次を軽く受け流した。「ローレシアの兵士全てがロトの勇者様みたいに強い訳じゃあありませんよ。それに、あくまでも、彼等はあなた達を守ってくれる、いわば防波堤みたいなものです。心配しないで下さいよ、策はありますから。さ、メイジバピラスさーん、こっちへどうぞ」
ナリーノが宙に向かって呼び掛けると、森の中から待機していたメイジバピラス達がぎゃあぎゃあ言いながら、、一匹、また一匹と地上に下りて来た。20匹は下らないのではないか。
「彼らが我々の直面する危機を救ってくれる心強い味方です」
「こいつらがローレシア軍と戦ってくれるのかよ…」
「いいえ」ナリーノはきっぱり言い切った。「直接戦えば確かに勝てるかも知れませんが、それではこちらの被害も大き過ぎます。それに、そんな勝ち方をしても、次にローレシア軍が来た時対処出来ないではありませんか。我々が勝ち取らねばならない勝利とは、敵に対する絶対的大勝利に他なりません。そうでなければ、彼等の侵略を防ぐ事は出来ないのです。まあ、見ていて下さいな。デルコンダル王、未来の英雄が、野蛮な軍事大国化から臣民を守るべく一世一代の計略を仕掛ける様を! とにかく」
ナリーノはここで初めて、群衆一人一人の目をじっと見据えた。
「皆さんは、黙って状況の推移を見ていて下さればいいのです。努々自らを、一時の恐怖に駆られて売国奴と化すような馬鹿げた真似だけはしないで戴きたい。ボクの話は以上です。では!」
ナリーノは切り株からポーズを決めて軽やかに飛び降り――と言っても切り株はせいぜい30センチくらいの高さしかないのだが――人々の方を振り返って子供に諭すよう人差し指を立てた。
「じゃ、皆さんは絶対に森から出て来ないで下さいね。ボクは最後の仕上げにかかりますから。どうです、お二人さん、見に来ますか?」
「ふむ、良かろう。お手並み拝見と行こうか」
「ダメです、使者が戻ってきません」
「そっちがその気なら、こちらとしても手荒な手段に訴えるしかあるまいて。よし、半数は船上で待機し、いつでも出航できる様準備せよ。我々は正面からデルコンダルを制圧する。出発だ!」
将軍の命令でローレシア軍がデルコンダルの街中に向けて進軍を開始すると、城下町はおろか城内までがもぬけの殻であった。
「人っ子一人居ませんね」
「家財道具も一切合財引き払ってますよ。手際の良い連中です」
「フハハハ、恐れを成して退散したか! よし、城内を制圧せよ!」ローレシア軍の将軍は、手柄を確信して嬉しそうに命令を下した。
「あれがローレシア側の将軍ですよ」城の尖塔で昼食用に出されたサンドイッチを頬張る竜王に、ナリーノが紅茶と一緒に望遠鏡を渡す。
「いや、無くとも見える。…あ奴、あまりおつむ良さそうには見えんな。貴様相当見くびられておるぞ。むぐむぐ…それにしてもこのサンドイッチ旨いな。このピクルスが良い」
「でしょ? うちの城のシェフ優秀ですからねー。オヤジがグルメだったんでこういうところには金かけてるんです。モグモグ…だからここでガツンとかましてやるんですよ。ふふふ。見てろよアイン、ジョンの仇を討ってやる」
「確かに美味ですね…。しかし、我々がここに居る意味は何かあるんですか?」
「勿論!」私の問いにナリーノは即答した。「一つは貴方達に、ボクが役に立つ男だって事を解ってもらう為。もう一つは、世界中にデルコンダルと貴方達が正式に手を組んだって事を知らしめる為。そしてもう一つは」ナリーノは黒胡椒をたっぷりかけた厚焼き玉子とローストビーフのサンドイッチを頬張った。
「ボクの身の安全の為ですよ。な、バッピー」
メイジバピラスがナリーノに頭を撫ぜられて、ぎゃあと一声鳴いた。
さて、我々が昼食用に饗されたサンドイッチを片付け終わるころには、ローレシア兵達はデルコンダル城内をあらかた制圧してしまっていた。ナリーノはその様子を確認すると、ピイッと一回、人には聞こえない笛を鳴らした。
すると、何処に潜んでいたのか茂みの奥からリビングデッドが数体、もぞもぞと正門の方に歩いて行くのが見えた。残りのお茶を全部飲み干したころにリビングデッドが帰って来たのを見計らって、ナリーノは尖塔からテラスへと飛び降りると、ローレシア兵の前に颯爽とに着地した。
「ヤーッホー! ローレシア野蛮帝国よりの皆様、我が高貴にして洗練された文明の地、デルコンダルへようこそ!」
「き、貴様ナリーノ王太子、いやナリーノ王! ローレシアにかなわぬとあって、とうとう観念したか!」
「うひゃひゃひゃひゃ!」ナリーノの侮蔑に満ちた哄笑が場内に響き渡る。
「まっさかー! そんな訳無い無い。ただ君等ローレシア軍にはね」ナリーノはあの爬虫類的な笑いを見せた。「アインの奴に、ボクの本当の恐ろしさをちゃあんと伝えてもらわないといけないんで」
「何をぉ! 何処から見ても貴殿に勝ち目など無いではないか! 観念せい!」サーベルを振り回すちょび髭の将軍を相手に、ナリーノはどこから見ても余裕綽々のていである。
「そうかな?」
将軍が弓兵にナリーノの狙撃命令を出すより前に、ナリーノは例の笛を二度鳴らした。
「ヨシ今だ、バピラス君Go!」
ナリーノが笛を吹くと、油壷を抱えたメイジバピラス達が次々森から飛び出した。メイジバピラスの群は整然と隊列を組んで真っ直ぐローレシア海軍の船に向かって飛んで行き、上空から実に正確に油壷を船の上に落として行った! バピラス達は一通り油壺を投げ終わると、船に向かって一斉に炎を吐いた。木製の軍艦は次々炎に飲み込まれて行く。
「ギャー! 我が軍の船が〜っ!」
「ウヒャヒャヒャヒャヒャ! あーっはっはっはっは! あーおかしいサイコー!」
「ぬぬぬぬ…よくもやってくれたなナリーノ王! だが貴殿を討てば、わしらの勝ちじゃあ! 討て、討て討てえええ!」
「ボクがどうして一人でのこのこと、大勢の敵の前に現れると思うかなー?」
ナリーノが下から私達を手招きしたので、私達はローレシア兵の前へ進み出た。兵士達の狼狽が明らかに伝わってくる。ローレシアの将軍が顔色を変えた。
「ゲーッ! た、退却、退却だあ!」
「将軍無理です、正門が何時の間にか閉められてます!」
「ぬわにい?!」城内に閉じ込められたローレシア兵はパニックに陥っていた。
「くっ、と、統率が取れん!」
「そいつは大変で。じゃ、ボクはここで、ばいばーい☆バッピー、僕を連れてってくれる?」ナリーノはメイジバピラスの足につかまって中に浮いた。「貴男達も出来る限り早くデルコンダル城から脱出なさい」
ナリーノの言うがままにかなり高くまで飛ぶと、ナリーノは例の笛を短く、強く三度吹き鳴らした。
数秒後。
足下のデルコンダル城は、数百のローレシア兵もろとも木っ端微塵に吹き飛んだ。
「火薬ですか…トンヌラ王も使ってましたね」
「ふむ、言うだけあって見事な戦略だ」
「お褒めに預かり恐悦至極」ナリーノはメイジバピラスにつかまったまま、上流階級特有の仕草で一礼した。
民衆の元へ戻ったナリーノ王は、一躍英雄扱いとなった。その手際の鮮やかさ故に、誰もがナリーノを褒め称え、国の救世主に祭り上げた。
彼を祭り上げたのは、何もデルコンダルの人々だけではなかった。都市経済同盟の代表達は次々にデルコンダルに有利な条約更新を約束し、自分の国へと帰っていった。
「どうです? ボクは役に立つ男でしょ?」ナリーノはにやにやしながらにすり寄って来た。
「どうしたも…貴様はこれでもう満足なのでは無いのか? 自分の国も守れたし、これでロト三国の連中は、デルコンダルを警戒して当分は手を出して来はしまい」
「ボクを不義理者にさせないで下さいよ」そういう言葉が己には全く似つかわしくないのだという事に、本人はまるで気付いていないように見えた。「貴方達二人が居なかったら、今頃ボクは生きてやしませんよ。貴方達の御陰でボクはこの国を守れたんですからね、ボクにとっては大恩人も同然です。出来る限りの事はさせて戴きますよ」
その夜、木っ端微塵に吹っ飛んだデルコンダル城跡にて、簡単な勝利の宴が行われた。
破壊された筈のデルコンダル城を見て回って解ったのは、破壊されたのが実は城の一部でしかなく、本丸はほとんど無傷で済んだ事だった。ナリーノはあらかじめ壊しても良い部分を知っていて爆薬を仕掛けたに違いない。畏るべき戦略家だ。おそらくは暗殺された前国王の手で、いやもっと以前より、この城はその可能性を考慮して作られていたとは考えられるが。
私達はナリーノが常々自慢していた城のシェフ達が腕を奮う料理に舌鼓を打ち、美酒を振舞われた。空は吹き抜けで星が見えたが、そう寒くは感じなかった。気候のせいなのだろう。他の客達も同席していたので、我々は大人しく末席に座して(ナリーノは私達に上座に座るように再三頼んだのだが、私達は固辞した)他の客を極力怯えさせないように気を使っていた。
食事が終わって席を立とうとすると、門の辺りがにわかに騒がしくなった。兵士達が騒ぎ出し、やがてそのうちの一人が、ナリーノ王に何事かを告げた。ナリーノが兵士に命じると、兵士は門の方に駆出していき、やがて数名の兵士達が物々しい様子で広間に何者かを連れてきた。
連れて来られたのは、ムーンペタで私の帰りを待っている筈の地獄の遣いだった。
地獄の遣いは私の姿を見るや、息も絶え絶えもつれ込んで私の足下に転がった。
「は、ハーゴン様…ロト3国連合軍が。ムーンペタに向けて進軍を開始しています。すぐお戻り下さい」
「奴ら、我々がムーンペタを離れたのを知って、制圧しにきおったか」
「早く戻らないと部下達が…ユカやオルフェも残してますし」
「待って下さい。こちらへどうぞ」ナリーノが、文字通り飛んで帰ろうとする我々を引き留める。
「この国にも旅の扉がありましてね。ムーンペタまで行かなくとも、ムーンブルク国内には通じておりますよ。おっと、同盟を組んだ訳ですから、ボクもお手伝いさせていただきます」ナリーノはこの隙に半ば強引に竜王の手から握手を奪う事に成功したので、竜王はしぶしぶナリーノの手を握り返さざるを得なくなった。
ナリーノの厚意に甘える形で旅の扉を通り抜けると、遥か彼方のムーンペタが、多くの軍勢に囲まれて今にも攻撃を受けんとする寸前であった。
「急がなくては!」
「歩いては間に合わん! 飛んで行くから後から来い!」竜王は翼を広げて駆け出すと、みるみるうちに巨大な竜の姿に変化する。後から付いていっても足手まといになるだけなので、飛び立つ寸前で尻尾に何とかしがみ付く。
「わーん、ちょっと待って下さいようお二人さん!」
ナリーノはあわてて笛を吹くと、メイジバピラスに肩をつかまれて宙に浮く。ナリーノは背中に着地すると、竜王の尻尾に捕まってヒイヒイ言っている私を背中まで引き上げてくれた。
よじ登ったすぐ眼下には、ムーンブルク軍の兵士達が陣を張って攻め込む準備を始めていた。竜王は空低くを滑空していたが、直ぐに高度を落とすと、本陣に向かって突っ込みながら猛然と羽ばたく。翼は凄まじい風を伴にして、ムーンブルク軍の兵士達の真っ只中へ急降下した!
風圧に薙ぎ払われて、ムーンブルクの兵士達は面白い様に転倒する。体制を立て直そうとするはなから強風に煽られて、辺りを転げ回る。旗印も仮テントも吹き飛ばされ、兵士の上に被さって身動きを取れなくした。後方の兵が弓を引き絞って我々を狙おうとするが、放たれた矢も標的に届く遥か手前であさっての方に逸らされる。
竜王は陣の中央にゆっくり着地すると、翼を広げて兵士達を威嚇する。
「ほうれ、かなわぬ事が判ったなら、とっとと退却する事だな!」
ドオン、と海の方から大きな音がして、何かが飛来した。
「砲撃して来おった!」
「そんな無茶苦茶な! 町はどうなっても良いって言うんでしょうか?!」
「威嚇射撃か」ナリーノが言った。「黙らせて来ましょう。ボク変身しますから、思いっきりあっちに投げて下さい」ナリーノは背中から飛び降りると、ドラゴラムの呪文を唱えた。竜王よりは遥かに小さいが、それでも家一軒くらいはゆうにある。それを借りてきた猫みたいに首筋を摘み上げて、軽々と放り投げた。ナリーノは海の方へ飛んで行くと、沖の軍艦に向かって炎の息を吐いて次々と船を沈めて行った。
本陣をめちゃめちゃに荒らされ、海軍を半壊させられたのを見て、ムーンブルク軍は命からがら敗走していった。
「わあっはっはっは、愉快愉快! 楯突いた相手が悪かったな!」
「しかし変ですよ。見て下さい、貴男はともかく、ナリーノ王は殆ど反撃を喰らっていません。これはどういうことでしょう」
「ふむ。確かに、連中殆ど交戦もせず撤退しておるな…待て! あれは何だ! 町中から火の手が上がっておる!」
「あ、あれは魔物達の軍勢では?!」
「しまった! 陽動作戦であったか! すぐに戻るぞ!」
町中に戻ってみると、炎と煙に混じって白い発光体が街のあちこちから上がっていた。その先には魔物達の軍勢と、その首領とおぼしき三つ目のグリュフォンが街を焼き払っている。悪魔神官達がマヒャドの呪文で必死に炎を消して回るが、炎の勢いには到底追い付かない。
屋敷に戻ると、負傷したユークァルとオルフェをちょうど直している最中だった。
「兄さん、それがおかしいんです」
「何がおかしい?」
「魔物達はユークァルを狙って来たんです。そんな事があり得るでしょうか?」
確かに、何故ただの人間であるユークァルを魔物達が狙う必要があったのか、おかしな事には違いなかった。が、今結論を出せる事でも無い。総ては生き残ってからだ。
「今はいい。とにかく、怪我人の治療を頼んだ」
「任せて下さい」
「あ、待って。オレも行く」外に出て行こうとする私達を、オルフェが呼び止めた。「怪我は大した事ないからさ」
「残っててやれ」
「ええ? どうしてさ。オレも戦うよ」一緒に表に出ていくのを止められて、オルフェは唇を尖らせる。
「ユカと一緒に居てやれ。好きなんだろう? 心配するな、我々が何とかする。それより、あいつを守ってやれ。放っておくと、血を見たさにろくに怪我も治らん内に飛び出しかねんからな」
「うん。…ありがと。ごめん」
「謝る事は無い。好きな女を守ってやるのは恥ずかしい事じゃない」
「って、お、おいちゃんっ! なんちゅう事を………バカーッ!」
「知らんと思っておったか? それから、おいちゃんと呼ぶなと何度も言わせるなよ」竜王はに、と意地悪く口端を吊り上げると、オルフェの背中にもみじ落としを喰らわせて玄関を出ていった。
オルフェ達を置いて屋敷を出ると、不意に急激な脱力感が襲った。簡単に振り払える程の微弱なものではあったが、瘴気がうっすらと町全体を覆う。目の前を逃げ惑う人々が、急な脱力感に襲われて崩れ落ちて行く。その身体から青白い光が抜けて行くのを、私は見た。
「あれは!」
あちこちから燐光が発せられ、光の群れは明滅しながら、宙を舞う三つ目のグリュフォンに向かって吸い寄せられていた。
「あの青白い光は、人々の魂に違いありません!」
「奴らの好きにさせてなるか! 奴は私が片付ける。後は頼んだ!」
竜王はそれだけを言い残すと地を蹴って翼広げ、闇けぶる宙へと飛び立って行った。
闇に向けて広げられた翼は真っ直ぐに、街の人々の魂を集める魔物に向かって広げられる。腰にぶら下げた無骨な鋼の剣を鞘から抜き払い、下段より大きく薙ぎ払う動きは、しかし余裕で躱される。
「貴様は…ジャミラスか!」
「我が名を記憶の片隅にでも留めて戴けたとは誠に光栄」
「ああ」竜王は眉間に皺を寄せた。「我を魔族の王として承認するのに、真っ先に異議を唱えた連中の筆頭だったからな!」
竜王は欠けた鋼の剣を手に再び振りかぶる。が、ジャミラスの方は受けて立つ様子もなく、のらりくらりとかわしながら後じさる。
「逃がすか!」
「ふふん、貴公の相手などさせられては生命が幾つあっても足らんわ、ほれ!」
ジャミラスが獅子の前脚を広げる。と、その先から回収された人々の魂が蒸気となって吐き出され、白い霧となって竜王の身体にまとわり付く。
「…これは、ムーンペタの連中の魂…?」
ジャミラスにしてみれば、ほんの時間稼ぎのつもりだったに違いない。だが、それは竜王自身が気付いていなかった、思わぬ内面の変化を喚び起こしていた。確かに、妖気を以てムーンペタの人々の魂を焼き尽くせば、あるいは力ずくで引き裂けば、この軛を断ち切る事は容易い事だ。だがもしここで彼等を傷付けたなら…。
一瞬の躊躇だった。だが、敵がそれを見逃す筈も無かった。
飛び去ろうとしたジャミラスの翼が、羽撃くのを止めた。
「おやおや、これはこれは。魔王としてその名を恣とした貴公が、たかだか人の子の生霊如きを振り払えぬとは。……! これは驚きだ! もしや、貴公、人の子等の生命を気遣っておられるのかな?」
「き、気遣ってなどおらぬ! こんなもの…!」
動きが止まる。
黄金色に蠢く視線の先がジャミラスを見ていないのに気付いた。その視線の先には、逃げ惑い、崩れ落ちる人々が、火を消して回る悪魔神官達や、魔物達と戦う私達が居た。
「無理をなさらずとも、素直に認めてしまいなさい」
「ぐっ…」
獅子の爪が蒼白い皮膚を切り裂く。血飛沫が雨の様に飛び散り、真下に居る私達の顔に衣服に降り注ぐ。深い傷ではないが、竜王は避ける事も出来ず成すがままにされている。
「そんな霧、振り払ってしまえばいい!」
竜王を援護しようとボウガンを番えるナリーノに、私はかぶりを振った。
「彼はきっと、私達の事を気遣っているんです」
決しておくびには出さないが、何処かで私達の事を気遣ってくれている。
だからこそ。
呪文を詠唱する私に気付いて、ジャミラスはその前足から、今度は黒い霧を噴き出して辺りを覆い尽くす。詠唱を終えて放たれる筈だった魔力の塊は、黒い霧の中に拡散して阻まれてしまう。霧は辺りに広がって、消火に励む悪魔神官達の邪魔をする。霧が視界をも阻んでしまう為、ナリーノのボウガンも標的を見定められずに、やがて下ろされる。
「この霧を何とかしなければ、何とか…」
「クソッ、あれじゃ狙えない!」ナリーノは歯噛みして、悔し紛れに足元を蹴った。「ムーンペタの連中の事なんかどうでもいいじゃないかっ!」
「ナリーノ王! 貴男何と言う恐ろしい事を仰るのですかっ!」
「フン! 数え切れん程の命を奪っておきながら、今更人道主義に転向か? 奴の気紛れな気遣いのせいで町が滅びたらそれこそ街の連中に取っちゃいい迷惑だろうさ!」
私は何も言い返せなかった。目の前で現在と過去とが交錯する。
いいや、今惑うている時ではない。『今日のプライドより明日のご飯』だ!
思考を切り替えろ。模索せよ、何が己に可能で、求められているのか。原因と目的、最善の手段を。
あの悪しき黒い霧を晴らすには、どうすれば良いのか。
霧。
闇夜に閃く稲妻の如き閃光。
そうか! ルビス様、感謝致します。
私は、その手に握り締めた雨雲の杖を、天に掲げた。
魔力が天に向け迸る。雨雲俄かに掻き曇り、鈍く濁った空はまた一段と低くなり天の恵みを喚起する。恵みは凝縮して一滴また一滴、やがては雨となってこの地に降り注いだ。雨は滝の如く降り注いで街を焼く業火を瞬く間に制圧し、煙り混じりの白い霧が辺りを包む。黒い霧は降り注ぐ雨と霧に溶け、やがて大地に吸い込まれ、消えた。
視界が開けた中から、ナリーノが立て続けにジャミラスに向かってボウガンを打ち込む。だがやはり、距離があり過ぎるせいなのか、ジャミラスを傷付ける決定打とはなり得ない。私もジャミラスに向かってバギクロスを放つ。が、流石に距離が遠過ぎる。ジャミラスは私が呪文を詠唱する姿を視認するや、竜王の身体を楯にして呪文をかわす。鎌鼬にその身を切り裂かれ、苦悶に呻く姿に、私は呪文での援護を取り敢えずは、諦めざるを得なかった。
「任せるしか…無いのか…」
ナリーノは諦めて、ボウガンを降ろした。
「信じましょう…信じるしか、ありません」
「ジャミラス…貴様…ッ…」歯がみすればその音が敵にさえ筒抜けな程の近距離で、ジャミラスの奴と対峙していた。
「己が身を楯にされ、味方の術で切り刻まれる気分は如何ですか?」ジャミラスの爪が今し方付けられたばかりの、胸を抉る傷に突き立てられる。「綺麗な…色ですね」
この期に及んでまでも、生霊共に縛り付けられ、一方的に傷付けられながら、何故、無理にでも弾き飛ばしてやらないのか。実際、未だに解りかねていた。何かがそうさせなかった。それが何かは解らない。解らぬが、しかしそれが現状を悪くしているのには変わりない。何故だ?
ネコ爪で掻かれた傷など大した事はない。だが、あ奴の…ジャミラスの一言が、頭から離れない。私が、虫螻共の命を気遣っていると?
そうだ。確かに。不意に、もう一人の自分が思考に割り込んで来て、当惑を覚える。何だお前は? お前は、私自身なのか?
お前は、お前自身が思っている程、他人を憎んでなど居ない。そう囁きかける、もう一人の己。
違う、私はただ…人々の魂を傷付ける事は、必死に人々を守る為に力を尽くしてくれた悪魔神官共の努力を無にする事になる。そうなったら、きっとハーゴンの奴がまた落ち込むに違いない。あいつはちっとも悪くない癖に、直ぐに悲しんだり傷付いたり落ち込んだりして、挙げ句の果てに自分を責めて心を閉ざしてしまうのだ。それが、嫌なだけだ。
それで十分ではないか。それだけで。
いいのか?
十分だ。
自分の中に芽生えたこの不思議な感情に、戸惑いを覚える。今までなら考えもしなかった。人の為? 何故奴らを守る為、いや、誰かの為だけに、己が傷付く事を平然と受け入れているのか。奴らが私を受け入れている訳でもあるまいに、何故?
構うものか。人の為ではない、己の為だ。もう一方の自分が返す。
ただ、そうしなければならない、そうしたい、そう感じるだけだ。理由など要らぬ! したいようにやる、やりたいようにやるだけだ! ただそれだけの事だ!
芽生えた「感情」が膨れ上がり溢れ出て、焼き尽くさん程の光が総身を貫き、噴き出す。その光は、しかし、身体を傷付ける事は無い。
その時初めて、私は、憎しみ以外の感情が、力となり得るのだという事を知った。
その時、私はその場で何が起こったのか直ぐには解らなかった。ただ、頭上から発せられた幾条もの光線が辺りを覆い尽くして行き目が眩んだ、それ以上のことは何も憶えていない。
辺りを眩い黄金色に包んだ光は膨れ上がり、波動となって街中を、ジャミラスに操られていた人々の魂を覆い尽くし包み込んで行く。霧は拡散し、悪しき魔力の軛から解き放たれたムーンペタの人々の魂は、本来あるべき場所へと次々帰って行った。
「くぅおっ! さ、流石は光の竜、我々の手には負えぬ、退却だ!」
「そうは行くか! 逃がさぬ!」竜王は再び鋼の剣を、今度は中段に構え直して飛びかかる。
「いえ、意地でも逃げさせていただきます。ベギラゴン!」
ベギラゴンの炎で眼下の家々が炎に包まれ、ジャミラスとの間に炎の壁を造った。一瞬の怯みを逃さず、ジャミラスはロンダルキアの方へと飛び去ってしまった。魔物達も一斉に退却して行く。
「魔物と通じておったのは、どうやらロトの連中も同じらしいな」辺りに光輝を撒き散らしながら降りて来た竜王に向かって、私はいらえた。
「の、様ですね」
焼け出された人々が、悪魔神官達に先導されて広間に集まってきた。
魔物に追い立てられて家を焼かれ、あげくに魂を無理矢理吸い出されたせいで、皆顔に生気が見られない。恐怖や敵対感情や、過去のしがらみさえも、皆の上に等しく訪れた厄災の前に麻痺していた。煤にまみれ、煤を被った毛布にくるまって互いに身を寄せ合う。晩秋の夜風は容赦なく、焼け出された人々の身を打ち据える。私達は私達で吹きっ晒しの中、否応なしに人々と向き合う羽目になった。
随分長く引き延ばしては来たが、何れはこんな時が来ると覚悟はしていた。とはいえ、対処の方法を予め考えていた訳でも無く、考えていたとしてもその場に至ればやはりどうこう出来たとは思えない。どうすべきか思案しつつ皆の様子を伺ってはみたが、誰も彼も似たようなものだった。共通の問題を抱えている内は未だ良い。だが、一度収まれば、又嘗ての、忘れかけていた感情が、蟠りが蘇ってくる。
暫しの沈黙が、いたたまれない。
「…あんた達、これはどういうことなんだい?」
私達を伺うよう、初めて口を開いたのは、見知らぬ老婆だった。老婆の一言を切っ掛けに、人々は堰を切ったようにしゃべり出した。溜め込んでいた感情があちこちで噴き出し、激しい流れとなって迸る。
「マリア様があんたらからこの街を取り返そうと軍隊を送り込んでくれたというのに、あんた達が追っ払ってしまったそうじゃないか! だから魔物達が街を焼き払ってしまったんじゃないかっ!」これは乳飲み子を抱えた女。
「明日から商売あがったりだ! あんたらのせいだ!」どこかの店主の声。
「じゃあ何でが魔物と戦ってくれたの?」若い女。
「家に点いた火を消してくれたのはこの人達だよ? おいらを助けてくれたのも」子供の声。
「ガキは黙ってろ!」男の声。
「アタイも助けてもらったよ?」女の声。
「私の魂を救ってもらったんだ。あの光に包まれた時の事、忘れちゃいないだろうね?」年輩の女。
「さっぱり解んねえ。どっちが俺達の味方なんだ?」若い男の声。
「出て行け!」
石礫がどこからか飛んできて、額を穿った。拳大の、鋭く尖った石片だった。眉間から一筋、朱が溢れ出る。石礫が再び飛んだかと思うと、制止する者との言い争う声が上がる。
私達は群衆に囲まれ、彼等の問いに答えあぐねていた。どう真実を述べたところで、彼等を満足させることなどどうして出来ようか? 私は額から溢れる血を拭うでもなく、唯唇を噛んでいた。
「まあまあまあ。待って下さいよ皆さん。ユカちゃん、こっちにおいで」
聞き慣れた声を肩越しに覗き、目を瞠る。突っ立っている悪魔神官達をかき分けてナリーノがしゃしゃり出てきたのだ。その手にユークァルの手を取って。
「な、ナリーノ王! 貴男…」
私は慌ててナリーノを制止しようとしたが、ナリーノにはまあ任せておけと言わんばかりに適当にあしらわれてしまった。
「彼らが貴方達の敵である筈がありません。何故なら! 彼女、彼女の名はユークァル=ムォノー。皆さん聞いた事ある人もいるんじゃありませんかね?」
大衆の中でも聡い連中がざわつき出す。
「待て、その話聞いて…」さっきまで気怠げにしゃがみ込んでいた竜王が慌てて起き上がる。
「まあまあ、悪いようにはしないから座って座って。そう、皆さん。なぁーんと、彼女は前ムーンペタ町長の孫娘さんなのです。話によるとムーンペタの町長は十年ほど昔に、ありもしない収賄疑惑で捕まって街を追い出されたとか。それっきりムォノー家の消息はぷっつり途絶えていました。そこへ彼らがユークァルを連れて来た」
「それは…」完全に、私達の敗北であった。
「確かに彼らの流儀は、我々人のそれとはあまりに違います。しかし、結局誰が貴方達を守ってくれたんですかネ? んまあ、ボクに言えるのはこれだけですよ」独断場を終えて壇上を去るナリーノは、僅かながら伺い知れる程の勝ち誇った笑みを湛えていた。
「やられたな、ナリーノの奴…」
町長の家に戻って来た第一声と共に、竜王はユークァルを疎ましげに一瞥した。
「彼女のせいじゃありません」私はきっぱりと言った。「我々がナリーノ王に対してカードを見せすぎたのが悪いんです。確かに、もっと警戒すべきでした」
「兄さん、ユークァルさんが狙われてたのは、そのせいだったんですね…」ザーゴンはユークァルの傷を手当てしてやっていた。包帯を手際よく巻くと、鋏で裁ち落とす。「となると…余り考えたくはないのですが、魔物達を差し向けたのは…やはり…」
「私とて信じたくはない。彼等と刃を交えた時でさえ、私は彼等を、その名に相応しいと認めざるを得なかった。……8年の歳月が、彼等を変えてしまったのだろうか…」
そうは言ってみたものの、あの三人がこの抑圧と暴虐をもたらした事はもう分かり切っていた。そして、その原因を種蒔いたのは、やはり私なのだ。
蒔いた種は刈り取らねばならぬ。
これからの事を思うと、少しばかり眩暈がした。休みたかった。解ってはいても、その重圧に耐え難かった。今は、暫しの猶予を…。
咳き込んだ。口中に拡がる金属の味。
口元を押さえていた手を広げると、黒ずんだ赤色の斑点が手を染める。
まさか。
「兄さん、どうしたのですか? 顔色が優れませんが」
胸の病が再発したのでは…?
「いや、煙を吸い込み過ぎたらしく喉が、ゴホゴホッ、た、たいした事はないよ。それより、疲れたようだ。少し、休ませてくれないか」
慌てて取り繕い、急いでその場を後にした。この事は誰にも隠さねば。隠さねば………。
次の日。
ママレードとバターたっぷりのトーストに、絞り立てのミルクに取れたての卵と果物がたっぷり添えられた素晴らしい朝食は、サマルトリアからの無粋な伝令によって中断の憂き目を見た。
「朝っぱらから来なくても良いではないか。せめて朝食を終えてから来るがいい、TPOを弁えぬ奴だな」
「そういう訳にも行かないでしょう、もう来てしまったんですから」
「そうさな、とにかく見せて見ろ」
伝令から恐る恐る手渡された手紙を広げて、竜王は眉を顰めた。
「そちら様のひ孫様は、当方が大灯台にてお預かり申し上げております。御本人はお帰りになりたくないそうですが、どうしてもお連れしたいと申されますならば、当家所有の家宝である雨雲の杖を御返却戴きたいと存じます。その節は貴殿自らの手でお返し戴きたく、また、必ずお一人でいらっしゃいます様、お願い申し上げます。なお、約束を守られなかった場合のひ孫様の安全は当方では保障致しかねますので御容赦願います。
それでは、お越しをお待ち申し上げております。
サマルトリア王、トンヌラ」
竜王は受け取った手紙をびりびりと破り捨てた。
「フン、ふざけた連中だ。それにしても、大灯台へ来い、とはな」
「たぶん罠ですよ、これは」
「だろうな。だが解っていても行かねばならん。ぼうずの命がかかっておるからな。だが馬鹿正直に奴等の言う事を聞いてやる事もない、な?」
「なら、ボクもお供させて戴きますネ。うーん、それにしてもこのスクランブルエッグは極上ですね。むぐむぐ」
ナリーノはあれ以降、自分の城に帰らずここに泊まり込み、である。今朝などはちゃっかり朝飯にありついて、タダ飯をたらふく平らげていた。
「ナリーノ、お前良いのか自分の国は? こんな奴を国王に持っては、デルコンダルも災難な事だな。ユカ、サラダ取ってくれ」
「なあに、あそこまでコテンパンにされて、その上今回のムーンブルク軍の敗退を知ったら、奴らそうそう攻めては来れませんって」ナリーノはバターをロールパンの中にたっぷり挟み込み、そのまま一気にパク付く。「それより、これは急を要することなんじゃないですかネ? ひょっとするとあいつらとの直接対決、って事にもなりますからね。ボクとしてはジョンの仇がありますから、イヤって言われても付いていきますヨ☆で、紅茶おかわり」
「…チビの命は、ジョン並か…」竜王は、焼きたてのロールパンにスクランブルエッグとユークァルに取り分けてもらったほうれん草のサラダとベーコンを物理的許容量の限界まで詰め込んで噛み締めながら、地獄の遣いBが及び腰でナリーノに紅茶を注ぐのをじっと見守っていた。
皆をその背に乗せ、大灯台に向かって翼を広げる。大灯台までは一日もあれば着くという事で、途中休憩無しに一息で飛んで行く。
「風圧がすごいな」ナリーノは乱れる縦ロールを頻りに気にしていた。「こんなんじゃ眠れないや」
「寝たら落ちるぞ」
「オレだって飛べるのにぃ」オルフェが悔しそうに呟く。
「じゃあユカ乗せて付いて来るか?」
「そいつは勘弁!」
「だろうな、そんな事は言わん。どうだ二等兵、大灯台が見えて来たか?」
「うん見えるよ」オルフェは早速双眼鏡で大灯台の方を覗き込む。「おっさ…ううん隊長」
「へえ、君二等兵なんだ?」ナリーノが嬉しそうに言った。「じゃあ上官の命令は絶対服従だね」
「ええっ?! ちょっと待てよ、何でお前なんかの言う事なんか聞かなくちゃなんないんだよー!」
「国王陛下と呼べ!」ナリーノはすかさずオルフェの頭を殴り付けた。「上官にそんな口を聞いたら軍事法廷にかけてやるぞ」
「ほう、そうかナリーノ。という事は貴様、我が軍に入隊すると言う事だな。よろしい。では貴様を我が軍の二等兵として正式に入隊を許可しよう。オルフェ念願の上等兵な。良いか、我が軍では上官の命令は絶対服従だからな。逆らったら軍事法廷なしでその場で射殺。今決定」
「うわーい、やったー! オイラ上等兵だ〜! 隊長殿ありがとうであります!」
「うくく、何でボクが二等兵なんだー! ボクはデルコンダルの国王陛下なんだぞっ! 最低でも下士官くらいから始めるべきだ!」
「なあに」竜王は不満たらたらなナリーノに向かって愉快そうに口端を歪めた。「我が軍は出自は問わん。実績主義なのさ」
メルキドを背に、ずっと南下した先に大灯台はあった。
嘗てはメルキド南の浅い海を航行する際の安全を守る為、夜になると灯を点した世界最大級の灯台であった。が、神官達の話によれば、ロト王家から紋章を守る為魔物達に塔を襲撃させて以来、この塔はもう使われていないのだそうだ。
「まさか、上から来るなんて思っちゃいないだろうな〜」
高度を下げ、屋上に向かって滑空する。と、オルフェが下を覗いて何かを頻りに気にしている。
「どうしたオルフェ上等兵?」
「海がさ、ざぱんって言ったから魚かなと思って…うわっ!」
下から見慣れたものが我々の側面を掠めて通り過ぎた! 鎧の反射光が水飛沫をまといながら蒼く煌めいて、刹那、目が眩む。
「ゲッ!」オルフェが叫ぶ。「勇者ロトだっ!」
「ロト? ロトってあの? 冗談も休み休み…わっ!」
下からほぼ垂直に飛び上がった鎧の戦士は、そのまま真っ直ぐ背中に向けて落下して来た。あんなのを食らったら全員サメの餌だ。この辺りは水温が高く、凶暴なサメがうようよ居るのだ。
「ハーゴン、悪いが振り落とすぞ。オルフェ頼んだ。ユカ、お前角に捕まっておけ。しっかりとな」
「いきなり、そんな無茶だよー!」
身体が斜め45度に傾き、私達は見事に放り出された。ユークァルはしっかり角に捕まって無事だったが、私はオルフェが捕まえてくれていなかったらミートパイの中身になっていただろう。ナリーノはというと、鳥の翼を模したマントを広げると、マントが風を孕んで塔の屋上に優雅に着地した。
「オルフェ上等兵、良く出来たな! 後で勲章やるから楽しみにしておれ」
「まあ貴男という人は良くもそんな減らず口を…わあ!」オルフェに何とか捕まえてもらっているのを斜め上からロトに狙われ、すんでの所でスライス神官にされるところだった。法衣の裾が綺麗に切り裂かれる。
「ユカ、元の姿に戻るから、屋上に飛び降りろよ」
竜王は人の姿に素早く変化して塔の上に飛び降りた。ユークァルも後に続く。
「この機械人形め、こっちだこっち、狙ってみるがいい!」手招きして挑発する。挑発を知ってか知らずか、ロトはそのまままっすぐ剣を掲げて突進する。竜王は僅かに後方に避けようと体勢を作って、ぎりぎりの所で斜め前に飛び退いた。ロトはそのまま塔の屋上の床に激突する。と、煉瓦で組まれた筈の床が僅かにたわむ。
「フェイントも見抜けんのか、間抜けめ。…む? な、なんだ? うわあっ!」
「のひーっ!」
「わ〜!」
「あ、落ちます」
ロトが高速で屋上に激突したショックで、大灯台屋上の床をぶち抜いてしまったのだ。屋上に降り立っていた面々は、見事に最上階へと放り落とされた。
我々が最上階で見たのは、三人が優雅にお茶を嗜んでいるところだった。が、空からの来訪者時々煉瓦という不測の事態に、午後の茶会は慌ただしくも中断の憂き目を見た。倒れた花瓶に押されてティーカップが引っ繰り返り、ムーンブルク女王自慢の練り絹のドレスがレモンティで赤茶に染まる。
「ぶほっ…!!」
「やあっ! ちょっと! 染みになっちゃうじゃないのっ! これ、どうしてくれるのよ!」
「フン、その胸に血でもっと大きい染みを作ってやる! そうなりたくなければチビを返して貰おうか!」竜王はボロボロの鋼の剣を抜き放つと、大振りに構えて斬り掛かる!
「ふぎゃっ」私が床に打った尻をさすっていると、切り裂かれたテーブルが目の前に転がって来てサマルトリア王が椅子ごと倒れ込んだ。ユークァルが間髪入れず飛びかかって、サマルトリア王の首にナイフを突き立てテーブルクロスを血で染める。
「こ、こいつ狂ってる! 何とかして下さいよッ!」ナリーノがロトとやり合って喚いている。ロトの剣を鞭で絡め取りながら、素早くガーターベルトのナイフを引き抜いては間接部に押し込むが、全く効いていないのだ。
「んなもんがこいつにきくかよっ! おりゃ!」オルフェが背後からロトのバーニア部分を思いっ切り蹴り上げた。ロトは蹌踉めくが、ナリーノに絡め取られた剣を力ずくで振り上げて鞭を引きちぎった。
「ぼっボクの単分子鞭が効かないだとぉ?!」
「お前何処からそんな物持ち込んで来た…っオルフェッ!」
私は初めて、無表情だったはずのロトの瞳に、怒りの色を見て取った。ロトは体勢を持ち直し、剣を体ごと水平に回転させる。
そこには、背中を蹴り上げたおかげで僅かに体勢を崩したオルフェがいた。
「オルフェーッ!」
イオナズンと鋼の剣が同時にロトを襲うが、到底間に合わない。
派手な血飛沫と共に、オルフェは首を刎ねられた!
ロトは直ぐに、魔法の衝撃をもろに受けて前方に吹っ飛び、塔の壁をぶち破ってそのまま放り出された。
「首を、首を繋げなくては!」私は慌てて駆け寄り、オルフェの首と胴を抱き込む。「ザオリクッ!」
「ええい、邪魔立てするな!」私の隙を見て取りムーンブルク女王が杖から放ったベギラマを、竜王が身体で受け止めて阻む。
「こ、こいつらロトの勇者じゃないッ!」ナリーノがローレシアの剣を受け止めて叫んだ。「似てるけど、違う! ニセモノだっ!」
ナリーノの叫びに、一同は振り返った。
「こいつら、ジョンを知らないんだッ!」
偽ローレシアが憎々しげにナリーノを睨み付け、向う脛を蹴った。ナリーノはもんどり打って転がり回る。
「ばれちゃ仕方がない、最後の手段だっ!」生き残りの二人は窓際に駆け寄って、手元の怪しげなレバーに手をかけた。我々が駆け寄ろうと足を踏み出したのと同時に、何度も体験済みのあの沈み込むような体感が、ズン、という爆破音と共に骨を通じて伝わって来た。
「オルフェ、オルフェ目を覚まして!」オルフェの体に血が通ったのを確認し、オルフェの頬を叩く。
「…え、うーん…何? 何かあったの? ってわーっ!」
「ほいっと」状況を察するや、ナリーノはとっとと窓の外に飛び降りた。
「お、おかしいわ! 旅の扉が出てくる筈なのにっ!」ニセムーンブルクが足下を慌てて見回した。
「え、そんな…そんな筈が…うわーっ!」
「キャァーッ!」
「リレミト!」
目の前を、竜王が脇にニセローレシアをひっつかんで飛び出していったのを最後に、視界がぶれて、私達は塔から叩き出された。
もうもうと埃が立ち上がる中、私はオルフェとユークァルを連れてゆっくり塔の残骸を離れた。オルフェは首筋を撫でながらも記憶が飛んでいるのを訝しがったが、もはや一々かまってはいられなかった。
「…ムーンブルクは助からなかった。見ない方がいい、頭を砕かれておるからな。それにしても…こいつら皆影武者とはな…随分舐められたものだ。チビもおらぬし」
偽ローレシア王は我々を前にして、憮然として、座り込んでいた。もう、覚悟を決めていたようだった。「殺す気か? 好きにしろ。誰も迎えに来やしないだろうし。俺達は国に捨てられたんだ、死んだも同然さ」
「ならば話せるだろう、チビは、そして本物のお前さん達は何処に居る?」
「知らないな」偽ローレシア王は地面から目を逸らそうとしない。「俺達だけじゃない。城の人間も、大臣も誰も王の行方を知らないんだ」
「ふん、役に立たん連中だ」ナリーノがジョンの剥製をニセローレシアの背中に投げつける。「お前達は最初っから、奴らの囮用模型だったのさ。罠に誘い込む為の」
「だろうな」偽ローレシア王は生気の抜けた声を無理矢理絞り出した。「国の為と信じて、これが世界の為になると信じて、自分を捨てて影武者として生きる事を受け入れたのに…これでは…」私は直ぐ、偽ローレシア王が手元で小瓶を弄くっているのに気が付いた。
「彼を止めて下さいっ! 彼は毒を…」だが、その目の前で偽王は小瓶の中身を一気に呷った。毒を吐かせようとし、キアリーの魔法をかけたが、即効性の毒には全く無力だった。
「…反逆者には、なれないんだ…ごふっ」
二人の影武者の遺骸――サマルトリア王のそれはもう見付からなかったので――を弔った後、ユークァルがぽつりと呟いた。「本気で、私達を殺すつもりだったんでしょうか」
「どゆこと?」
「こんなやり方をしても私達を『確実に』殺す事は出来ません。無駄が多すぎます」
「確かにな…。とすれば、何の為に?」
「雨雲の杖を取り返す為、では無いでしょうね」
竜王は腕を組んでしばらく考え込む風を決め込んでいたが、やがて一言、誰に言うでもなく呟いた。
「時間稼ぎ、だろうな」
時間を稼ぐ?
彼らには、ここまでして時間を稼がなくてはならない何かがあったのだろうか。これほどまでに多くの犠牲を出しても余りある対価を得られる程の、何か。とすると、それは……?!
電光の様に、一つのある考えが私を支配した。
だが、その様な、人の身に余る事、あるまじき事を彼らは望んだのだろうか?
そして、その先何処へ行こうというのだろうか?
私には解らない。
解らない。が、今ならはっきりと言える。
それは、私がかつて陥った、あの愚かさと何も変わる事が無い。
否、もっと涜神的ですらある。
「彼らが、何処にいるか解りました」
「何だと?!」
「何処なんですそれは!」
私は覚悟を決めて話し出した。
「ロンダルキアです」
ムーンペタに戻る途中、私はずっと喋り詰めだった。要求されたからでもあったが、胸の内にあったものを押し留めておけなかったのだ。
「彼らが何を企んでいたか、ようやく解りました。おそらく…三神器は、異世界への扉を開く鍵なのです。彼らは、神になるつもりなのです。天と地を繋ぐ雨雲を手に入れて、天に一番近い聖地より天へと繋がる虹の橋を渡し、神の座に登りつめる。それが、先代ムーンブルク王からの、ロト三王家の野望だったのです」
「まて、最初から説明しろ」
「ああ、申し訳有りません。頭の中でずっと考えを独り温めていたものですから、自分の中ではもう出来上がっていたのですが…。ええと…随分前にお話ししましたが、疑問は二つ。三神器が単に魔の島に渡る為の道具であるとするならば、彼等にとってそんな物はもはや必要無い筈です。なのに、何故今さらそんな過去の遺物を集めるのか。もう一つは、虹の橋を架けるのに、何故ロトの印が必要なのか。太陽と雨があれば、虹の橋は架けられるというのに、です。そこまではお話ししましたね?」
「これ飲みなよ。おちつくよ」オルフェに渡された水筒の中身はすっかりぬるくなった蜂蜜入りのレモンティだった。一気に飲み干して、話を続ける。
「そこで私は仮説をうち立てました。これら3つの神器には、隠されたもう一つの意味が付与されているのではないか、と。あくまでもこれは推論に過ぎませんが」
「珍しく自信たっぷりだな」
「ロトの印は」私は竜王の冷やかしを無視して話を続けた。「元々は大地母神ルビス様が勇者ロトに与えたものです。故に、大地の加護を象徴するものと考えられます。一方、太陽の石は太陽の恵み、つまり天の加護の象徴です。そして天と地の間を繋ぐもの、それが雨雲の杖なのではないかと想像します。つまり、3つの神器は、雨と太陽を結びつける大地と、天と地を繋ぐ雨雲という2つの意味を象徴していると」
「雨雲の杖がそんな意味を持っていたとは。だが、それと、神になるという途方もない思い付きが何処でどうやって繋がるのだ?」
「遥か昔の伝説に、こういうのがあったのですよ。当時は気にも止めませんでしたから、記憶の彼方に埋もれていましたがね。『世界のいと高き所、最も光と闇に満ちし場所に、世界の主がましまして、主を倒せし者の願いを叶えるであろう』とね」
「ボクも行かせてもらいますよ」ナリーノは、どこまでも我々に付き合うつもりらしかった。拒んだところで、這ってでも付いてくるつもりなのは明白だったが。
「勝手にしろ。確か、ゲレゲレの敵討ちだったな」
「ジョンだあぁァッ! ジョンなんだアァァッ!」
ジョンの剥製を抱えて絶叫するナリーノを横目に、私は竜王に囁いた。
「あれ、わざとでしょ」
「当たり前の事を聞くな」
ムーンペタに戻り我々は即、ロンダルキアへ登る準備を整え始めた。もはや一刻の猶予もならない。彼等も解っていて、我々が来るのを待っているのだ。
「僕らも付いて行く。いいだろう?」私達がロンダルキアに行くというのを聞きつけて、アーロンとザーゴンが2階から降りて来た。「冬山は厳しい。準備して行かないと」
「兄さん、私に手伝える事があれば言って下さい。力になりたいんです」
「ああ、是非来て欲しいが…どうしましょう」二人が来てくれると言うのなら、これほど心強い味方はいない様に私には思われた。だが私に決定権は無い。かの気紛れなる我が主を仰ぎ見ると、僅かに躊躇いが掠めたのが垣間見えた。が、それは足早に過ぎて、もっと他の、例えば時を惜しむが故の即断と言った物に差し替えられていた。
「別にかまわん。だが、命の保証は出来んぞ。足手まといになればいつでも捨てて行く」
竜王の返事に、二人は安堵した様子で支度に取りかかった。
「ハーゴン様、これを。もう、お持ちではないのでしょう?」
出発間際、悪魔神官の一人が、私に破壊神シドーの姿を象った木像を手渡した。
黒檀を彫り、丁寧に磨き抜かれた邪神像。不思議な位手に馴染む。
懐かしいような、忌まわしく、触れられたくない様でもあるような。
心惹かれもするが、厭わしくもある。その奥底をかき乱されるような、見るまいと目を瞑って来た何かを、覗き込みたくなるような。いつの間にかこの像に魅入られていた自分に気付き、慌てて像を袋にしまい込んだ。
「おい、ハーゴン、貴様この世界に戻ってから何だか変だぞ? どうしたのだ?」
竜王に肩を揺すぶられて、私は後ろを振り返った。そこには、在る筈の世界が、僅かにぶれて、透けて色褪せて行った。
その時、私は見た。
もう二度と見る筈の無かったもの。
在り得ない世界。
何故、今、この私が、
信仰を捨て、狂気を捨て、
償いの為に生きると決意した筈の私が。
この私が、幻視するのか。
燃え落ちる、世界樹。
世界の滅びの日。
神々の黄昏。
出来得るのならば、二度と見たくなかった。
灼熱の冷気。
世界が、滅び行く様。
我が肉体が朽ちる日。
破滅……………。
………………………。
…………………………………。
「……しっかりしろ、しっかりしろハーゴン」
身体を揺すぶられ、頬を何度も叩かれて意識を取り戻した私の目に、最初に飛び込んできたのは我が主の顔だった。ぶれても、色褪せてもいない。
「私が解るか?」
まだ身体が強張るが、問いかけに、殆ど痙攣する様に何度も頷いた。
「そうか、良かった。気がふれたかと思って心配したのだぞ」
「わ…たし……な…にを…」
「私の目を見たかと思ったら、いきなり目を見開いて金切り声で訳わからん叫び声を上げてわめき散らしたあげく、胸を掻き毟り引き付けを起こして卒倒した。目は血走るわ、口から泡は吹くわ…。お前があんなに取り乱したのは初めて見た」
「もう、何ともありません」
「本当だな? 本当なのだな?」
私は私が見た筈の物を無理矢理無意識の領域に押し込めて、精一杯力強く、頷き返した。
* * *
「塔が見えたぞ! おい、あれか死者の塔というのは」
眼前に、雪に輪郭をぼかされた石造りの塔がそびえ立つ。皆が自然と早足になり、吹く風が厳しさを増した。
「思ったより時間がかからなかったな、ハーゴン」従弟が肩をポンと叩く。
「ああ…神殿までもっと歩いたような気がするんだが…」
「気のせいだろう、僕らも随分歩いてきたから」アーロンはそっけなく答えた。
塔が見えてすぐに、我々は神殿の門に辿り着いた。
「うわー、でかいなー。上まで見えないよ」
「…吹雪のせいだと思います…」終始無言だったユークァルが、安心したのかようやく口を開く。皆気持ちは同じだったらしく、早速門前で服に付いた雪を払い落としている。
私は未だ、しかし違和感を拭い去る事が出来ずにいた。
言い表し様の無い不安。不吉な予感。
「とにかく、入りましょう。先に私が神殿の門を開けておきます」
私が皆より先に一歩踏み出した途端、目の前から神殿の門が消えた。
堅固だった筈の石造りの床は白く塗り替えられて積もりたての新雪と化し、支えるものを無くした私の身体は、新雪と共に地の底へと落ちていった。
私は、クレバスに落ちてしまったのだ。
「おい! ハーゴンがいなくなったぞ!」
「あ、ありゃりゃ? 神殿がない! 何で? どうして? どこ行っちゃったのさ!」
「まやかしか…くそっ、やられた!」
「兄さんっ! 兄さぁーんっ!」
「このクレバスに落ちたみたいですね」
雪に顔を押しつけられている割には皆の声は比較的良く聞こえてくる。返事をしようと息を吸い込んだ瞬間、また雪が滑って数メートルを落下した。滑り落ちる中途で岩だか氷だかに身体を打ち付け、身体が動かなくなる。
雪が身体の隙間に染みいり、じんわりと体温を奪ってゆく。
意識が遠のく。
誰が死者の塔の幻を見せたのだろう。
クレバスに落ちて、私が死ぬ事を望んでいた誰か。
誰が……。
………………!!
そうだったのか。
そこまで、私は望まれざる者であったか。
もう、限界、だろうか。
『何故』の答えを出すには、私は罪深過ぎたのだろうか。
「おおい、聞こえるかぁ〜」
「大丈夫かぁー」
「相当深そうだなー。こりゃあ、ムリかな」
「ムリなんて事があるか。貴様はそれで良いかもしれんが、こっちはそうはいかんのだ。おーい、今助けにいくからなー、聞こえてたら返事寄越せよー」
しばらくして、ようやく聞こえる程の声が届いてきた。気を失っていたのだろうか。我に帰って気力を振り絞り、私は叫んだ。
「…ダメですっ! 来ないで下さいっ!」
「な、ん、だ、と? 聞こえんぞーっ!」
「来ないで下さいっ! 危険すぎますっ!」
「バカ言え、そんな訳に行くか! 今助けにいくぞ、待っておれよ。うむむ、コートが邪魔だな。オルフェ、置いてくから畳んどけ」
「わ、ちょっとおっさん無茶だよ! …痛てっ……一番寒がりのくせに…あ、パッチなんかはいてる。やっぱりオヤジだ痛ててて…ゴメン、悪かったってばさあ、耳ひっぱんなよ」
「本当に馬刺しになりたいのか? バカモンが。ん? ユカ、どうした? ああ、ロープか。解った、誰かに端っこ持っておいてもらえよ。お前じゃ一緒に落ちてしまいかねんからな。いいか、ナリーノには絶対渡すな」
「酷いなあ、ちょっとは信頼して下さいよ。ムーンペタでも助けたでしょ?」
誰も巻き込みたくない。
「来てはいけません! ……助けにきたら、貴男も助かりません…」
「何を言うか、おい!」
死ぬのは私だけでいい。
「私はもう、助かりません。雪山のクレバスは危険です。貴男はここで死ぬべきじゃない! だから、私はいいから、先に行って下さい! ……お願いですから…」
粉状の雪が、顔に降り掛かった。
雪が擦れる音がして、鈍い衝撃が身体を襲う。加えられた重みで息が詰まって、激しく咳き込む。
「誰が、私はいいんだ?」
振り返れば、竜王がいた。
「死にたくば、この私が止めを刺してくれよう。だが、それは貴様が決める事ではない。貴様の生命は我が物と、貴様認めたであろうが。よもやその盟約忘れたか?」
冷えきった手が首を締め付け、私の顔を雪の中に2・3度強く押しつける。
「虚無による救いなど夢見るな、このスカタンが。誰が許そうとそんなものはこの私が許さん。良いか、蔑まれ、辱められようとも、卑しめられようとも、汚らわしくとも、我在る限りは地を這いつくばり、泥水を啜ってでも生き延びよ。そして」
雪の中から引きずり出され、胸ぐらを掴まれて平手打ちが二、三発飛ぶ。
「地獄の底まで付いて来るんだ。良いな? 寒いからって寝ぼけておると寝たまま死ぬぞ」
ああ、あの目だ。
根の国で私を魅了した、あの瞳。
だが、あの時とは違う。
従わせるでも、幻惑するでもない。
ぱさっと、雪の粉が舞った。
「?…ロープが、落ちてる…」
竜王は、全てを察したようだった。
「ふん、下らん感傷だ。罪の意識などに苛まれている暇があったら、今夜のメシの事でも考えておけ。言ったろう、『今日のプライドより明日のご飯』って。もう忘れたか?」
「しかし、どうやってここから…」
「こちとら誰かさんと違って、自殺願望なんぞありゃせん。角につかまれ」竜王は己の頭を指差した。
私がしっかり角をつかんだのを確認すると、竜王の体は見る見る巨大化し、蒼い肌と紫のローブの代わりに煌めく竜鱗が体を覆う。もしこの世に完璧な生物が存在するのならば、それは彼の事だろうと掛け値なしにそう断言出来る。無駄の無い筋組織、複雑でいて、尚且つ均整の取れたシルエット。それが、最初は首だけ、すぐに巨躯が続いて、アーチを描いて雪中からその姿を現わした。
「う、おっ」
体がクレバスにちょっとはまりかけ2メートルほど沈んだが、すぐに浮き上がり、その麗しい全身が地上に晒される。頭を下げたので、私は地上に下りた。巨躯は私が降りて直ぐ小さくなり、いつもの人型に戻っていた。
「ううーっ! さぶ、さぶ!死ねるゥーッ! オルフェッ! 服貸せ服っ!」
「そりゃ寒いよ自分で脱いだんだからさっ! はいっ!」
「……っと、オルフェ、そいつは後だ」
竜王は受け取った筈の上着をオルフェに放り返し、裸足のまま雪を踏み締めてアーロンへと歩み寄ると、突然胸ぐらをつかんで殴り飛ばした。
「………!!」
「手加減はした。貴様がハーゴンの従弟でなかったら、この場で殺していた。奴に感謝するんだな」
「……くっ、そんな情けはいらん!」
「貴様など殺す価値もない。それに、大体察しは付いておる。…理由は、魔物狩りか?」
「……」アーロンは答えなかった。
「同族を守る為、一族の裏切り者を葬り去る、と言ったところか。こら、ハーゴン湿気た面するんじゃない。貴様のせいじゃないんだからな」竜王はそう言ったが、その口振りはどことなく歯切れが悪そうだった。そもそもどう慰めの言葉をかけようが、私が自ら招いた事態なのは明白なのだ。
「仕方有りませんよ」私は無理に笑顔らしき物を作ってみせた。
本物の死者の塔が、少しだけ緩んだ吹雪の向こうからその姿を覗かせていた。
塔の中は至って簡素な造りで、最上部まで吹き抜けた塔の内側を、階段がぐるりと螺旋状に這わせてある。
「意外と綺麗なものだな、大して埃も積もっておらん」
「ロンダルキアに資材を運び入れてるっていう話は聞いてたけど、あいつら、こんな所に使っていたのか…」ナリーノが塔を見上げて舌打ちする。
「ロト廟を建てるという話、やはり名目に過ぎなかったようですね」柱に軽く手をかける。「相当手を入れています」
「元は知らぬが、その様だな。8年もの間廃墟だったとは思えん。とにかく、登るか」
私達は当の内側を壁沿いに巡る螺旋階段を、一歩一歩踏み締めていった。螺旋階段には手すりも柱も無く、ほぼ一人分の幅しかない。高所恐怖症でなくて良かった、とつくづく思う。
「ねぇ、凄いねぇこの階段。オイラ目が回りそうだよ……」
「あんまり下を見ない方が良いです」ユークァルが言った。
「うん、あんまり、見ないようにしとく…………れれ。何か、変だよ?」
「何が変なんですか?」
問われて、オルフェは遥か下方を指差した。「階段、無くなってる…………れれれっ!?」
大して良くはない目を凝らして見下ろすと、螺旋が三重程塔の内側を取り巻いて居た筈が、一重分確かに足りない。下方で微かな地鳴りが聞こえて来る。
「階段が落ちてるぞ!」
よくよく見れば螺旋階段がドミノ倒し式に崩れて、我々を追いかけてきているではないか! 階段の崩れる速度は加速度的に増し、上へ上へと逃げる我々を嘲笑うかに一気に追い付いて、足下を奪って行く! 我々はあっと言う間に真っ逆様に落ちて行った。
床に叩き付けられる直前にアストロンが効いたおかげで、何とか五体満足で済んだ私の前に、オルフェが空からユカをつかんで降りてきた。
「あれ、階段壊れてなかったんだ?」
言われてみれば、確かに階段は崩れ落ちた様子もない。「以前はこんな仕掛けはなかったのですが……どうやら、これも幻術のようですね」
「また貴様か! アーロン!」竜王は再び従弟の胸ぐらをつかんだが、従弟は知らんとそっぽを向いた。
「いや、違うでしょう。ここまで大がかりな術を使うには、予め相応の準備をしておく必要がありますから」
「マリアだな」ナリーノが嬉しそうに宙を見上げる。「フッフッフ。マッリアちゃ〜ん、剥製にして可愛がってあげるからねー☆」
「オレこいつ嫌だよぉー。サイアクゥー。キモーい」オルフェはユカに囁く。
「それは、気に入るの反対ですか?」ユカはオルフェの顔をじっと覗き込む。ユカにとってはいつも通りなのだが、オルフェはまだ今一つこの反応に慣れていないのか、慌てて視線を逸らす。
「う、うんまあそういう事かな、でも奴の首を切ったりはしないぜ」
「どうしてですか?」
「どうしてって、うーん」オルフェは考えあぐねて暫し首を捻っていたが、やがてユカに笑いかけた。「やだけど、殺すのはもっとやだからさ。とか何とか言ってるうちに、こっちの方がやられちゃうと思うけどね、ヘヘ」
「それよりみんな、大丈夫か? 怪我は無いか?」
「おっさん、こっちは大丈夫だぜ」オルフェが問い掛けに、手を差し上げてひらひら振った。
「そっちは大丈夫の様だな、減らず口を叩けるくらいだからな」竜王は言うなりオルフェの頭にげんこつをくれる。
「ボクも平気ですよ」ナリーノはマントをひらひら振った。「風のマントがありますからね」
「貴様の事は聞いてはおらぬ。どうせ殺しても死なないだろうからな」
「私も大丈夫です。アーロン、君は大丈夫か?」
「悪運だけは強いんでな。……あれ?」従弟は辺りを見回し、私もそれに釣られて周りを見る。
「ザーゴンがいないぞ」
一度塔を出て周辺を見回しても、塔の中をくまなく見渡しても、どこにも弟の姿は見当たらなかった。我々は仕方なく、一旦塔の最上階に向かう事にはしたが、消えた弟の謎は私達の士気を明らかに鈍らせてしまった。足元が崩れる幻をクリアして、祭壇の部屋への扉を開く。
扉を開けた私を待っていたのは、一陣の雪混じりの風であった。
塔の中はあの当時とはすっかり変わり果てていた。祭壇は破壊され、瓦礫に埋もれて既に形を成していない。天をも支えんと伸びる柱はへし折られて、煤に塗れて黒ずんでいる。
その最中にあって当時と変わらぬ、否、一層異様さと巨怪さを増した佇まいを誇る、邪神像。神の似姿として作られ、幾多の血を吸った、黒々と艶光りする異形の像。私は唯、唯ひたすらに圧倒されていた。見慣れた筈の其れに圧倒されるのには、何処かに罪悪感がこびり付いていたから、なのかもしれない。
「ヤホー、遅かったじゃんあんたら」その場に立ち尽くしていると、神像の裏から二人の若者がひょっこり顔を出した。
「トンヌラ! それにアイン!」
「出た、筋肉バカ王アイン君!」
「うわ、ナリーノ。何でお前がいるんだよ! デルコンダルに帰れよバカ!」
「俺が筋肉バカならお前はキチガイだろ! 一緒にすんな、あっち行けよキチガイ!」アインとトンヌラはナリーノを見付けるや、野良犬でも追い払う様にしっしっと手を払い除ける。寧ろ犬以下の扱いだ。
「思いっきりなめられてるね、ナリーノ! わっ、何だよ! いきなり殴るなよー! 暴力反対! いでででで」キレたナリーノにぶん殴られて、オルフェは頭を抱える。やれやれ、なるべく近付かないでおこう。
「上官に逆らったら死刑です」オルフェを殴るナリーノにユカが真顔で刃を向けたので、私は慌ててユカの手を引いた。
「わりーんだけどさー、俺ら、今お取り込み中なのよねん」ローレシア王アインが一同に向けて、ひらひら手を振る。「だからさ、あともうちょっとだけ遊んでてくれる? 暇つぶしは用意してるし」
「ほら、アレ」トンヌラが巨大神像を指差した。「あんたのツレ」
「え? ……!?」
トンヌラが指差した先、血塗るられた巨怪な異神像のてっぺんには、居なくなっていた筈の私の弟が縛り付けられていた。
「な、何故弟を…私が代わりにでも何でもなる! だから、弟は…」
「るせーよっ!」トンヌラは冷酷無比な支配者然として懇願を突っぱねた。「テメーのせいで、うちの妹が行き遅れてるんだよ! あいつ、悪魔神官の妄想やおい小説なんか書きやがって、ちっとも現実の男に興味示さねぇし…ハァ…」
「ンな事を理由にしなくても…逆恨みでしょう」
「るせぇな! こっちに取っちゃ立派な理由だっちゅうの!」半ば切れ気味に噛み付くトンヌラ。どうやら、己の名前と同じ位妹の事がコンプレックスになっているらしい。とはいえ、幾ら何でもそんな事にまで責任は取れません。
「いーじゃないか。ヲタク万歳、ヲタクイズビューティフル! 何ならボクが君の義理の弟になってもいいんだぜ?」ずずいとしゃしゃり出てくるナリーノに、トンヌラは足下の石礫をぶん投げた。ナリーノは石礫を避けるが、避けた石が後ろにいたアーロンの頭に当たって、従弟は頭を抱えてしゃがみ込む。つくづく周りに迷惑まくる人達だな、この王族連中は。
「バカ野郎、それが一番嫌なんだよ!」
「何でだよ、共通の趣味と高貴な家柄、ぴったりのカッポーじゃ…第二夫人が嫌ってならマリアが第二夫人でも…がふっ!」アインの投げた二発目の石礫に、ナリーノは敢え無く撃沈。オタップル、或る意味お似合いかも知れないが、トンヌラ在る限り二人は永遠に結ばれる事はないであろう。相手がアレでは、トンヌラがマジギレするのも無理からぬ事では、ある。
「誰が高貴だっつーの。お前の欠陥DNAを後世に残したら、ロト王家末代までの恥だっ!」
「その意見だけは大いに賛成…」
「あんたまでそんなこと言いますかーっ! あんた、ボクと一緒にあの高慢ちきロトトリオをぶっ飛ばしてくれるんじゃなかったんすかーっ!」ナリーノはすっと音もなく手を差し上げた竜王の胸ぐらをつかんでゆっさゆさと揺すぶる。その合間にもトンヌラは、どこからとも無く取り出した分厚い冊子を取り出してページをめくり始めた。こんなバカ共は相手にしておれん、ということか。冊子の表紙には、金の箔押しで『異世界魔王全カタログ』と印されている。
「…一体、其れを何に使おうというのですか」
問いつめる私に、トンヌラが口端を吊り上げる。「さっき言ったろ、ちょっとした時間つぶしの退屈凌ぎさ。…そこで今日は皆さんに、ちょっと殺し合いをしてもらいます」
「…殺し、合い?」
「そーだよ」アインが伸ばした髪を素っ気なく跳ね上げる。「全員で殺し合って、最後の一人だけが生き残ることにしよっかなーと思ったんだけど、三人で話し合った結果、それじゃちょっぴり残酷かな? ってことになってさ。だから」
「生贄を選ぶことにしたわけよ。そこそこ扱い易くて、敵にした時一番厄介な、となると、自ずと生贄ちゃんは限定される訳。なー?」
「おうよ。それにさ、邪神を召喚しちゃった大神官の弟ならポテンシャルは期待できるよね。依り代としての」アインの台詞を受けて、トンヌラが本の表紙を軽く叩いた。
「うわ、いいなぁ。ボクも欲しかったんだよね異世界魔王全カタログ。Vol.2からは全巻揃えてるのに…15000ゴールドで買うけどどうよ?」
トンヌラは羨ましがるナリーノを無視して『異世界魔王全カタログ』を開き適当なページをめくる。トンヌラが召喚の呪文を唱えようとすると、アインがカタログを覗き込んで文句をたれた。
「なんだよこれ、ダセェな。もう少しマシな魔王呼ぼうぜ?」アインはミルドラースのページを人差し指で神経質につつく。
「うるっせーな。お前が呼ぶんじゃねーよっ」
「いくら何でもこんなデブ呼ぶこたないじゃん。もう少し、カッコイイのにしようぜ」
トンヌラは不満げに考え込むが、小さく舌打ちすると、やがて仕方なさそうにページをめくった。
「解ったよアイン。じゃこのデスタムーアって奴にしようぜ。三段階で変身するんだってさ、ほら。超合金のロボットアニメみたいでかっこいいだろ?」トンヌラはアインにカタログのデスタムーアの項を見せる。
「こんなのやだよ。ジジイだし、なんか変身する前に殺されそう」
「ちぇ、文句が多いなあ。じゃあアイン、お前選べよ。俺、お前のカッコイイの基準がいまいちよく解らんし…」トンヌラは投げやりにアインにカタログを渡す。
「じゃあ、これにしようぜ。このデスピサロって奴」アインは適当にカタログをめくって、ページを指差す。
「ダメダメ、デスピサロなんかロザリーをヤり殺されてキレちゃっただけのへたれ魔王じゃん。秒殺されちゃ足止めの意味無いし却下」
「…ちっ。解ったよ。よし、じゃ、これ。今度こそ決定! このエスタークって奴にしようぜ! な、もういいだろ?」
「もういいだろ? ってお前がずーっと文句入ってたんじゃねーかよ! たくよー。お前昔っからそうだよな。まあいっか、じゃあこれね」トンヌラはカタログに折り目を付けて、召喚の呪文を唱え始めた。
「…貴様等、人の生命を何だと思っている!」
「…貴様等、『異世界魔王全カタログ』の価値を何だと思ってるんだぁー! 価値が12000ゴールドに下がっちゃったじゃないかぁ!」
「あんたにそんな事を言われるとは思っても見なかったなー、な、アイン」
トンヌラの挑発に、竜王は拳を握り締める。勿論ナリーノのヲタク魂の叫びは皆にスルーされたままである。地面を蹴って飛びかからんばかりの竜王に、トンヌラは人差し指をちちっと軽く振って見せた。
「アンタんとこのお孫さん、どうなっても知らんよ。ま、何はともあれ頑張ってちょ。それでは、ゲームの始まりです!」
歯ぎしりする我々を尻目に、二人は手を振りながら悠然と段を上がって行った。
二人が段を上がりきらない内に、辺りの空気が私達の頭上に酷く重くのし掛かって来た。鼻腔を突く、鉄錆の匂い。此処からは頭上の様子ははっきりとは見えないが、それでも我が弟が苦悶に身を捩る様は目の前に落ちて来た、血に塗れたサンダルが伝えてくれる。
「い、今から、助けに行くっ!」
サンダルを拾い上げ、握り締めて叫ぶ私に向かって、細い腕がひらひらと振られた。が、その腕が跳ね上がって、下からでもはっきりと見える隆起が盛り上がり、弾ける。降り注ぎ、頬にへばりつく赤い液体。
「……う、ぐぐっ、に、兄さんっ…わ、私は……貴様などに…乗っ取られはしない……負けない、絶対に…ご、ごはっ!」
腹の傷を引き裂いて、エスタークの腕が肘まで伸びた。
「っど畜生どもがっ!」竜王は神像目掛けて正面から飛び上がった。が、身体から突き出たエスタークの右腕がさっと伸びると、掌で地面に向かって叩き付けられる。真っ逆さまに落ちてくると、受け身も取れずに床に沈む。私がすぐにベホマの呪文をかけると、身体をもたげて危なげに片膝を付いた。
「くっ、仕方ない、背後からよじ登るか」
竜王は神像を支える台の裏から像にしがみ付くと、身体をぴたりと寄せてひきがえるの様になりながら存外器用に登っていった。私はその様子を見上げながら、ただ弟の無事を祈る事だけしか出来ないでいた。
以前の私の様に。
壊れ行く世界、腐敗し、堕落し、虐げられる世界を、ただいつか救いの時が来る様にと祈っていただけの、無力なころの私に。
今は、ただその世界が、かけがえの無い私の弟の命にすげ変わっているだけで。そして、弟は世界の様には強くない。私の弟として生まれたばかりに、ただそれだけの為に、私などより遥かに強く、気高い心を持つ弟は、魔王をこの世に呼び出す為の触媒としていわれなく肉体を苛まれ続けているのだ。そして、その当の私は、ただその様を見上げているしか出来ないでいる。
私はそんなに無力なのか?
世界に対して、人はそんなに無力なのか?
違う、私はそう信じたい。
今なら、今の私なら言える。
「オルフェ、私を乗せて飛んで下さい!」
「え、ムチャだよそんな!」
「オルフェ、いいから飛びなさい!」
「わ、わかったわかったから」
私に肩をつかまれて、オルフェは殆ど無理矢理に頷かされた。
「いいですか、エスタークの腕の左側から近付いて下さい。余り近付き過ぎないように、いいですね」
「あ、う、うん。解ったよ。…あんまりしがみつかないでくれる?」
私がオルフェの背中に跨ると、オルフェの体が宙に浮いた。
「何だお前ら、邪魔しに来たのならとっとと降りろ!」
邪神像の上まで飛び上がると、肩口の辺りで魔王の腕と奮闘中の竜王が私達を睨め付けた。傷口は思っていた以上に広がっており、今にも肘が抜け出そうな有様。腕が払い落そうと大きく辺りを薙ぐ度、血が溢れ出る。私は思わず口元を抑えたが、直ぐにかぶりを振った。
「邪魔にはなりません。だから、なるべく奴の腕を引き付けてください!」
「…何か考えがあるようだな、良かろう! …だが、早く決着を付けろよ。かなり、弱ってる」私が頷いたのを認めて竜王は肩口から飛び降りると、翼を広げてボロい鋼の剣を振り翳しエスタークの巨大な腕と渡り合う。
「ええ、勿論です!」私とて、この戦いを何時までも長引かせるつもりは毛頭無かった。決着が遅くなればなる程、私達の勝算は少なくなる。だからこそ、好機を逃す訳にはいかなかった。
私はこの戦いを注視していた。意識を集中し、エスタークの腕が伸び切るその瞬間を待っていた。
「バギクロス!」
呪文の威力を凝縮して放つ。辺りに真空の渦が巻き起こり、エスタークの腕の一点を狙って、真空の巨大な大鎌が襲いかかった。魔王の腕は刃を受けた瞬間痙攣し、その一瞬を狙って剥き出しの骨に鋼の剣を叩き付けられる。腕は裁ち落とされ、地上へと落ちて行った。
「ハーゴンさん、ヤリィ!」オルフェが飛び上がって喜んだので、私は危うくエスタークの腕と一緒に落っこちるところだった。私が必死にしがみついたので、オルフェはぐらぐらしながら、弟を抱えた竜王と共に地上へと降り立った。
しかし、私達を待っていたのは、虫の息で床に横たえられた弟の、見るも無惨な姿であった。血を拭っても、ありったけの回復魔法をかけても、溢れ出る血を、傷口を塞ぐ事は叶わなかった。それどころか、断ち切った筈の異界との門は一向に収束する気配を見せず、弟の身体を蝕んでいく。
「に、いさ…ん……」弟後に濡れた唇から、掠れた声が漏れる。
「もう、無理に話すな」
「…いえ、いいんです……は、なさせて……」ザーゴンは肩に置かれた従弟の手をゆっくりと外して、胸元に置いた。「どうしても、話しておきたい…から…」
弟は、何とか弱々しい笑みを浮かべようと苦心していたが、直ぐに激しい吐血によって笑みは崩れる。
「私は…兄さんを、恨んではいません……確かに、悪く言う者は居ました。でも…兄さんの事ですから、熟慮に熟慮を重ねての決断だと…は…」
「もう、いい…」私は弟の手を握り締めた。随分と、熱が失われていた。「良いから」
「だから、兄さんが生き返ってこの世界に戻って来たと知った時、私は……どうしても、会いたかった。伝えたかったんです…しかし、出会えても兄さんはずっと忙しそうにしていて…、そうかと思えば何かを思い詰めている様子で」
私は今更ながら酷く後悔していた。折角兄弟の邂逅を果たしたというのに、まともに二人で話す機会すら作らず、その場の対応に追われる日々だった。後ろめたさは確かにあった。だが、仮にも血の繋がった肉親ではないか。己の事にばかり囚われて、何故もう少し弟の事を気遣ってやれなかったのだろう?
「良いんです…ただ……」
「ただ?」私は掠れ声を聞き逃すまいと、僅かに身を乗り出した。
「もう一度会って、伝えたかった…。…本当は、少しだけ…貴男を、羨んでいました。兄さんは、私とは出来が違いましたからね。不肖の弟です。私は誇らしさと同時に、貴男を見上げるしか出来ない自分の非力さ故に、己を恥じてもいました。嫉妬は、己が匹敵しうる相手にだからこそ抱ける感情です。だから……」
私は弟の手を握り締めた。「そんな事は無い。不肖だなどと…決して…」
「兄さん、貴男が死んだと知った時、私は悲しみと同時に、微かな安堵を感じもしたのです」
ザーゴンは硬く目を閉じた。僅かに上下する胸だけが、未だ息があるのを報せてくれる。
「けれど……私の奥底から沸き上がって来た感情に、私は戦きました。あんなに尊敬していた偉大な兄の死を、安堵したなどと。私は、そんな自分が許せませんでした。私はその想いを胸に秘め、神の赦しを得るべく、祈りを捧げる日々を送りました。しかし…ある日、貴男の帰還を知り、とうとう告解の秘跡を受ける事を決意したのです……私は告解室で、思いの丈を吐露しました。ずっと貴男を羨んでいたこと、匹敵できぬ己を恥じ、また、貴男がロト三王家に反旗を翻した後、討ち果たされたのを知った時のあの感情が、ずっと私を苛んで来た事も………告解室は静けさに包まれていました。暫くすると告解室の扉が開き、私は驚きました。私の告解を聞いていたのは、父でした」
「……」
「…父は…何も言わずに入口を指差しました。父は、兄さんが世界を滅ぼそうとしたのを知って、兄さんを勘当し、また、兄さんの帰還を知っても知らぬ存ぜぬを貫いて来た人でした。だから、私は父の怒りを買ってしまったのではないかと畏れました……だけれど、父は、唯無言で教会の入口を指差しただけでした…私が何か言おうとすると、父はかぶりを振りました。そして『行きなさい。お前を許せるのは、神でも、ましてや、私でもない』と」
私は話を聞き終えても未だ、押し黙ったまま唇を引き結んでいた。脳裏に、父の姿が浮かぶ。厳しくはあったが温かい父の面差し。私は弟の手を強く握り締めた。弟は酷く激しく咳き込み、身を丸める。蒼白の面に脂汗が滲んでいた。空気は益々重く淀み、瘴気が押し留め様もなく濃度を増していく。
「に、いさん…と、どめを刺して…下さい…」乾いた血をこびり付かせた唇が、小さく戦慄いた。私はこびり付いた血を懸命に拭い取るが、小さく咳き込むと又拭った後が血に汚れる。
「とどめを、刺せ、だと?! 何故…」
弟は無理に笑ったが、直ぐその端から血が溢れ出る。「まだ…魔界との門は閉ざされては…げふっ…このままでは、いずれ、他の魔王が私を依り代として…これ以上、迷惑はかけられない…だから」
「だから、命を絶つというのか」私は弟の法衣を握り締めた。弟は、小さく頷いて答えた。
「自ら命を絶つ事は、許されていません、から…」
私の所為で、皆が傷付き苦しむ。
私の所為だ。
「兄さん…そんな顔を、しないで下さ…ぐ、うぅ…」溢れても溢れても猶止めどなく溢れ出す朱。
もう、助からないのだろうか。
だが、私は、私の手で決着を付けかねていた。唯、熱を失いつつある手を強く握り締め、熱を呼び起こそうと、命を繋ごうと願うばかり。どうして、自ら手を下せよう?
「私には……出来ない…」其れだけを言うのが、精一杯だった。
不意に、私達の上に影が射した。
細身のナイフが閃き躍る。銀の刀身は喉笛を目掛けて滑り込み、止める間も術も無い間に素早く柔い肉を切り裂いた。あれほど吐き出されたのに猶も鮮血が勢い良く迸り、辺りを濡らす。大きく瞠られた弟の瞳は、やがて虚ろなただのガラス玉と化し色を失って行った。ナリーノはナイフを拭うと鞘に刃を収める。
「な、ナリーノ!」
「良かったじゃないですかハーゴンさん、貴男の弟さんがこれ以上、魔王を召喚する為の依り代にされなくて」
「何だと! 貴様に、貴様にそんな事を」
私達が何か言うより早くアーロンがつかみかかった。が、つかみかかったはずの非力な従弟は、ローレシアの王子の次くらいには力のあるナリーノに簡単に締め上げられ、首を極められる。
「ぐうぅ…ッ…」
ナリーノはアーロンの首を極めた手を強く一度締め上げてから、従弟を床に叩き付ける。「ボクはね、彼が、本人の頼みであっても、実の弟を自分の手で止めを刺したとなれば一生悔やむだろうと思ったから、代わりに手を汚したんだ。憎まれ役には慣れっこになってるしね。元はと言えば、君がこんないい人を殺す為に隠れ蓑として弟さんを連れて来たのが一番悪いんじゃないですかね?」
アーロンは、返事をしなかった。
「ちっ…時間稼ぎにもなりゃしなかったか…」頭上で響く声に、私達はその存在を半ば忘れかけていた二人の姿へと漸く意識を向けた。唇を噛み締める。
「マリアの奴、まだかよ…おっせーな」
「準備、出来たわ」
背後の扉が開いたので、扉に押し出されてアインは蹌踉めく。トンヌラが素早くドアノブに手を伸ばして扉を大きく開いた。
「ちぇ、なーんかそういうとこ、要領いいよなお前」
「お前が鈍いだけだって。…そか、準備完了か」
「ええ」マリアは二人のやりとりをいつもの事と聞き流しているようだった。マリアは扉を閉めると、二人に向かって「少し、良いかしら?」と言い残して一人段を降りて来た。
「皆様、初めましての方も大勢いらっしゃるわね」王女は優美な仕草で一礼した。「私がムーンブルクの女王、マリアです。そして…お久し振りです。何とお呼びしたら宜しいのかしら…大神官猊下、…いや、聖下とでも?」
背後で押し殺した笑いが漏れたので、私は肩越しに竜王を睨め付けた。「呼び捨てで結構です、女王陛下。今の私は一介の僧侶ですらない。……私は、棄教したのです」
「そうでしたか」マリアはわずかについと目を細めたが、自ら慇懃で、遠回しなやりとりに終止符を打った。「私も、名前で呼んで下さいませ。此処では女王としての権能も、何の役にも立ちそうにありませんものね。マリア、で結構ですわ。…腹の探り合いは止しましょう、さほど時間は御座いませんの」
私達は互いに、互いの変わり様をじっと見つめ合っていた。
8年の時を経た邂逅。
初めて彼女と出会った時も確かに彼女は美しかった。肩口で躍る銀の髪、澄んだアイスブルーの瞳。なめらかで白い肌に、清楚だが際立った容貌。しかし、歳月は彼女を更に磨き上げていた。14の彼女が宝石の原石ならば、今の彼女はさながら、研磨され台座に嵌め込まれて飾られた極上の宝石だ。
「髪は…切ったのですね」
「ええ。何時までも、夢見る少女ではいられませんもの」皮膚の一枚奥に憎しみを隠したまま、彼女は艶然と微笑む。「貴男は余りお変わりないようですわね」
「見た目は、そうかも知れませんね。時の永い種ですから」
「おっ久しー☆マリアちゃーん」
「ナリーノ、貴男は黙ってて頂戴」マリアはぴしゃりとナリーノを窘める。その態度は有無を言わせぬ物だった。「貴男には関係無いわ」
「ちぇ、絶対剥製にしてやる…」ナリーノは何か物言いたげにしていたが、直ぐにその迫力に気圧され、ぶちぶち文句を言いながら後ろに引っ込む。マリアは何も無かったかのように距離を詰めて来る。
足取りが、段を降りきる手前でぴたりと止まった。
「貴男が戻って来る事を知ってから、どれだけこの時を待ち望んでいたことか」
言の端の一つ一つが、臓腑に食い込む。
「貴男は城に攻め入った時、お父様を始め城の者達を悉く殺し悪霊の神々の生贄に捧げたわ。けれど、私の命は助けた。私はあの時、命乞いをする位ならば、敵の情けを受ける位ならば、自決して果てるつもりだった。けれど、貴男は私を犬の姿で城の外へと放り出した。私がどんなに屈辱を覚えたか、貴男には決して解らないでしょうね、偽善者さん。私は父の後を追う事も許されず、泥水を啜り、身を縮めて風雨に耐え、時には人々の足蹴にされたわ。私はこのまま畜生の姿で、世界の滅ぶ日まで惨めに生きながらえねばならないものかと我が身を嘆いたものだわ」
マリアは段を降り切ると、先程まで私の弟が縛り付けられていた邪神像をついと見上げた。神像に触れた手が形を辿り、触れる事で嘗ての記憶を蘇らせようとしているように思えた。
練り絹に包まれた手が、動きを止めた。
「憶えているかしら? 貴男との二度目の邂逅…そう、丁度この部屋だったわ…立場は逆でしたけれど。私はあの時、貴男に問うた。『何故、私の命を助けたの?』と」
マリアは不意に、私を見た。全てを見透かそうと、懸命に食らい付いてくる少女の眼差しに、私には思えた。
「けれども。貴男は最後まで、私の問いには答えようとしなかった」藍玉の双眸が冷ややかに、私の眼を覗き見る。灼熱の冷気が内で燃え上がる。薄絹に包まれた細い拳が固く握り締められ、思いの丈の強さを思い知らされる。
「もう一度、聞くわ。何故、貴男はあの時私を生かしておいたの?」
形良い唇から迸る激情。
「貴男があの時私を邪神の犠牲に捧げていれば、私の人生はここまで狂う事は無かったのに。いっそ、あの時死んでいた方がどんなに、楽だったか。何故? どうしてなの?!」
「犬になったのが嫌だったの?」
「勘違いしないで頂戴」マリアは横から口を挟むオルフェへの一喝を飛ばす。「お馬さん、私は犬にされた事を恨んでいるのではないわ。私の命を奪わなかった事を咎めているのよ。私は生き残ったお陰で、そして、齢14にして広大な領土を有する王国の、唯独りの王位継承者として祭り上げられた。それが、どんなに辛く苦しいことかは同じ立場に立たされた者にしか解りますまい。どれ程の親切めかした好奇の犠牲にされてきたか、政治的駆け引きの駒として値踏みされて来たことか! …誰も、私を、全てを失った、孤独な一人の少女としては見てくれなかった。私は世界を救った英雄で、広大な領土を有する王国の王位継承者で、そして、未婚の女。それが何を意味するか位、貴男には解るわよね?」
私は頷いた。解るからこそ、一言一言が、痛い。
「だから私、貴男を憎むわ。そして、貴男に後悔させてあげるわ。私に情けをかけたその事を」唇が、綺麗な形に吊り上がった。仄かな紅色が冷気にあって、鮮やかに色付いている。
血の所為なのだな、と思う。色合いこそ似ていないものの、何処か魅入るような、全てを見透かすような眼差し。魅入られて、当然だ。私は忘れかけていた、彼女を一目始めて見た時の事を思い出していた。凛として、可憐で芯が強く、しかし何処か頑なで、そして…孤独で、嫋やかな、少女。
アイスブルーの瞳の奥に秘めた愁い。
彼女は、変わっていない。
「いいえ」私はかぶりを振った。「私は貴女をこの手にかけなかった事を、後悔してはいません。寧ろ、そうして良かったのだと、私はもっと大きな、取り返しの付かない過ちを犯さずに済んだのだと信じています。…貴女の御陰で」
だから、手を差し伸べるしかない。
手を取ってくれるよう、祈りつつ。
「だから、今度は私が、貴女を過ちから救う番です」
「…もう、遅いわ」マリアは拒むように目を伏せる。「私は何もかも失った。貴男のせいで」
「いいや、貴女は私とは違う。貴女は、まだ引き返せる、未だ」
「間に合う、ですって!? はっ、笑わせてくれるわね。私…私達はもう、貴男の持っている雨雲の杖さえ手に入れれば天に昇れるまでの処へと来ているのよ。今更引き返すつもりなど無いわ」
「では」今度は、私が距離を詰める番だった。マリアは怯んで、邪神像から手を離し後じさる。「何故、貴女はこのように、うだうだと過去にしがみつくのですか? 貴女は、引き返したいのだ。出来得るならば。貴女の望みは神になる事などではない。違いますか? 貴女の望みを当ててみましょうか。貴女は」
「女王としてではなく、世界を救った勇者としてではなく、一人の女性として、否、一人の人間として愛されたかった。違いますか?」
「辞めて! なんて事言うの? いやらしい!」
マリアは耳を塞いだが、私は引き下がる気は毛頭無かった。「貴女は力を求めた。誰にも己の存在を脅かさせない為に。しかし、力を手に入れた所で貴女の恐れは決して消えはしないでしょう。貴女は欲すべき物を間違っている。神の如き力を手に入れたとしても、貴女の渇望は満たされる事は決してありますまい。その力を、貴女はどう使うつもりなのですか? 絶え間ない不信に苛まれた暴君となりたいのですか? 貴女の名をして、我が名に比す悪名として後世に残したいのですか? …私は、貴女…貴女達にそうなって欲しくはない」
「近付かないで!」
「今の貴女に本当に必要なのは、己の存在を脅かされない力などではない、貴女を、女王として、政治の道具として、勇者としてではなく、貴女自身として受け入れてくれる友なのです」
私は言い終えると口を閉ざし、彼女の反応を待っていた。
不意に辺りが哄笑で満たされ、私は怯んだ。マリアの口元に滲み出た笑みはしかし、酷く、寂しげだった。
「友なんて、居ないわ」
「…えっ?」私の戸惑いが、マリアには可笑しかったらしかった。彼女はころころと、少女めいた笑い声を上げる。その声が、酷く虚ろに反響する。
「ウフフ……でも、貴男、変わっていないのね。ちっとも…優しさのつもりで、私を苦しめるのも、ちっとも……何故、私なんかに優しい事を言うの? 貴男の一族を追い詰めたのも私、貴男のお友達を魔物に命じて襲わせたのも私。貴男の弟を、足止めに利用するようアイン達に提案したのも私。なのに、何故私を憎まないの? 聖人ぶって私を見下し、辱めようと言うの?!」
「………」
違う、と即断するには、私の言葉は説得力を持たなさ過ぎる。否、恐らく、彼女の方が正しいのだろう。私は足下を見つめながら、ずっと言葉を探していた。
「私の大切な仲間や、肉親が傷付けられるのは苦しく、辛い。私自身が傷付けられるより、ずっと」私はかぶりを振った。「しかし憎しみはもっと苦しく、辛いことです。……綺麗事に聞こえるかも知れません、ね。でも、憎しみは結局、憎しみの連鎖しか生みません。……今なら、私が受け止められる」
「自惚れないでよ!」
「自惚れではありません。今なら、全てを私にぶつければいい。貴女を陥れ、苦しめ続けて来た全ての原因は私だ。…それで、気が済むなら。貴女が、それでやり直せるのなら」
「…それで、良い、というの?」
「貴女が全ての頸と復讐心を、私と引き替えに断ち切るというのなら。私の命など軽いものです。しかし……生憎と、私の命は私だけの物ではもはや、ありません。貴女の人生が貴女にとっては何であっても、既に貴女自身の手から離れたところで価値を決められているようなものです。良くも悪くもね。ですから」私は肩越しに仲間の姿を振り返る。「ですから、貴女が私の命を軽く扱えば、私の仲間は貴女を許してはくれないでしょうね…面倒な事ですが。それでも私は、何と皆を説得してみるつもりです」
「……」マリアは、ふと顔を上げた。「貴男は、幸せな人ね」
「そうかも、しれません」
「…貴男、やっぱり、変わってない。純粋なのね。でも、もう、いいの……私はあの時の私じゃないの。私はしがらみに囚われて、もう身動きが取れないわ。目指す道程がどんなに愚かしいものであっても、既に、私自身の望みでなくなっていても」
「変わってない、貴女は、変わってない」私はマリアの手を取った。「偽悪ぶるのは止しなさい。貴女は自分を傷付けているだけだ。そんな事をして、何になるのですか。貴女は、私のようになってはいけない! 貴女は、勇者でしょう!」
私の手を振り解こうとしたマリアの手が、暫し硬直した。
「…勇者になんか、なりたくなかったわ……」
手の上に、温かい液体がひた、と一つ落ちた。
マリアは、泣いていた。
「全ては私が最初に言い出したの。私は怖かったわ。このまま、私の人生を大人達の思惑でいいように操られるのが嫌だった。だから、アインとトンヌラの二人を唆して王位を継ぐよう説得したわ。父王二人には退位していただくようにして、ね。そして三人で、父上の遺志――神となる計画を引き継ぐ事を決めたの。私達三人が力を合わせれば怖いものなんて何もないとあの頃は信じていた。私達は、神すら滅ぼしたのだから。だけど…私達は、あの頃の私達ではなくなってしまった。怖れていた大人達と、私達は同じになってしまったのね。……お笑い種だわ」
マリアは涙を拭った。濡れた藍玉が艶めいて、睫の上で雫が跳ね、零れ落ちた。「私には、二人を引き留める責任があるわ。彼等の運命を狂わせたのも、私の責任、だか……!」
マリアの細い体躯が、一瞬強張った。
胸に散る紅い薔薇。マリアの身体が頽れ、続いて深紅のケープが覆い被さる。
「ご、めん…なさい……それから……」マリアは最期に、力無く微笑んだ。哀しくも、美しい微笑み。「仲間だけは、大切になさっ………」
「マ、マリア!」助け起こそうと駆け寄る私の足下に矢が次々突き刺さる。溢れた血が、目地に沿って流れて行く。
「な? 女はすぐ裏切るから信用ならないって。言ったろ?」
「と、トンヌラ…」マリアに向けてボウガンを放ったのはトンヌラだった。トンヌラはボウガンを放り捨てると、狼狽えるアインに向かって一喝する。
「ぅ、ウダウダゆーなっ! 俺らはもう、引き返せねーんだよっ! 走り続けるしかねーんだよ…なのに、あいつ立ち止まろうとしやがって…しっかりしろよアイン!」
「…お、おうっ」アインは一度だけ、息絶え冷たくなったマリアの骸を見下ろした。「と、とにかく! お遊びはおしまいだ!」
「…貴方達は…彼女は仲間でしょう! 何と言うことを…」
「あんな奴、仲間じゃねえよ! 裏切ったのはマリアの方じゃねーか! 今更臆病風に吹かれやがって。そもそもマリアを誑かしたのはお前じゃねーか! そんな事言われる筋合いはねーよっ!」
「……許しません!」私は雨雲の杖を握り締め、二人を睨め付けた。
「ちょっと待て」
が、立ち上がろうとした途端肩を掴まれて引きずり戻され、私は床に叩き付けられて尻餅を付く。「あいたぁ…ちょ、ちょっと何するんですかっ!」
「先程から口を挟まずにおればウダウダウダウダウダウダウダウダと言いたい放題言い腐りおってからに」竜王は軽く私を足蹴にすると、前へと進み出る。「さっきお前、またぞろ勝手に己の命を人様にくれてやろうとしたな、馬鹿者が! 全く以て学習能力が無いというか何というか、お前自身にお前の命を預けて置いたら命が255個在っても足りんわ! …とにかく、お前は引っ込んでろ」
「へ?」惚けた面の私に向かって、竜王は顎をしゃくった。
「一人でやる、と言っておるのだ。邪魔、どけ」
呆れ返ったのは少なくとも、私だけではなかったらしい。アインとトンヌラは互いの顔を見合わせた。「はあ?」
「三人揃わぬ貴様等など、何を怖れる事があろう? …さあ、かかってこいアホガキ共。お尻ペンペンしてやるから覚悟しろ!」
「てめぇ、バカにすんな! お前らこそ、一度にかかってこいやぁ!」
「いや、何遠慮しておく。…却って弱点が増えるからな!」
「ふっざ、けんなよ! なめやがって!」トンヌラはボウガンを投げ捨てると、手摺を乗り越えて飛び降りた。 隼の文様を施した鍔を持つ細身の剣が躍り掛かる。竜王はかわす事無く殆ど無抵抗で突き刺された。
「やったぜ! …うっ!」
下から手を振り払われ、トンヌラは柄を手放してしまった。そのまま体当たりをかましたので、トンヌラは吹っ飛ばされてアインと激突し、二人は勢い余って引っ繰り返る。竜王は腹から細身の剣を抜き取ると、傷に手を翳して瞬時に癒してしまった。
「く、くそ、奴、剣を奪う為にわざと急所を外してトンヌラに刺されやがったたんだ!」
竜王は無言で冷たく笑うと、トンヌラから奪った隼の剣を振り翳し、二度三度と空を切った。「中々悪くない剣だな、拝借させて貰うぞ」
「ぐっ…」トンヌラは悔しそうに床を叩いたが、アインに退けとばかりに突き飛ばされて床に転がされる。アインは腰に下げた大剣を鞘から抜き払い、大きく振りかぶって叩き付ける! が、刃は火花を散らしつつけたたましい金属音を立てて床の隙間に食い込み、アインは引き抜こうと力を込める隙を狙われて脇腹を蹴り上げられ、床に転がる。竜王は大剣も引き抜こうと柄に手を掛けたが、これはトンヌラの体当たりで敢え無く阻まれる。
「と、と、と…」
「右です、右!」
「余計な世話だ! お前らは後ろ引っ込んでろ」竜王は向かって右から大剣を大きく薙ぐアインの剣を、体を開き蹌踉めきながらも何とか躱す。「口を出せば、お前も戦いに加わったとみなされる、ぞ。とりゃっ!」
なるほど、ね。
バラモスの様な卑怯者なら兎も角、仮にも勇者と呼ばれた一国の主が、戦いに加わらぬ者を突然襲うような卑怯な真似はすまい、と読んだ訳だ。あの二人に白兵戦を挑まれて匹敵する者は彼を除いて他にいない。術なら多少対抗も出来ようが、乱戦に於いては派手な魔法は却って使い辛い。魔法を得意とするムーンブルク女王が居ない分、魔法を怖れる必要はさしてない。
「ああ、あの娘が居たなら、お前らも少しは有利に闘いを進められただろうになあ」竜王は隼の剣を軽く振り回して挑発する。挑発に乗せられて、アインが正面切って斬り掛かる! が、細身の剣で刃を受け止めると見せかけ、剣を振り下ろした処を狙って籠手目掛け刀身を叩き付ける。アインは刃を離しこそしなかったものの、僅かに怯んだのか次の振りへの動きが遅れる。そこを目掛けて追撃を叩き込む。
「う、くっ!」握りが弱い所為で体勢を立て直し辛く、剣としては遥かに軽い筈の隼の剣で撃ち負けて、ローレシア王は受け切れずに追い詰められて行く。アインを助けようとサマルトリア王が放ったベギラゴンも軽く弾き返された。彼等は能力を特化したが故に、個々の能力は常人を遥かに上回るものとなった。だが、一人が欠ければ個々の弱点をさらけ出す事になる。
そして、彼等はとうに、世界を救うために戦う勇者としての心を失ってしまったのだ。今の彼等は、世界を救った勇者ではなく、自らの野望に燃える施政者に過ぎない。共に苦労を分かち合った者同志の友情と信頼は失われ、代わりに二人を繋ぎ止めるは野望と打算。もはや、二人など畏るるに足りぬ。
「おっと!」隼の剣が真ん中当りで刀身を真っ二つに断ち折られ、竜王は目をぱちくりさせた。軽い金属音が響いて、薄い刃が床を滑って行く。竜王はぽいと剣の柄を投げ捨てた。「折れちまったな」
「ゲームオーバーだっ!」アインが大きく稲妻の剣を振りかぶった!
「どうかな?」竜王は床を滑り行く刀身を素早く足で踏み付けると、刃を拾い上げて真っ直ぐに突き付ける。アインの喉元には、隼の剣の破片が狙い違わず突き付けられていた。
「確かに力は強いし剣捌きも素晴らしく巧い。だがな、此処が決めだと気張ると、溜めが大きくなり過ぎてワンテンポ剣を振るのが遅れる、それがお前の弱点だ。どだ、間違っておるか?」
「う、ううっ…」アインは悔しげに歯噛みした。
「それからお前」竜王は続いてびし、と剣を握り締める手と反対の指でトンヌラを指差す。「非力な癖に突っ込み過ぎだ。アインと違って隙の無い動きが出来るのだから、ヒットアンドアウェイを心がけるべし。互いに功を争って戦っているようにしか見えなんだぞ」
「る、る、るっせぇ! い、い、いちいち説教しやがって!」一々痛いところを突かれて、トンヌラは顔を真っ赤にして叫んだ。「ひ、ひ孫の命が惜しくないのか」
「ぁん?」突き付けられた刃の矛先が僅かに鈍る。
「もっかい言うぞ。あんたのひ孫の命が惜しかったら、雨雲の杖を渡せ」
「まだそんな事を言うか、バカガキ共。人が親切で言ってやってるのに…貴様等に勝ち目など無い。悪足掻きなどせずさっさと諦めろ。殺さぬだけでも情けと思え。これというのも…うぐっ」竜王は口を噤んで喉元まで出かかった台詞を呑込んだ。もしも彼等が己の血を引いていると知らされたらどういう反応をするか、想像するだに怖ろしい惨劇が待ち構えているのに気付いたのだ。これこそ正しく、言わぬが花というものだ。
「赤の他人の癖にガキガキ言うなっ! もう一度言うぜ、あんたのひ孫、俺らが死んだらどうなるか」
竜王は一度だけ瞬きした。「チビと引き換えだ」
「それは出来ないな」トンヌラの口振りには、立場の逆転に対する確信が滲み出ていた。アインも応じる。「杖を返してくれたら、場所はちゃんと教えてやるよ。心配しないでいいよ。今はちゃんと生きてるからさ」
「…しょうがありませんよ。諦めましょう」
「ちっ」竜王は私から受け取った雨雲の杖を、アインに放って寄越した。アインは杖を受け取ると、素早く剣の間合いから離れる。
「やったなトンヌラ」二人は手を叩き合い、誇らしげに雨雲の杖を掲げる。
「チビはどこだ。約束は守ってもらうぞ」
「あんたのひ孫、この神殿の食料倉庫にいるよ。早く行ってあげた方がいいんじゃない? んじゃ」そう言うと二人は早足で上の階へと消えて行った。
「ね、あの二人止めなくていいの?」オルフェが心配そうに階段を見上げた。
「いやチビが先だ。あ奴ら、恐らくはそこまで計算に入れてチビを下の階に閉じ込めておいたのだ。おいハーゴン、食料倉庫はどこだ?」
「神殿の下の階を奥に行った所です。行きましょう」
地下倉庫の扉を開けると、ぞっとする光景が待っていた。
部屋一杯に火薬の匂いが立ち込め、ぎっしり火薬の詰まった樽が部屋中所狭しと並べられている。床には魔力を封じ込める魔方陣が描かれ、その中心にひ孫の入った檻が天井から4本のロープで吊されている。そのロープの先には、ややこしい仕組みはともかくとして、檻にかかる負荷がなくなるか、大幅に振り切れるか何かしてバランスを崩すと摩擦熱が起こって発火する装置が仕掛けられていた。檻の中ではひ孫が憔悴し切ってうずくまっていた。
「チビ! 今出してやるからな。オルフェ、ユカ、お前ら装置外せ」
「ダメですほら、良く見て下さい」私は一同を制し、部屋の下方を注意深く指差す。「部屋中にテグスが張ってあるでしょう。あれに引っかかるとロープが切れる仕組みになってます」
「ええい、腹立たしい連中だ。これも時間稼ぎのつもりか…クソッ」
「火薬をダメにしちゃえば?」
オルフェの提案に、ナリーノは侮蔑を以て返す。一々目を見開き、肩を竦めて当惑めいたポーズを取ってみせる。「雨雲の杖はさっき取られただろう。オルフェ、キミはバカか?」
「うるさいなナリーノのバカ! 二等兵は死刑なんだぞ!」
「寧ろキミが死刑。死んだら剥製にしてボクの部屋に飾ってやるよ」
「二人とも、いい加減にしなさい!」喧嘩が始まりそうだったので、私は二人の間に割り込んで二人を牽制した。
「待って、くれないか? このテグス、どうも繋がり方がおかしいと思わないか?」アーロンが二人を割って進み出たので、私は驚いた。
「え? いや、そう言われれば、そうと言えなくも…しかし、何故」
「そんな事はどうでも良いだろ」アーロンは素っ気なくいらえると、杖を振り翳す。杖から光が迸り、辺りは光に包まれる。光がやがて収まると、部屋中に張り巡らされた糸は三分の一くらいに減っていた。「やはり幻影だったか。これなら何とか通れるだろう」
「これならオルフェはダメでもユカなら通れるな。よし行って来い」
ユークァルは防寒具を脱ぐと、嫁入り前の娘にはさせたくないようなみっともない格好で這いつくばって発火装置を外しに行った。
「あ、アーロンお前…有難う…」礼を言う私に、アーロンは素っ気なくいらえた。
「自惚れるな、お前の為じゃない。ただ、こんな卑劣なやり方が許せないだけだ」
籠から降ろされた少年はぐったりしていたが、御先祖様の姿を見付けるや、しっかと袖にしがみついて離さない。仕方ないので抱きかかえ、背中を軽く叩いてあやしてやる。
「ひい、おじい、様…」
「ああもう、無理して口をきかんでいい」
「余は…曾爺様をお恨み…申しておりました…。父様が亡くなったのも、太陽の下を堂々と歩く事さえ許されないのも、全て曾爺様のせいだと。…故に…父様の言いつけに逆らって…。余は解っておったのじゃ。父様が死んだのは、本当は、サマルトリアがごり押ししてきた現国王の妹君と王太子との婚約に父上が反対したせいであったと。でも…余は、寂しかったのじゃ。ロトの勇者達は、そんな余の事を友達だと言ってくれた。だから…もっと、もっとリカルドのいう事を聞いておれば良かった…」
そう言って、竜王のひ孫は抱き人形のようにしがみついて啜り泣いた。
「あーはいはい、全く、でかい赤ん坊だな。……アーロン、ロンダルキアから降りる時にチビを連れて行ってくれ」
「あ、はい…か、構いませんが…」アーロンは突然呼ばれて目を瞬く。
「余も…供を」
「馬鹿ぬかせ。眼の下にくまさんが一杯住んでおるぞ、家に帰ってゆっくり寝るがいい。あ、すまんすまん。あの城、トンヌラのとんちきが地下迷宮ごと吹っ飛ばしてしまいおったから何にも残っておらん。そうさな、ムーンペタにでも行くが良い。リカルドも居ないが、ムーンペタの奴らなら、そうお前に邪険にすることもないだろうよ」
ひ孫はこくこくと頷いて、漸く袖口を離した。ゆっくりと、足下に降ろしてやる。
「さて、これでこちらは背負う物がなくなったわけだ」ナリーノは火薬を指差した。「この火薬で塔ごと奴らをふっ飛ばしちゃいましょう! これで全てはめでたしめでたし」
「いやそいつはだめだ。もし奴らの開いた天界への門が利用出来るなら、我々も天界に行かねばならん。それこそが我らの宿願だからな。さ、行くぞ」
我々は改めて螺旋階段を上り、祭壇より儀式の間に向かう。
「何故また祭壇があるというのに、上にも儀式の間があるんだ?」
「それは…祭壇が集約点なら、上の儀式の間は丁度、レンズの役割を果たしているのです。焦点がなければ、聖地の力――我々は竜脈と呼んでいましたが――を有効に利用する事が出来無いのです。力はあるだけでは唯の力に過ぎません。我々がその力を利用するには、力にベクトルを与えてやることが必要です。ま、理屈はこれ位にしましょう」
ドアノブに手を掛ける。中から、特別変わった気配は感じられない。
扉を開いて中を覗き、私は顔を伏せた。
「どうした、とっとと中に…うわ」
部屋の中には魔法陣が描かれ、ロト一族の三種の神器が正三角形を描くように配置されている。真ん中には魔法陣によって集約された魔力が渦を巻いており、その中では…かつてアインとトンヌラであった肉体の残骸が、辺りに散らばって床を所々赤く染めていた。
「裏切りを怖れて、最後まで正しい扉の開き方は教えなかったのだろうな」
「マリアは、もう彼らも信用出来なかったんでしょうね」
生死を共にした仲間すらも信じられぬ孤独に、私は胸が痛んだ。
「おそらくはな。ところで、どうやって魔法陣を起動させればちゃんと旅の扉が現れるのだ?」
「それは簡単です」私は魔法陣をチェックしながら部屋を一周して、結論を出した。「三種の神器の配置が間違っています。どなたか磁石をお持ちでないですか?」
「オーケーオーケー、ボクが持ってますよ。ペルポイの職人に特注で作らせた、金無垢のヤツがね。ほら、裏に歌姫アンナのブロマイドが入ってるんですよ。アンナもザハンの金持ちと結婚して引退しちゃったからな〜」
私はそれには応えずに、ナリーノから金無垢の方位尺を借りて方角を測った。
「ああ、やはり。ユークァル、その太陽の石をそちら側に置いて、雨雲の杖とロトの印の場所を入れ替えて下さい」
ユークァルが私の指示通りに三種の神器を配置し終えると、暴走気味だった地脈の力が徐々に収斂して力の渦を形作る。渦はやがて収まって行き、私達には馴染みの、あの旅の扉が現れた。それを見届け終わった瞬間、安堵と悲しみと怒りと疲労とやるせなさ、そして自責の念が一度に押し寄せ、立ちくらみが私を襲った。私は壁に手を付き、額に手を当てて深呼吸した。
ひゅうっと言う、不自然な呼吸音。
胸を締め付けられる様な痛み。こみ上げる不安。
目が霞む。頭が眩む。
苦痛に耐えられなくなった瞬間、私は喉元にせり上がってきた鉄の味を辺りに撒き散らした。
「ハーゴンッ!」
「ハーゴンさんっ! 大丈夫かよっ!」
体を支えきれなくなって崩れ落ちる意識の端で、抱え起こされる感覚だけが、唯一ある。
「しっかりしろ、これからだというのに」
手が強く、強く握り締められる。握り返したかったが、もう指先にも力が入らなかった。
「…昔からの、ゴホッ、胸の、病…」
「馬鹿が。どうせ貴様の事だからもっと前からこうなっていたのを知って、黙っておったのだろう!」
私は項垂れた。
「馬鹿野郎、死ぬな、生きろといったであろうが! 例え天地が貴様の命を定めたとて、この私がその様な運命は認めぬ! だから生きろ、良いな! 何故…何故貴様の様な良い奴が不治の病に冒されねばらんのだ。貴様が何をしたというのだ。馬鹿野郎…馬鹿野郎……。何の為に、何の為に、貴様をここまで連れてきたのか解らぬではないか……。」
そう出来るなら、もしそれが許されるのならば、そうしたかった。だが、もう…。
ああ、神よ、神よ、何故貴男は私を見捨てたのですか?
「馬鹿者! 祈りなど捧げるな! 良いか、罪も許しもありはしない。そんなものはまやかしに過ぎぬ。何故に神は世界を創造し、自我を与え、人々に自らを崇拝させるか、まやかしの罪と救いとを説いてきたのかが、貴様にはまだ解らぬのか? 良いか、それはな、神が我々を苦しめ、その藻掻き苦しむ様、絶望に身を焼かれる様、無力さに歯噛みする様、そして、奴に救いを求め、自らを放棄する様を愉しむ為だけにだ。気に入るとはな、そう言う事なのだよ。滅ぼされずにいられるという事はな。……そうだ、私はその事を知ってしまったが故に殺されたのだ。世界の秘密を知ってしまったが為にな……。だから、だからこそ、貴様の様な良い奴が苦しみ、虐げられる様な世界を造った、そして、私と、我が血を引く者達とを、己れの愉しみの為だけに弄んできた世界の主を、この手で、この手で裁く日までは、貴様には生きていてもらわねばならんのだ! この世に世を享けてより、初めての、そしてたった一人の友を、失う訳にはいかんのだ! 死なないでくれ。置いて逝かないでくれ…頼む……」
「今」私は、懸命に残りの力を言葉と共に絞り出した。「友、と、仰いましたな…」
「ああ」小さく頷いた。「だから、逝くな。泥水を啜っても、木の皮を囓ってでも生きてくれ。私の為に」
私は、小さく頷いた。人の為に死ねるとは何度も思えたが、人の為に生きられる、と思えたのは、恐らく、この時が生まれて初めてだったように思う。
視界が明るく、眩い光に満たされた。この光に、私は見覚えがあった。
強く温かく、優しい光。
光の波動が止めどなく溢れ出し、部屋を、そして私達を包む。
魂の暗い闇の奥底が根底から照らされ、癒され、蟠っていた何かが頭を擡げて来た。痛みが薄れ、身体が軽くなって行く。
凍り付いていた記憶が、感情と共に鮮やかに蘇る。
二度と思い出すまいと自ら、封じていた記憶。
「お…もい…出しました……」
「どうした、何をだ」肩を揺すぶられ促されて、私は、記憶の糸を辿り引きずり出す。
「私が何故、己れの内に罪を認めてしまったのかを……」
私は唇を噛み締め、何度も擦り合わせた。乾いた血が、こびり付いていた。
「それは、私もまた、世界の秘密を知ってしまったからです…」
世界の秘密。
私を呪縛して来た、最後の呪いの枷。
その鍵は、自ら差し入れ回さねば。
己を解き放つのは、己自身なのだ。
「その秘密とは…ああ…、私が最も愛し、己の全てを捧げて来た神が、己の慰みの為だけに、世界を、そして私を弄び、慰み物にして、捨てた事です。……私は、世界の秘密を知ったから、もう、用済みになったのです……私は、神の玩具として選ばれた贄だったのです」
「やれやれ」
その場に似つかわしくない、やけに醒めた嘆息が辺りの空気を乱した。
「ボクは貴男の事、もう少しドライな方だと思ってましたヨ。魔王にしちゃ優し過ぎますねェ。はっきり言ってチョーがっかり、失望しちゃいました」
「貴様に対してなら幾らでも非情になれるが?」
「そうですかネ?」
かちゃっ、という僅かな金属音が鼓膜を刺した。
「身内の命がかかっていてもですかネ?」
私達は彼に気を許し過ぎていた。否、許していたつもりはなかったが、それでももっと警戒しているべきだった。ナリーノのボウガンは、正確にオルフェの後頭部をぴったりマークしていたのだ。
「う、うう、おっさん……」
「どういう心算だナリーノ」
「いや何、折角ロトの3人組がいいものを残して行ってくれた訳ですから、それをボクが有効活用してあげないと勿体無いかなー、なーんて考えてるだけですよ。ただその為には、貴男達にもちょっとだけ協力して戴かないといけない訳で。いやあ、ボクは野蛮人じゃありませんから、奴らみたいに貴男達に死んでくれ、なんて言ったりはしませんよ」
「へへんだ、ナリーノのバーカ! オレはさ、竜王に何とも思われちゃいないんだよッ!」
「はいぃぃ?」
「オレ、散々おっさんとか言ってヤな事言ったしさあ、ホラ、下級妖魔だからあんまり強くないし、バカ話するだけで大して役にも立ってないお荷物だもんね。だから、お前なんかに人質に取られたって何とも思わないし、オイラが殺されちゃっても全然平気なんだよ! や、ヤーイ、ザマーミロバカナリーノ!」
「…う、くそ。こんな奴を人質に取るんじゃなかった…」
ナリーノは舌打ちしながらもボウガンの照準をオルフェの後頭部から1ミリたりとも離そうともせずじりじりと後じさる。
「どうしたナリーノ、引き金は引かないのか。後が無いぞ」竜王は後じさるナリーノを追って一歩一歩距離を詰めていく。距離を詰められぬようナリーノは更に後ろに下がった。
「ううっ」
「引いてみろ」口ぶりは笑っていなかった。
ナリーノの足元で、欠片が塔の外に落ちていった。欠片はからからいう音を立てて落ちていったが、すぐに外の吹雪に掻き消された。
「貴男に世界の半分をあげますよ、闇の世界をね!」
ナリーノはオルフェを突き飛ばし、ボウガンの照準を竜王に向けた。
ナリーノの体が、後に仰け反った。
「バナナァーッ?!」
何かに足元を取られ、ナリーノの体は竜王が間合いに飛び込む前に虚空に放り出された。
「くっそー! 憶えてろよぉぉぉ! ボカァ必ず戻ってくるからなぁぁぁ……」
ばっ、と布が風を孕む音。ナリーノが風のマントを広げたのだ。マントは風を胎み、ナリーノの体を巧く気流に乗せる。と、急に風向きが変わり、ナリーノはロンダルキアの強風に煽られてあらぬ方へと流されていく。
「うぎゃっ」
死者の塔、遥か下方が血に染まった。ナリーノは死者の塔に叩き付けられて、そのままずるずると塔に血痕を擦り付けて墜ちて行った。
「あーあ、やっちゃった」
「ふん、阿呆が。世界の秘密を知る者は消される運命にある、今し方そう言ったばかりではないか。……ことにオルフェ」
「な、何?」
竜王は無造作にオルフェの肩を叩いた。
「あまり卑屈になるな。それではユカと同じだぞ。お荷物だったらとうの昔に鍋にして喰っておる」
「う、うん」
「しかし、何でナリーノ王は落ちてしまったのだろう。……? 何だこりゃ」
「何でまた、こんな所にバナナの皮が…」
アーロンが、ナリーノが立っていた辺りに落ちていたバナナの皮を摘み上げた。
* * *
天界で、世界の総てを映し出すという水晶球を片手に、マスタードラゴンはバナナを頬張っていた。
「ふふん、あのキチガイ王は早速脱落か。中々の悪辣ぶりであったが、所詮は人の子、まだまだ甘いわ。…それにしても、流石は我が血を引く者ぞ。我が子等よ、せいぜい余を愉しませておくれよ。そうでなくては、汝を何の為にニヴルヘイムから脱走させたか解らぬでな……ククク…」