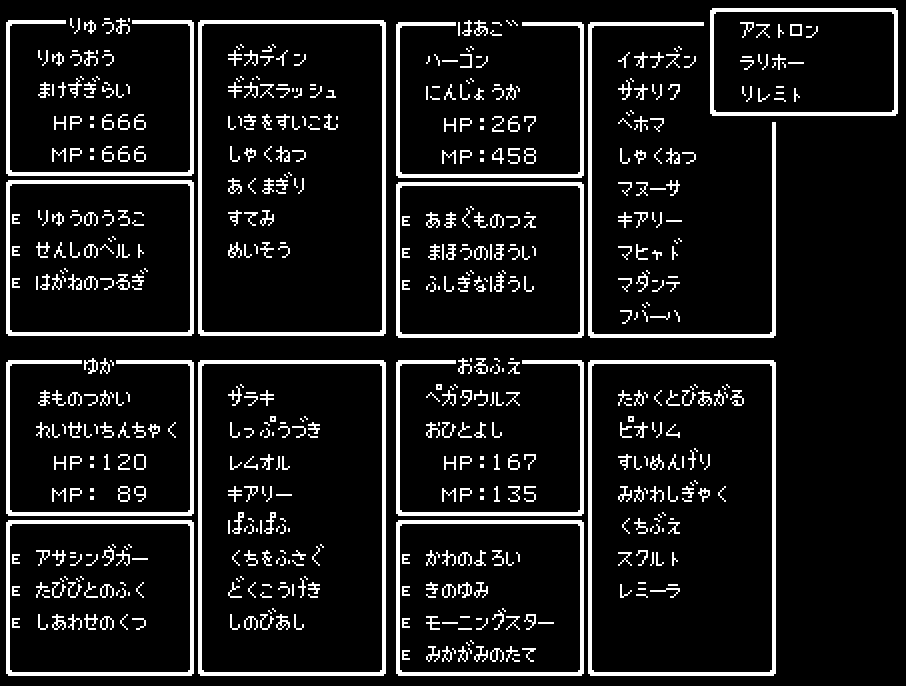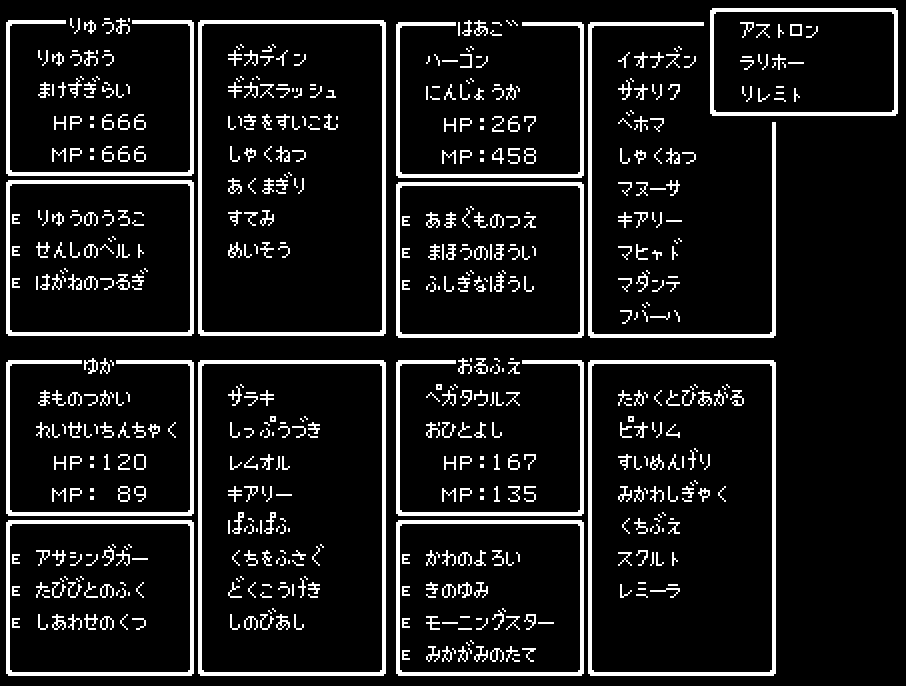第V章 タイジュ国 〜殺人依存症の愛玩人形は綿菓子の夢を見るか?〜
小さい時の事は良く憶えていません。
憶えてる事と言えば、おじいちゃんが生きていた頃に住んでいたお家にはテラスがあって、いつもテラスからお兄ちゃんと屋根に昇ろうとしてお母さんに怒られていた事、お庭には、紅色の花を付ける木蓮の木と、春になると黄色い花が咲く木があって、春になると小さい花をいっぱい付けてた事、賄いのばあやが作ってくれたブルーベリータルトが好きだった事位です。
ある日、お城の兵士がいっぱいやってきて、おじいちゃんを連れていきました。2〜3日経って、おじいちゃんは帰ってきましたが、おじいちゃんはいっぱい殴られた痕を付けて、ぼろ切れのようになっていました。そのショックでしばらくしておじいちゃんは死んでしまいました。それで、あたしたちはその大きいお家を出ていかなくてはならなくなりました。
それからあたしは、さる偉い人の所に連れていかれました。そこでは色んな事をされました。あたしの左目は義眼なんですけど、その目もここで無くしました。
そして、そこで、偉い人に命令されて、お父さんを殺しました。言われた通り、お父さんを薬で痺れさせて、動けないお父さんと無理矢理しました。お父さんは泣きながら、「やめろ」「何で」って……。それから、殺しました。お父さんの心臓、ドクドクしてて、赤くて綺麗で暖かかった。とっても……。
それからあたしは、偉い人に命令されて、人を殺すようになりました。魔物も、人間も区別なしです。そしてしばらくして、あたしはある人の手に売られていきました。何でも、新しい御主人様は魔族の王でとても強い大魔王なのだそうです。でも、命令を下す偉い人が変わるだけで、他は何も変わりませんでした。
でも、暗殺に失敗して、二人に付いていくようになってから、何かが変わりました。
あたし、ずっとこう思ってました。
この世の中に、取り替えの効かないものはないって。
でも、二人とも違うって言うんです。
竜王は「お前は取り替えが効くかもしれないが、私は違う。それは、私が神でお前が虫螻だからだ」って言います。
ハーゴンは「この世の中の命は皆尊くて、かけがえのない物です」って言います。
私には、解りません。
何が正しいんでしょう。
誰が正しいんでしょう。
どっちが正しいんでしょう。
* * *
「ふんふん、良い匂いがするな」
「ホントだあ。お祭りでもするのかな。オレ、お祭りって初めてなんだ。何か買って」
「ダメですよ、路銀はほとんど無いんですから」
「何を言う、これというのも全部お前のせいではないか。オルフェに何か買ってやれ」
そう言われて、私は言葉に詰まってしまった。それというのも、前の世界で勇者ロトの襲撃を受けた時、私を庇って深手を負った竜王の傷を治す為、皆で温泉に駐留したのは良かったのが、間抜けな事に今度は私が風邪を引いて寝込んでしまったという前歴があるからなのだった。これは当分強い事言えないぞ。まいったな。
「うーむ、ここはどの辺なんだろうな」
「世界樹の外回りである事は間違いないみたいですが。世界樹の外回りの世界といえば、タイジュ国にマルタ、カレキの国辺りでしょうか。ん?」
さっきから誰かに引っ張っられていると思ったら、オルフェがもの欲しそうな顔で私の裾をつかんでいた。
「そんな事どうでもいいよ、オレお腹空いちゃった。さっきからすげえいい匂いするんだもん。何か食おうぜ。な、ユークァル」
ユークァルもこくこくと頷く。
「あ、ほらほら、ミートパイ大食い競争だってさ! おっさんなら絶対優勝できるよ。出てみたら?」
「ん? いい匂いのもとはあれか?」
広間の一角には仮設舞台が立てられ、人々の熱気とミートパイの匂いで一杯だ。舞台にかけられた垂れ幕には「第一四回 星降りの夜杯 ミートパイ大食い競争」と書かれている。会場脇の立て看板には「出場者募集中」とも書いてある。
「ああ、そうか。星降りの夜の祭りか。もうそんな時期なんですね」
「何じゃ、その星降りの夜というのは」
「世界樹の外周部でしか見られない天体現象です。一年に一度、空から雨の様に流れ星が降ってくるんです。星降りの夜が近付くと、人も魔物も不思議と元気になるんだそうですよ。本で読んだだけですから実際に見た事はないんですが。そう言えば」
「そういえば?」
「その時期には、世界樹の外周部の国々が集まって、収穫祭を兼ねた祭りを行ないます。そこでは各国が魔物使いを出して魔物達を戦わせる大会を行なうんだそうです。あくまで伝説に過ぎませんが、星降りの夜の大会に優勝した者は、その願いがかなうんだとか」
「戦争の代わりというわけだな」
「まあ実際そんな所でしょう、それぞれの国の威信を賭けて魔物使いを選ぶのですから」
「あ、それ見たいなあ。ねえ、お祭りが終わるまではいるんだろ? 見ようぜ見ようぜ」オルフェが袖を更につかんで横に振った。
「うーん、居たいんですがねえ」私はうなってしまった。私だって星降りの夜は一度くらい見ておきたい。でも、先立つものが無くてはねえ。自爆なんですけども。
「見せてやれよ。宿とメシさえ何とかなればいいんだろう?」
「路銀はどうするんですか」
「簡単なこった。稼げばいいんだろう?」竜王はミートパイ大食い大会出場者募集の看板を指差した。
「ミートパイ大食い競争に出て優勝すればいい。賞金300ゴールドもあれば、3人なら木賃宿で安いメシ食ってれば2週間はいけるだろ。出場は今からでも間に合うらしいからな」
「そういう貴男はどうするんですか」
「だから今から喰いだめするんだ。星降りの夜まで何もしないで寝てれば2週間くらい何てこたないさ。メシ喰わん生活は根の国で慣れっこになってるからな。まあ任せておけ」
「何で人間じゃなかったら大会に参加出来ないんだっ! 魔物差別じゃないのかっ! じゃなくて誰が魔物だっ!」
で、ここは第14回ミートパイ大食い大会の受付である。参加を決意したまでは良かったのだが、受付の男が竜王を一目見るなり、魔物は参加を認めないと言い出したのでゴネている最中という次第だ。
「どっから見たってあなた人間じゃないじゃないですか」
「うっ…」
「それにあなた、そんな事言ったってですね」受付の男は一呼吸置いた。「誰かが優勝したさにボストロールなんか連れてきたらどうするんですかっ! そんなのが来たらいくらパイを作ったって足りやしないでしょ!」
「う、まあ…」流石の竜王もこれには納得せざるを得なかった。
「第2回の大会の時にね、キラーエイプ連れてきたバカがいましてねぇ」男の声はかすかに震えていた。「あの時の実行委員長は私だったんですよ。大赤字でね、ホントに大変だったんですよっ! 第6回の大会なんか、変化の杖でキラーリカント連れてきた奴もいたし。そいつはマルタのマスターでしたがね。あとレムオルでキングスライム連れてきて、自分の分を食べさせていたマスターもいましたね。だから、第12回からはモンスターマスターも大会出場出来ない事になってます。納得しました?」
「…した」
「けっ、メシ食いそびれたっ!」
ミートパイ大食い大会への出場を拒否されて、空腹と苛立ちが頂点に達したらしい。竜王は早くも周囲に向かって八つ当りを始める。
「あーあ、おっさん八つ当りしてるよ。オレも腹減っちった。何かないの?」
「誰がおっさんだっ! オルフェっ! もっかい言ってみろ、馬刺しにしてやるっ!」
竜王に首を絞められて、オルフェはじたばたもがいている。
「あのねえ、いい歳こいた大人が何やってるんですかっ。ちょっとは我慢して下さいっ」
「やかましいっ。もとはと言えばお前のせいではないかっ!」
げに食べ物の恨みは恐ろしいもので、今度は私が竜王に、頭を拳で挟まれて締め上げられる番だった。
「そんな事してもお腹はふくれません」
誰もが解っていながら八つ当りの対象にされるのが嫌で、誰も決して言わなかった事をユークァルはあっさり言い放った。
「…ふんっ、そんな事は百も承知だっ。可愛げのない奴め。こうしてやるこうしてやるっ! どうせ痛くないんだろう!」八つ当りのお鉢が回ってきて、ユークァルもほっぺたをつねり上げられている。ユークァルは相変わらずちっとも痛そうな顔をしないので、かえって竜王の苛立ちをつのらせてしまったようだ。
「ああっ、くそっ!どこのバカが第2回大会の時にキラーエイプなんか連れて来たんだぁっ!」竜王はそう言うなり、辺りの椅子や街路樹を蹴飛ばし始めた。
「すっげえ八つ当りの仕方だなあ」
「同感」
▼りゅうおうはこうえんのきにやつあたりした! こうえんのきは 150ダメージをうけた!
木陰の先で、何かが弾んだ。
「ぶふっ」
蹴られた衝撃で木は大揺れに揺れて、何かが竜王の顔の上に向かって落ちてきた。“何か”はそのまま地面に落ちて、2〜3メートルほど転がって止まった。見ると、手足を付けた毛玉のようなものが突っ伏している。どうやら生き物のようだ。
「さる?」オルフェが屈み込んで毛玉を小枝でつつく。
「さるじゃないとおもいます」ユークァルが毛玉を引っ繰り返した。「何でしょう」
毛玉がむくっとおきあがった。
「わたたっ、ひどいなあ、せっかくお昼寝してたのに…わた?」
「わた?」
「わた? わた、わた、わた…どこかでそんな魔物の話を見た憶えが…あーっ、思い出した! 確か、世界樹の精霊わたぼうっ!」
「そうだよ、ボクはわたぼう。世界樹の精霊で、タイジュ国の守護者なんだ。よろしくね……?! わ、わたあぁーっ!」
「どした? わたぼうとやら」
竜王はわたぼうの顔を覗き込んだ。
「竜王とハーゴンだっ! どどど、どうしてこんな所にっ!」
一瞬の沈黙。
「やべ、こ奴我々の事を知ってやがるっ! 捕まえろっ!」
▼わたぼうはにげだした!
かくして、我々とわたぼうとの鬼ごっこが始まった。
「ええい、ラリホーっ!」
▼ハーゴンはラリホーのじゅもんをとなえた! しかし、じゅもんはきかなかった!
「ボクは眠らないよー♪」
「では、これではどうです! マヌーサっ!」
▼ハーゴンはマヌーサのじゅもんをとなえた! しかし、じゅもんはきかなかった!
「ええっ?! な、何故…得意な呪文の筈なのにっ」
「じゃ、今度はオイラだっ! ボミオス!」
▼オルフェはボミオスのじゅもんをとなえた! しかし、じゅもんはきかなかった!
「ボクには魔法効かないよー♪」
「げ、効かないのかよ! じゃあ戦術変更。くらえ、足払いっ!」
▼オルフェはあしばらいをかけた! しかし、わたぼうはさらりとかわした!
「ボクはやすまないよー♪」
「だああっ!」オルフェはバランスを崩して、そのまま公園の木に向かってスライディングする。
「あー、いってえ。あのわたぼうってやつメチャクチャすばしっこいじゃん」
片膝付いてお尻をさすりさすりしているオルフェの脇を、もっとすばしっこいのが飛び出していった。かわし切れずにオルフェはまたひっくりかえる。飛び出していったユークァルはわたぼうに向かって飛び掛かると、あっさりわたぼうをかかえて戻ってきた。
「捕まえてきました」
「おお、よしよし良くやったな」竜王はユークァルの頭を、髪が乱れるくらいわしゃわしゃ撫でてやる。その態度と来たら、さっきまで、その目が気にくわんだの何だの言っていた相手に対するものとは思えない。
「ん?ちょっと待て。…?! おいこら、こいつ、首の角度がおかしいぞ! ユークァル、何をした!」
竜王の問いにユークァルはあっさり答えた。「口封じしました。違いますか?」
「ばかたれ、殺す奴があるかぁーっ!」
この後すぐ、私がわたぼうにザオリクをかけまくったのは言うまでもない。
「…で、この後どうすんのさ」
わたぼうを捕まえて一段落した後、私達は今後の身の振り方を決めるべく青空作戦会議を開いた。
「まあ、わたぼうはとっ捕まえたから色々ややこしい事を騒がれて追い回されたりはしないだろうが、金がなあ…」
「お金が必要なんですね。稼いできます」
「だ、だめだよユークァル、まずいよそれは」
「う、お、お前はいいから座っていろ」
「なぜですか?」
「何故ですかってダメなものはダメなんだ。何でも人に聞かんでちょっとは自分で考えてみろ、この馬鹿娘!」ユークァルが立ち上がろうとするのを見て、皆であわてて止める。にわか会議の間はいきなり気まずくなってしまった。ユークァルは解ってないんだろうなぁ。
「どこかで星降りの夜の祭りの間だけ、働かせてもらうって言うのはどうです?」
「何でたかだか祭りを見にいく為だけに、アルバイトなんぞせにゃならんのだ? いやなこった。お前一人でやれ」
「オレ達で何か芸でもやろっか」
「あの、そ、それは勘弁して下さい…。そもそも私には芸なんて出来ません…」あの一件以来、芸という言葉は私の中ではタブーとして刷り込まれている。条件反射的に脳裏でパノンばりのダジャレが増殖して、私は立ちくらみに襲われる。
「ちぇ、じゃどおすんだよっ。見てえよおぉぉぉー祭り見てえよぉぉぉー」
「五月蠅いっ! ここでだだこねたところで路銀が何とかなるとでもいうのかっ!」
一同は腕組みをしたまま、考え込んでしまった。
「…なあ、星降りの夜には、魔物使いの大会があるんだったなあ」
「え、ええ」
「どうだ、我々でチームを結成して大会に出てみないか?」
「は?」竜王がいきなり突拍子もない事を言い出したので、これ以外の返事が思い付かなかった。
「いいか、ハーゴン良く聞けよ。人間どもにとっては、人間以外の種族など皆同じ魔物なわけだ。さっき大食い大会の受付で言われただろうが」
「は、はあ…確かに」
「だからな、我々で星降りの大会に出るんだ。魔物使いは、まあ役不足だが、唯一の人間であるユークァルにやらせるとして、私とハーゴンとオルフェで出れば、頭数は揃うだろ。優勝すれば賞金くらい出るだろうし、賞金が出なくたってどこかの国にスポンサーになってもらってだな、優勝したらいくらいくら報酬を出すようにと事前に交渉しておけば良いではないか」
「あ、そっか! あったまいい!」
「ふふん、どうだ、名案であろう」名案をひねり出して、竜王は得意げだ。
「ダメですよそれは」
「ん? ハーゴン、何でだ?」
「決まってるじゃないですか、この時期になって、大会の代表が決まっていない国なんてある訳ないじゃないですか」
「あ、それそうだよなあ…うーん、名案だと思ったのになー。いまさら代表が決まってませんなんて国ないだろうしなー、ちぇっ」
オルフェはその案を気にいっていたのか残念そうだ。が、竜王は諦めない。
「そんなもんはだな、その国の魔物使いを皆が見ている前でこてんぱんにのしてやれば、あなた達、そんなに強いんでしたらぜひともうちの国の代表に、って話になるだろうが」
「ううん、そんなうまいこと話が進みますかねえ」
「お前な、自分達の実力ナメてるだろう。私がいて、フルパワーのお前がいて、まあランクは落ちるかもしれないがオルフェだって多少は戦える。だろう? 1/16の手錠が付いてようが、そんじょそこらの魔物に負けるつもりはないからな」
「まあ、そうでしょうけど…そんなので本当に上手く行くんですかねぇ?」
「やってみなくちゃわかんないんじゃない? とにかく、まずここの国の王様にでも交渉してみようよ! 当たって砕けろ Go for breakだよ! あー、なんだかワクワクしてきちゃった! 祭りが見れて大会にまで参加出来るなんてサイコーじゃん!」
「そうしてみるか。よし、行ってみよう」
一同が立ち上がった時、わたぼうの口元が僅かに引きつっている様に見えた。気のせいだろうか?
それにしても、タイジュ国の人々は、自国で星降りの夜の大会が行なわれるというのに、どうもその事を手放しで喜んでいるようには見受けられなかった。星降りの夜が近いというにもかかわらず、である。タイジュ国の人々が星降りの夜の祭りを楽しみにしていない訳では決してない。ミートパイ大食い大会が祭りの2週間も前に開かれて、あんなに盛り上がっていたのだから間違いはないだろう。だが、王宮までの道のりの間、人々が星降りの夜のメイン・イベントである筈の大会に関する話題に、タイジュ国のたの字も出てこないのは不思議と言わざるを得なかった。
「あの、すみませんが」
我慢出来なくなって、私は道端で遊んでいる子供に声をかけた。
「何だよおっさん達、はっきり言いな!」
「お、おっさん…この私がおっさんだと?! このクソガキがぁっ!」
年端も行かぬ少女に殴りかかろうとする竜王を、オルフェが必死で押えている。
「この国で星降りの大会が開かれるのに、何故人々は自国の代表の話をしないのでしょうかね?」
「ああ、なーんだ、お前達よそ者だから知らないんだ」
少女はそう言って自慢げに講釈を垂れた。
「うちの国が優勝する訳ないだろ。今のメダルフェチの王様が即位してから、タイジュ国は今まで一度も優勝した事ないんだからな! おかげで王妃にも逃げられてやんの。今年なんかまだ代表も決まってないんだぜ? ま、わたぼうがトンズラこいてるから、今年は代表出せないんじゃないかってみんな言ってるぜ!」
「わたぼう?」
「この国じゃさ、星降りの大会の代表は、わたぼうが連れてきたマスターって決まってるんだ。でもさ、わたぼうが選んでくるのってろくでもないヘボマスターばっかりだもんだから、わたぼうの奴、『今度ヘボマスターを連れてきたらわたぼうの毛をむしる』なんて王様に言われちゃってさ、それっきりどこにも見当らなくなっちゃったんだぜ。あーあ、今年はタイジュの主催だってのに、主催国の代表が出ないんじゃつまんないってみーんな言ってるぜ」
「そうだったのですか…」
「おーい、サンチー!」遠くで少女を呼ぶ声がした。さっきの子供達だ。
「っと、わりいけど、じゃあな! ダチが呼んでっから」少女は言うだけ言うと、とっとと広場の方に走り去っていった。
彼女の背中を見届け終えると、一同顔を見合わせる。
「主催国が代表出さないなんて前代未聞ですね」
「なるほど、ようやく運が向いてきたな」
「…そこで、我々がタイジュ国代表として優勝を確約する。代わりに、我々に支度金2000ゴールド、優勝が決まった時点で10000ゴールド払うというのはどうでしょう。国家の威信がかかっているとなれば、決して無茶な額ではありますまい?」
「何でも、タイジュ国はお前…あ、いやいや…陛下が即位してから十数年、一度も星降りの夜の大会で優勝した事が無いと聞くが?」
我々がいるのは、タイジュ国王宮の謁見の間である。王宮は、タイジュ国の家屋はみなそうなのだが、世界樹の表層をくりぬいた造りになっているお陰で、辺りに心地好い木の薫りが充ちている。タイジュは豊かな国であると聞くが、王宮の造りはむしろ簡素であると言って良い。そんな中で、我々は星降りの夜の大会の、今年の主催国タイジュ国国王と直々に交渉しているのである。普通ならよそ者が突然王宮に押し掛けて、国王に会わせろなどと言った所でかなう筈もないのだが、星降りの大会に代表を出せないかも知れぬという危惧もあったにせよ、我々に直接会って話を聞こうと言い出すあたり、なかなか気さくな王である。
「そなた達、その様な事を申すが、本当に強いのか? 星降りの夜の大会はレベル高いんじゃぞ。魔物使いがその様な年端も行かぬ娘ごでは……それに、支度金を渡してドロン、なんて事はないんじゃろうな?」
「ふふん、確かにそうですな。…おい、ハーゴン、お前の実力見せてやれ」竜王に軽く肘鉄を食らわせられ、私はつまずき気味に立ち上がった。
「ほお、面白い。では試しにここでそなたらの力を示してみせよ」
「は、はあ。あのー、ここでやっても宜しいんでしょうか?」
「かまわんかまわん。ドカーンとやってくれ。城の一つや二つ潰れたところで、世界樹の復元力があれば、一晩で元に戻るわい!」国王はそう言うと、あごが外れそうな勢いで、がっははは、と笑った。
「王様、それ、言い過ぎ」
先程まで王の傍に侍っていた道化師達があわてて飛び上がった。本当に大丈夫なのだろうか?
「解りました、では皆様方、危険なので離れて下さい」
皆が移動したのを確認し、私は呼吸を整え、軽く息を吸う。
「イオナズーンッ!」
呪文の詠唱と共に轟音が響き渡り、辺りは高熱と爆風に包まれた。爆風が収まると、広間の天井三分の一が見事に吹き抜けになった。辺りではまだ煙が燻っている。
「うむむ……何と見事なイオナズンじゃ! 余の人生、生涯見た中で最も凄いイオナズン、いやいや宇宙で五本の指に入るイオナズンであったぞよ! いや、アッパレアッパレ!」
「王様、それ、言い過ぎ」
王の傍に侍っていた道化師達がまたまた飛び上がって驚いた。どうもこの王様、大言壮語と言うか、やたらと物を大袈裟に言う性癖があるらしい。
「いやいや、そなたらの実力相解った! ……うーむ、しかし、このままでは我が国の代表にはなれんのう」タイジュ国国王はさも残念そうに首を傾げた。
「? 何が不満なのさ」
「星降りの夜の魔物使いは、世界樹の精霊わたぼうが選んできたモンスターマスターによって行なわれるという慣習になっておるのじゃ」王は実に残念そうだった。「そなた達が強いのは充分に解っておるが、わたぼうを連れておらねば話にならんのう…わたぼうの奴、わしがこの間『今度お前の連れてきたモンスターマスターが優勝できなかったらお前の毛をむしる!』と脅してしまってからこの方ずっと行方知れずなのじゃ。ううむ、困ったもんじゃのう…こんな事なら脅かさなければ良かったかのう…」
「わたぼう! 陛下、今わたぼうと仰いましたな!」竜王は目を見開くと、わざとらしくのけぞった。
「何と言う偶然か、わたぼうならここに連れてきております。ユークァル、わたぼうをここに」
何が偶然なものか。確信犯の癖に。
「…はい」ユークァルが、首と腕を紐に繋がれて猿回しのサルの様になったわたぼうをひっぱり出してきた。
「う、わたわたーっ!」
嫌がるわたぼうを無理遣りに、国王の元へ引きずりだす。わたぼうは短い手足をわたわたさせて、意地でも逆らう様子である。
「わたぼう、いいのかそんな態度で。そうか。……ユークァル、わたぼうの首へし折っていいぞ」
「わ、わたーっ!」
▼わたぼうはすっかりわたわたしている!
「冗談だ。ユークァル、本当にやるんじゃないぞ」
竜王はユークァルの手からわたぼうを取り上げると、わたぼうに向かって意味ありげな一瞥をくれた。
「ま、別にな、貴様がタイジュ国の代表候補を探すのをサボッて公園の木の上で昼寝してた、なんて事は…」
「わ、わたわたた…わかったわた。…うう…王様、こ、この人達をタイジュ国の代表として承認するわた…」
タイジュ国王の顔がぱっと明るくなった。
「おおお、そうかわたぼう! 余は嬉しいぞよ! これでタイジュ国の優勝は間違いなし、ようやっとあのマルタ王やカレキ王にバカにされなくて済むというものじゃ! めでたしめでたしじゃ!」
わたぼうの不安をよそに、タイジュ国の国王は、既に自国の優勝が決定事項であるかの様にはしゃいでいた。
「お、ユークァル、似合ってんじゃん! イケてるイケてる」
オルフェが感嘆の声を上げた。ユークァルが着ているのは黄緑色の長袖の、優しい風合いの厚手の綿のシャツと、濃いピンク色の、腰と裾を絞っただぼだぼの、くるぶし丈のパンツ。パンツの裾には黄色いリボンで止められた金色の鈴が付いていて、彼女が動くたびにちりんちりんと涼しげな音を鳴らした。足には白に空色のラインの入ったサンダルを履いている。
「お前は優しい色の方が良く似合うのだな。これからはそういう明るい色を着るようにしろ。そっちの方が娘らしくていい」
「珍しいですね、貴男が彼女を誉めるとは」
「私がユークァルを誉めて悪いか。たまにはこういう事を言ってやったっていいだろうが。まあ、前の服があれなら何着たって多少はマシに見えるがな。あれは捨てとけよ」
相変わらず素直じゃない人だよなあ。
だが、誉められている当の本人は衣装の具合がどうも気になっているらしかった。特にサンダルと、パンツの袖口に付いている金の鈴がちりちり鳴るのが不快らしい。
「しばらくすれば慣れますよ、ユークァル。最初は戸惑うかも知れませんが、もう貴女は誰かを暗殺する為に、音を立てずに忍び歩きする必要はないんです。その為に、私達がいるんですから」
「そおだよっ。ユークァルが人殺ししなくても済むように、俺達頑張ってんじゃんかよ」
オルフェが賛同するのを聞いて、ユークァルは鈴を外そうとするのをやめた。やはりまだ、少しばかり気になってはいるようだが、その内慣れるだろう。そのつもりでこの服を選んだのだし。
そう、彼女が、もう二度と人殺しなどしなくてすむように…。
「そっちのローブも坊主っぽくて良く似合ってるじゃないか」
と、この人がいる限り、私に感傷に浸るヒマなどないのだった、まったく。
「それどういう意味ですかっ」
「堅っ苦しくて辛気臭いところかな。あと、囚人服よりは堂々として清潔感もあるし、いいんじゃないのか。帽子も似合ってるぞ、神官臭くて」
「坊主坊主って言うのやめて下さい。開店休業中なんですから」
そう、実際の所、今の私は神官でも何でもないのだ。信仰を無くした神職など惨めなものだ。支えを失って、ただ後悔だけがあって、そこに竜王が現われて、望まれたから付いていった。そこに何があったのだろう、理想? 償いのチャンス?
「またどうせくだらん事を考えているんだろう、辛気臭い顔をしおって」
竜王が私の頬を思いっきりつねった。はい、図星です。すいません。
「そおだよっ。せっかくの星降りのお祭りなんだからさっ、屋台行こう屋台。俺、リンゴアメ食べたいな」
「それくらいならいくらでも買ってやろう。そうだな、じゃあ私もタコ焼きでも食うか」
た、タコ焼きってあんた…。
「そうそう、ユークァルにも何か買ってやらんとな。何がいい? よし、わたあめでも買ってやろう」
ってちょっと、あんた、それは皆の金だろうがっ!
まだ星降りの夜までは1週間余りあるというのに、バザーはもうあちこちで屋台やらござを引いた商人やら旅回りの芸人やらが青空市場を開いていて、随分賑わっていた。ミートパイ大食い大会だけではなかったようだ。広場のあちこちで人々が街を飾り付けていて、初めて来た時に比べるとすっかりお祭りムードで一杯だ。
「どうだ、わたあめ美味いか」
「お砂糖なんですね、これ。そうだ、わたぼう、わたあめ食べる?」
ユークァルに言われて、わたぼうはわたわたと首を横に振った。彼女に首の骨をへし折られてからというもの、我々を完全に警戒してしまっている。
「毒、入ってないよ?」
ユークァルにわたあめをちぎってもらって、わたぼうはびくびくしながらわたあめを口に含んでいる。口封じ…いやいや、大っぴらに騒がれない為とは言え、わたぼうには悪い事をしてしまったものだ。
「あ、あんなところでテンタクルス焼きが6ゴールドだって。テンタクルスって美味しいのかな? わわわ、ね、これってスライムってやつだろ。かっわいーなあ。この黄色いの一匹欲しいな。ね、買って」
オルフェはさっそく屋台のスライム売りに捕まっている。
「何だ、オルフェお前スライム見た事ないのか? こんなの町外れに行けばごろごろしておるぞ。それに、スライムってのは大抵赤いのか水色のやつばっかりで、こういう色のは後から着色してるんだ。3日もしたら色が落ちておる」
「スライムの黄色い色は、タンポポの染料を使っているんです」
「へえ、ユークァル物知りなんだなぁ」オルフェは尊敬の眼差しをユークァルに向ける。
「粗悪なものだと黄色い絵の具を使ってる事が多いんです。そういうのは寿命が短くなってしまうから良くないと思います」
「ふん、お前に生命をいたわる感情があるとは終ぞ知らなかった」
「自然死はつまらないから…」
「うわ……」
「……………。もういい、お前口きくな。なあ、ハーゴンも何か買えよ。金はあるだろ」
「うーん、どうしましょう…わあ!」
「あっ…」
誰かに突き飛ばされた衝撃で、私は屋台の果物篭中に突っ込んでしまった。頭を上げると、再びタイミング悪く後から突き飛ばされてレモンの山に沈む。埋もれてた帽子を拾い上げ、レモンの山から這い出ると、目の前でスリとおぼしき男が青い服の少年に捕まって腕を極められていた。
「お前が財布をスッたのは解ってるんだッ!」
「し、知らねえよっ」
「じゃあ、これは何だ? 言ってみな!」
少年はスリの腕をさらに締め上げると、スリの懐から青い巾着袋を取り出す。
「これは俺の財布だ!」少年はそう言うと、スリを地面に投げ飛ばした。
「あいててててて」
「フッ、これに懲りたら二度とこんなマネはするなッ」
少年は逃げていくスリに向かって一瞥をくれると、踵を返して歩き去ろうとした。
「わたあめ…」
「ん?」
騒ぎに紛れて気付かなかったが、どうやらさっきの騒ぎでユークァルはわたあめを落としてしまったらしい。そして、少年はそのわたあめを踏ん付けている。
「それ、あたしの…」
「な、なんだよ、その目は」
ユークァルを知る者にとっては常と変わらぬ様に見えるのだが、初対面の少年には、彼女の態度が自分への挑戦だと映ったらしい。
「わたあめくらいいくらでも買えばいいだろッ! ほらよッ!」
少年は取り返した財布から、ユークァルの足元に金貨を叩き付けた。
「そう…だよね。…いくらでも、替えはあるよね…」
ユークァルの小さな手が、金貨に伸びた。
「ユークァル、こんなお金受け取ってはいけません」
私は彼女の手を握り、金貨を拾おうとする手を押し止める。
「……どうして?」
「どうしても、です」私はかぶりを振った。
「…おい、てめえ! そういう態度はねえだろっ! ユークァルに謝りやがれっ!」止める間もなく脇からオルフェが少年に躍り掛かった。少年はオルフェを軽くいなすと、逆にオルフェの足をなぎ払って辺りに転がした。オルフェは果物篭に突っ込んで、今度はリンゴを辺りにばらまく。
「い…ってぇー」
「とにかく、このお金は受け取れません」私は改めて金貨を拾うと、少年に向かって金貨を突っ返した。少年は私達をしばし睨みつけていたが、そのうち手から金貨をひっつかむと、決まり悪そうに人込みの中に消えていった。
騒ぎは収まったが、私達の間には、洗いたてのシーツを汚された様な気まずさが残ってしまった。きっとユークァルは、荒んだ生活の中で、人に何かを好意を以て贈られた事が無かったのだろう。まだ彼女に、嬉しいという感情や、感情を認識する能力は育ってはいないけれども、そうした経験の積み重ね一つ一つが本当はとても大事な事なのだ。だから、今日の様な事は、本当は、あってはいけない筈、だった。
終わった事を悔やんでも致し方なく、とりあえずはユークァルを慰めるつもりで、新しいわたあめを買ってあげる事にした。
「あの、すみませんがわたあめを一つ」
「はい、わたあめ一個だね」わたあめ売りの年配の女が出来合いのそれを渡そうとするのを押し留め、私は女に囁いた。
「実は、あの子なんですが、今までわたあめなど食べた事が無いんです。生まれて初めてわたあめを買ってもらったのに、それを落としてしまって…」
「あらやだ、こんなに貰っちゃ」
「いいんです、だから彼女の為に、特別大きなわたあめを作ってあげてくれませんか?」
年配の女は目をまん丸くしていたが、やがて、すぐに人懐こそうに笑った。
「何だ、そんな事なら余計余分にお代は貰えないよ!」
私がユークァルを呼び寄せると、女はさっきのわたあめの2倍はゆうにありそうな大きなわたあめを、目の前で作ってユークァルに手渡した。
「お嬢ちゃん、はい、おばさんの作った特別製のわたあめだよ」
「特…別?」ユークァルは義眼の嵌った目を瞬かせる。
「そうさね。これは魔法のわたあめで、一口食べると心がワクワクドキドキしてとっても楽しい気持ちになれるんだよ。いいかい、他の子には誰にも内緒だからね」
「どうして、あたしに特別なんですか?」
「それはね」わたあめ売りは言った。「嬢ちゃんが可愛いからよ。それに、嬢ちゃんはうちの息子に良く似てるからね、うちの息子はいい男でねぇ。自慢の息子なのよ。さ、どうぞおあがり」
「ユークァル、お礼を言いなさい」
ユークァルは何か言う代わりに、深々と一礼してわたあめを受け取った。
わたあめの屋台を離れてから、ユークァルは再びわたあめを食べ始めた。
「あれ? これ、味がさっきのわたあめと違う。同じ砂糖で出来てるのに…変ですね」
「わた? ……おいしいわた! わたわた! わた?」
ユークァルにわたあめを貰ったわたぼうも、一緒に首を傾げている。
「お、おいらももらっていいかな」わたぼうの様子を見て、オルフェもわたあめをつまんだ。
「どうぞ」
「ふーん、むぐむぐ……こいつはうめえや!」
「わたあめなんてどこで買っても同じだろうに…どれ食わせてみろ」
竜王はユークァルのわたあめから一つまみをちぎって口に放りこんだ。放りこんだわたあめの全てを、余すところ無く味わい尽くす様に噛み締める。喉の奥にわたあめを流し込んで暫らくの後、竜王は心底腹立たしげに言い捨てた。
「畜生、またあの女にやられた」
「は?」
「あのわたあめ売りのババア、とんだ食わせ者だ! ルビスの奴、こんな所にまで来てやがったのか! あのお節介焼きめっ!」
「ところでハーゴン、予算の残りはどれくらいだ?」
「そおですねぇ。毛布を人数分買ったのと、私とユークァルの分の服を買ったので…残り1200ゴールドくらいですか」
「そうか、よし、それだけあれば十分だな」
「は?」
「トトカルチョだ。こういう大会にはつきものだろうが。自分達のチームに賭けて旅の資金を稼ぐんだ! 行くぞお前ら! おっと、ユークァルは居残りだぞ。わかったな」
と、いう訳で私達は、闘技場の酒場の地下一階に来ている。本当はこんな胡散臭い所には来たくなかったのだが、竜王がどうしても行こうというので仕方なく付き合う。
竜王の言い分はこうだ。
「いいか、この手の大会は、大抵裏で賭事なんかやってるもんだ。ここで旅費を稼がなくてどうする」
「まったく、そんな事に手を出して、全財産すったらどうするんですか」
「あー、だからお前は頭が固くてやなんだ。いいか、この大会には我々も出場するんだぞ。つまり、自分に賭けて優勝すれば、賞金はもらえるわ、掛け金はもらえるわで大儲けでウッハウハではないか」
「またそんな調子のいい事言って…知りませんよ。全部スッたら貴男の責任ですからね」
「まさか、お前優勝する自信無いのか? とにかく、オッズを見て、下馬評を聞いてよそのチームへの対策も立てんといかんだろ。そういう訳で情報収集だ」
そう言われてしまうと反論の言葉は思い付かなかった。確かに、他のチームがどうあれ、この組み合わせなら1回戦であっさり負けるというのはないだろう。そんな訳で、他国チームの情報を仕入れる為と自分に言い聞かせ、要するに例の如く巧い事丸め込まれて、酒場に潜入する事にしたのだった。
で、酒場はというと、それはもう予想通りの大にぎわい。酔っ払いが唾を飛ばして、どこの国のチームが強いだの、どこが穴だのとやっていて、酒場はにわか予想屋の溜り場となっていた。
「う、酒臭」
「あ、親父、俺エール一杯」オルフェがエールを注文しようとしたのを見て、竜王が間髪入れずにオルフェの頭をどつく。
「バカモン、ガキは酒飲むなっ」
「ちぇっ、都合のいいときだけガキにすんなよなっ! それに、俺はあんたが思ってるほどガキじゃねえっつうの!」
「バカだなオルフェ。いいか、そのエールの分が大会後に何倍にもなって帰ってくるんだぞ、ちょっとは我慢しろ」
そのセリフ、そのままそっくり返してやりたい。
「おお、オッズが出てるぞ。……何?」
「どうかしたんですか?」
竜王が、賭けの倍率を書き込んだ黒板を指差して言った。
「何で、タイジュが一番人気じゃないんだ?」
「何でって、星降りの大会ではここんとこタイジュは勝った事ないんでしょう? それに、ユークァルの事もほとんどウワサになっていないと思いますよ。彼女はモンスターマスターとしては無名ですしね」
「ふぅむ、ま、そう言われてみればそうかもしれん。だが、しかし…納得いかんなぁ…う〜む…」
「そんな事言っても仕方ないですよ。…逆に考えれば、倍率が高い分、優勝できれば倍返しじゃないですか」
「そうそう、オレ達一人勝ちだよ? エール飲み放題じゃん」オルフェが同調したので、竜王はようやく納得したようだった。懐から財布を取り出し、賭の仕切人に声をかけた。
「そうだな。おい、オヤジ、タイジュ国に1000ゴールド賭けるぞ」
「物好きだねー、アンタ達」
「何だ? お前ら」
背後からの野次馬の冷やかしが、竜王の手を止めた。
「タイジュに賭けるなんて物好きだねって言ってやってんだよお」
「ほう」その反応があまりに冷ややかだったので、私は竜王が、次の瞬間怒り狂って酔っ払いを殴り付けるのではないかと肝を冷やした。
「兄さん、どう物好きなんだ? 我々よそ者なんでな。教えてくれないか?」予想に反して、竜王は近くの椅子を引くと酔っ払いの席に向かい合って座り込んだ。口振りは穏やかだが、相手を威圧しているのには変わり無い。冷やかしで声をかけたつもりだったのか、酔っ払いは明らかに面食らっている。
「え? あ、ああ。まあよ、まず、今年のタイジュ国は2週間前になってもモンスターマスターが決まらなかったてぇのが一番でかいかな。つまり、その、それは準備不足って事だろ? な、相棒」
「お、おう」酔っ払いの連れが相槌を打つ。二人とも、目が宙を泳いでいる。
「なるほど。他には?」目を反らさぬまま、竜王は続きを促した。
「な、なんと言っても今年の本命はマルタ国のマスターだな。あそこはここ数年、毎回カレキ国と優勝争いをしてるし、マスター本人も相当の使い手らしい。う、ウワサによると、マルタ国のマスターは、魔王級の魔物を連れているらしいぜ。なあ?」酔っ払いは必死に相棒に相槌を求める。既に酔いなど吹っ飛んでいるようだ。
「そ、そうだよ。な、どんな魔物を連れてるかはくわしくはしらないけど」
「それに、タイジュのマスターは聞いてみりゃ13〜4の娘だって言うじゃないか。なあ兄貴」
「そ、そうだよ。この世界、魔物だけじゃなくてマスターの経験が物を言うからなあ。なあ?」
「ふん、なるほど」
竜王が少しだけ溜飲を下げた様子を見て、素早くオルフェが駆け寄って耳元で囁く。
「ちょっと、おっさん大人げないぜ。やめとけって。みんな見てるよ」
「お前またおっさんって言ったな!」
「いてえっ、ちぇっ、すぐ殴るんだから」
テーブルの周りの緊張が僅かに緩んだ。私はほっと一息ついて、オルフェに目配せした。
「フッ、タイジュ国のマスターが情報収集ってわけか」
「ん?」竜王が怪訝そうに声の方をを振り返る。
そこに立っていたのは、昼間バザー会場でスリ相手に大立ち回りを演じ、ユークァルのわたあめをふんづけた、プラチナブロンドに青い服のあの少年だった。
「げ、バレてぇーら!」オルフェがすっ頓狂な声を上げて飛びあがる。
「そんな風に話してたら誰だって判るさ……?」
「あ、貴男、昼間のわたあめの……!」
整った顔立ちの、ごく薄いアイスブルーの瞳が傲慢に歪む。
「ハハハハハ! あの娘がタイジュの代表か! こいつぁいいや! おい、タイジュの代表はわたあめ食った事無かったらしいぜ!」
「何が娘、だ。貴様も大して変わらんガキのくせに。こんなガキ無視無視。オヤジ、タイジュ国に1000ゴールド。あと、このテーブルにエール3つな」竜王は改めてバーテンに注文を通し、テーブルにふんぞり返る。さっきまで幼児性丸出しで酔っ払い相手に喧嘩売っていた癖、少年が出てきた途端に大人ぶった態度で振る舞うのが、私にはちょっぴり可笑しかった。
「おい、今、タイジュのマスターがどうとか言ってたよな?」
「ああ。間違いねえ」
「て事はさ、あそこにいる恐ぁいお兄さん達がタイジュの代表サンって事?」
「いやぁ、マチコ姉さん、あれはタイジュのマスターの連れてる魔物よきっと。さっき言ってたじゃない、タイジュの代表は13〜4の女の子だって」
「あっ、そっかー」
半径3メートルより外が急に騒がしくなった。今までタイジュの代表が表立って出てきた事はないのだから当然だろう。とは言え、こんなに余り騒がれて正体がばれでもしたら、大会当日を迎える前に追い出されかねない。
「早く出ましょう、賭け金も払った事ですし、長居は無用」
「そうだな、こんなクソガキの顔を見ながら酒を飲んでも旨くない、ユークァルの方がずっとマシだ」
竜王はテーブルに出されたエールを一気に飲み干すと、勘定を置いてテーブルを立ちかけた。
「ナァんだ、もう帰っちまうのかよ。臆病風にでも吹かれたのか?」
何でも無い外野の冷やかしに、竜王は一瞬身を硬くした。だがそれは、先程の癇癪とは違う、もっと余裕の無い、薄氷を踏むが如き緊張に満ちていた。
「行くぞ」何故か言葉少なげに、振り切るようにドアへ向かおうとする。すると、声のした方から、どことなく爬虫類を思わせる三本指の手が素早く伸びて、マントのちょうど肩から首筋の辺りをつかむ。手の持ち主はその手を振り解く間も与えずに竜王の身体を引き寄せ、頭から無理遣りフードを剥ぎ取った。酒場のランプの黄色い光の下に、人ならざるその素顔が晒される。そのやり取りに外野がわっと沸いた。
「よ、根の国から帰って来たんだってだなぁ。久しぶりだな、ケケケ。元気にしてたか?」
「げ、バッ、バラモス! 生きてたのか貴様! な、何でお前ここに?」
「何もそんなこそこそしなくたっていいじゃねえかヨォ、この世界の連中は、オレ様どころかてめえの事だって何にも知りゃしないし、知ってたところで何とも思いやしないさ。心配すんな」
「………」竜王は返事をしない。
「バラモスってあの、その、あの、魔王バラモス? もしかして、知り合いなんですか? ………?!」
「よお、ハーゴンじゃねぇか。まさか俺の顔まで見忘れちゃあいないよなぁ? お前達も大会に出るのか。こいつは驚きだ!」
聞き馴染みのあるその声に、振り返る。振り返って、私は声を失いそうになった。
私と共にロトの勇者一族に倒された筈の、シドーの従属神、ベリアルがそこにいた。
我々の間を、先程の少年が遮った。
「どうだい? こいつらがマルタ国の代表チームだ。おっと、自己紹介を忘れてた」
青い服の少年が、帽子を脱いだ。
「俺の名はテリー、マルタ国の代表マスターだ。ま、よろしくな。例の彼女に伝えといてくれよ。楽しみにしてるってさ」
「おい、凄い事になったな」
「ああ、マルタ国とタイジュ国の代表がこんな所ではちあわせるたぁなー」
「殺気がびりびりしてやがるぜ」
「なな、どっちが強そうに見える?」
「う〜ん、どっちもいけそうだよな。タイジュにも賭けとこうかな?」
野次馬のざわめきが、今度ははばかる事無く拡がっていった。かたや優勝候補の最右翼、かたや主催国秘蔵の初登場マスター。この組み合わせが人々の気を引かない訳が無い。ましてや、我々はここでは賭けの対象になっているのだ。ここでどう動くか、それが彼らの欲望にとっては非常な関心事なのだから。だが、当事者にとっては人々の欲望などどうでも良い。この組み合わせは、余りにも因縁深いものであり過ぎる。
「まあでも、タイジュ国の代表がオマエさんで良かったってもんだ。これでマルタ国の優勝は決まったも同然だもんナァ。ケケケケケ」
「…何だと? 三下魔王の分際で、良くそんな口が聞けたものだな」
「おーお、三下とは言ってくれるネェ、そういう自分は何様のつもりだァ? オレ様に声をかけられた途端にこそこそ逃げ出そうとするヤツに言われたかないねェ」バラモスの口ぶりには、明らかな挑発の響きがあった。私は唾を飲んでいた。
「貴様にやられるほど落ちぶれてはおらん!」
驚いた事に、振りかざした拳をバラモスは片手で受け止めた。
「ゲッヘッヘー、残念でしたァ」
「ぐぅっ……!」
「お前さぁ、このバラモス様をナメてもらっちゃ困るナァ。昔の頃とは訳が違うぜ?」受けとめた拳を爬虫類の手で握り込み、そのまま腕を背中にひねり上げると、反対の手で袖口の止め金をむしり取った。袖がずり落ちると、その手首には、太い文字で“1/16”と刻まれたあの囚人用腕枷がはめられていた。
「ナァ、いくら何でもその格好で、オレ様と対等に渡り合おうなんざぁ虫が良すぎるんじゃねえのかァ?…これがある限り、てめぇはこのバラモス様には死ぬまでかなわないんだよッ! 何だったらマルタに1000ゴールド賭けとくか? ケケケッ」バラモスはそう言って外したカフスボタンを床に投げ捨てると、竜王を殴り付け、その鳥じみた足で腹を思いっきり蹴った。竜王は無抵抗に吹き飛ばされ、その勢いで辺りのテーブルをなぎ倒した。口中を切ったらしく血が一筋流れ、客先からは悲鳴が上がる。
「フフン、ハーゴンよ、お前もヤキが回ったようだな。せっかく生き返ってきたのにこんな奴と組んでるようじゃあまたあちらに逆戻りだな」
「き、さま…ら……」
「うぉっと、ヤル気なの? 竜王ちゃん」
「バラモス、その辺で止めておけ」
「ケッ、デュラン、貴様にゃ関係無い、口を出すなッ」
ベリアルたちとは少し離れた席に腰掛けていた男が制止するが、バラモスは投げやりにいらえただけで手を離そうとはしなかった。再び爪を振り下ろしたバラモスの手にフォークが突き刺さり、バラモスはその皺だらけの眉間に皺をもう一筋余計に寄せた。
「関係なくはないな、酒が不味くなる。お前達二人の間にどのような因縁があるのかは知らないが、決着は闘技場で着ければ良かろう?」デュランと呼ばれた男がフードを跳ね除けると、やはりそこには人ならざる魔族の戦士の姿が現れた。バラモスに向かって対等な口を利く事、そして何よりあの鋭い眼差し。おそらくは彼、デュランもテリーの使役する魔物の一体であり、そしてかなりの強者である事は間違い無い。
「お客さんっ! お店ん中で暴れられちゃ困ります。外でやって下さい」店のマスターが大声で叫んだ。「兄さん、あいつらアンタの魔物でしょ、ちゃんと責任持って下さいよ!」
テリーはそれまで腕を組んで静観していたが、店のマスターに促されると、手下の魔物達を連れて店を引き上げた。
「おっと、お二人さん、タイジュの活躍楽しみにしてるぜ! 決勝戦で待ってるぜ……生きていられたらな」
「おっさん、口切ってるぜ。これ、タオル」
テリー達の後ろ姿が見えなくなるのを見て取ると、竜王は血の交じった唾を地面に吐く。オルフェに渡されたタオルを受け取りもせず叩き付け、私達の事を振り返りもせず、店を後にした。
「それにしても偉い事になっちゃったなー」
「今のままでは優勝どころの騒ぎではないな…クソッ、バラモスめ」
定宿に帰るなりの第一声と共に、竜王は壁に拳をを叩き付けた。石造りの壁がちょっとだけひび割れた。
「何でだよ。おっ……とととあんた、あのメチャクチャ強い妖魔の君だってやっつけちゃったのに、それよりあんまり強そうでもないあのバラモスとか言う奴に何でかなわないんだよ?」
「端的に言うと、こいつのせいだ」竜王は袖を降ろして手首に収まっている1/16の手錠を見せた。「こいつがなけりゃ、お前等が居なくたって負ける気はせんさ。いいか、あの妖魔の君って奴は幻術使ったり魔術使ったりする、言わば頭脳派だろう。確かに、私は力こそ封印されているが、技やスピードは衰えてはいないつもりだ。それに、お前も含めて妖魔どもってのは、本能的に妖魔の君に対して恐怖や服従心を抱くものなのだろう? だが私にはそれが無い、ただそれだけだ。多分、妖魔の君が自分のテリトリーでバラモスと戦ったら、バラモスは泣きながらしっぽを巻いて逃げるこったろうよ」
「バラモスって、どんな人…人じゃありませんが…なんですか?」
魔王バラモス、大魔王ゾーマの腹心として、もう一つの世界を侵攻し、勇者ロトによって倒されたという伝説の魔王。伝説にこそその名を記すものの、それ以上の事は断片的にしか伝わってはいない。思い切って聞いてみる事にする。
「そうさな、一言で言うと、三度のメシより弱い者いじめが大好きな奴だな。趣味は嫌がらせで特技は拷問」
「うへ、サイテー!」
何だそりゃ。全然イメージが違い過ぎるじゃないか! 伝説の現実に我知らず頭を抱える。
「そうなんだ。あいつは本っ当ーにサイテーな奴だぞ。卑屈でやる事がみみっちくてな〜、恋人同士を、片っぽは昼間、もう片方は夜に動物の姿に変えちまう呪いをかけてだな、二人を引き裂いてその様子を楽しんだり」
「うーわ、…でもさ、今の竜王じゃそんな奴にも勝てないんでしょ?」
「うっ、痛い所を…何とかせねばな、何とか」
「それにしてもおかしな話です。何故彼等はテリーの使い魔という立場に甘んじているのでしょうか。かつては魔王として怖れられるほどの力の持ち主でありながら」
「そんな事は決まりきった事だ。お前以外と頭悪いな」
「貴男はは相変わらずお口がお悪いですね」いつもの覇気が感じられ無いので心配していたが、こんな口を叩ける気力があるのだから、から元気かもしれないがまあ一応は大丈夫だろう。機嫌が悪いとこういう事を言い出すのは毎度の事なので、取り合わない事にする。竜王は私の反応が鈍いのにがっかりしたのか、つまらなさそうに話を続けた。
「奴らは私が戻ってくると、自分達がのさばっていられなくなるから目障りなんだ。だから今回だけ、一時的に共闘しておるのだ。恐らくは我々がタイジュに向かっているか着いたかを何らかの方法で知って、それで我々がこの大会に出場するのを予測してテリーに取り入ったのだろう」
「だとすると、彼らともし決勝で会う事があったら…」
「最悪の場合を覚悟しておかないといかんだろうな」竜王は大して旨くも無さそうに、買って来たクルミを指で割って頬張った。
その日の夜中。
熱帯夜という訳でもないのに寝苦しく、何度も寝返りを打つ。眠ろうとすればするほど目が冴える。星降りの夜が近付いているせいなのだろうか? しばらく毛布を被って横になっていたが、どう足掻いても眠れそうにないので、しばらく起きている事にした。
身を起こすと、既に先客が居た。
「貴男も起きていたのですか?」
「ああ。それより」しかし、その返事は心ここにあらずと言った口ぶりだった。「ユークァルがいない」
「え?」そう言えば、脇にいつも寄り添っている筈の彼女はいない。「何処へ?」
「あ奴、今さっき出ていった。つけてくる」
そう言うと、相変わらず、返事も聞かずに寝床を飛び出していった。
竜王が帰って来たのは、ちょうど朔月が地平線の彼方に沈んだ頃だった。私は彼がてっきりユークァルを連れて戻って来るのかと思っていたので、独り浮かない顔をして戻って来た時、いわれの無い不安が胸中に暗雲の如く広がって行くのを感ぜずにはいられなかった。
「ユークァルは、どうしたんですか?」
「…ああ、見付けた」
「見付けたって…」私は彼がこんな顔しているのを見た事が無かったので、次の言葉を続けるのに躊躇いを憶えた。「どうして連れて返って来なかったんです?」
視線を落として、今度は目を逸らさずに言葉を続けた。「どうしてかって?」
「それは…ユークァルは独りきりじゃなかったからだ。あの娘は、かつての自分の主人に呼ばれて出ていったのだ」
「その主人とは…まさか…」
「皆まで言わずとも解っておろうが」竜王の顔は苦渋に満ちていた。「バラモス達だ」
「そんな…」
「バラモスの奴、『いいか、ユークァル、マルタとタイジュが当たったら、その試合中オレ様がお前に合図を送る。そうしたら、後からナイフで刺せ。いいな』とさ」
「それはもしや…あの、それで、ユークァルは頷いたのですか?」
竜王は答えなかった。
「……それから、あ奴らは、ユークァルに服を脱ぐように命じた。奴ら、あの娘に向かって『奴には可愛がってもらったのか?』と言いながら、ユークァルを…」
「もう、いいんです、これ以上は結構です」聞きたくなかった。解っていても、受け入れられなかった。
「あの娘はじっと耐えていた。いや、ただ逆らわなかっただけだ。為すがまま、されるがままにな………あの娘には、我々の様に耐えるという感情も感覚も無いのだ。胸くそ悪くなったんで、奴らに気付かれない内に退散したがな。…まああの様子ならその内戻ってくるだろう。気付かないふりをして寝ておけ、それが優しさというものだ」
何故、と言いかけて、私は言葉を飲み込んだ。
本当は、ユークァルを一番助けたかったのは、何より竜王自身に違いなかったのだから。
竜王はそこまで言うと、頭の上から毛布に潜り込んでしまった。私もそろそろ、無理にでも眠りに就こうと布団を被ると、聞こえるか聞こえないか位の声で、ぽそっと、漏らした。
「……無力というのは、哀しいものだな……」
「おい、わたぼう、貴様この手錠を何とかする方法無いのか」
竜王の問いにわたぼうは頑なにいやいやしてみせた。協力拒否を決め込むつもりらしい。
「お前なー、タイジュ国が優勝出来なくても知らんぞ。本当に良いのか? 毛を毟られても」
わたぼうは顔をそむけて見ないふりをする。
「し、知らないわたっ。知ってても教えないわたっ」
「なあ、わたぼうお願いだよー。リンゴアメ買ってあげるからさぁ。ねえー、どうしてダメなんだよー。ドケチー」
「ば、買収には応じないわたっ」
「本当にわたぼうのくせにムカつく奴だな。国王にわたぼうが優勝を邪魔してるって言い付けるぞ」
「わたぼうはのび太ですかっ。やめなさいって子供じゃないんだから。わたぼうももう少し協力的になって下さいよ。死活問題なんですから」
「う、うう、でも知らないし教えないわたっ」
あくまで強硬なわたぼうに、竜王は力ずくに訴える。平手打ちを二三発はり、それでも言う事を聞こうとしないのを見ると、ユークァルにわたぼうを放ってよこした。
「ユークァル、首をもっかいへし折れっ!」
「バカな事仰いますな! 焦った所でどうしようもないでしょう!」
私はルビス様から預かり受けた雨雲の杖で思いっきり後頭部を殴り付けた。ユークァルが本当にわたぼうの身体を引き寄せたのでオルフェがあわててわたぼうを引き離す。
「いててっ! お前最近偉く暴力的だな。しかし、こいつじゃ埒があかん。仕方ない、あてにはならんが、我らがスポンサー殿にでも御助力を仰いでみるか」
「うーん、そういうものはないのう…」
やはりというか何と言うか、タイジュ国国王の口からは、予想すべき答えが返ってきた。
「強力な魔法の武器なんか無いのか。あれば闘いの助けになるし、うまくすればこれも破壊出来るかもしれん」
「キューリさんの剣や妖魔の魔剣で無理だったんですから、余程の武器でないと無理でしょう」
「それでも、素手よりはマシだろう。今のままなら、素手では奴にかなわんからな。それにしても、売るんじゃなかったかなあ」竜王はキューリ嬢の家宝の剣を思い返して目を瞑る。
「売らなかったら私が貴男に食われてましたよ」あの時の飢えと睡眠不足に血走った目を思い出して、私は少しばかり身震いする。
「うーむ、星降りの夜の大会を開催するようになってからは、戦争らしい戦争は一度も起きておらぬからのう、武器のたぐいはほとんど残っておらぬのじゃよ。鋼の剣ぐらいならあるのじゃが…魔法の楯ならあるが、それではダメじゃしのう…」
「むう……仕方ない、武器はそれで行こう…とほほ…まいったな」
「ねえ、王様、この国に何でも外せるような優秀なカギ師とかいないの?」
「この国は豊かじゃから、あまり泥棒もおらんし、みな鍵をしっかりかける必要がないんじゃよ」
「うーむ」
「まいりましたねぇ」
「どうするよおっさん」
「黙れ馬肉」
一同は向かい合って、黙り込んでしまった。このままではタイジュの優勝はおぼつかないどころか、下手すると全員殺されてしまいました、なんて事になりかねない。何せ、パワーが最大時の1/16しかない状態で無類の強さを誇ってきた竜王が、魔王バラモス相手に手も足も出なかったのだから。
バラモスだけなら何とかなったかもしれない。しかし、これは魔物使い同士の闘い。あくまでも3対3の闘いであり、敵はバラモスだけという訳には行かないのだ。破壊神シドーの従属神ベリアル、正体不明の魔族デュラン。現時点での個々の能力はあちらの方が上と見るべきだろう。もとより私もオルフェもパワータイプではないから、魔王級の魔物に正攻法で来られてはどうしようもない。
「ホントにそなたらでもマルタのマスターにはかなわんと言うのか、のう? タイジュの優勝はどうなるんじゃ?」
「うむむ、まあ何とかしてみるさ。勝負は時の運とも言うしな」
国王の沈んだ様子を見て取って、竜王は慰めるように馴れ馴れしく王の肩を叩いた。それは、ともすれば自信をなくしてしまいそうになる自らへの励ましの様でもあった。
* * *
明日は星降りの夜の大会だというのに、私は宿屋を抜け出して、行く当ても無く夜空の下を彷徨っていた。
興奮して眠れないのだろうか。
いや、違う。私は明日、星降りの夜を迎えぬまま、バラモスの奴に殺されるやもしれぬのだ。あんな三下魔王を力でねじ伏せられぬとは、1/16の手錠のせいとは言え、私も地に墜ちたものだ。
この手を繋ぎ続ける、呪いの。
屈辱の時。私は今でも鮮烈に思い起す事が出来る。
この腕がこれほどまでに重く、この手錠がこれほどまでに疎ましく想われた事があったろうか。己れの致らなさをこれほどまでに思い知らされた事があっただろうか。
無かった、と言えば嘘になる。いや、今までの人生総てが、屈辱の歴史だったと言っても良い。ユークァルと私との間には、実際大した違いは無かった。ただ、ちょっとばかりの立場の違いによって、私は守られ、ユークァルは壊された。それだけの差だ。
ユークァルも、壊されるまでは、己の無力さに歯噛みしていたのだろうか? ひょっとすると、今でも?
あの娘は何時もそうだったに違いない。多分、あの時も。
こうして、ユークァルは心を閉ざしてしまったのだ。
誰も手を差し伸べてやらなかったから。
誰にも手を差し伸べてやる事など出来なかったから。
誰も本気で殺しにも来ないし助けにも来ない。生殺しのまま弄ばれ続けて。
あ奴も、同類だったのか。
初めてではない、異質な気の接近が思考を中断させた。国王から貰い受けた鋼の剣を引き寄せて身構える。
蒼白く瞬く燐光。その光には見覚えがあった。
「ロ…ト?!」
私は己の甘さを悔やんだ。バラモス達が大会の日までは手を出して来ないのですっかり気が緩んでいたのだ。
ロトは無言で翼を広げた鳥の文様を象った鍔を持つ剣を振り下ろした。
ここで傷付く訳にはいかない。ましてや、魂の無い人形如きに再びねじ伏せられるなど。
反射的に、振り下ろされた剣から身を守ろうと腕を翳す。鋭い金属音が一閃、不思議な事に刃はこの身を貫く事無く鞘に収められた。手首を見ると、力を封じ込めていた呪いの手錠に一筋切れ目が入り、手首を傷付ける事もなく手から割れ落ちた。私はあっけに取られ、しばし手首を見詰めていたが、やがて、顔を上げ何も映さぬ我が子の眼を凝視した。
「何故…貴様は私を倒す為に我が父から遣わされたのではないのか」
「神聖な星降りの夜を血で穢す事は許されません。それにもう一つ」無感情な筈の我が子の、その唇が意味ありげに、次の言葉を一呼吸遅らせた。
「魔王バラモスを倒す事」
「そんな事は貴様等のやる事だろう、何故私が。それに」
最後まで言い終わらぬうちに、問いは機械的に遮られた。
「バラモスとの戦闘によって星降りの夜を台無しにする事は命令に反します。それに、大会の決勝戦での戦闘以外の方法では、周囲の被害を完全に防ぐ事は不可能です」
血の通わぬ言葉。こ奴は何処まで作り替えられたのだろうか。
「どうかな? もし、奴らが闘いに観客を巻き込もうとすればどうなる?」
「闘技場は観客が戦いに巻き込まれない様、二重三重の魔法防御壁が張られています」
我が子の磨り硝子にも似た瞳を見ている内、ふと、我が子に問うて見たくなった。
お前もユークァルと同じく、誰かに『壊された』のか? どうやって『造られた』?
壊されるその瞬間まで、お前は抗い、そして己の無力を呪ったのか?
問いを投げ掛ける前に、ロトは星空の彼方へと飛び去って行った。
* * *
メイン・イベントまでにはまだ時間に余裕があるので、私達はプレ・マッチを観戦することにした。
プレ・マッチとは言え、それぞれの闘い毎に色々と趣向が凝らしてあって、メイン・イベントがなくてもそれ単体で楽しめるくらい密度の濃い内容である。例えば、スライム限定戦だとか、魔法禁止戦、はたまたマスター12歳以下部門、65歳以上部門etc.…。きっと、将来のメイン・イベント出場者が、こういう大会の中から経験を積んで頭角を現していくのだろうし、もしかすると昔メイン・イベントにでていた人があの65歳以上部門で戦っていたりするかもしれない。ドラマだなあ。
で、私達はコロセウムの観覧席で、思い思いに好きなものを食べながらプレ・マッチを観戦している。本番までまだ時間があるとは言え、結構客足は早かったので、いい席を取る事が出来たのは誠にもって運が良かったと言えよう。
「ハーゴンさん、オレにもポップコーンちょっとちょうだい。あ、すげえ、あのスライムイオナズン使ってるよ」
オルフェは2本目のバナナを頬張っていた。で、私がバター味のポップコーン。その横で竜王が七面鳥の足の焼いたのを袋一杯買い込んで、さっきからそればっかりをずーっと食べ続けている。何でも「なあ、バラモスって毛を毟られた太った七面鳥に似てないか? それを言われると奴はメチャクチャ怒るんだが、その怒って暴れるところがまたそっくりで」だそうである。ユークァルはイチゴシェイクをわたぼうと一緒に飲んでいる。
「いいか、よーく見とけ。あれがモンスターマスターだからな。今日はあれをやるんだ」
「うん」
「お前はモンスターマスターなんだ。だから、以前も何度か言ったけれども、間違っても相手のモンスターマスターの背後に回って首をごきっ、なんてやるなよ。いいな? 勿論ナイフでぶすっ、もダメだぞ」
「…とりあえず、だめなんですね」ちょっと考えるような様子の後、ユークァルが答える。
「そうだ。それがこの大会のルールだからな。戦場にはルールはいらんが、これはゲームであって、戦場じゃない」
「ルールを守ればいいんですね」
「そうだ。まあ、お前は後ろでおとなしくぼーっと突っ立ってるだけでいい。相手もお前を狙っては来ない。お前は命令を下してるフリをすればいいんだからな」
「…うん」
「ふう」一息付いて座席にもたれると、竜王はまた七面鳥の足を食べ始めた。
「プレ・マッチを観戦とは、随分余裕があるようだな、優勝候補さん」
わたぼうとシェイクを飲んでいたユークァルの隣にやってくるなり、テリーは足を組んでふんぞり返った。一同は渋い顔をしてテリーを見ている。
「そう腐った肉でも喰わされたような顔しなさんな。なあ、ユークァルだっけ。お前の事見てると、魔物使いって言うよりは、魔物に使われてるって感じだよな、はは」
「ユークァル、ここでテリーの奴にがつんと言ってやれ。でないとナメられるぞ。tell him ガツン、だ。わかったか?」
「……」竜王に促されて、今までずっと押し黙っていたユークァルが、テリーの間合いへ一歩、初めて踏み込んだ。あの無表情な瞳に見据えられて、テリーは明らかに狼狽した。
「あたしたち、負けません」ユークァルははっきり宣言した。
「だって、あたしは虫螻だけど、竜王は神様だから」
「…ユークァル、もういい。お前口聞くな」
ほおら、だから言わんこっちゃない。いつもそんな事ユークァルに吹き込んでるから、こんなしっぺ返しを食らうんです。テリーは大笑いしてるし、ああ、情けない。
「ポンピンパンポーン♪星降りの大会本部よりお知らせです。ただいまから本戦出場者の受付を開始しますので、各国の代表はコロセウム正面ゲート前まで集合して下さーい♪」
「ううっ、緊張するなあ」
「足だけはひっぱるなよ」
という訳で、私達は闘技場の正面ゲートで、本戦登録の為の行列に並んでいる。
本当は、事前に各国が、代表は誰か、どのような魔物を出場させるのかを事前に書類で出しているのだが、参加の確認やら替え玉使用の防止やら色々事情があるのだそうだ。そうこうしている内に登録の順番が回ってくる。
「じゃあ、お名前をお願いしますね。そうそう、名前は4文字以内でお願いします」
「へ? よ、4文字? 聞いてないよ〜」
「どうする、ユークァル。4文字では入らんぞ」
「どうしましょう…」
「はーいはいはーい! オレ提案しまーす!」
一同が考え込んでいる所にオルフェが手を挙げる。
「何じゃ、言うてみい」
「あのさあ、オレずーっと思ってたんだけど、ユークァル、って言いにくくない?」
「ふむ」
「…言いにくいですか?」ユークァルに真顔でまじまじと見詰められたので、オルフェはあわてて目を反らした。
「だ、だからさあ、愛称で登録したらどうかな? ユ、ユークァルだから、ユカ、とかさ」
「愛称で? それなら、ムォノーだからモノ、で良いではないか。この娘にはちょうどいい……って、痛い、痛いやめんか! わ、悪かった! 解ったと言っておるだろうが!」
「…冗談でも、許しませんよ…」気が付くと、私は竜王の頭を雨雲の杖で何度も殴り付けていた。自分でも身体の内側から妖気を発しているのが解る程、気の昂ぶりが抑えられずに溢れ出る。
「ツッコミのつもりなら、杖じゃなくてハリセンにしろよ。痛いんだぞ。…ふふん、どうやらお前も私の影響を受けてきたらしいな。妖気を漂わせておるぞ。まあいい、好きにしろ。だが私は呼ばんからな」
「じゃあユカね、決定。ユ、カ、と」
「次は私か…ってちょっと待て………確か……4文字…だったな………?」
「あ……」
「は、入らん…」りゅうおう、は4文字では入らなかった。
「じゃあおっさんも愛称で入れようか。何がいい?」
「き、貴様……おっさんって入れたら桜鍋にするぞ!」
「りうおう、とかどう? ぎゃはははは!」
「くぅあぁー! そんな名前は嫌だぁ!」
あーあ、また始まった。これでは幼稚園児の引率と変わらないじゃないか。でかい分こっちの方が余計に厄介だ。
「じゃ、先に書きますよ、ハーゴン、っと」
「じゃおっさん、しばらく悩んでて。オレ自分の書いとくし…オ、ル、フ、ェっと」
「あのー、オルフェさん、ですね?」
自分の名前を登録し終えたオルフェに、受付嬢が声をかけた。
「すみません、この名前では登録出来ません」
「え! な、何でぇー?」
「大会規則第5条によって、小さい『あいうえお』の文字は登録に使用出来ない事になっております。申し訳ありませんが、もう一度書類をお書き直し下さい」
「え? え? 何でさ? そんなあー! じゃ、じゃあ何で濁点と半濁点は1文字に数えないのかよ?!」
「去年まではそうでした」受付嬢はあっさり答える。「第5条は今年改訂されましたので、今年からは濁点と半濁点は1文字に数えなくて良くなりました」
「…そんなあ、マジかよ…」
へなへなと力が抜けていくオルフェの肩を支え、竜王は優しく耳元で囁いた。
「良かったな、オルフエ」
ファンファーレが鳴り響き、本戦がいよいよ始まった。
テト「という訳で、いよいよ星降りの夜の大会本大会の開幕です。実況は私モンスターマスターのテト、解説はゴーレムのベベさんをお迎えしてお送りします」
ベベ「フンガーフンガー(どーも、ゴーレムのベベです、どぞ、よろしく)」
テト「相変わらず何を言ってるのか良く解りませんが、どうぞよろしく。ところでベベさん、今年の優勝はどの国の代表になるんでしょうか、予想を聞かせて下さい」
ベベ「フンガガフンガー、フンガ(っつーか何言ってるか解んないなら呼ぶなよ……ま、いいけどよ)」
テト「皆さんには、今回ベベさんに事前に作成してもらったフィリップを準備してますのでこちらを見ていただきましょう。おお、やはり一番の優勝候補はマルタ国代表チームですか! まずは順当な所ですね」
ベベ「フンガフンガ(ま、当然でしょう)」
テト「対抗馬には何と! 意外と言っては失礼かも知れませんが、我がタイジュ国チームをあげてますねー」
ベベ「フガフガ(一応義理って事で)」
テト「おっと、そうこうしている内に第一回戦選手入場のようです、そちらに注目してみましょう」
控え室の袖口で係の者に促されて、ユカが入場した。
「タイジュ国の代表は、未知数の可能性を秘めた若き美少女モンスターマスター、ユカ!」
アナウンサーのコールに会場がどっと沸く。
「対しますは、今年から初参加のグランバニア国代表、エニクス国王です!」
流石は大国グランバニア、国王自らの参戦とあって、応援も物凄い。と、我々が入場する番だ。控えは壁で仕切られ2つに分けられており、入場するまでは相手がどんな魔物を使役してくるかは解らない仕組みになっている。
「続いては登場モンスターの紹介です。タイジュ国の魔物は、左から順に名前:りゅうお、種族:りゅうおう、名前:ハーゴン、種族:ハーゴン、名前:オルフエ、種族:ペガタウルスとなっております」
二人は嫌そうに、顔を赤くしてうつむいている。それにしても種族:ハーゴンって何だ? そんな事書いてないのに参ったな。後で訂正してもらわないと…。それとも、タイジュ国王が間違ったのかな? あのおっちょこちょいで早とちりの王様ならやりそうな事だけども。
「対するグランバニア国の魔物は、名前:スラリン、種族:スライム、名前:ピエール、種族:スライムナイト、名前:ゲレゲレ、種族:キラーパンサーとなっております」
「ふっふっふっ、このパーティで、ミルドラースもゲットだぜ! な、ゲレゲレ」
ベベ「フンガー! フンガー!」(ってそれはポケモンだろ!)
グランバニア国王が早くも勝ちを観客にアピールする。
「げ、ゲレゲレ?」
「な、何だ。俺らの方がマシじゃん? な、なあおっさ…うそ、うそだから」
やっといつもの調子に戻ったな。あの二人、ゲレゲレの名前を聞いた途端に元気が出てきて、現金なものだ。それにしても、グランバニア王のネーミングセンス、ワルキューリ=ド=ブリュンヒルト(以下略)並みにキツい事には違いない。スライムナイトのピエールも大概だしね。
「って言うか、スライム出してくるって事は、相当自信あるって事だよな。やっぱイオナズンくらいは使うのかなあ」
「相手を油断させる作戦か? 下手な魔物より強いのかもしれん。気をつけろ」
「まーかせて」オルフェは親指を立てた。「それより、大丈夫かな、どうしよう…」
「それでは」審判が赤い旗を振り上げた。
「試合開始っ!」
実はてんで弱かったグランバニアチームを攻略したのち、我々は大方の予想を覆し、他チームを秒殺する勢いで順調に勝ち進んでいった。マルタ国のテリー達のチームも同じく順調に勝ち進み、我々は決勝の場でテリー達と因縁の決着を着ける事になった。
我々は入場前に、最後の作戦確認会議を開いた。
「いいか、ハーゴン。お前はひたすらバラモスにラリホーをかけまくれ。あいつは良く寝るからラリホーは間違いなく効く筈だ。いいな」
「はい」
「それからオルフェ、お前はピオリムをかけまくってひたすら敵の攻撃をかわす事に専念しろ。無理に攻撃はしなくていい。それはハーゴンも同じだ。お前は隙があった時だけベリアルに何でもいいからあいつに効く魔法をかければいい。お前の方が私よりあいつの弱点や特技については良く知っておるだろう。それと、奴は昔のお前を知ってる以上、動揺を狙って過去の事をとやかく言ってくるのは間違い無い。良いか、その時は『今日のプライドより明日のご飯』だぞ」
「…何ですか? それは」
「文字通りの事ではないか」竜王は真顔で言った。「いいか、お前の下らんプライドの為に皆が死んで、貴様に責任がとれるか? お前は考える必要の無い時にまでごちゃごちゃ要らん事を考えすぎるきらいがあるが、今はその時ではない。それを思い出す為のおまじないだと思っておけ。簡単な言葉の方が憶えやすくて思い出し易かろう」
「…。解りました。で、貴男は?」
「わたしはあのデュランという奴を何とかする。あいつの実力が未知数な以上、最初に潰しておかねばならんだろう」
「強化魔法とかいらないの?」
「お前達は自分の事だけ考えろ。いいな」
私達は無言で頷いた。
「それとユークァル」
竜王はユークァルの肩を軽く小突いた。
「今まで良くやった。決勝もこの調子でな。いいか、お前はモンスターマスターなんだぞ。それさえ解っておれば良い」
「はい」ユカは素直に頷いた。
「それでは本日のメイン・イベント、星降りの夜大会の決勝戦、選手入場です! 青っコーナー、150パウンド(一部嘘あり)マルタ国代表、『青い稲妻』テリー選手! 対しまして、赤っコーナー、110パウンド(以下同じ)タイジュ国代表、『沈黙の薔薇』ユカ選手!」
「お、おい、勝手にキャッチフレーズ付けられとるぞ」
「テリー君、『青い稲妻』だって。ダサダサだなあー、うひゃひゃ!」
「……『沈黙の薔薇』も結構、恥ずかしいぞ」
「続いては、苛酷な予選を勝ち抜いてきた各国の登場モンスターの入場です!タイジュ国チーム、左から順に名前:りゅうお、種族:りゅうおう、名前:ハーゴン、種族:ハーゴン、名前:オルフエ、種族:ペガタウルスとなっております」
今度は変なキャッチフレーズを付けられなくて済んだので、私達は緊張の中、小さく安堵を漏らした。
「対するマルタ国チームのモンスターを紹介します! こちらは右から順番に、名前:バラモス、種族:バラモス、名前:ベリアル、種族:ベリアル、名前:デュラン、種族:デュランとなっております。では皆様、両チームに盛大な拍手をお願いします!」
駒は出揃った。
「それでは、試合を開始します!」
試合開始の赤い旗が目の前で踊った。
「よし、行け!」
「ラジャー!」
「解りました!」私達はユークァルをかばう様な布陣でマルタ国チームを迎え撃った。
「バラモスは援護射撃だ。後ろに下がって集団攻撃魔法を使え。ベリアルは師匠と組んで二人掛かりで竜王を潰せ! あっちのチームの要は奴だからな。ってあれ? ちょっと待てよおい!」
一方、テリーは手下に指令を与えていた。優勝候補を自称するだけあって、確かに彼の判断は的確で、もし魔物達が彼等に忠誠を誓っているのなら私達は本当に命を失ったかもしれない。が、魔物達はてんで勝手に攻撃を開始している。優秀な司令塔も、言う事を聞かない部下ではただの飾りだ。
「こ、こら! バラモスっ! ベリアルっ! 言う事を聞けっ! お前等のマスターは俺なんだぞっ!」
「知らんなあ。なあ? ベリアル?」
「誰が俺達のマスターだって?」バラモスとベリアルは互いに顔を見合わせてニヤリと笑った。
「畜生っ! これじゃどっちが主人だか解らんじゃないかァッ! バカ、バカァッ!」
手下と思っていた魔物達の離反という、私達にとっては予想通りだがテリーにとっては予想外の展開に、テリーはパニックを起こしていた。半泣きのテリーに向かって、我々は好機とばかりに反撃を開始する。
「ふん、そんな所だと思ったわ。己れの技量に余る魔物ではいくら強くとも役には立つまいよ!」
「やっぱインスタントチームの弱さが出てるよなっ! ピオリムッ!」
「では私も、ラリホーラリホーラリホーマ♪ 三連掛け!」
▼ハーゴンはラリホーのじゅもんをとなえた!バラモスはねむってしまった!
「バカモノどもが! この魔王バラモス様に、ラリフォォォーァぐぉときまふぉあああが効くとでも思って、ふぁああ、いるのふぁー、グガー、グオー、グガー」
「言う側から寝とるではないか、馬鹿者が」
竜王はいびきをかくバラモスを軽く足蹴にして、デュランに向き直った。
「貴様の相手はこの私がしてやろう。せいぜい楽しませてくれ」
「良かろう。ベリアル、邪魔はするなよ」
「へいへい」黄金色の体躯が二人から離れた。「そういう訳で、ハーゴンよ、せいぜい可愛がってやるぜ」
こうして私達は、ベリアルと対峙することになった。何という運命の皮肉なのだろうか。
だがその運命を云々する場では、今は無い。雨雲の杖を振りかざし、呪文の詠唱に入る。が、様子がおかしい。
ベリアルが、三叉戟を何時までも構えようとしないのだ。
詠唱が殆ど終わりかけるか終わらないかと言う時に、ベリアルは口を開いた。
「なあ、大神官様よ、こんな茶番は無しにしようぜ」
「?」
「何の為にお前が死者の世界から脱走してきたかは知らんが、よくもまあおめおめと、どの面下げて人前に出ようっていうんだ?」
「黙るが良いベリアルよ! 今はその答えを出すべき時ではない! 戦え!」
動揺を振り切って再び始められた呪文の詠唱を、ベリアルが遮った。
「大神官よ、言葉尻が震えてるぜ。お前はそんな風に自分を誤魔化すのに慣れちゃいないないはずだぜ、そうだろう?」
完全に見透かされている。
「あの糞真面目なお前が、どうしてまあここまで変わっちまった? あれほどまでにシドー様に信仰を捧げたお前がよ」
私には答えられなかった。今はその問いに答えを出す時ではない。解っていても、解っていても、私が失ってしまったあの『
Why
』が姿を見せないまま蘇って来ては呪縛するのだ。そしてベリアルは全てを知っていて、私にあの『Why
』をけしかけるのだ。
「お前に殺された人間どもの怨念がお前を呼んでるぜ? 何なら代わりに送り届けてやろうか…ん? のうのうと生き延びて、お前はいつからそんな厚顔無知になった? それとも、己の罪を償う為に、か?」そう言ってベリアルは総てを見透かす様に薄笑いを浮かべた。
今の私には看過する事すら出来なかった。例え、ここで自分が死んでしまってはその答えを見付ける事すらかなわないのだとしても。
その答えを見付ける事すらかなわないのだとしたら?
だとしたら?
「だとしたら、もう一度死んで詫びるしかないよなあ? 大神官猊下様よ!」すっと、ベリアルが息を深く吸ったのを、私は聞いた。
目の前を、灼熱の吐息が迫っていた。
「ハーゴンさんっ! よけろよッ!」
オルフェの一言が私を現実に引き戻した。
私はこの世界に、その答えを見付ける為に戻ってきたんじゃないか!
生きなければならない。
生きなければ!
「今日のプライドより明日のごはんっ!」
雨雲の杖に呪力を込めて振りかざす! 杖を媒介にして迸る呪力は魔法の霧を噴射し、ベリアルの灼熱の炎と衝突して水蒸気を撒き散らした。熱気が会場を包み、むっとした空気が辺りに充満する。
「ケッ!」動揺を誘う作戦が失敗したのを知って、ベリアルは地面に唾を吐き捨てた。
「お前らなんぞこの一撃でふっ飛ばしてくれる! イオナズンッ!」
私達を覆い尽くそうとした筈の爆炎は、逆流してベリアルを包み込み爆発した。
「やったね! マホカンタ作戦大成功!」この戦いに備えてタイジュ国王から借りておいた水鏡の楯が効いて、オルフェは飛び上がって喜んだ。
「いや…ベリアルに炎は効きません」ぬか喜びするオルフェを制して、構えを取る。
濛々と立ち上がる煙の中、ベリアルの影がゆっくりと起き上がってきた。
「このベリアル様をナメやがって…灰も残さず焼き尽くしてくれるわっ!」ベリアルは息を吸うと、吸った息の何倍もの圧力をかけて灼熱の息を吐き出した。間髪入れずにフバーハの魔法で光の衣をまとわせると、ベリアルの炎の息も衣に阻まれて余り効果が無い。
「ぐうう、一介の神官と下級魔族の分際でふざけやがって!」
頭に血が上ったベリアルは、その巨体で体当たりをかましてきた! オルフェはベリアルの体当たりを避け切れずにふっ飛んでしまった。あと少しスクルトが遅れていれば、体中の骨がばらばらにされていただろう。素早くベホマの呪文をかけてやる。
「くわっ、あいつ、体でかいのにメチャメチャ素早ええー!」
「このままでは攻撃を仕掛ける余裕が……うわっ!」ベリアルの三叉戟が飛んできて、私の法衣を引き裂いた。すんでの所で逃れたが、気付くのがもう後少し遅ければ串刺しになっていたかもしれなかった。少しばかり足から血が流れる。
「ほぉら、考え事をしてるヒマはないぜ。それとも思い出したかい? 己れの為した事を。後悔してるんだったらとっととあの世へ行きな!」
ベリアルは投げた三叉戟を地面から引っこ抜くと、再び振りかざして突っ込んできた。魔法で素早さや防御を上げても、流石に破壊神シドーの従属神の一柱が相手では、その内追い付かれるのは目に見えている。
「オルフェさん、ハーゴンさんを連れて空中に逃げて下さい」
「ユカ!」試合中初めてユークァルが口を利いたので、私達は驚いて振り返った。
「オルフェさん後」
「うわっと!」1秒前オルフェが立っていた辺りに、ベリアルの巨大な三叉戟が突き刺さっていた。
「オレはそんな隙を与えてやるほど紳士的じゃあないぜ、お二人さんよ!」三叉戟を引き抜こうとベリアルが手を伸ばした背後から、オルフェが思いっきり尻に水平蹴りを見舞った。ベリアルが不恰好に倒れている間に、私はオルフェの背に跨がって二人して宙に舞い上がる。
「グヘヘヘ、このオレの翼は飾りじゃないんだぜ!」
ベリアルはすぐさま我々の後を追って飛び立った。が、予想通り体躯の割に小さな翼のおかげで、地上でのような素早い動きは出来ないようだ。
「オルフェさん、絶対に制空権は取られない様にして下さーいっ!」
「あの娘、余計な事をしおって…!」
「魔物使いが自らの魔物を使役するのが余計な事なのかな? 隙ありっ!」デュランの両刃の剣が竜王の肩口を切り裂く。
「ふん、やるな。では、こちらも敬意を表して呪文は使わぬ事としよう」
竜王が目を閉じて傷口に手をかざすと、傷はみるみるうちに塞がっていく。
「瞑想か」デュランの冷徹な瞳の奥に、闘う者が宿す悦びの光が見て取れた。「ようやく本気を出させてくれそうな相手が現われたか」
「そちらはどうかな?」
竜王は手に付いた赤い血を舌で拭って、凄味のある笑みでデュランに応じた。
ユークァルの読みは完璧だった。
地上では恐るべき武器になる筈の巨躯も、空中戦においては厄介なお荷物でしかない。
ベリアルは我々を捕まえようと小さな翼で空中戦に参戦を試みたが、素早さと空中での所作では例え神と下級魔族とは言え、オルフェの方に分があるというものだ。それに、私はオルフェの耐久力を多少侮っていたかも知れない。オルフェは見た目以上に強靭で、オルフェがまだまだ飛び回れる内に、冷静さを失っていた事と相俟って、ベリアルの飛翔スピードは極端に落ちていた。小回りの聞くオルフェと違って、無駄な動きが多過ぎるのだ。
ベリアルは三叉戟をブーメランの様に回転を加えながら水平に投げる。オルフェは羽撃くのを止めて高度を下げ、三叉戟がベリアルの手元に戻る前に私がマヒャドを立て続けに打ち込む。ベリアルは何でもない様に表層に凍り付く氷を弾き飛ばした。が、その鱗にうっすらと浮かぶ霜と、凍傷らしき症状が出ている様が見て取れる。
「マヌーサ!」
魔法の霧がベリアルを包み込む。再び投げた三叉戟はあさっての方向に飛んで行き、ベリアルは戟を取りに行く隙に何発ものマヒャドを立て続けに食らった。制空権を取られた上に霧に視界を遮られて、思うように攻撃が当たらないのに業を煮やし、ベリアルはオルフェの真下に着地して地面を蹴って反動を付けると、槍を構えながら突っ込んで来た!
「今ですっ!」
ユークァルの合図に応じて、私は唱えた。
「アストロン!」
私達の体は鋼鉄の塊と化し、従って、天則に逆らう事無く落下した。
血肉の通った標的が、鉄の塊となったのに気付いた時、ベリアルはもう眼前の危機を避ける事が出来ない程、完璧な攻撃の体勢に入っていた。
激突、そして墜落。
ベリアルの体が押し潰される感触。
金属の体が生身に戻った足元に、ベリアルの潰れたひきがえるの様になった身体の感触が伝わって来た。
一方、竜王とデュランの二人は、実に際どいつばぜり合いを演じて観客を喜ばせていた。傍目には一進一退を繰り返しているように見えたが、そうではない事に気付いている者が居た。撃ち合っていても、相手が打ち込む早さも角度も手加減しているようにしか思えないのだ。それでいて、こちらの全力での一降りを的確に受け流す。
「…貴様、よもや、本気を出していないのではあるまいな?」
竜王は、だったらどうする、と言わんばかりに鋼の剣を振り下ろす。デュランは刃を受け止めると、そのまま鋼の件を押し返し、なぎ払った。
「本気を出せ! それとも、我が相手では本気を出せぬと言うのか!」
「いいのか、本気出して」
「へ?」デュランのガードが一瞬甘くなったのを、竜王は見逃さなかった。
「死ぬぞ」口振りとは裏腹に、その口元は愉悦に歪められていた。
「食らえ、我が必殺のデェェーモォォーンスラアァーッシュ!」
▼りゅうおうはあくまぎりをはなった!
ベベ「フンガー! フンガー!(悪魔斬りって素直に言えよ!)」
「どわーっ!」デュランはものの見事にふっとんだ。
「うーむ、やはりはがねのつるぎでは威力がいまいちだな」
闘技場の壁に叩き付けられ、デュランはしばらくの間埃の中に埋もれていた。が、立ち上がるとすぐにつかつかとテリーのもとに歩いていった。
「ギブ・アップだ。私は降りる」
「し、師匠ッ!」
「まだまだ、お前も私も修業不足の様だ。…一年後、だな」
すがるテリーを降り払って、デュランは弟子に最後の引導を渡した。
「終わったか…あとはバラモスだけだな…!」
「グヘヘヘ、待たせたなあ。主役は最後に出てこないとカッコウがつかねえからなァ!」言うなりバラモスは殴りかかって来た。攻撃をかわした後の地面がバラモスの拳で抉れて、半径1m程の窪みを作った。バラモスは次々に爪を振りかざし、徐々に竜王を追い詰めていく。
「ラリホー!」
「そう何度も同じ手にノるかっ!」バラモスは予めマホカンタを唱えていたらしく、あっさり跳ね返される。オルフェが跳ね返されたラリホーで、床に崩れ落ちてしまった。
「オルフェッ! オルフェ、起きて下さいっ…」
私がオルフェにかまけている間に、バラモスは舞台端で竜王を捉えていた。二人は暫く睨み合っていたが、バラモスは後ろにいるユークァルに、ほんの一瞬視線を移した。
(今だ、ユークァル!)
私は直ぐに、バラモスの行動が何を意味するか把握した。
だが、私は、ユークァルを祈るように見守っているだけだった。人々が凝視する前で下手な事を口走る訳にはいかなかった。だが、そんな事よりも、何時かの夜の出来事が、頭からこびりついて離れなかった。そして、何よりも、彼女を信じたかった。
ユークァル、貴女が修羅の道から逃れる事を望みますように。
貴女が、殺人機械としてではなく、一人の人間として生きる事を望みますように。
私の、そして皆の気持ちが、貴女に通じますように。
ユークァルが、僅かに動こうとしたように見えた。竜王はバラモスの猛攻を耐えていたが、気配に気付いたのか、体を逃がして後ろのユークァルを見た。
(動けっ! 動けユークァル!)
(お前は、モンスターマスターなんだからな)
ユークァルは、動かなかった。
「どうした、ユークァル! 命令を聞かんかっ!」バラモスは喚いたが、ユークァルは動かなかった。
「あたしは、モンスターマスターですから…」
「何だと? もう一度言ってみろッ!」
「あたしは、モンスターマスターです」ユークァルは毅然として言った。「モンスターマスターは、闘技場の上ではルールを守らなくちゃいけないんです」
初めて命令に逆らったユークァルに戸惑うバラモスは、肩を軽くつつかれて身を硬くした。
「どんな命令を下したのだ? 言ってみろよ。どうしたバラモス、言えないのか? 野郎が」竜王はぐっと顔を寄せて、耳元で囁く。「私はなあ、案外多くの事を知っているつもりだぜ? 貴様等が理不尽に下した恥知らずな命令の事とか、な」
バラモスは射竦められた獣のようにビクついていたが、直ぐに肩に置かれた手を振り払った。
「ヘ、ヘヘヘヘ…だがヨォ、お前のその腕に、16分の1の可愛いブレスレットがある限り、お前はこのバラモス様には絶っっっ対にかなわないんだヨォ!忘れちゃいないかぁ?ギャハハハハハハハ!なぶり殺しにしてやるッ!」
バラモスの高笑いを無視して、竜王は、無言で、その右腕を誇示する様に高く突き出した。左手は思わせ振りに袖口を止めるカフスを外し、腕の輪郭に添って長い袖を降ろしていく。
「忘れちゃいないさ」その手首に、あの手枷は無かった。
「ゲッッ!!」
バラモスは一瞬ひるんだ様子を見せたが、素早く動いて私の腕をつかもうとした。
「仲間の命が惜しくないのか? …ヒィッ!」
私の手首をつかもうとして、バラモスは、間違って触れてはいけない物に触ってしまったかのように私をつかんだ手を振り払った。
私は冷静だった。冷静なつもりだった。が、しかし、その卑劣さ、そして、過酷な運命をユークァルに課したものへの憤りに、押え切れぬ激情が、妖気となって迸っていた。
「往生際が悪い! それでも、嘗ては魔王を名乗った者の振る舞いか!」
バラモスは気圧され、後ずさりして、突如踵を返した。
バラモスは、そのままユークァル目がけてメラゾ−マを放った!
「しまった!」
私達はこうなる可能性を考慮しておくべきだった。我々はつい、この戦いではルールに従うのが当然の事だと思いこんでたが、バラモスがそうであると信ずべき理由など何もなかったのだ!
「死ねええええええ!」
ぼんやり立ち尽くすユークァルの前を、白い影が遮った! 白い影はユークァルを庇うようにバラモスの前に立ちはだかると、その手に持った楯を天に翳す! 楯は陽光を反射して煌めくと、バラモスの放った巨大な火球を跳ね返し、バラモスは己の放った火球に包まれて、焼き七面鳥宜しく転がり回る。
「フンギャー! アチ、アチチアチ!」
「ざけんなクサレ七面鳥! オレ様あるかぎり、ユカには手を出させねえぜッ!」白い影の正体はオルフェだった。「おっとといおいでー。アッカンベー」
バラモスは怒り狂ってオルフェにつかみかかろうとしたが、肩に手を置かれて、今度はゆっくり振り返った。
「バラモス、年貢の修め時だな」
「う、うへ、うへへへ…か、勘弁してくれよ、な? ゾーマ様んとこに居た時からの長い付き合いじゃねえか。ほら、オレ様とお前の仲だしさ、お互い何も知らない間柄じゃなし。な? その…死ねーっ!」
「バラモス、貴様のクズぶりは相変わらずだな。行くぞ」
「行きます」何も言われなくても、どうすべきかは直ぐに察せられた。
「食らえ! 必殺、逆風の
ー!」
「塔
ー!」
ベベ「フンガー! フンガガフンガーッ!(何で特技が連携するんだっ! それはサガフロンティアだろ! ゲームが違うっちゅうの!)」
「うぎゃらぽろぴれぱれぇーッ?!☆」
こうして、バラモスは星になった。
会場は一瞬、水を打ったように静まりかえり、すぐ、その数倍の歓声で沸き返った。
「今年の大会優勝国は、タイジュ国に決定です! 何と言う番狂わせでしょう! 何と言う奇跡でしょう!」
人々の歓声も、勇者を称えるファンファーレも、私達の耳には届いていなかった。ただ、ただ何か大きな事を成し遂げた後の虚脱感と、心地よい疲労感のような物、そしてこれが何かを決定的に変えてしまったのだという無闇な確信だけが、少なくとも私の中にはあった。
日が暮れて空が金を帯びた朱色から淡い葡萄色、深い紺そして射干玉の闇に塗り替えられると、私達は人々に促されて展望台に連れて行かれた。人々がすずなりになって夜空を見上げる中、私達は優勝者の為に用意された特別席に案内される。横では国王と、家出したと噂に聞いた王妃が、仲良く椅子を並べて私達を待っていた。促されるままに席に付く。
私達も星空を見上げていると、誰かが星空を指差して叫んだ。
「始まったぞ!」
流星が一つ、輝きを放って尾を一筋、空に残して墜ちていった。
それが引き金になったかの様に次々と、天という天、空という空から星々が、輝きが、恵みの雨の如くこの大地に、私達に、数多の生命に降り注ぐ。
天は、その恵みを、あまねく総ての命に分け隔て無く分け与える。人も、魔物も、草木も水も土も、罪人の私にも、総てに。
どうして、世界を滅ぼさねばならないなどと思ったのだろう。
こんなにも、世界は美しいのに。
とめどなく溢れた涙を、拭う事無く何時までも私は星降り注ぐ満天の星空を眺めていた。
「この先のほこらへは、大会の優勝者しか入れない事になってるわた。…まさか、ホントに優勝するとは思わなかったわた…」降り注ぐ星々も疎らになった頃、わたぼうが私達を呼びに来た。
「フン、その口振りでは我々には優勝して欲しく無かったと言わんばかりだな。んー? お前の毛を守ってやったのは誰だと思っておるのだ?」竜王は嬉しそうにわたぼうの耳をひっぱる。
「どっちに転んでも辛いわた…」今度は、わたぼうは抵抗しなかった。
私達はわたぼうの手で、世界樹の奥にあるほこらへと導かれていった。
天より降り注いだ星々の光は、ここでは未だそこここに満ち溢れ、瞬いている。我々が祠に入ってしばらくすると、光は徐々に祭壇の一点に集められ、膨張していった。ほこらの中は生命の輝きで充ち溢れ、満たされる。やがて光は拡散し、祭壇の上には一抱え程もある光の塊…卵が残されていた。卵はニ、三度その身を揺さぶると、すぐにひび割れ、ひびの合間から見覚えのある生き物が顔を覗かせた。
「わた?」
「わたぼう!」
「そうわた。星降りの夜になると、ここから新しい世界樹の精霊が生まれるわた。星降りの夜の祭りは、世界樹の命の誕生を
言祝ぐ祝祭わた」
新しく生まれ落ちた命を見守りながら、私は命という物の重さの意味を噛み締めていた。
「すっごく綺麗だったね、ユカ」
「…ああ言うのが綺麗って事なんですね」
昼間の端の土手に腰掛けて星空を眺めるユークァルとオルフェの前に、テリーがひょっこり姿を現した。
「何だよテリー。てめまた文句言いに来たのかよ」
文句をつけるオルフェを尻目に、テリーは黙ってユークァルに右手を差し出した。ユークァルはどうしたらいいのか解らないようだったが、オルフェが耳元で手を握る様に囁くと、黙ってテリーの手を取った。
「おめでとうよ。…来年は絶対負けないからな」
テリーはそれだけ言うと、また人ごみに紛れて去って行った。
「ユークァル、ちょっとこっち来い」
祭りの後、興奮冷め遣らぬ広場の片隅で、竜王は腰を落ち着けて、宴会場からくすねた酒を独り、ちびちび飲んでいた。が、オルフェと一緒に星空を見ているユークァルを呼び寄せると、オルフェに席を外す様に告げ、ユークァルを隣に腰掛けさせた。
「飲むか?」
竜王はユークァルが首を横に振るのを確認してから、噛み締めるように語り出した。
「良いか、これはお前の一生を左右する大事な話だ。だから、良く考えてから、自分の意志で決めろ。わかったな?」
ユークァルはいつもの様に反射的に頷いた。
「お前は今まで、主人持ちの奴隷だった。そして、いつか私を殺す為に、任務として私に付いて来た。これはいいな? だが、今、お前に任務を与えていたお前の主人は居なくなり、任務は意味をなさなくなった。そして、お前に命令を下すものはもう居ない。だが一方で、今のままではお前は主人を持たない奴隷に過ぎない。以前、私はお前に、私は神でお前は虫螻だ、と言ったな? 何故か解るか?」
ユークァルは首を傾げ、じっと考えている様に見えた。
「解らんか? それはな、お前が自分は虫螻だと思っているからだ。今のままなら、新たな主人が現われれば、お前はまた主人付きの奴隷に逆戻りだ。そしてお前はそれを今まで、当たり前の事だとそう思って来た。そうだな? だが、本当はそうではないのだ。もし、お前が自分を…そうさな、もっと何か違うものだと信じる事が出来たなら、きっとお前は変われるだろう、多分な」
ユークァルは良く解らないと言ったように、数度瞬きをした。
「この国は豊かだし、大会に優勝した今、誰もが皆お前の事を好きだし尊敬している。誰もお前を傷付けようとする者はいない。きっと、ここでなら、お前は人としての心を取り戻していく事が出来るだろう。今回はまぐれで勝ったようなものだが、お前には魔物使いとしての素質があるようだし、なんならここで本格的に魔物使いの修業をしてもいい。まあどちらにしろ、ここにいれば星降りの夜の大会の優勝者として食いっぱぐれる事はないだろう。この国にはお前の過去を知る者は誰もいまいから、その事で、お前が将来過去を暴かれるのではないかと悩む事もあるまい、おそらくは。それに、この国の人々もお前がこの国に留まる事を望んでいる。ほらな、あっちでこの国の王がお前を呼んでおるぞ。きっと、この国に残って来年も大会に出て欲しいと頼むつもりなんだろう」
竜王は、そこで初めてユークァルの目線に合わせて膝を付いた。血を分けた実の子にすら向けられた事の無い、一緒に旅をしてきて今まで一度も見た事もない優しい瞳だった。「どうだ、ユカ、ここに残るか?」
ユークァルはちょっと小首を傾げた後、首を横に振る。
「付いて来る、というのか? お前、また新しい主人持ちの奴隷に戻る気か? 自由というのはな、一度手放したら容易には戻ってこない。私は暴君で、何時お前に酷い仕打ちをするか解らんのだぞ? お前が自由を欲するようになった時、私がお前に自由を与えるという保証はどこにもない。それに」
竜王は、あの、深奥を覗き込む様な目で、ユークァルの硝子の目を見据えた。
「私は、付いて来いとは一度も言っていない。それでも、お前は私に付いてくるのか?」
ユークァルは押し黙った。押し黙って、考える仕草を見せた後、言った。
「酷い事なんかされた事ありません」
「妙な事をいう奴だな。散々殴ったりつねくったり足蹴にしたりしただろうが」
「あれ、酷い事だったんですか?」
ユークァルにまじまじと見詰められ、竜王は深い溜め息を付いた。
「もう、良い。…それがお前の答えなのだな」
国王に呼ばれてユークァルが去り、人々の姿もまばらとなった頃、私は広間の隅っこで、竜王が瓶を片手に一人佇んでいるのを見付けた。何だかその背中が何時になく寂しげで、余計な世話とは言え声をかけずにはいられなかった。
「どうしたのですか? 目出度い祭りの夜だというのに」
「目出度いものか」竜王は例の調子で毒づいた。「あの娘、我々にまだ付いて行く気らしい。私はあ奴にそれとなく、この国に残る事を勧めたのだが…あ奴ははっきりと、自分の意思で付いて来る事を決めてしまった。止められると思うか?」
「何故です?」真意を測りかねて、私は訊ねた。「それが、彼女が熟慮の末に出した結論であるのならば、むしろ喜ぶべき事ではないのですか? 何故そんな沈んだ顔を?」
あんまりにも真っ直ぐに見つめ返されたので、私は恥じらいを覚えた。どうして今まで気付かずにいたのだろう、皆の運命全てを背負っているのが、他ならぬ竜王自身である事に。馬鹿を言ったり、過剰なまでに自信家ぶったりするのも、運命に押し潰されない為の、精一杯の抵抗だった事に。
「そんな事は問題ではないのだ。そんな事は」
竜王は拳を硬く硬く握り締め、痛々しいまでの苦衷を滲ませて一言一言を吐き出した。
「ここに留まっておれば、あの娘も救われたかも知れぬというに……あの娘を連れて行く事で、あれに今以上の幸福を我々が与えてやる事が出来る、などと、まさか本気で自惚れている訳ではあるまいな? 我々がこれより進む道は神意に叛く道。どうして、今までの様に何とでもなるなどと楽観的になれる? どうして、あの娘が、我らと共に行く事によって、死ぬより苦しむ目に会わないと、殺人機械として仕込まれて来た嘗ての日々より悲惨な目に会わないと、何故言える? 私には言えぬ、私には…………」