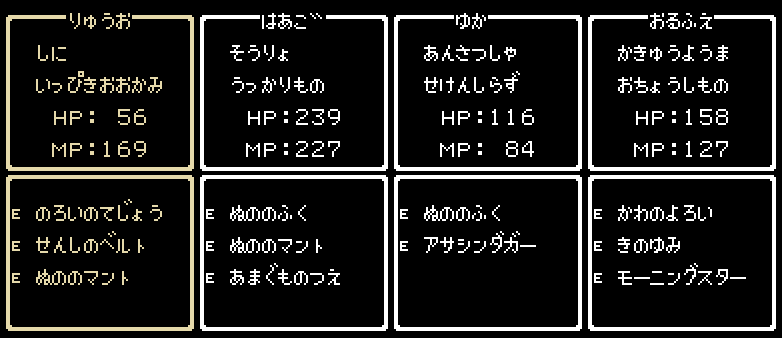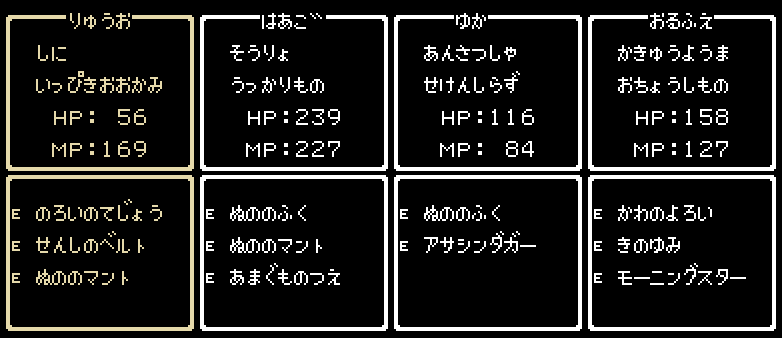第IV章 ロザリーヒル 〜血と鎖〜
「…ふむ、針の城を破壊したか」
大理石造りの広間にある玉座は、光に対して逆光になる様配されている所為で、座す者の姿を鮮明にはしない。
「ですから、もう限界なのでは。早くあ奴らを滅ぼさねば、被害は広がる一方です」
天空人の騎士団長は熱弁を振るって世界の支配者へ現状を訴える。黒々と艶めいて、ぴんと張った髭が熱を入れれば入れる程に滑稽さを増す様子と来たら、さながら哀切な調べの如きであった。
「恐れながら…マスタードラゴン様、あ奴に情けをかける訳は、我々とて重々承知の上で御座居ます。しかしながら…」
玉座に座す、影が動いた。
「情けをかける理由が解る、と? 面白い。申してみよ」
「あ、あの…いえ、そういうつもりでは…」
意外な返答にすっかり狼狽える騎士団長を睥睨し、マスタードラゴンと呼ばれた玉座の主は含み笑いを漏らした。
「気にせずとも良い。しかし、ともなれば野放しにしておくわけにも行くまい。相分かった。何とか手を打とうぞ」
「ははあ、恐悦至極に存じ上げ奉ります」
滑稽さの上塗りとばかりにうやうやしい一礼の後に針金髭の騎士団長が去った後、玉座の影は小さくなって行き、ちょうど人型に近い大きさになった。とはいえその影は人より長く、姿は人に似て非なる形。影は玉座から降り立つと、玉座の裏にある小さな隠し扉を捜し当てて鍵を開け中に入っていった。
「そろそろ、放ってはおけぬようになったか…ククク、面白い。流石我が血を引く者、やりおるな」
小暗い通路を縦横に通り抜け、深く降りた先に、目当ての部屋はあった。
「が、この封印を解いた今、それも終わりか…もう少し楽しませて欲しかった処ではあるが、致し方有るまい」
鍵束の中から特別複雑な作りの鍵を一つ取り出すと、マスタードラゴンは慣れた手付きで鍵穴に鍵を差し入れた。
「この試練、汝等に越えられるかな? ……百年の封印を今解こう。目覚めよ、伝説の勇者よ!」
扉の中から、冷ややかな大気が洩れ広がった。正面にあるは青白い光を帯びた、二抱えほどもある天青石の柱。中に封じられるは、蒼い鎧をまとった一人の戦士。
「やはり、そうなのですね」
沈黙の中、一人ほくそ笑むマスタードラゴンの後で女の声が響いた。凛とした、豊かで、そして深い憂いを秘めた響きである。
「?! る、ルビスではないか! どうして、ここへ?」己以外はいてはならない筈の隠し通路に第三者が現われて、マスタードラゴンは明らかに狼狽していた。
「後をつけて参りました」
ルビス、と呼ばれた女の声が、僅かに上ずった。
「ある程度想像はついておりました。わたくしが石にされ、塔に封印された際置き去りにしてしまった我が子が、わたくしを助けてくれた伝説の勇者である事、そしてその子が400年の後、何らかの手段で甦っていた事も。貴男があの方の余りに非道な行いを見兼ねて勇者を遣わした事、人々を救う為ならば詮無き事と諦めておりましたのに」
ルビスの黒目がちな瞳に大粒の涙が滲む。
「なのに、なのになのになのにっ! 貴男と来たら貴男と来たら貴男と来たら! 実の孫を殺戮機械にしたて上げ、冷凍カプセルに封印したあげく、実の父親と二度も戦わせるなんて! それでも貴男神ですか人の親ですか世界の支配者ですかっ! ロトの人生何だと想っているのです! そんなひどいそんなひどいそんなひどおぉぉぉーい!」
「う、あ、これには色々と深い訳が……」
「どんな訳です! 出来るものなら申し開きなさって下さいませ!」ルビスの舌鋒は留まるところを知らない。「それは、わたくしを妃に迎えたいからなのでしょう! 自分の息子の恋人を妃になんて、こんな破廉恥な事ってありますか! わたくしが今でもあの方をお慕い申し上げていてなびかないから、あの方を殺してまでも口説き落とそうという魂胆なのですね! このスケベジジイ! ばか! ヘンタイ! ひとでなし! ムッツリスケベ! セクハラオヤジ! わたくしの大事なものを二つも取り上げておきながら、よくもいけしゃあしゃあと! わたくし、ほとほと愛想が尽きましたわ。決めました」
世界の支配者を殴り放題、言いたい放題言い尽し、すっきりした顔でルビスは宣言した。
「おいとま申しあげます。わたくし、これからは自らの愛に生き、殉じる事に致しますわ。うふ☆」
「ま、待てルビス」これが先程まで玉座の上でふんぞり返っていた世界の主と同じ神かという威厳の無さ丸出しで恋々と縋り付くマスタードラゴンを足蹴にし、ルビスはとっとと青銅の扉を足で蹴り閉じて去って行った。
「そなたが天界を離れ、世界を見捨ててしまったら、誰が地に生きとし生けるものを見守って行くのだ……。ああ、行ってしまった。参ったな、予定外の
因子
がまた一つ増えてしまいおった」
あの時、私は鎖に繋がれ吊されていた。
我ながらつくづく鎖に縁があるのか、ゾーマの城の地下深い一室、漆黒の闇の中、雫の落ちる音だけが酷く、耳障りなくらいに反響する。
ここは拷問部屋。
勇者の手によって配下の魔王バラモスが倒され、石像と化したルビスがその呪縛を解かれ助け出された、という報が伝えられてから、ゾーマの様子は酷く落ち着かないものになっていた。殆ど八つ当たりの様に町や村を配下の魔物達に襲撃させ、部下のつまらぬ阻喪に残忍な刑罰を与えた。
そして、とうとう奴は私に、勇者を倒せと命じたのだ。
無論私は聞く耳持たなかった。例え伝説の勇者であったとしても、何故たかだか人間の男一人如きに自ら出向かねばならないのか。私はゾーマの使い走りではない。奴に恐怖の故に仕えている連中とは訳が違う。そして何より、私はゾーマを憎んでいた。
正直、侮っていたやも知れぬ。奴には私が、何故かは知らぬが必要なのだと。恐らくはそれ故に、奴に従うのを拒んでも、今まで何とかお目こぼしを受ける事が出来たと言うわけだ。今までは。
だが今回は違った。
あの時の私には解らなかった。あ奴――大魔王ゾーマが、勇者――つまり自らの滅びの時を怖れるには、奴は余りに強大に見え過ぎていたのだ。恐怖を与える者が恐怖に怯え滅びの時を怖れる様など、誰が想像できよう?
こうして、私は地下牢に繋がれた。
ここに繋がれるのは初めてでは無かった。奴の命令を拒む度、見せしめに痛め付けられた。だが、今度こそは生きてここから出る事はあるまい。
後悔の念は無かった。何時かこんな日が来ると、何処かで解ってはいた。それがただ、少しばかり予定より早かった、それだけの事だ。
だが。
かなうならば、短い生涯に受けた我が苦しみの数々の、ほんの一握りでも、この手で奴に味わわせてやる事がかなうのならば、我が命さえも惜しくは無いというに。
ほんの僅かでも。
当時の私は気付く由もない事だが、奴はあの時、別の形でそれを味わっていたのだった。
鉄格子から漏れる僅かな明かりさえもが、深い闇に遮られた。金属の扉に負荷がかかり、軋みながら闇の主人を迎え入れる。
奴が、来た。
水滴の音に混じって、衣擦れの音が空気を裂き、足音さえもが冷ややかに、響く。地を這う蛇の如く、気配を殺してはいる。が、それでも、一段気温が下がるのが、離れた先からも感じられる。
全ての熱と、生命を奪う瘴気が、床を伝って染み渡り、やがて総身を這い回る。己を蝕む瘴気から、少しでも我が身を守ろうと、皮膚が抗うように逆立つ。
気力を振り絞り、荒く息を吐く。
「まだ、余に逆らう気力は残っていると見える。何時まで虚しい試みを続けるつもりやら……素直に従っておれば、かほどに苦しまずとも済んだであろうにな……愚かな………そなたは何時もそうであったな。余を主と認め、恐怖と忠誠とを以て仕える事を拒み続けて来た」
ゾーマは忍び笑いを漏らした。指先が爪を立て、首筋から喉元を辿る。震えが止まらぬ。止められぬ。冷たい手が、喉笛を捕らえる。奴と私はその血に別の理が流れる者。未来永劫相容れる事はあるまい。
「余は慈悲深い。もう一度だけ、機会をやろう。……余の命に従い、天界の刺客を屠って参れ」
そう口にしながら、ゾーマは愉しげにその骨張った手に力を込めた。私など奴にとっては、生まれたての雛鳥同然だった。何時でも握り潰せる。何時でも。あ奴の
掌
の上より逃れられる者など何処にもおるまい。
ゾーマの奴は、私を嬲りものにする時に限っては、何時も決まって手心を加えていた。故に他の魔物共から妬まれ、厭われ、憎まれて来たのだが。他の連中がどう想っていようと気には止めなかったが、何故に奴が私を特別扱いするのか、そればかりは未だ判然とせぬままであった。本当はゾーマにとって勇者などどうでも良く、ただ私をいたぶる事で気を紛らわせんが為の仕打ちなのだ、としか想い至らなかった。
「…御免…被る…」
ゾーマの乾涸らびた口元から、嗤いが消えた。
喉笛を捕らえていた手をそのまま壁に叩き付け、飽きる程に何度も私の頭を壁に打ち据えた。ゾーマは私の頬に爪を食い込ませ、顎をねじ上げて無理矢理顔を上げさせた。
「判っておらぬようじゃな、とことんまでの大馬鹿者が。手慰みは、仕舞いじゃ」
私はすぐには、その意味するところを飲み込む事が出来無かった。そして、その意味する所を知った時、初めて、私は、殆ど絶望に近い我が生にも、一筋の光が射し込み得るのだと、そして、心底から愉快だと、想った。この世を闇で覆い尽くし、恐怖と邪悪で世界を塗り潰し、我を絶望と苦痛によって支配して来た大魔王ゾーマさえもが、己が掌の上で弄んで来た者達と変わらぬ存在に過ぎなかったのだから。
「…ふっ、ふ、ふ、ふははははは! 貴様でさえ滅びを怖れるのか、恐怖王! …ぐ、ご、ごほっ……」
ゾーマの青紫にぬめる爪が、肉に捻込まれ深紅に染まる。
「過ぎた口を。そなたがマスタードラゴンの血を引く者でなければ、とうに滅ぼしておったわ! …何故余がそなたを滅ぼさずにおったか、教えて遣わそう。そなたは、奴、マスタードラゴンに対する余の切札だからじゃ。だが、余がこの闘いで生き延びる事がかなえばもうその必要もない。…次に余がこの部屋の扉をくぐる事があれば、そなたの生命は無いと知れ。だが」
ゾーマはそのしなびた頬に笑いを含ませた。
「それまでの間、生きていられるかな?」
どれだけの時間が経ったのだろう。鉄製の扉の軋みが私を目覚めさせた。
私は己の死を覚悟した。ゾーマが帰って来たのだ。奴が己の恐怖を克服し、今までに奴がしてきたどんな仕打ちよりも残忍なやり口で、私を死に追いやる為に。
だが、そこにゾーマの姿は無く、代わりに、全身鎧を身にまとった戦士の姿があった。戦士は無言で、足音を反響させながら、剣を杖代わりに重い足取りで近付いて来た。
男は私の前で立ち止まった。兜のひさしを上げた中から、若い男の顔が覗く。
若い女から見れば何処か影のあるいい男、と言った処か。が、私には解る。間違いなく、奴は同類だ。若造の癖に、これほどの闇を眼に宿している者が、真っ当に日の当たる場所を歩んで来た筈が無い。どんなに輝かしい鎧を身にまとっても、染みついた血の臭いは誤魔化せぬ。ゾーマの配下にこの様な男が居たとは聞き及ばぬが、この、瞳に影を濃く宿す若者こそが、我が生に終止符を打つべく冥府より遣わされた死神なのであろうか。自らの死に際してまでも、いや、だからこそやも知れぬが、そんな事をぼんやりと私は想っていた。男は身構えると、無言で、鞘から翼を広げた鳥を象った鍔を持つ一降りの剣を抜き放った。奥歯を食いしばる。
だが、予想した苦痛は私を襲う事は無かった。青白い気を発する刃は、我が身を繋ぎ留めていた鎖を、粘土を切り裂くが如く易々と切り落とす。身体は支えを失い、その場に倒れ込み、膝を付く。
「…な、何者だ、貴様……」そこまで言い終わるか終わらないかの内に、口中に鉄の味が広がって、血の交じった咳が喉を塞ぐ。
「ここはもうすぐ崩れ落ちる」男は初めて口を開いた。低く、殆ど消え入りそうな程に生気の無い声。「大魔王ゾーマは俺が倒した。早く、逃げろ」
何だと?
この男がゾーマを倒しただと?
そんな事があり得るのか?
「何故…私を助けた…。敵……やも…しれぬ…ぞ…」
「あんたの事はルビス様から聞いている。必ず助けてくれとの仰せだ」
内に闇を秘めた、暗い瞳。
これが、ゾーマが怖れていた光の勇者なのか?
否、そんな訳があろう筈もない。それ位の事は私にも解る。
この男は、闇に属する者。我と同じく。
なのに、…何故。
「行くぞ。リレミト!」
ある一つの方向――私を助けたこの男――に対する一群の不透明な感情、それは、直ぐに収まりが付かない程に膨れ上がり、ある方向に向かって、我が身を突き動かさんとしていた。
男は、ラダトーム北西の小さな洞窟にいた。
人間共が吹聴しているのを耳にして、私は初めて奴、大魔王ゾーマを倒した英雄の名がロトという名であると知った。
あの日から、ある疑念が己の胸中を捉えて離さなかった。それを確かめる為、私はここに来たのだ。
洞窟の中は暗く見通しの利かない狭く入り組んだ作りであったが、やがて洞窟の奥の一室に、仄かな松明の明かりが灯っているのを認めた。ロトは、そこで何かを刻んだ石版を小さな木箱に納めているところであったが、敢えて気配を消さずに近付くと、直ぐに気付いて身構える様子を見せた。
「ああ…あんたか…」見覚えのある顔に、ロトは緊張を解いた。
「何故、身構える?」ロトの反応に、己が内の疑念は殆ど確信に近い物へと変わっていた。「生きながらにして伝説と化した勇者殿が、何を恐れる事があろう?」
「あんたには関係無いだろう」奴は一瞬視線を泳がせた。
「ああ、関係は無いな、確かに。……だが、納得はいかん」
「納得…だと?」
「そうだ。一介のヒトの子に過ぎぬ貴様、その眼に暗い光を宿す闇の住人たる貴様が、何故に我が父の加護を得たのか。それを確かめに来たのだ!」
言うが早いか、男を組み敷き、額を隠すバンダナをむしり取る。
額には、嘗て、男が、物として扱われていた印、奴隷の焼印の痕が、消し様もなく刻まれていた。
激情が、憤怒が、嫉妬が肉と霊との全てを捉えて、私の理性を吹き飛ばした。
「…貴様…! 奴隷の分際で! 貴様如きが、神の子たる我を差し置いて、我が父の加護を得るなど、どうして納得が行くものか! 奴隷の癖に! 人間の分際で! 虫螻の分際で! 何故だ! 何故父は、私を、私を見捨てたのだ! 何故…」
男は何故自分が刺されるのか解らない様子で、殆ど無抵抗のまま息絶えた。
復活の余地も無い程にめった刺しにして、返り血に塗れながら、私はこの時、初めて我が父への憎悪をはっきりとその胸に刻み付けた。
私は待っていたのやもしれぬ、この時が何時か来る事を。
勇者と呼ばれる若者――何でも、ラダトーム王家のふれこみによると勇者ロトの生まれ変わりなのだそうだが――が、神の命を享け、私を倒す為に遣わされてくるだろうその時を。
とうの昔に解っていた。父にとって、私は虫螻共さえの価値も無い、取るに足らぬ存在に過ぎぬと。邪魔になればこそ、消しにかかったという訳だ。何たる慈悲深き、正しき神よ!
だからこそ、だからこそ、父にとって私などよりも遥かに気遣われ、守られている人間共を痛め付けずにはおれなかった。嫉妬しているのか、と言う者もあろうが、人間共などと比するのも哀れではないか? 神の子たる我と虫螻を比べる事に、何の意味があろう? それよりも、父にとって、人間共が少なくとも何らかの価値を有している、その事実こそが私にとって意味のある事だった。
配下の魔物共は躊躇を覚えていたようだった。やり口が容赦なかったせいだろうか。上級の魔族共は、私が純血の魔族で無い事を理由に難癖を付け、私に従い主と認める事を一様に拒んだ。私に奴らを支配し統治する力がないとは思わなかったが、こんな連中を従わせたところで何時裏切るか解ったものではない。奴らを尻目に、私は独りで全てを成し遂げなければならなかった。
私はゾーマとは違って、虫螻をいたぶるのに悦びを見いだす趣味は持ち合わせていなかった。ただ、ひたすら、人間共の作り上げてきた物、守って来た物を破壊し、壊していくだけが全てだった。そうすれば奴は、我が父は、少なくとも私を見捨てたのを悔やむだろう。自分が後生大事に抱えていた物を目の前で壊されるのだから。だが、私など、最初から全てを奪われていたのだ! 我が痛みの千分の一、万分の一でも想い知るが良い! 私は、私が奪われ続けてきた物を取り返す為に、ただその為だけに、この手を血に染め、多くの命をその手にかけた。
だが私は、所詮甘っちょろい若造に過ぎなかった。あまりに青く、若過ぎた。
跫
が聞こえる…。遥かの闇より。私は、何時かこの城の地下に幽閉されていた、あの冷たく、暗い時間を想い出していた。
「良く来た、勇者よ」
暗闇に、青白く光る発光体が音もなく現われた。
蒼く光る鎧をまとった戦士。
その兜の下に見えた顔に、私は、初めてゾーマに凝視された時に似た、あの戦慄を想い出し、喉の先まで出掛かった言葉を飲み込んだ。
「…何故だ……何故、貴様が生きている…?」
兜の覆いの下に垣間見えたのは、あの時、確かに私自身の手で止めを刺した筈の、勇者ロトだった。
その目はしかし、鈍い鉛色に澱み、一遍の光すらも宿してはいない。…何故、誰も気付かないのだ。
こ奴はもう、生者に非ず、人に非ず。
この様な者が、光の勇者であろうか?
否、否、三度否!
これが、世界を統べる者の遣い?
光は闇で闇は光。
これが、世界の秘密?
これが神意であったのか?
「正面に見えますのが、ロザリーヒル名物・ロザリーの時計塔でございまーす。ここは、かつて勇者を殺そうとし、人間を皆殺しにしようとした魔王デスピサロが、恋人のエルフ、ロザリー嬢を匿う為に建てた塔だと言われておりまーす。塔の内部は拝観料、大人2G子供1Gで見学出来まーす」
大人二人、子供(?) 二人、計6Gの拝観料を払って入口を通され、ガイドの案内に従って時計塔内部を上がっていく。中はすっかり観光用にディスプレイされ、往時を偲ぶ影もない。
「えー、この窓から、外の世界に出る事叶わぬエルフのロザリー嬢は、下の世界を眺めていた訳でございます。それというのもこのロザリー嬢、流した涙がルビーとなる不可想議な魔力を秘めていたが為、欲深な人間達の手で随分と酷い目にあったのだそうです。しかしこの塔の事が人間にばれ、愛するロザリーを人間の手で殺されたデスピサロは、人間達全てに復讐する為、自らに進化の秘法を施して魔王と化したのでございまーす。結局デスピサロは伝説の勇者達に倒されたのですが、こうしてみると可哀相な魔王だったのかもしれません」
「ふーん、魔王って言っても色々いるんだねぇ。なあおっさん」オルフェはすっかり感心した風で、竜王の服の裾を頻りに引っ張る。
「何だ? それはどういう意味だ? 喧嘩売っておるなら即座に買うが…ところでオルフェ、さっきから何をきょろきょろ見回しておる」
「いや、ルビーの欠片が落ちてないかなーなんて」ロザリーを可哀想と言う舌先の乾かぬ内に、ルビーの欠片を探してきょろきょろするとは、まったく呆れて物が言えない。と、言いたいが、オルフェの事だから、放っておくといつまでも下ばかり見ていかねない。
「やめなさい。落ちてる訳ないです。そんなもの、有れば皆がとうの昔に拾ってます」
「そっか、そうだよな、ちぇ」オルフェはつまらなそうに口を尖らせた。
「ないですね」ユークァルもオルフェにつられて一緒に下を探し始める。
「デスピサロとやらの事を可哀想と言う割には、貴様も随分と欲深だな。…ばか、お前も一緒に探すな」竜王はユークァルの頭をげんこつで殴った。「みっともないからやめろ。皆が見ておるではないか」
「おいちゃん、殴ることないじゃん。暴力はんたーい!」オルフェがユークァルをかばってその手を引いた。「いいよ、ルビーもないし、見るとこも見たからさあ、次に行こうよ、次。早く他の世界が見てみたいしさ」
ロザリーヒルを後にして、私達は次なる目的地を目指してまた長い旅路に戻ってきた。
「ロザリーヒルは面白かったねえ」オルフェはかの観光地をいたく気に入ったようで、旅の間中何度もその話をしたがった。「デスピサロってかわいそうな奴だよなー。だって、恋人殺されちゃうんだもん。ね、そう想わない?」
オルフェの問いに竜王は鼻で笑って返した。「フン、それは奴がただ甘かっただけだ。愛する者は時として枷ともなり得る。魔族の長たるにはそれを覚悟せねばならぬ。いつ自分が裏切られるか解ったものではないのだからな」
「げ、おっさん冷てーのっ! そんじゃさあ、コイビトとか家族とかっつーの、全然居なかったわけ?」
「五月蠅い、馴れ馴れしいわ馬鹿者。……ん…そりゃまあ…その…浮いた話の一つや二つ、無い訳ではない。別に、誰かさんとは違って堅物じゃあないからな」
「堅物で悪う御座いましたね。生臭よりはいいでしょう」
「いや、その…」
「どんな話? どんな話? 聞かせてよ! ねえねえねえ。ユークァルも聞きたいよね、ね!」
「はい。聞きます」聞きたい、とは到底想っていなさそうなユークァルであった。
「ほらぁ、ユークァルも聞きたいって。ね、おいちゃん教えて!」
「…聞きたいか?」オルフェにせっつかれて、竜王はちょっと困った様に私の方に目線を送って寄越す。
「聞きたい聞きた〜い! ねえ? 興味ナイ? えへへ…オイラも、ちくっとばかし『レンアイ』って奴をしてみたいんだよねぇ〜。ハーゴンさんも興味あるっしょ?」
「私は、特には。お話ししたければ伺いますよ。御自由にどうぞ」
「…何だ、冷たい奴だな…言っておくが、誰にもこんな話をした事は無いのだぞ…」竜王はのろけ話をするには意外なくらい照れくさそうに口を開いた。よくよく想い返してみれば、我々とこうして一緒に旅をするまでは、こんな話をする相手も居なかったのだ。
「あれは…そうだな、ずいぶんと昔の話だ。まだ、世界が闇に覆われていた頃の事だ。あの頃は私もまだ若造で、何時も尖がってて、力も無いのに気ばかり急いていたせいか、出る杭は打たねば損だとばかりに随分と辛酸を舐めさせられていたものだ。己の不遇を嘆き、この世の全てを憎むと、そして己を虐げてきた大魔王ゾーマに、今はかなわぬまでも、何時か必ず復讐を遂げるのだと固く誓っていた。無論、確かに、あの当時でも我を見捨てた父・マスタードラゴンを憎んでいた事は疑い無いが、それでも、あの当時を想い返すと、目先の事に目を奪われていたせいなのやも知れぬが、やはり、父へのそれよりもゾーマへの憎悪の方が人一倍強かった様に想う。あの頃は、本当に孤独であった。他の魔物達は、恐怖故にゾーマに忠誠を誓っていた連中ばかりだったから、何時も逆らってばかりいるのに大した処罰も受けないでいた…とはいえ、他の連中だったら存在ごと消されてもおかしくないような事態でも、拷問を受けるくらいで済む、といった程度の差でしかなかったが…そんな訳で他の魔族からは疎まれておった。勿論、それには私が光の側の存在であったからというのもあっただろうがな。あの当時はいつも、一人になりたくて、こっそり城を抜け出しては、人知れぬ、昼も夜もない時を過ごしていたものだ。あれは…何時だったろうか…。珍しく月の煌々と照る満月の夜だった…」
そこまで言うと、竜王はふと目を閉じて押し黙った。その様子は、昔を酷く懐かしむようにも、厭うているようにも想われた。
「気に入りの場所があってな…切り立った崖の中間にある、小さな洞穴だ。住むには狭すぎるが、ほんの一時他の魔族の連中から身を隠すには十分だったから、よくそこで時を過ごしたものだ。…だがそこだって、心底くつろぐという訳には行かなかったのだぞ? 何時誰かに知られて、気を許した隙に襲われるか、解ったものではなかったのだからな。だから、あの女が、初めて我が前に天より降り来た時、私は、あの女が、罠にはめる為のまやかしか、さもなければ他の魔王が放った刺客ではないかと…自分の居場所を奪いに来たのではないかと怖れたものだ。
だが、女の様子は少しばかり違っていた
身構えた私に、女は、己が我に敵意を持たざる事を示そうとした。武器を持たぬ身である事、一人で来た事を告げ、名をルビスと名乗った。
ルビスという奴の名前は、聞いた事があった。生きとし生ける命を慈しむ大母神、大地の精霊。何故そんな奴が、私に会いに来たのかますます理解しかねた。我が身は日の光さえ射さぬ闇の底にあり、そもそもが、生きる世界の違う者同士なのだ。
何故、ここに来た? 私は女に問うた。
闇に閉ざされたこの世界、慈しんで来た命が、唯一者の慰み者になる為だけに握り潰されていく世界に。
お前等、あ奴がどう答えたと思う?
あ奴はな、我が父が、風の噂に私がこの世界にいる事を知り、父の命によって自分が遣わされたのだ、と。ようやくお迎えに上がりました、天界に戻りましょう、とそう言ったのだ、ぬけぬけとな。どういう事か解るか? 私がどれだけ抑え難く怒りを覚えたか、何故に、激情を押さえられなんだか、お前達に解るか?」
「全然」
オルフェが即答したので、竜王は返答に詰まってしまった。
「…ん、まあ、そりゃそうだな。まあ良い」
「で?」
「腹が立ったから押し倒して、ヤっちまった」
「…」
「…」
「…何だ、どうした」
「あ、あのねえ…」
「な、な、なんだ? その眼は」
「…ひっでー! 超サイテーじゃん! 信じらんねー!」
「貴男って人は…見損ないました…いや、元からですが…最低ですね…」
一同の露骨な拒否反応は、竜王にとっては予想外のものだったらしい。
「う…、よっ、余計なお世話だ! 貴様等にはもう話さん」
「あ、ひねた」オルフェが肩に軽く手を置いた「おいちゃん、スネたって無駄だよ。おいちゃんはサイテーのゴーカン魔なんだからさー」
「黙れ黙れ黙れっ!」オルフェの手をはね除け、竜王は耳を塞いで怒鳴った。「貴様等に、私の気持ちが分かってたまるかっ! 父に見捨てられ、女に侮辱されたこの私の怒りが! もういい、お前等帰れ!」
「帰れって、どこに帰るんですか」
「うるさいっ、いちいち細かい事言うな!」
「それからどうしたのさ。悪かったよ〜、オイラが悪かったから話してくれよ〜」
オルフェにしつこく縋られて、竜王は暫く黙ってから、呟いた。「…本当だな?」
「うん、うん。本当だってばー」
「…わかった、話す。そんなに聞きたいか?」その様子が余り嬉しそうでも無いのに気付いて、妙な罪悪感が私を苛んだ。
「あの女は、その後も、暫くの間蹲ってずっと啜り泣いていた。余程堪えたのだろう。が、当時の私には、それがあ奴のした事、いや、父のして来た事全てに対する当然の報いとしか想えなかった。半時ほどそうしていただろうか。
「…当然の、報いだ」
殆ど声にならないほど、かすれた声だった。
「当然の報いだ」
もう一度、口に出してみた。聞かれようが聞かれまいが、どうでも良かった。だが、口に出してみた途端、私は激しい羞恥の念に駆られた。口にしてみたところでどうなるというのだろう。何が変わるというのだろう。本当の所を言おう、この女を陵辱したところで、我が怒りが、激情が、どう収まるというものでもなかった。いや、期待さえしていなかった。例え気が晴れたとしても、それが何だというのだろうか。そんなものは一時の気休めに過ぎぬ。何も変わりはしないと言うのに。変えられはしないと言うに。何? あの女に付いて行ったら、だと? 貴様、永きに亘って受けた仕打ちを忘れろと言うか? いいか、私は犬猫じゃない。捨てた飼い主にエサを与えられたからといって飛び付いて喰ったりするものか。ましてや、毒が混ぜられているやもしれぬエサなど、どうして食える? エサに毒が無くても、エサをやった奴は後ろ手に棍棒を隠し持っていて、殴り付けるつもりかもしれん。そうでないと信じろ、と言うのか? 信じていたら、今頃こうして生きてはいない。想像がつかんか? まあ良い。だが、私はそういう中を、潜り抜けて生き延びて来たのだ。
結局、自分の居場所は世界の何処にも存在しないのだ、という事に思い至って、私は惨めさに打ちひしがれていた。自分が自分であろうとする限り、己は誰にも望まれないのだと知って、誰がその孤独に耐えられよう? だが、私は耐える事を選んだ。そうせざるを得なかった。
啜り泣く声が途切れた。
「天界に、帰れ。ここに貴様の居場所は無い。ましてや…ましてや、天界に我が居場所などあろう筈も無い」
女はゆっくり身を起こしたが、立ち上がろうとはしなかった。
「帰って、あの糞親父殿に、私は貴男の息子に犯されました、とでも報告するが良いさ」
私は努めて無関心な風を装っていた。実際、この女がどうなろうが、どうでも良かったのだ。この女がどのように我が父から命を受けておろうが、知った事ではなかった。ただ、己を侮辱したこの女に己の為した事の意味を、身を以て思い知らせる事、それだけがこの女に対する全てだった。例え空しかろうと、行き場の無い憤怒の炎をとぐろを巻いたまま内に飼っておける性分ではなかったのだ。
だが、あ奴の唇から溢れた一言は、今までの私には予想だに出来ぬものだった。
「貴男は…貴男は間違っているわ。あなたは、そうやってただ自分の傷に甘えているだけではありませんか。貴男は、居場所は何処にも無いと言うけれど、貴男はそれを自分の手で、一度でも勝ち取ろうとしたのですか?」
「…何だと? …貴様、まだ足りぬと言うか」その細い首に手をかけた。だがあの女は怯みもせず、その両の眼差しで私を捉えて離そうとはしなかった。
「殺したければ殺しなさい。それで何が変わるのなら。貴男が私を殺す事で、貴男の帰る所を見付けられるのなら、それが貴男の救いになるのなら、私の命などいくらでも貴男に差し上げましょう。…でも、それで貴男の心は本当に救われるのですか? …貴男がお父上に見捨てられた事、その後の苦しみの日々、その傷のほんの僅かの痛みでさえも、そう、きっと私の想像を絶するものだったに違いありません。しかし…だからと言って、腹いせに他者を虐げて、何が変わるというのでしょう? 貴男のその行いは、結局は新たな憎しみしか生まないのに。貴男の父上が貴男の痛みを御存知ない様に、貴男が虐げてきた者達は、例え貴男がお気付きでなくとも、貴男と同じ様に傷付き、苦しむのです」
「救い? そんな事は、考えた事もない。ただ、奴に、奴に我が痛みを思い知らせてやりたいだけだ!」
だが、ルビスはかぶりを振った。
「貴男がしている事は、貴男の父上が貴男にした事と同じです」
ルビスの喉にかけていた手が僅かに緩んで、滑り落ちた。
私はその言葉をどう受け止めて良いか解りかねた。解りかねたが、聞き捨てるには余りにも真っ当過ぎて、目を背ける訳には行かなかった。真っ直ぐな、黒目がちの瞳で見据えられ、私は戸惑っていた。
「変えましょう」ルビスは私の手を取った。暖かくて、柔らかい手だった。「傷付けあって新たな悲しみを生み出すより、傷を癒しましょう。貴男にはその勇気と強さがある筈ですわ」
「何…だと?」
「貴男は、誰よりも優しくなれる人です。わたくしはそう信じております」
「優しい、だと? この私が?」
そんな言葉は生まれてからこの方、一度たりとも耳にした事は無かった。当然だ、魔界では、誰もそんな事を私に求めはしなかったし、もし誰かが私に優しさを求めたとしても、応じていたなら今ここでこうして生きては居なかっただろう。「どの面下げてその様な事を申すか。私は…私は貴様を…」
「皆まで仰らずとも解っております」ルビスの人差し指が、唇に触れた。「貴男は最後まで私の話を、聞いて下さいましたわ。辛い事、厳しい事も申し上げましたのに。貴男は誰よりも、傷付けられる痛みを知っている人です。他の誰よりも。傷付けられる痛みを知る者こそが、人に優しくなれるとわたくしは信じております」
雷に打たれたような衝撃が、私を打ちのめした。光に焦がれる己が、そこにいた。この光こそは、あの失われた「何か」、嘗て奪われたあの「何か」に違いない、と。だが、初めて射した光明が、光の源が己には手の届かぬ程の高みにあると思い知らされたとしたら? 高望みをして得られぬ苦しみを味わうよりは、いっそ無かったことにしてしまった方が、目を瞑ってしまった方が、どんなに楽だろう。
「私には、変える事は出来んのだ…何も…」
「私がいても…駄目でしょうか?」
「?」私にはあ奴の言っている意味が解らなかった。
「許して下さい、とは言えませんわね…。これも、貴男を欺いた罰なのでしょうね」あ奴は少しだけ弱々しく微笑んだ。「本当は、貴男の父上から命ぜられて貴男にお会いしに来たのではありません。お父上は、貴男の事など忘れてしまったかのように、魔王の脅威に怯える人々への対策に追われていらっしゃいます。大魔王ゾーマの闇の力はあまりにも大きく、貴男のお父上でさえも、闇の軍勢の侵攻をくい止めるので精一杯なのです」
「では、そなたは…自ら望んで、我が下へ来たというか? 何故に?」
「…貴男の父上は、貴男が生まれ落ちて直ぐ、大魔王ゾーマの手に落ちた事を御存じでした」ルビスは口を噤んだ。
「…済まぬが、私にも譲れぬ事がある」私は全てを察していた。
「私は、そなたの様には寛容にも優しくもなれぬ。我を虐げし者への復讐を果たす為、大魔王ゾーマを何時かこの手で倒す為に、私は今まで生きて来た。お前にとっては馬鹿げた事かも知れぬ。だが、私にも意地があるのだ。お前の様に全てを許してやることなど出来ぬ。…だから」あ奴の瞳が僅かに揺れていた。不思議な感情に支配されて、私は僅かに口篭もった。
「だから?」
今でも、何故あんな事を言ったのかさっぱり解らん。血迷っておったとしか言い様がない。だが私は思わず口走っていた。
「その日まで待っていてくれぬか?」と。
それから私とあ奴とは、他の連中の目を盗んでは逢瀬を重ねるようになっていた。人知れず城を抜け出さねばならないので毎夜とは行かなかったが。あ奴はあ奴で、天界の連中を束ねる身として、例えそれが神の御落胤でも何でも魔族と密会しておったなどと言う事になれば立場が悪くなる。だが、私はそれでも会わないという選択肢を選ぶ気にはなれなかったし、ルビスは私を受け入れてくれていた。あの女は、私にとって初めての「居場所」だったのかもしれない。
だがそんな日々も長くは続かなかった。あ奴がそう…半年ほどぱったり姿を見せなくなって、その次の満月の夜であったか…。私が久々の邂逅に何処かで浮かれていて、用心を怠っていたせいやも知れぬ。とうとう、二人でいる所を見られてしまったのだ。そして、奴らは、私が天界の間者ではないかと嫌疑をかけて来おった。つまりこうだ、ルビスが私に接触して来たのは、私を通じて魔族側の同行を探る為だというのだ。そして奴等は私を責めた。
私はその時、あ奴を疑ってしまったのだ。
今なら解る。ああやって、相手を疑うようにし向けるのはいつもの奴らのやり口なのだ。何故あの時、あ奴を信じてやらなかったのだろう。
ルビスは必死に否定した。
その時だった。天空人達がルビスを連れ戻しにやって来たのだ。
「ルビス様! こんなところで何を…!!」
「ルビス様、これは一体どういうことですか!」
口々に詰め寄る天空人達に、弁明することだに出来ず後じさるルビス。黒目がちの瞳を涙で潤ませて、己の無実を訴える。
「まさか…まさかとは思いますが…ルビス様ともあろうお方が、魔族に肩入れとは」
「そうじゃ」しわがれた声が詰問を遮ったので、天空人達は身を硬くした。生ある全ての者を
恐懼
せしめる闇の王が、手を伸ばせば届く程の近くに居るのだから。「この女が、我が配下を誘惑し、籠絡せんとしたのじゃ。この淫売め!」
「違いますっ! わたくしは、わたくしは…!」あ奴は目に涙を湛えて懇願した。だがあの時の私は、あ奴を信じてやれる程、強くは無かった。信じる事に慣れていなかったのだ。今だって慣れているとは言い難いがな。
「よくも、よくも我を謀ったな…貴様…」
「そんな…違います」
「貴様等もだ!」ルビスとの間を遮って邪魔をする天空人達を片手で一凪にすると、一人残らず首を引きちぎって、ルビスの足許に投げ付けた。
「お許し下さい…どうか、お願い…私を信じて下さいまし…」
「貴様! この期に及んでまだ保身を計るか! 愚かな女よ、死して償う気すらも無いのならば、永劫に生き続けるが良い! 貴様の愛する「人々」とやらが、この手で苛まれる様を無力に眺めながらな!」
あ奴はまだ何か言わんとしていたが、聞く耳持たなかった。あ奴を打ち据え、なおも引き立てて、長い髪を掴んで無理矢理立たせた。あ奴は涙に濡れて唇を振るわせたが、我が怒りの呪詛は、あ奴の舌よりも先にあ奴の上に振り下ろされた。そうして、あの女は生きながらにして石像と化し、まんまと私を誑かしたゾーマ達の手で、マイラの遥か北の、今は無い物見の塔の最上階に運ばれていった。
それから先の事は知らん。その件以来、私の手からは、例え仮初めなれどもまともな自由は与えられなかったし、あれからあの女には会っていない。この話は、これで終わりだ」
言葉が途切れた。小鳥の鳴き声と、風のざわめきだけが耳を擽る。私達は、いつの間にか立ち止まっていた。
「終わりって…おっさん、それで終わり?」
「終わりだ」竜王は再び歩き出した。「行くぞ」
「おっさん、それヒドすぎ! そんなの『レンアイ』じゃないよ〜」オルフェは早速ぶーたれる。そりゃそうだ。
「うるさい、現実はそんなもんだ」
「現実って…そんなのはあなただけです」
「故郷を焼いてきた奴や邪神を召喚して世界を滅ぼそうとした奴に言われたくはない」
「うっ…」
「そっ、それは…おっさんが全部焼いちゃったんじゃないかー」
「同意したのは何処の誰だ。それから、おっさんというな。縊り殺すぞ」
本当に、解っていながら嫌がるような事を平然と言い放つ。時々、何故この人に付いて来たのかが良く解らなくなる事がある。絶対にあの時私は騙されていたのだ。うん。そうだ。そうに違いない。
ユークァルが、空の彼方を指した。
「何かが、飛んで来ます」
「何も見えませんよ。気のせいでしょう」実際、その先には青い空が広がっているばかりで、鳥の飛ぶ影すら見当たらない。
「あ、でもいるよ何か」オルフェも同調する。
「何かって何だ。あれか?」竜王が問い返す。
「だからわかんないって。鳥かなんかじゃないの?」
「何かが飛んできます」ユークァルはいつもの調子で繰り返した。「…こっちに、向かってます」
その"何か"を見付けた、と思うか思わないかの内に、"何か"はかなりのスピードで拡大していく。太陽を背にして飛んでいるので、逆光になって視認しづらい。
「目標地点は、ここみたいです」ユークァルはあくまで冷静である。
「目標が、ここ?」
「抜き身の剣をもっています。攻撃の意志があるものと想われます。そして…」
「空飛ぶ鎧だっ! すげえや!」オルフェが叫んだ。
青い鎧が、太陽光を反射して一瞬煌めいた。
「あの鎧…」
「お前も見た事があるか」
「ええ」
空飛ぶ鎧の胸に輝く、翼を広げた金色の鳥の紋章が目に飛び込んで来た。
「ロトの鎧だっ!」
ハモる間も与えず、鎧の男はまっすぐに突っ込んできた。
土煙が上がって辺りの木が薙ぎ倒され、私達は吹き飛ばされた。
「お前ら皆逃げろっ! どっちにしろこんな状態では勝ち目はないっ」こんな時に限って、その手にがっちり絡み付く16分の1の手錠が嫌でも目に付く。
「逃げるったっておっさんはどうすんだよっ」
「無理です」ユークァルは冷徹に状況を分析する。「敵の飛行速度は、現在の4人いずれの移動速度をも上回ってます」
「だから」そんな事は解っておる、この馬鹿が、とでも言いたげに、竜王はユークァルに一瞥をくれた。
「私が引き付けるから、その間に逃げろと言ってるんだ! 奴の攻撃目標は、この私だっ!」
私達がおたおたしている間に、竜王は私達を押し退け、鋼鉄騎士の目の前に飛び出した。鋼鉄の騎士は青いマントをはためかせながら、心の臓を一突きにせんと剣をその手に握り締め前に突き出す。竜王はぎりぎりまで引き付けると素早く体を半身にして猛撃をかわす。鋼鉄の騎士はとどめを刺し損なうと、森の中に突っ込んで辺りの木を根こそぎ薙ぎ倒していった。見れば、騎士が羽織っていると想われたマントは、鎧の背中に付けられた排出口から吹き出すマナを燃焼した炎であった。
我々は、逃げているべきだった、というのは綺麗事であろう。そんな事はどだい無理だった。辺りの木々が進路を塞いでいたが、それはまた別の話だ。ただ、あまりの凄まじさに圧倒されて、見入っているしかなかった。いや、逃げる努力はしていた。していたが、それ以上に、騎士が放つ圧倒的な気と、そのパワーが私達を絡め取っていた。蝋のように生気のない肌、虚ろな瞳が、余計に死を想起させる。逃れられ得ない宿命の様に等しくのし掛かる、青い鎧の死神。その幻想を、私は振りきれないで居た。
頭上で、薄い金属片の振動音が耳を突いた。
「攻撃目標を変更」
空中でホバリングしたまま、鎧の戦士は右に90度旋回した。
蒼い鎧の戦士は私を見下ろしていた。
戦士は剣を突き出し、私に向かって真直ぐ突っ込んできた!
逃げようと駆け出した足が、縺れて転ぶ。虚ろな瞳には、私の姿だけが映っていた。
自分の周りだけが太陽の光を遮られている。
影が、瞳に映る私の姿が大きくなる。
もう駄目だ。死ぬんだ。
風圧が、目前に迫る死を予感させた。
「うわっ!」
脇から突き飛ばされて、頭から草むらに突っ込む。顔を上げると、さっきまで私のいた場所には、竜王が脇腹を貫かれながらも剣の柄をつかんで踏み止まっていた。血は剣を伝ってみるみる地面を紅く染める。
「い、今だユークァル!」
声を掛けられるまでもなく、ユークァルが戦士の背後から、ナイフを持って躍り掛かった。が、跳躍が足りなかったか、圧倒的な身長差のせいで、ナイフの切っ先は首筋を掠める事無く背中のバーニアに当たって金属音を立てる。
「うわちゃっ、だめか…」オルフェは目を覆った。
が、鎧の戦士は剣を抜くと、
「鎧のバーニア部が損傷しました。これ以上負担をかけると飛行に支障を来す可能性あり、帰還出来ない可能性あり。退避します」
と言うなり、とどめも刺さずに飛んでいってしまった。
後に残されたのは、傷付いた竜王と、勇者ロトの武具を身につけた男との闘いをただ茫然と見ているしかなかった無力な我々だけだった。
負った傷は呪文でも塞がらず、酷い苦痛を伴った。それに引き換え、あ奴は、どんなに殴り付け、壁に叩き付けられても、疲れ一つ見せず馬鹿の一つ覚えの様に急所をひたすら狙って攻撃してくる。岩をも砕くと怖れられたこの爪も、鉄をも溶かす灼熱の炎も、魔法も、あの輝かしい鎧の力によって阻まれてしまう。そして、私は、あの魔剣に切り刻まれ、疲労と苦痛のあまり、とうとう動けなくなった。
「……復讐か…? 400年前の…」
胸の辺りから口内一杯に鉄の味が込み上げ、また一つ血の花弁を冷たい石の床に散らす。
「…今はロトの洞窟と呼ばれているそうだが……あの洞窟で貴様に止めを刺した時の事、今でも憶えておる。…何故自分が殺されなければならなかったか、貴様には解らなかっただろうな……」
ロトは返事をしなかった。
「お前が憎かったのだ。いや、違う、私と貴様…人間共との間に何の違いも認めない、我が父が憎かったのだ。己の血を引く子が攫われようが放っておく癖に、奴隷上がりの貴様に加護を与えるあのやり方が許せなかったのだ……ぐ、ぐふっ…い、今となってはど、どうでも良い事…だが…な……」
別段何らかの返答を期待していた訳ではなかった。泥のような目をした、魂のない勇者。こんな者でも、勇者として人々に祭り上げられるのだ。その中身も知らずに…。
ふと顔を上げて、奴と目が合った。
澱んだ瞳が舐め回すように眼孔の中を蠢く。何かを探しているのか?何か…
一つだけ、私には思い当たる所があった。それは…
唯一つの、我がこの世に生を享けし意味の証。
たった一つの、母の形見。
胎内の記憶でしか知らぬ、母の温もり。
「う……」
まさか……。
「目標、光の珠の捜索に入ります」
父親に見捨てられ、母に先立たれた私に唯一つ残された、
「これは、たった一つの母上の形見だ。これは貴様等虫螻どもには相応しくない。これは私が受け取るべき物だ!」
かけがえのない温もりの証を、
「目標物を発見しました。回収作業に入ります」
奪い去る心算なのか。
「やめろ、やめろぉっ!」
これ以上何を。
もう、この命の他何も残されてはいないのに。
あ奴の剣が手の甲ごと我が心の臓を捉えた。奴は無造作に剣を引き抜くと、剣を引き抜いたのと同じ位事務的に、その手で心臓ごと、光の珠を抉り出した。
魂を引き裂かれる痛み、唯一の温もりを奪われる痛み。それが、この世の最期の記憶となった。
「………識が、戻ったようですね」
瞼が僅かに持ち上がったので、私は安堵した。血色の悪いのは相変わらずだが、ようやく峠を越したと言えるだろう。
「大変だったんですよ。ベホマの呪文でも傷は塞がらないし、薬草も効かない。傷口だけでも塞ごうと、外科手術をして。あまり得意ではないんですが…でも、治癒のスピードが極端に遅くて、これはひょっとすると呪いではないかと」
「…ああ、以前も…そうだった…」元気な時なら、きっとここで「バカモン、ユークァルの時で懲りたろうに、貴様もターゲットになっておるのだ、ちょっとは学習しろ!」位の事は言うのだろう。言って欲しかった。
「寝ている間も酷くうなされていて、苦しそうに、何度も何度も母上の形見を返せってうわごとのように」
「そうか…そうであったか…」持ち上がった瞼を、再び重たげに降ろす。
「ヤーイ、おっさんマザコン、マザコーン」
「オルフェ!」
「……貴様、母上への想慕を愚弄する気か。事と場合によっては許さぬぞ」
「ウハ! 母上だって〜! や〜っぱマザコンじゃん?」
「…黙れ、貴様に……ごほっ、何が解る…」
「オルフェ、やめなさい!」オルフェがからかうのをやめないので、私はオルフェを強く叱った。
「なんだよ〜。おっさんもハーゴンさんも、そんなにマジになっておこんなくてもいいじゃんかよ〜」オルフェは気まずそうに頬を掻く。
「マザコン、なんですか?」ユークァルも覗き込み、首を傾げる。
「ええい、違うと言うておるに! 二人ともこっちにこい! 想い知らせてくれる! …ぐ、ご、ごほっごほっごはごはっ!」竜王は立ち上がろうと腕を付いたが、直ぐに激しく咳き込んで倒れ込む。口元から血の帯が広がり、拭いたばかりの頬を汚した。直ぐに濡れタオルで拭ってやる。
「脂汗をにじませながら言っても説得力ありませんよ。オルフェ、怪我人をあんまりからかうものではない。冗談は言っていい時と悪い時があります。ユークァルも真似して聞くのはやめなさい」
「おっさん、ゴメン…オイラ親なんていないからさぁ、ちょっとウラヤマシかったんだ」オルフェは屈み込んで、竜王の顔をそっと撫でた。「オイラのせいで死んじゃったりしないよな。強いんだろ? 元気になったら、母上の話聞かせてよ。今度はちゃかしたりしないよ」
蒼白い手が伸びて、オルフェの手を軽く握った。オルフェが握り返す。
「……母上の…記憶…は、まだ…私が…産まれ落ちる前の…母胎の中の記憶しかない…。だから…顔も知らない…。…ただ、温かかった……。それだけだ…」
「……あの」ユークァルが口を開いた。
「……何、だ…?」
「マザコンって、何ですか?」
オルフェの手から、竜王の手が滑り落ちた。
「…頼む、こ奴にマザコンの意味でも教えてやってくれ…」
「イヤ、オイラ遠慮しとく」オルフェは気まずそうに笑った。「おいちゃんが教えてあげなよ」
傷は無理矢理塞いだが、容態は予断を許さなかった。傷口を即席で作った聖水で消毒し薬草を塗りつける作業を、殆ど休み無しで続けなければならなかった。その合間にも水を清め、手拭いを洗い、道具を煮沸消毒する。みんな疲れていたが、誰も休もうと言い出す者は居なかった。
血を拭っているユークァルの手に、血の気の失せた手が重ねられた。
「…ユ−クァル」
「?」
呼び止めたユークァルに、竜王は弱々しく微笑んだ。
「…今なら、私を殺せるかもしれんぞ…」
「どうして、そんなことを言うんですか?」
「どうしてって……それが、お前の使命では……なかっ…たのか……?」
返事を聞かず、竜王はそのまま意識を失った。
「そうですね。…どうしてなんでしょう。変ですね…」
ユークァルは濡らしたタオルで汗を拭き取ってやりながら、誰に聞かす風でも無く呟いた。
闇の中を、墜ちて行く。無限に。足掻こうにも羽ばたく翼も打ち萎れ、ただ堕ちるだけ。
無限は不意に終わって、地の底に打ち付けられる。全身を、引き裂かれる痛みが襲う。
「…気付いたか」
目覚めると、そこは今や廃墟と化した砦の中だった。思い出す。
きっかけはほんの些細な――奴らが、魔王とやらに捧げる貢納品の山から、ほんの馬車一台分の上前をハネた――ただそれだけの事だったのだが、それは直ぐに屍を山と積む程の争いとなった。
奴らは夜となく昼となく執拗に襲ってきたが、逆手を取ってこちらから奴らの砦に乗り込んで大暴れしてやった。連中の殆どは箸にも棒にもひっかかりそうにない下っ端風情だったが、それでも奴らの親玉は、多少は知恵も回るらしく…とはいえ、私に向かって、手下になれと平然と言ってのける程のおつむではあったのだが…お決まりのやり口ではあるが、数を頼んだ僕共に相手をさせておき、自分は安全な所から隙を見つけては殴りつけて来た。
だが、奴は強かった。少なくとも、今まで屠って来た、どんな連中よりも、だ。そして、私は徐々にではあるが追い詰められていた。そして、奴の鉄球に吹っ飛ばされて、雑魚共に袋叩きにされ、そして…。
思い出せない。まさか…死んだのか?
手を見る。…これは、何が、起こったのだ?
その手は、見慣れた私の手では無かった。青みの強い、くすんだ
青銅色
の鱗とかぎ爪に覆われ、至る処奴らのいやらしい緑色の体液で染まっている。腕も、肩も、足も、胸も全てだ。体を起こしてから気付いた。この砦は、こんなに狭かっただろうか?
変容する己が姿を受け入れられず、私は惑う。
「
覚醒
めたのだよ。隠されし、己が力に」低くくぐもった、
掠れた歪みを含む声
。直ぐに脳の指揮系統が筋肉に命令を下し、警戒態勢に入る。
「隠されし、我が、力?」
「その姿はほんの入り口に過ぎぬ。例えて言うなら、目の前にある階段を、ようやく見付けた、と言ったところか。…そこで安穏としているようでは、その程度で終わるであろうが。じゃが、忘れるでない。その煤けた醜い姿が、そなたの真の姿では無い、と。そなたの力は、まだまだ己の内に隠されておる。しかし今は言っておこう、よくぞここまで来た、と」私は辺りを素早く見回した。その声はまるで耳元で囁かれたかの如くに感ぜられた。が、それは確かに、空いたままに盲いたが如き闇の奥より発せられていた。
「貴様…何者だ?」
「名無き者に名を問われるとは、余の名も地に落ちたものじゃ」クックッと、声の主は喉の奥で嗤いを押し殺していた。直接響く、脳を犯し、擦り潰すような、耳障りなノイズ。
「何が可笑しい?!」
「ほう。では、そなたは何者じゃ? 名は? 申してみるがよい」
応えられなかった。
自分が何者かなどという問いが存在することすら、ほんの先程まで思いも寄らなかった。ただ、生きる為、生きていく為だけに生きていた。己と他者を識別出来さえすれば、名前すらも必要なかった。名を聞かれることさえなかったからだ。
しかし、問われて、私は初めて、嘗て何者でもなく、未だ何者にもなれずにいるのを思い知らされた。
「知りたいか? 名無き者よ」
『誰か』の誘いは、何時の間にか我が耳に限り無く甘美に響いていた。
私は、己が知る以上の何者かなのだろうか?
しかし、その甘美さ故に、私は『誰か』の誘惑に
躊躇
いを隠せないでいた。
「信じられぬか? では、信じさせてやろう」
『誰か』を取り巻く瘴気が、渦を巻いて辺りを覆い尽くしていく。その瘴気が私に触れた時、私は名状し難い感覚を覚えた。
私はこの感情を抱いた事が、ある。
我が身を捉える限り無い空虚…ああ、これは『恐怖』だ。その存在をすら省みる事の無かった、或る感情。『奴』こそが、私から全てを奪った………何だと? 私が、嘗て、何物かを所有していたとでも?
いいや、あった。確かに。
奪い去られていた筈の、『記憶』とすら呼べない『記憶』が、蘇る。
限り無く、温かいものに包まれていた、全てが満たされていた、何か。
急速に失われていく、温もり。
取り戻そうとしても、決して叶うことのない、何か。
直感が囁く。奴は全てのからくりを知っている、と。
皮膚が逆立つ。奴の仄めかしの裏にある企てを嗅ぎ取って、総身が戦慄く。
恐怖は、憎悪にその場を明け渡した。
「私は誰だ。何者だ。そして、貴様は、何者だ?」
『奴』は黙って、後ろの姿見を指差した。
「……!」
これが、私なのか?
私は己の変容に驚愕を覚えた。全身を煤けた青銅色の逆立つ鱗に覆われた、この巨大な竜が私なのか? 幻影か? それとも…。だが、確かに、私の影はいつもの姿ではなく、竜の姿を取っている。
「…戻、れるのか? まさか、ずっとこのままの姿で…」
「戻れるとも。再び竜の姿に戻れるかはまた別の話だが…おお、もっと良くその姿を余に見せておくれ」
私は『誰か』の望みになど応じてやるつもりはさらさらなかった。元の姿に戻りたい、そう念じて全身に意識をかけると、肉体はやがて、元の姿にゆっくり戻っていった。外では雷鳴が鳴り響き、稲光が辺りを照らし、闇より我が身をくっきりと浮かび上がらせた。
瘴気の揺らぎに気付いて、直ぐに緊張の糸を張り直す。闇が蠢くと、一歩、また一歩、「奴」の輪郭が立ち現れる。雷鳴に入り混じる、微かな衣擦れの音。
雷光が再び辺りを照らし、『奴』の輪郭が浮かび上がった。
「よくぞ、我が下へ戻って来た。世界を統べし神竜の子、王の中の王、竜王よ。今こそ語ろう、そなたの血の秘密、そなたが何者かを」殆ど皮と骨だけの乾涸らびた骸骨の、空虚な穴の奥に宿る澱んだ光が蠢いて、こちらを睨め回す。「我が名は大魔王ゾーマ。魔物を統べる闇の王じゃ。よく憶えておくが良い…忘れようにも忘れられぬじゃろうがな」
それは、俄には受け入れがたい、まるで遠い国のおとぎ話でも聞かされているような話だった。
この身が、世界を統べる神竜と、竜の女王間に生まれし、神の血を引く光の子であり、母の城で産み落された私の卵は、孵らぬうちに、奴…ゾーマの手で母の手から奪われ、母は私を守る為、奴の手にかかって殺されたのだと。
そして、世界を統べる王、我が父マスタードラゴンは、我が子と己の王国を天秤に掛け、子を捨てたのだと。
だが、そんな事がどうして信じられよう。私はここより他の世界を知らぬ。血で血を洗い、敵の屍を踏みしだく。そんな我が身に魔族の血が流れていないなどと。確かに、私は奴らとは違う。何かが違っていた。奴らは決して私を寄せ付けず、受け入れなかった。だが…。
「合点が行かぬようじゃな」
「ああ」私は頷いた。些かも、殺気を緩めてはいない。
「物心付きし時より、闇の世界を一人惑い、己を守る為闇を纏って来た故、そなたが己の光の本性をそう易々と受け入れられると思ってはおらぬ。だが…今すぐ、その身に解らせてやろう」影しか見えぬほど離れていた筈のゾーマが、目の前にいた。今まで、決して誰にも許した事のない間合いに易々と踏み込まれて、私は
戦
いた。ゾーマはぬめった光を放つ青黒い爪を、そのまま一分の間も与えず胸元に埋め込んだ。鮮血が迸る。
「…!」
力が、抜けて行く。
何の抵抗も示せず、我が身は蹌踉めき、崩れ落ちた。視界に広がる、真紅。
「ある種の瘴気――無論、その様な瘴気を操る者は、魔族の中にも滅多に、いや、まずおらぬのだが――に対する抵抗力を赤子ほどに持たぬ事、それが、そなたが魔族たり得ぬ、何よりの証拠」
横たわる私には目もくれず、ゾーマは床に流れる血を拭って、愛でていた。
「だが、他の者はもっと早く気付いていたであろうな…そう、それ…美しい…そなたの躰に流れる赤い血。これこそが、そなたを他の魔族共より峻別して来たのだから。気付かなんだか?」
「さて…これからどうしましょう。このままここにいては、いつ何時あの鎧の戦士からの襲撃があるかも知れません。…動けそうですか?」
「動けるも何も、動かなければ、殺られるだろう」
暗い夜の森で一夜を明かし、予断を許さないながらも何とか最悪の状況を脱しつつある今、先回りして次の一手を打つべきだ、というのが一同の共通した意見だった。しかし、肝心の竜王がこれでは、こちらからアグレッシブに動き回る訳にもいくまい。
「町に行きましょう」ユークァルが言った。「町中なら、無関係の人間を巻き込む可能性を恐れて襲撃して来ないでしょう。あの格好なら不意打ちはされないと想います」
「確かに。目立つもんねーあのかっこ。それに、びゅーって飛んだら町中の屋根を吹きとばしちゃうよ」
「どの町に行きますか? ロザリーヒルに戻ります?」
「そうだな…待て、オルフェ地図は何処に行った? あっちの山を越えた先の村に、温泉があるとか」
「観光マップに載ってたよ、それ」オルフェが観光マップを広げる。「目的地と反対側だったから寄れないねって言ってたじゃん」
確かに、温泉なら、傷を癒すのにはもってこいだ。怪我人が運び込まれても怪しまれないだろうし。
「温泉と言えば、マイラ温泉は最高だな。あそこは随分通ったものだ」
「マイラ温泉は有名ですからね」
「あー、それいいなあ、オレも連れてってよ。それどこ?」
「その前に死ななかったらな。…何だその情けない顔は? 心配するな、まだそう簡単にくたばる訳にはいかんからな」竜王は言うなり苦痛で顔をしかめた。「言っておくが、歩けんから、貴様おぶっていけよ」
我々は村に着くなり、早速温泉宿に大部屋を取った。竜王だけでなく、私達も夜通しの看病で疲れていた。オルフェもユークァルもどことなくやつれ気味で、宿に着くなりろくに顔も洗わず眠りこけた。
想えば、ニヴルヘイムからここに来るまでの間、ロザリーヒルでの短い滞在を除けば、我々がゆっくり一所に居を構えて休息を取った事など無かった。
何時まで、こんな旅を続けるのだろう。
我々の旅は逃亡の旅、流浪の旅であり、何処にもない場所を求めて彷徨う、行く宛も、報われる見通しも無い旅。
請われるがままに付いては来たものの、この先に望ましい未来があるとは到底思われなかった。
さて、お陰様で治療経過も良好で、体調も何とか歩き回れる程度には回復したので、私はさらなる治療を兼ねて温泉に入る事を勧めた。傷が塞がりつつあるとは言え復調したとはお世辞にも言えた身分ではないので、風呂には我々も付き添う。温泉がにぎわう時間を避け、こっそり入る。
「な〜んか、ドロボウみたいだね」
「…うるさい」
抜き足差し足忍び足で入った湯治場は、周りを柵で囲ってはいるものの、見上げれば青い空が広がる、湯をなみなみと湛える露天風呂。花崗岩で作られた龍の口からは湯飛沫が湯気を立てながら迸り、植え込みの緑から赤く実ったナナカマドの実が覗き、湯気を受けて雫を垂らしている。湯の中に身体を沈めると、身体中の疲れが湯に溶け出して行く様に思われた。
「ふぅ。百と八年の汚れを、ようやく洗い流せる」全身にかけ湯を存分に浴びせ、竜王は心地好さそうに身体を拭った。「背中流してくれ」
「煩悩もついでに洗い流して…あいた!」竜王に湯桶を投げつけられ、 目の前に火花が飛び散った。
「よっこらしょっと…。あ〜、こいつぁ気持ちいいや! いや〜ぁ、温泉って、こんないいものなんだねえ」オルフェは最初怖々お湯に足を入れていたが、直ぐに慣れてすっかり気に入ってしまったようだった。「こんないいものがあるんだから、オイラあの世界から出てきてホントに良かった」
「はっはっはっ、あの辛気くさい世界には温泉なんか無いだろう」竜王は湯に浸したタオルで顔を拭く。「なあ、もう少し強く擦ってくれ」
「傷、沁みませんか?」私は正直、怖々背中を流していた。ようやく抜糸が済んだばかりの痛々しい疵痕に、嫌でも目が引き付けられる。
「ああ、大分むずむずするな。だが耐えられん程では無いさ」
「あまり長い間浸かっていては駄目ですよ」私はお湯でふやけ気味の傷痕を観察する。「あとで薬油を塗り込みましょう」
「うむ、そうだな。…誰か入ってきたぞ?」
「あ、ユークァ…キャーッ! ダメ、ダメ!」
オルフェの叫びに、私もまた想わず眼を覆った。ユークァルが、男三人(人間じゃあないですけど)の露天風呂に前も隠さず素っ裸で入ってきたのだ。彼女の未成熟な体に刻まれた痕が、痛々しさをいや増す。
「あたしも、入っていいですか?」
「あ、あのなあ…、ユークァル、建前でもいいから、少しは恥じらって前くらい隠せ」
「なぜですか?」
「バカ! 何でもへったくれもない! 他の連中眼のやり場に困ってるだろうが。…それに、お前の傷だらけの貧弱な体など、見てても痛々しいだけでちっともそそらん、ほらっ!」
「そう、なんですか」ユークァルは投げられたタオルを受け取ると、いそいそと前を隠した。「あたしは大丈夫ですけど…」
「ああ。まあ例外はいるがな。なあオルフェ」
「う、うるさいやいっ!」オルフェの顔が茹でダコみたいに真っ赤になったので、一同は大笑いした。
「あ、それより、あの丸太小屋何? ほらあっち」オルフェの指差した先には、大の大人4人も入れば一杯になってしまいそうな小屋が建っていた。小屋の小さな煙突からは、白い煙がもわもわと空に向かって立ちのぼる。
「巧く誤魔化したな。あれはサウナだ」
「しつこいなー、ゴマカしてないよ。で、サウナって何?」
「一種の蒸し風呂だな。暖まるぞ。一緒に入るか?」
「良いんですか? 病み上がりなのにサウナなんて…」
ちょっとだけだ、というので、皆でサウナに付き合うことにした。丸太小屋の中は独特の熱気が立ちこめており、早くも汗が皮膚の表面からぷつぷつと吹き出る。
「うううー、こんな熱いとこがまんできないよう。オレ出るよ」オルフェは早くもギブアップして小屋から出て行った。
「何だ、あいつ全然根性無いな。ユークァル、お前入ってるのなら、この砂時計が落ち切ったら起こしてくれ。ちょっと休む」
「…寝るんですか?」正直、私はもう熱が全身に回って頭がくらくらしていた。本当に平気なのだろうか?
「おいおい、寝るって、ここでいびきをかいて寝るわけじゃないぞ。ただちょっと休むだけだ。それに、こいつが起こしてくれるから大丈夫だろう。行けるな?」
竜王に軽く肩を叩かれて、ユークァルはこっくり頷いた。
「遅いですね」二人がサウナに入ってから早半時が経とうとしていた。
「ユークァル、大丈夫かな?」
「ちょっと心配ですね…。見て来ましょう」
小屋の扉をノックしたが返事が無い。無遠慮とは知りつつ扉を開ける。
「!! オルフェ、水! 水持って来なさいッ! ああだから言わんこっちゃない!」
サウナ小屋の中に飛び込んだ私の眼下にあったのは、サウナの中でうだってのびている二人の姿だった。
療養の為とは言え、毎日ひなびた温泉宿で風呂に入ったり出たりを繰り返しているだけの日々に、皆そろそろ退屈してきた。傷が癒え疲れも取れて体調が良くなってきたかと思いきや、今度は連日の小雨。
「あー、ヒマだ。何かないのか何か」竜王は床にぶちまけられたトランプを恨めしげに見つめていた。セブンブリッジ&コンストラクトブリッジにスピード、ばば抜きじじぬきナポレオン、大貧民に51ポーカーブラックジャックにカブラミー、ダウトにページワンとやっていないトランプゲームはない。とはいえ殆どのゲームは天然ポーカーフェイスのユークァルが一人勝ちで、直ぐにつまらなくなって辞めてしまったのだが。しかも、ユークァルは平気で巧妙なイカサマをやってのけるのだ! 彼女にゲームの概念を教え込む所から始めないといけない事が解って、竜王はさっさと匙を投げてしまった。無論私が尻拭い役である。
「ねえねえおっさん! ビッグ小ニュース!」オルフェが片手にチラシを持って戻ってきた。
「形容が矛盾してます」すかさず突っ込むユークァル。
「貴様におっさんと呼ばれる歳ではないわ」竜王はぶちぶち言いながら、ぶちまけたトランプをかき集めて一人遊びに興じている。赤と黒のカードを交互に並べ、手際よくシークェンスを作って行く。
「だって500年は生きてるんでしょ? ゆうにおっさんだよ。ひょっとしてじいさんでもいいんじゃないの? って痛ってー! 物投げる事ないじゃん! 暴力反対!」
「黙れこのとんちきが。ハーゴンだって100歳越えておると言うに、人間の歳と一緒にするな! そもそもお前も妖魔だろうが!」竜王はオルフェを怒鳴りつけたが、興奮しすぎて案の定激しく咳き込んでいる。
「だから安静にしなくちゃダメだって言ってるでしょう。オルフェもやり過ぎです。で、そのビッグ小ニュースって何ですか?」
「っていうかさぁ、毎日温泉に入ってばっかで退屈じゃん?」オルフェは背中に回していた手を大仰に突き出して、手に持ったチラシをさも宝物ででもあるかのように見せびらかした。「ジャンジャジャーン、何と! この世界屈指のお笑い芸人、らしい、パノンがこの街に営業に来るってよ! やったね! オイラぜってえ見に行くぜ! な、ユークァルも見に行こ!」
「勝手に行け、止めはせん」興味なさそうにあしらわれたので、オルフェは唇を尖らせた。
「ちぇっ、何だおっさん喜ぶと想ったのにさっ」
「またおっさんと言いおったな! 貴様、その内桜鍋にしてくれるわっ!」
オルフェは鼻先に突き出したチラシをぱっと引っ込めた。美しくまとまりかけていた赤と黒のシークェンスは、造物主の気紛れで再びカオスに帰した。
で、当日私は、結局パノンの舞台を見に行った。オルフェが前の公演を見に行って「面白い、面白い」と言っていたのもあるが、何よりヒマだったのだ。
場所は民宿の宴会場。宴会場とは言っても、こんな老人ばかりの温泉宿でそうそう宴会など行われることもなく、宿側の方でたまに名も知れぬ吟遊詩人や歌姫、流れの踊り子や芸人の類を招いて公演をするらしい。
時間が来たので、入り口近くで立ち見する事にする。こんな温泉宿でも存外人は集まるもので、用意された折り畳み椅子には、老後を温泉漬けの毎日で過ごす老人達が溢れていた。
ひなびた温泉宿特有のチャチな舞台に、これまた安っぽいセット。幕は破れたのをつぎはぎにして塗縫い合わせてあるが、色味を合わせていないのでパッチワークの出来損ないのようだ。その中をチープなファンファーレと老人達の拍手に促され、派手な衣装をまとったパノンらしき男が登場した。パノンは舞台に上がるなり、派手な身振りで客席に愛敬を振りまき、挨拶もそこそこに客席に降りていく。パノンは老人達が握手を求める中を闊歩して、ある客に目を留めた。
「お客さん、ちょっと袖を持って下さいね」パノンは客席の老人に衣装の袖口をつかませて、言った。
「おはなしっ!」
客先がどっと沸く。
刹那、何が起こったのか、私には解らなかった。
「で、ここだけの話、今日は犬を連れてきてるんですけどね、舞台の上で綱をほどいちゃおうかと。ここだけ野放し、ここだけのばなし、ここだけのはなし」
パノンが懐から、ミノーンを取り出す。
もしや、これは。
「で、これが私の相棒のミノーン。こいつが皆さんにミノーン話をしたいと申しております。ミノーン、ミノウン、身の上話」
伝説の。
「私のもう一人の相棒マッドロンを呼びましょう。ま、ドロンと消えちゃった」
真夏でもフレイムを凍り付かせるという、絶対零度の怒涛のオヤジギャグ……?!
「おい、どうしたハーゴン、面白いというから聞きにきてやったのだがどうだった? もう終わってしまったのか? おい!」
私は無言で舞台を指差す。
「は? 舞台? ……?!」
笑いと拍手の中、絶対零度の気に当てられて、私達は自我の崩壊の危機を感じただただ立ち竦んでいる事しか出来ないでいた。
「…くしゅん!」
「バカたれが。あんな所で何時までも立ち竦んでおるから湯冷めするのだ。看病人が風邪を引いてどうする」
温泉で今までの看病疲れが浮いてきた所に湯冷めが来たものだから、身体も動かない程の酷い熱に襲われ、竜王に罵倒されながら寝込んでいる。私としては、高熱の原因は他にもあると想っているが。
実際熱の具合は本当に酷いもので、今でも時々パノンが現われては
「ドラキーに会えてドラッキー!」とか
「アクバーは悪ばー」
という薄ら寒いダジャレをとばす幻聴が聞こえるのである。パノンがミノーンを持っている幻覚が見える事さえある。オルフェによると、夜の夜中にうなされながら「もう止めてくれー、それ以上言わないでくれー」と苦しそうに耳を押えて呻いていたそうである。
外は雨がしとど降りしきっている。この雨ももう5日近く続き、止む気配を全く見せない。竜王は、もう一回風呂に入るといって出ていってしまった。部屋の隅ではユークァルとオルフェがトランプをしている。私は一人、ベッドの中に身を横たえ、痛む頭を押さえながら雨音に耳を傾けていた。
「ルビス様ぁ、本当に天界に帰らなくていいんですかぁ?」
「いいのっ。だって、わたくし、もうあの方には愛想が尽きました」
幻聴が聞こえる…。パノンのダジャレとは違う、梵音ともいうべき豊かな響きだ。
「しかし、何故あの様な下郎の輩にそこまで肩入れされるのか」
「下郎とは何です! 酷いわキューリ、仮にもマスタードラゴン様…様なんていらないわね…の御落胤、御子息、御曹司なのですよ! それを…そんな、ひどい…」
ああ、これは駄目かもしれない。キュウリがしゃべっているなんて、ノンセンスもいいところだ。脳が圧迫されて、かなりキているらしい。
「でもぉ、悪の大魔王ですよぉー? 何されるか解ったもんじゃないですよぉー? 本当に大丈夫なんですかぁー?」
「根の国におけるきゃつの所業の悪辣ぶり、ルビス様も御存じであろうに、妾に見て見ぬ振りをせよと仰せか? くうぅ〜っ、よくも、よくも我が一族に伝わる家宝の剣を奪い去りおって…キーッ!」
「貴女達には解らないかも知れませんね。でも、あの方は、本当はとても孤独で悲しい人なんですわ…」
バックに点描が飛んだ。ああ、私はもう死ぬんだ。
「っていうかぁ、ルビス様雨雲の杖盗んできちゃったでしょー。あれチョーまずいですよぉー」
「盗んできたんじゃありません。少しの間借用しているだけです」
ルビス、と呼ばれていた女性が、きっぱりと言った。ルビス様の名前まで出てくるとは、もうそろそろお迎えの時期も近いのだろう。
「しかしまた、何故その様な御無体を…」
「うふ」ルビスと呼ばれた女性が悪戯っぽく笑う。「それは、あの方がこの温泉宿に停泊しているという情報をつかんだからな・の☆だって、こうやって雨を振らせておけば、私達がお迎えに上がる迄に、あの方が他の街や村に向かって移動してしまっていてお会い出来ない、っていう事はなくなるでしょう? …勿論、例の件もあるのだけれど…ダメダメ、ルビス。笑顔で行かなくちゃ♪」
「ビミョーに痛々しいですぅ〜」
ガラス戸をノックする音が聞こえた。
いや、風の音だ。
幻聴を確かめようと、首だけで窓の外を覗く。
ガラス戸の向こうには、天女の如く美しい女性が、お供2人に傘を持たせて宙に立っていた。
「幻覚だあぁっ!」私は叫んだ勢いで、ベッドから転がり落ちてしまった。
「あらあら、幻覚とは失礼ね、開けて下さいませんこと?」
「幻覚じゃないです」ユークァルが無情に窓を開けた。窓の外の佳人は窓枠に軽く身を屈めると、御足を部屋に踏み入れた。長い蜂蜜色の髪は先が僅かに雨に濡れて縺れており、仄かに透き通る肌を引き立たせている。
「有難う、お嬢さん。貴女達も入っていらっしゃいな」
天女は誰かが許可した訳でもないのに勝手にお供を部屋に呼び入れる。と、ミョーにキャピキャピしたミニスカギャルと、全身を甲冑で武装した厳めしい女の、およそこの女性の供には似付かわしくない天空人の二人組がずかずかと踏み込んできた。
「ていうかぁ、マロン雨に濡れちゃってぇ〜、冷たくてしょうがないのォー。タオル貸してェー」
「済まぬが、火を拝借出来ぬか? 身体を濡らしてしまった故。……!」
どこかで聞き覚えのある声、口調。ふらつく頭を押え、良く目を凝らすと、金髪三つ編み鎧兜の天空人と目が合った。
「キューリさん!」
「ハーゴンッ!」
私達は久々の再会に、息も忘れて見つめ合った。
「………きーっさまーぁっ! よよよよくも模範囚の振りをして、妾を謀ってくれたなっ! この超極外道悪魔神官がぁっっ!! バカパァーンチ16連打ぁぁぁっ!」
「ぎゃあっ! 痛い痛いっ! ややややめて下さいっ!」
久しぶりの再会は、やはり痛みを伴わずにはいられない代物であった。
扉の向こうでかなだらいが落ちてくわんくわんいう音が部屋中に響いたので、皆の視線は一斉に入口の方に集中した。
ドアの向こうには肩にタオルをかけて好い加減で帰って来た竜王が立っていた。竜王は口あんぐりでルビス様を凝視していたが、ようやくその強張った口を動かした。
「る、ルビス! そなた何でこんな所へ…?」
「おお、おお…」ルビスと呼ばれた天女は感激に打ち震え、頬を紅潮させた。「こうしてお会い出来るのは、もう何百年ぶりの事でしょう…私、この日の事を待ち焦がれておりました。お慕い申し上げております…ぽっ」
「うわ、ルビスやめろ皆の前で抱き付くのはっ! こらオルフェ、笑うな、笑うなと言うに!」
「あらいやですわ。もうそんなダーリンてば☆チュッ」
「だ、ダーリン…」
ルビス様に抱き付かれて無理矢理キスの嵐を浴びせられ、ヘビに睨まれたカエルのように脂汗を滲ませる。げらげら笑うオルフェを睨み付けたが、もうだめだ、まるで威厳無し。私まで笑いがこらえきれなくなりそうだ。きっと鏡を見たら、口元がにやついているに違いない。
「昔のお前はもっとしとやかで、しかし芯の強い、しっかりした女だったでは無いか。何時からそんなおポンチになってしまったのだ…あいてて!」ミニスカ天空人ギャルがすかさずかなだらいでツッコむ。実際、あのスカートはパンツが丸見えで目のやり場所に困る。
「何言ってるんですぅー! ルビス様が壊れちゃってぇこんなおポンチになったのもぉー、もとはと言えばぁぜえぇーんぶ、貴男達のせいなんですからねェー! あ・な・た・た・ち・の!」彼女は直ぐに手元のかなだらいを私の額に直撃させ、『貴男達』の中に私自身が入っている事を痛みと共に思い知らせた。
「あいたた…わ、私ですか?」
「私がか?」
ミニスカ天空人は力一杯頷いた。「そうですぅーッ! 貴男が世界をぶち壊そうなんて言い出さなければぁ、貴男達が根の国から脱走なんかしなければですぅーッ!」
脱走、という二文字を聞いた途端、先程まで大人しくしていたキューリ嬢がすくっと立ち上がった。鍛え上げられた筋肉が波打ち、ぴくぴくと痙攣するや否や、果敢にも竜王目がけてつかみかかった!
「キ、サ、マァーッ、良くも我が一族の家宝を奪ってくれたな! とっとと返せ! 返さんかーっ!」
「ああ、悪いなキューリ、あの剣な、金が無かったもんで路銀の足しにしようと売っぱらっちまった」
「ギャーッ! キキキ貴様あー! ブッコロス!」
「ごふっ」キューリ嬢のエルボーがちょうど傷痕に食い込み、体を折ったところに延髄へのかかと落としを決められて、竜王はもんどりうった。床が鮮血に染まって、私は焦る。
「ま、待って下さいキューリさんっ! 例の剣が無かったら、私、彼に食われてましたって!」
キューリ嬢の攻撃の手が、一瞬止んだ。
「なぬ?! 貴様もか、貴様もかぁーっ!」
「う、ギャアアアアアアアアアッ!」
「キャァーッ! キューリちゃん、それはやりすぎぃ〜ッ!」
同情を引く事によって敵意を和らげようとする私の作戦は見事に失敗に終わった。それは結果として怒りの対象を私に振り分けるという結果しか生まなかったのであった。という訳で、私は更に過酷な攻撃に晒されるハメになり、見えるところ全てに引っ掻き傷と噛み付かれた痕を刻み込まれる事とあいなった。
「うっわー、ヤバキチだよあの姉ちゃん」
頭を掻き毟り、血走った目で喚き散らすキューリ嬢に噛み付かれている私を横目に、竜王は弱々しく言った。「だろう?」
私の怪我はどうと言う事はなかったのだが、竜王の方はそうは行かなかった。塞がりかけた傷痕を抉られて、竜王は血反吐を吐いてベッドに横たえられ、滲み出る脂汗をふき取られながらうんうん唸っていた。ふらふらしながらも必死に手当している中を、キューリさんは当然の報いと言わんばかりに見下していた。ちょっとは手伝ってくれればいいのに。
竜王はと言えば、出血こそ何とか収まったが、先程までの生気は何処かに引っ込んでしまった。弱々しい光を湛えた瞳を僅かに覗かせ、肩で息をしている。
「ごほっ…ロトの奴め…」
「キューリさんには何にも言わないんですか」タオルに付いた血を洗い落とし、私は何気なく聞いた。
「あのバカには何を言っても無駄…」
キューリ嬢が鯉口を切ったので、私は真意を悟った事を目線で伝えた。
「…天災と思う事にした。それならば諦めも付こう」竜王は再び目を伏せた。「あ奴…しかし、一体何者なのだ…? たかが人の子如きで、何百年もの間、年も取らず生き長らえる事など出来はしまい? なあ、ルビス、そなたならあ奴のことについて何か知っておろう。あ奴は…ロトとは、何者だ?」
汗を拭うルビス様の顔に、僅かな影が差した。そして、決意を固めたかのように、唇を振るわせた。
「…そうですわね、貴男が存じ上げている筈も御座いませんわね…あの子は、わたくしと貴男の、たった一人の息子ですわ」
「へ?」
一同は、呆けたようにルビス様の一挙一動を、まじまじと見つめた。「なーんちゃって♪」といい出すのではないか、とじっと待ちかまえていたが、ルビス様はそのまま何の素振りも見せなかった。
「…マジ?」
「そうなんですか」
「うっそ〜ん! マロン聞いてないよぉ〜!」
「そ、そんな話、妾も聞き及ばぬぞよ!」
「な、何だと?! そんな馬鹿な話があるか!」しかし、一番驚いたのは当の本人だった。布団をはね除けて起き上がり、ルビス様の方を鷲掴みにする。「そもそもそなたが子供産んだなんて話、一度も聞いておらぬぞ! 何時だ! 何時産んだっ!」
「わたくしが打ち明ける前にとっとと石にしてしまったくせに。そんな、ひどい…」
「う…うむ、そうであったのか」
鷲づかみにした肩から手を離すと、竜王はわざとらしく咳払いした。こういう所はてんでらしくない。
「半年もの間現れなかったから、気にはしておったのだが…そうか、そういう訳だったのか…。酷い事を…もし、あの時、そなたを信じてやれれば…」
「もう、良いのですわ」ルビス様はけなげに微笑まれた。「あれは、仕方のないことだったんですわ…過ぎた過去ですものね」
竜王は黙って、ルビス様の肩を抱き寄せた。
「あたたかい…なのにどうして…まだ、諦めてはおりませんのね」
「ああ。愚かしい事やもしれんが」竜王は抱き寄せた手を放した。「その為には、行く手に立ちはだかる者は、例え我が血を引きし者といえども許す訳には行かぬ。それだけは、解ってくれるな?」
ルビス様は無言で、手を握り締めた。「良いのです…あの子は、もう死人も同然ですから…」
「…? そなた、何か知っておるのか? あ奴は、魂を抜かれた木偶になっておった。400年もの間に、一体何があった?」
「わたくしにも解りませんわ…。ただ、あの子は、いざ勇者が必要になった時の為にと、天空上の奥深くに封印されていたのです…」
「何…だと?」握られていた手を、強く握り返す。
「今の今まで、存じ上げませんでした…。あの方…いや、マスタードラゴンさ…様は要らないわね…は、こんな時の為にと、秘密裏の内に準備していたのですわ、きっと。…私、腹を決めております。腹を痛めて産んだ子が、例え理由は何であろうとこのような仕打ちを受ける故はないと。ですから、私はこの経緯を、最後まで見届けとう御座います。ですから、貴男が例え何を仰ろうとも、私は付いて参ります!」
と、まあそんなこんなで我々4人にルビス様一行が合流する事となり、我々一行は7名を数える大所帯となってしまった。勿論ルビス様達が金子の工面など考えてもいよう筈も無く、別室を借り出したり食費を捻出したりとやっているうちに、大してあるわけでもない蓄えは見る間に底を尽き、我々は這々の体で宿を引き払うハメになったのだった。
「お、おいルビス、そなた本気で付いて来ると言い出すのではあるまいな?! だめだ、いいか、絶対に認めんからな!」
「マロンもですぅーっ! ね、ルビス様、天空城に帰りましょーよぉーっ!」
「その通りじゃ! こんな悪逆外道の輩に…ぎゃっ! よくも妾の三つ編みを引っ張ったな!」
「悪逆非道で結構だ! ルビスを連れてとっとと帰れこのバカ女!」
村を出てからもべったりのルビス様に、いい加減うんざり…いや、最初から相当うんざりしていたのだが…と言った面持ちで、竜王はルビス様が絡めてくる腕を振り払った。
「何故一緒に来るのがだめなんですか?」ユークァルが真面目に質問したので、オルフェはまたぞろ笑いを堪えている。真面目に昔話を語った後とのギャップが可笑しくてしょうがないらしい。
「は、恥ずかしいからに決まっておるだろうが! こら抱き付くなっ!」
「何故ですか?」
「五月蠅い、ちょっとは自分で考えろ」竜王は真顔で聞くユークァルを投げやりにあしらった。
「何ででしょう」ユークァルはオルフェに言った。「変ですね」
顔を引きつらせて笑いをこらえていたオルフェは、ユークァルに追い打ちをかけられてヒイヒイ笑い転げた。あんまり笑い過ぎて涙目になっている。
「うっひゃっひゃっひゃっ! おかしすぎて涙がでらぁ! おてんとサマが二つもあるし…あれ?」
「太陽が二つ? …!」オルフェが指差した方向で、何かが太陽光を反射して煌めいた。それが何者かを認識した途端、それ…すなわち勇者ロトは、我々が身構える前に、凄まじい風圧を伴って襲いかかって来た!
ロトは風を切り、木々の間を縫い空を裂いて何時までも何処までも執拗に追い続ける。疲れという物を知らぬが如く、機械仕掛けの死に神の如く。
「キャーン!」マロンがキューリの背後に回り込み、ぴっとりしがみつく。「キューリちゃん、頑張って☆」
「こらーっ! 妾を楯にするなーっ!」普段なら笑える光景なのだが、そうとばかりも言ってはおられぬ。マロンに腕を捕まれてキューリ嬢は必死に振り払う。
「コラ、キューリにマロン、遊んでるヒマがあったらとっとと逃げんか!」
「何を申すか無礼者が! 敵に背を向けるなど言語道断支離滅裂!」キューリ嬢は大股に踏ん張り剣をかまえると、ロトの攻撃を上段の構えで待ち受ける。
「お前の方が支離滅裂だこの石頭! いいか、そんなに死にたきゃ殺してやる!」
「何じゃとおぉぉ…ヒィ!」二人の間に蒼白く燃える大剣が振り下ろされ、三つ編みの毛先が宙に舞って、キューリは仰け反った。「わっわっ妾の親譲りの髪をば、良くも切ってくれたなー! デァリャーッ!」
キューリが振り下ろした剣の切っ先が、真横に飛んだ。
刃が木の幹に突き刺さったのを、キューリは口をあんぐり開けて見つめていた。「こやつ…一体…」
「ぼーっとしてるんじゃない、殺されるぞ! いいか、そいつが、そいつがロトだ!」
「こ奴が…こ奴が勇者ロトと申すか…信じられぬ…」キューリは改めて、ロトを見た。と、ロトの腕がキューリに伸び、キューリの胴を素手でなぎ払って弾き飛ばした!
「ぐわっ」キューリは木の幹に叩き付けられ、そのまま根本までずり落ちた。
「キューリ離れろ!」竜王が怒鳴りつける。「こ奴には、魂が無いのだ」
「言われずとも解っておるわ」キューリは片膝を付いて起き上がった。口の中を切ったらしく一筋赤い血が流れるのを、剥き出しの腕で無造作に拭う。折れた剣の柄を放り捨て、代わりに背中に背負っていた楯を構える。「ただ、妾には、きゃつが光の勇者であるという事が信じられぬ。言われねば気付かなかったであろうよ」
「ああ、要領の悪い女だな!」竜王はキューリの首根っこをひっ捕まえて引きずると、内側から足を引っかけて転がした。キューリは宙で一回転すると、ぐうっとうめいて草にまみれた。「さあ、これで1対1だ。貴様の目当ては私だろうが」二人は睨み合い、間合いを計って一歩も譲らない。どちらも動けないのだ。焼け付く殺気がじりじりと、見ている我々の皮膚をも焼かんばかりに突き刺さる。
と、二人の間に割って入る者があった。
「ロト、お願いです! 血の繋がった実の父と傷付け合うのはやめて!」それはルビス様だった。ルビス様はさっと腕を広げ、二人の戦士の前に立ちはだかった。
「やめろルビス、無駄だ。奴は魂を抜かれた脱け殻に過ぎん」
「殺すというのなら、わたくしもその剣に貫かれて死にます!」
「やめんか! 下がれ馬鹿者!」
ロトとの間に立ちはだかるルビス様を何とか退かせようと、竜王は無理に腕を引いて脇に突き飛ばした。往時の16分の1しか力を発揮出来ないとは言え、非力な女性を押し退けるには充分過ぎるくらいの力で、とにかく、ルビス様は突き飛ばされて地面に転がされた。衝撃の故か、ルビス様は未だ立ち上がれずに居る。
ロトの目に、赤い光が宿った。それは、私の目には忌まわしいものに感じられた。ロトは抜き放った剣を振り被った。
「やめてぇっ!」
「うおっ」
どっ、と地面が揺れて、枯れ草が舞い上がった。
振り下ろされた剣の切っ先が、ルビス様の亜麻色の髪を僅かに切り落とした。髪がドレスの裾を伝って地面に落ちる。
「間に合いましたわね」ルビス様はにっこり微笑んだ。
「馬鹿者! 何と言う事を!」ルビス様に脇からタックルをかまされ、竜王は地面に叩き付けられていた。
「馬鹿、じゃありませんわ、貴男」ルビス様は優しく愛する人を窘めた。「愛する人一人救えなくて、どうして、世界を守れるのでしょう? 貴男の居ない世界など、私には無価値ですわ。…お慕いもうしあげます。ぽっ☆」黒目がちなルビス様の瞳が涙で潤み、頬に赤みが差した。
「あ、あ…あの……あのなあ…」
「ルビス様ったらぁ、本気だったのねぇ…」マロンが目をぱちくりさせた。「ジョーダンかと」
「妾には解らぬ世界じゃ」
「ヒューヒュー! お熱いね〜! オイラ当てられちゃったよ。エヘヘヘ〜まいったね」
急に場が和んで、辺りが妙な雰囲気に包まれてしまった。生死を賭した戦いにはおよそ似つかわしくない光景だ。
「ば、馬鹿っ。男の戦いに女が口を出すな!」
「結構保守的なんですね…」
「ユークァル、お前黙ってろ! こ、こら、ルビス、お前いつまで私の上に乗ってるつもりだ?」
「あ、ご、ごめんなさい………………!」
目の前に、ロトが立っていた。
私達はロトに魂を奪われたように、ただ見ている他に無かった。何の意志も、感情も、伺い知る事は出来なかった。
ロトの瞳だけが、機械的に動いた。
「ルビス…光の側・重要人物。その生命保護は最優先事項」
「目的:優先順位…1/目標及びその援助者を殲滅」
「禁止事項:許可無き光の側の重要人物の抹殺」
「矛盾します」
「…は? 何…だ?」
ロトは無表情に再び繰り返した。
「矛盾します」
ロトは剣を鞘に収め、そのまま何も言わず飛び去っていった。我々は、ロトが飛び立って行った方角を、阿呆のようにただ見上げている他無かった。
一同は我に返り、呆気に取られてお互いを見合った。ユークァルは首を傾げオルフェは目を白黒させていたし、キューリ嬢は遅ればせながら折れた剣とその刃を拾い集めて何とか繋げないかと弄くり回していた。
「何だったのぉ〜? あれ」
「あの子の中で、一体何が起こったのかしら…」空を見上げるルビス様の肩に、蒼白い手が触れた。
「ルビス、お前とにかくいいから一度帰れ」
「ええっ?」ルビス様は雷に打たれたように身を硬くし、不安げに竜王の顔を見た。が、直ぐに本心からの言葉と悟って、ルビス様は神妙な面持ちで続く言葉を受け止めた。
「いいかよく聞け、ルビス。ロトだけでは無い、我々は既に、あちこちから狙われておる。我々がのたれ死のうが何しようが、この世界がどう変わるという訳でもあるまい。だが…もしお前が万一巻き込まれでもしたら、この世界はどうなる? お前の生命はお前だけの物ではない筈。違うか?」
二人はしばらく見つめ合い、やがてルビス様が目を伏せ、頷いた。
「そう、ですわね…。でも、わたくし、もう天空には帰れませんの」
ルビス様は肩の手を振り払い、私の方を向いたので、私は少なからず不意を打たれた。ルビス様は歩み寄ると、始めてお会いした時から手にしていた、こぶし大の緑柱石を埋め込んだ灰青色の杖を私に手渡した。
「貴男を信じて、これを託します」
「…! これは、雨雲の杖では? この様な物を、この、この私が、お預かりしてよろしいのですか?」
「わたくしは、貴男がして来た事も、何故貴男がそうせざるを得なかったのかも、存じているつもりですわ。キューリより、貴男の根の国での行状も聞き及んでおります」ルビス様はきっぱり仰った。「…それに、500年以上もの間孤独に苛まれて来たあの方が、貴男を友と選んだのは、あの方の心を解きほぐす何かが貴男の中にあったからこそだとわたくしはそう信じております。どうか、あの方を宜しくお願いします。そして」
ルビス様は私の手を、強く握り締めた。か細い手、儚くて柔らかい手だった。
「この杖を、無事守り抜いて下さいまし。勝手なお願いとは存じますが…どうか…」
ルビス様が天空人二人組を従えて去っていく後ろ姿を目で追いながら、私は、ルビス様が杖を託した時、その瞳がごく僅かな悲しみを帯びていたのを忘れられないで居た。