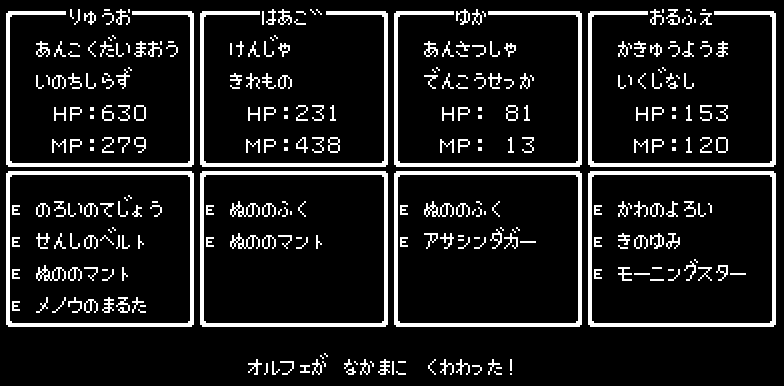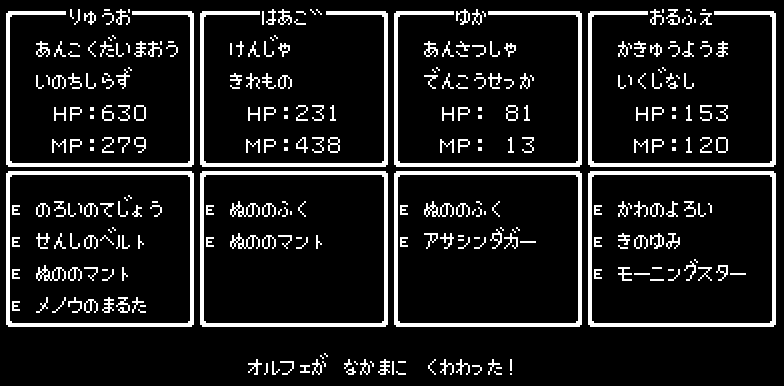第III章 針の城
「これが、旅の扉か」
「ええ…どうします?」
我々は、探し求めていた当の旅の扉を見下ろして、唯呆然と腕組みしていた。
竜脈から流れ込む気が激しく渦を巻き、溢れ出た気が迸って頬を舐める。渦の奔流に、その場の誰もが飛び込むのに躊躇を覚える。微かに唾を飲み込む音が聞こえたかも知れない。
「どうやって、入ります?」
「お前は何時も理屈っぽくていかん。うだうだ言わず飛び込めば良いではないか。ほれっ!」
「ってちょっと待って下さいよ。いきなり飛び込めと言われても…うわーっ!」言うなり背中を強く押されて、ろくに物も食べていない貧弱な身は無論抵抗も出来ず、そのまま旅の扉へ落っこちた。迸る竜脈のエネルギーに、身体がぐちゃぐちゃに掻き回され眼が回る。三半規管が掻き乱されて頭がくらくらする。胃袋が攪拌され、吐気が…と言っても、吐く物なんざ胃袋に詰まっては居ない。
「ほら、貴様も飛び込めっ!」視界の端で、竜王がユークァルをつまみ上げて旅の扉に放り込む。眼前でくるくると、流れに巻き込まれて抗う術もなく踊るユークァル。無表情なのだけが私と違うのだが。
「ふむ、大丈夫そうだな…では、行くか」
「あんたは卑怯だーっ! 自分が最後に…わーっ…」
竜脈の奔流に翻弄され、乾燥機に放り込まれた洗濯物のようにメチャクチャにされながら、私は旅の扉を潜り抜けた。
身体が突然解き放たれ、私は己の身が、いつの間にか時空のうねりから万有引力に委ねられたのに気付いた。
私達は、旅の扉から滝壷の上に出てしまったのだ。
「どわーっ! またかーっ!」
「やっぱりぃーっ!」
気付いた途端のお約束、天則には逆らえず、どぼーん、と、 3メートルはあろうかという水しぶきを上げて、私達は滝壷に落っこちた。
そしてこれこそが、この世界で始まる物語…つまり、破壊と、それに伴う混乱の、全ての幕開けとなったのだった。
事の始まりから話そう。
私達が水面から顔を上げて最初に目に飛び込んで来たのは、この世のものと思われぬ麗々しき人々の一行――白を基調に金と銀で縁取られた馬車に乗り、従者の馬具に到るまでもが絢爛豪華にして精緻な細工を施され、この世の贅を尽くした衣装を身にまとった煌びやかな人々――が、首だけの私達を視線で威嚇している、という光景であった。何故彼らが、私達に向けて敵意に満ちた視線を送るのかは、私にはすぐには解りかねた。が、やがて彼ら一人一人の顔を見るにつれ、彼等の敵意の原因が、彼らの中の一番格上と思われる者が、我々の出現の所為で水しぶきを浴びてずぶ濡れになった為に御機嫌を損ねたからだと知った。
「ひゃあ、まさか下が水になっておるとはな!」竜王は目の前の水面から顔を出し、開口一番首を左右に振って雫を飛ばす。
「ちょっと、ちょっとちょっと!」あちこちに水を飛ばすのをやめさせようと、ローブの裾を引っ張った。これ以上ケンカを売ってもろくな事になりゃしないのは目に見えている。
「何だ?」訝しむ竜王に私が無言で後ろを指さすと、指の動きに合わせて後ろを振り返る。一行が渋い顔をして我々を見ているのに漸く気付いて、竜王は水の中から体を起こした。
「おお、済まんな」
文字通り水も滴る良い男、の騎士団長らしき人物が、竜王が伸ばした手には目も向けずに剣の切っ先を向け、それから遅れて顔を出したユークァルに鋭い一瞥をくれた。だが、ユークァルはユークァルで口からぴゅーっと水を吹き出し、更に騎士の怒りを煽るのであった。あーあーあー。しーらない。
「ここは妖魔公の所領地。下級妖魔如きの立ち入る事罷りならん。ましてや人間の入って良い所ではないわ、早々に立ち去れい」
「誰が下級妖魔だ誰が」妖魔騎士が手を出す様子がないのを見て取ると、竜王は行き場のない手を横に払った。「それより、手を貸す気が無いのならそこを退いてくれんか。このままずっと浸かっていたら風邪をひいてしまうわ。端的に言うと邪魔」
「退け? だと? 下級妖魔の分際で! 身の程思い知らせてくれる!」
妖魔の騎士が振り下ろした刃を、しかし竜王は絶妙なタイミングで鎖を翳して受け止めた。刃と鎖が激しくぶつかって火花を散らすと鎖にひびが入り、強く引っ張ると粉々に砕ける。竜王は破顔一笑、にこやかに妖魔騎士の肩を叩いた。
「おお、有り難い。よくぞ我が軛を断ってくれたな。これが邪魔で邪魔で困っておったのだ、感謝するぞ。ところで貴様、ついでで悪いが、この辺りの地理に疎いのでな、最寄りの町が何処にあるのか教えてくれぬか?」
「くっ、お、おのれ…よくも陛下の御前で恥をかかせてくれたな!」妖魔の騎士は顔を紅潮させてたじろいだ。全く怖れも憧れも抱かれず、近所のタバコ屋の老婆の如くぞんざいに扱われたのが余程誇りを傷付けられたと見える。妖魔騎士は肩に置かれた手を振り払うと、「憶えておれ!」とありがちな捨てゼリフを吐き、とっとと一行を先導して去っていった。勿論、最後に、ここから今すぐ立ち去れ、と付け加えてから。
「何じゃ、あ奴ら。妖魔如きの分際で偉そうに…ケチケチケチケチケ…へーっくしょい!」
ともかくも、今度も無事には済まなさそうな事だけは、確かなようであった。
妖魔公の領土から出ていけと言われてはみたものの、幼いユークァルを連れた我々が、広い領土の端から端まで一日二日でひとっ飛び、という訳にはやはり行かない。我々は連日の強行軍でへとへとに疲れ切っていたし、何よりここは、単調な風景故に、時々自分達が何処に向かって歩いているのか解らなくなってしまうのだ。
我々はひとまずキャンプを張る事にした。ちっとも風景が変わらないので、いい加減嫌気が差したのだ。空は薄暗く曇っていて、陽光差す様子も日が暮れる様子も無い。我々は、まず火にくべる薪を探す事にした。
「この森…陰気臭いと思わんか?」最初に口を開いたのは竜王だった。「薪になるような小枝も落ちておらん」
「変な森ですね」ユークァルが同意する。見回してみれば、此処は実に不思議な森であった。生えている植物が珍しいから、ではない。植生が、そして木々の生え方がおかしいのだ。
「自然の森とは思えませんね…」
「下草すら、生えておらん。いや、あるにはあるが、狙って配置したかの如くだ。しかも決まった種類の草ばかり。どうなっておるのだ?」
竜王はそう言うなり、手を伸ばして木の枝をへし折った。
「…何じゃ? これは」
へし折った木の枝を差し出したので、手に取る。枝は木の温もりの代わりに、ひんやりとした石の感触を伝えて来た。
「細工物…だ…」
「瑪瑙ですね」ユークァルが受け取った小枝を翳した。
「気が狂っとる!」竜王は荒々しく瑪瑙の幹を蹴った。木が揺れたが、木の葉も、虫も落ちて来なかった。「この木も、これも、この草もだ! これを作った奴は気が触れておるに違いない! 無駄の極致だ! 世界の全てが自分の思うが儘で無ければ気が済まぬと言わんばかりだ!」
「貴男みたいですね」私が真面目に取り合わなかったのに憤慨して、竜王は喚いた。
「何だと! 私はな、今まで自分が生きてきて、思う通りになった事など唯の一度も無いわ! ここは…まるで、まるであのニヴルヘイムの様だ。誰も、何もまともに生きちゃ居ない」竜王は渋面を一杯に作って吐き捨てた。「早くここを出よう。寒気がする」
とはいえ、皆疲れていて、挙げ句水の中に飛び込んだおかげで体を冷やしていたので、今すぐに歩き回るという訳には行かなかった。無理矢理手持ちの寄せ集めで火を起こし、毛布にくるまって暖を取る。ユークァルの髪の毛を良く確認してからタオルで拭いてやり、梳ってやる。肌が冷たくて、さっきの石肌の様だ。私はユークァルの肩を抱き寄せ、火元に寄せてやった。ユークァルも私達も、火の灯る様を、ここに生きているものは私達と火の他に無いのを確かめるかにじっと見つめていた。皆、この世界の無機質さに耐えられなかったのだ。
ユークァルが、突然肩に掛かった私の手をはね除けた。
「あのぉ……」
聞き覚えのない、少年の声。
「誰だ!」手元の松明をつかみ、声のする方に火を向ける。瑪瑙の森が火の光を反射して不思議な煌めきを作る。
木陰に潜む誰かが動くか動かないかのうちに、ユークァルが素早く草むらに飛び込んだ。
「う、うひゃあ! や、やめてぇ〜! か、カンベンしてよ…オイラ、何にもしないからさぁ」
「何じゃお前は?」
「オ、オレオルフェ。よ、よろしくな、ヨソ者さん」
木陰からユークァルにナイフを突き立てられて出てきたのは、額に一本角を生やしたペガタウルスの少年であった。
私はユークァルにナイフをあてがうのをやめる様指示した後、ペガタウルスを手招きした。彼は我々が自分に害をなす意志の無い事を知ると、手招きに応じて恐る恐る近付いて来た。
「よ、よお」少年は強張った愛想笑いを浮かべて挨拶した。我々も軽く会釈する。
「あんた達、よその世界から来たんだろ? 見た目で解るよ」
「ああ、そうだが?」
「あの、お願いがあるんだけどさ」オルフェと名乗ったペガタウルスは、意を決して一歩前に進み出た。
「あんた達、オイラを一緒にこの世界から連れ出してくれよ」
「何だ? 突然。どういうつもりだ?」
竜王が凄んだので、オルフェはまた少しあとずさった。
「ま、まあ。それより、訳を聞かせてごらん。もっとこちらに来なさい」
私の手招きに応じて、オルフェはまた一歩だけ、明かりの中に踏み込んだ。それから、そこにしゃがみ込んで、今度は堰を切ったように話し出した。
「オレ、もうこんな世界いるのやなんだよ。ここじゃどんな風に生まれついたかが全てでさ、後からどんなに努力したって、それが生まれつきでなきゃ何の意味もないし誰も認めやしない。そもそも生まれつき凄い奴には努力したって一生追い付けっこない。ここにいる限り、オイラみたいな出来損ないは一生下っぱ妖魔なのさ」
「はあ? 何だそりゃ。誰がそんな事決めたんだ?」
「この世界を治めてる、妖魔公がそう決めたんだ、だからしょうがないさ」
「何じゃ? その妖魔公とやらは」
「さっきの御一行様ですよ」私は素早く耳打ちする。
「なるほどな。だが貴様等、それで良く反乱を起こさぬものだな。誰も不満に思っておらんのか?」
「不満なんか抱いちゃいないさ、だって皆外の世界なんか知らないし、興味無いもの。これが当たり前だと思ってるのさ。それに…例え不満を持ってたって、妖魔公が怖くて誰もそんな事言えっこないよ…」
「フン、根性無しどもめ。それではアリンコと同じではないか」竜王はぶつくさ不平をたれた。「ニヴルヘイムと言いここと言い、どこも大して変わらんな。なあ、世界とは、どこもかしこも皆このような物なのか?」
「貴男が外の世界を知ったきっかけは?」
私は竜王を無視してオルフェに話を続けさせた。此処の様な閉ざされた、画一的な価値観しか持ち得ない筈の世界で、オルフェが外の世界を知り、努力や自由という概念を得たのには、何らかの外的要素が加えられたからだとしか思えなかった。この世界に外界との交流があるとは殆ど考えられないから、もしかするとこれが次の世界への旅の扉のヒントになるかもしれない。
「妖魔公が出来の悪い美術品を近くの溶鉱炉に焼却処分するんだ。俺達下っぱ妖魔は、ホントは近寄っちゃいけない事になってるんだけど。でも、それが人間には有難いらしくてさ、出来損ないの美術品を拾いに来て、自分達の世界でそいつを高値で売りさばいてるんだって。元値がタダだから大もうけってわけ。ウマい商売だよネ。最初はオイラも、妖魔の掟に従って溶鉱炉には近付かなかったんだけど、ホラ、怖いもの見たさってあンだろ? のぞいてるうちに声をかけられて、そこで人間達と色々話をするようになったんだ。でさ、外の世界はこんなだとか、こんなおもしろいものがある、とか。俺は生まれた時は貧乏だったけど、商売で今じゃお城みたいな家に住んでる、とかね。オイラが外の世界を知らないのに人間達はびっくりしてた。…オイラ、うらやましくなっちゃってさ。人間達は一緒に来いよ、って言ってくれたけど、オイラには、とてもじゃないけどそんな恐ろしいこと出来なかったよ。ただでさえ禁を破って溶鉱炉をのぞきに来てるのに、もしこの世界を抜け出したなんてことが妖魔公にバレたら、地の果てまで追っかけられて八つ裂きにされちゃうよ」
「…ふむ。事情は解った。だが、何故、今、我々なのだ?」
「もう我慢できないんだよ。あんた達を見かけて、オレ、ピーンと来たんだ。あんた達、あの妖魔公に睨まれても平気だったじゃないか。こいつら、もしかしたらメチャクチャ強い奴かもしれないぞ、ってね。こういう奴らに付いて行けば、オイラも自由になれるかもしれないって。何でもするよ、荷物持ちでも何でもさ。だから、お願いだ、オイラを連れてっておくれよ」
オルフェの懇願に、私は彼の頼みを聞いてやりたいと思った。だが、竜王はそれを制して先に答えた。
「オルフェとやら、良いのか? そんな事で。貴様はここから抜け出せればそれで良いと思っておるようだが、その考えは甘いのではないか? その妖魔公と言う奴は裏切り者を許さない、厳しい奴なのだろう? 抜け出たら抜け出たで、貴様は追っ手に怯えながら暮らさねばならんのではないか? それに、貴様がそんな負け犬根性でここを出て行く限り、貴様は一生その妖魔公とやらの影に怯えながら生きねばならん。もしもお前が本当の自由を手に入れたいと願うのならば、自らの血で贖え。自らの力で妖魔の掟とやらを克服してみるが良い」
全てを聞き終えると、オルフェは弱々しくうなだれた。
「そんな…ダメなのか…やっと、勇気を出してここから出てこうって決めたのに…」
「誰が駄目だと言った?」
「え?」オルフェが顔を上げ、目を真ん丸くした。白い手の上に蒼い手が重ねられ、白い手を握り締めた。蒼い口角が悪戯げに吊り上がる。
「そんな下らん掟はぶち壊してしまえ。ちょうどあ奴らのやり口に腹を立てていた所だ。貴様のすずめの涙みたいな貧弱な勇気に免じて、力を貸してやろうではないか。だが、代償は高く付くぞ」
オルフェは顔を明るく輝かせた。「ホントにホント!?」
「ああ、本当だともさ。私はたまにしか嘘は吐かん」
「………」
「やったぁ! やったあぁ!」火の周りで唯独り、陽気にギャロップを踏む少年。陰気臭かったその場がほんの少し明るくなった。
「オルフェとやら、だが貴様案外愚か者ではないようだな。臆病は蛮勇に優る、とは言ったものだ」
「え?」
訳が解らぬといった面持ちのオルフェを一瞥し、竜王は戯けたように肩を竦めた。「人間達を鵜呑みにして付いて行っておったら、お前は今頃その連中に見せ物小屋に売り飛ばされておったに違いなかったからさ」
「では、まず連中をぶちのめす方法を考えよう。奴らは何処に住んでおるのだ?」
「はいはいはーい!」オルフェは早速手を差し上げた。「針の城っていうでっかい城だよ。凄くでっかい木なんだ。昔は茶色の幹に緑の葉っぱが生えてたんだけど、それが美しくないからって妖魔公が根っこの街を焼き払って木の養分にしたんだ。焼き払われて死んだ妖魔達の血を吸った青い薔薇の蔓が巻き付く、紫色の幹の幻想的なお城さ」
「ふむ…、その何とか言う城は木で出来ているのか。なら…」
「針の城、だよ」
「針の城…か、そいつを焼き払ってしまえ。我々が内部から連中を攻撃して城をメチャクチャにしてやるから、我々が合図したら貴様は城に火を放て。その針の城とやらはでっかい木なんだろう? 油を撒いておけばさぞかし良く燃える事だろうて」
「そ、そんなメチャクチャな! 良くそんな事思いつくなあ!」オルフェは目を瞠った。オルフェにとっては冒涜中の冒涜、言われるまでは脳裏を掠めもしなかったに違いない。
「この人は、こういう人です」
「黙れハーゴン、余計なお世話だ」竜王は私を牽制してから続けた。「いいか、どんなに無茶をやるにしても、その無茶を通す為には確実な積み重ねが必要だ。一見奇跡に見えるような事も、その裏には、その奇跡を成立させる要因が絶対に存在している。奇跡は待っていても起らん。起こすものだ」
我々は肯いた。
「まず、火を点けるには油が相当要るな。あと、沢山の柴やら枯れ草が欲しいところだ。勿論薪も要るが………おいオルフェ、手に入るのか? まさか他の木も全部瑪瑙や水晶で出来ている訳ではないだろうな?」
「ううん、この森だけ」
「油を染み込ませる為の布がいりますね」ユークァルだけは相変わらず、マイペース且つ冷静だ。相も変わらず、逆らうことなく一同の意見を受け容れる。彼女が暗殺者だと言うことを、時折忘れそうになる。
「いいところに気付いたな。ユークァル。よし、どっかからかっぱらって来い」
「火を付けるのは一ヶ所だけではいけませんね。数ヶ所ほぼ同時に火を放てば、すぐに火を消されることはないでしょう」
「枝の方から火を放たんとな。しかも途中で消えては困る。…おい、ハーゴン、ぼーっとしてるな」
「あ、は、はい。…そ、そうですね…。外に火を点けるには、火を点け易い場所と時間を考えないといけませんね。どうします? …オルフェ、城の見取り図はないのですか?」
「我々が内部に進入して、注意を内部に引き付けている間に外周部に火を放てばいいではないか」
「またそんな無茶苦茶を…」私は無茶加減を窘めながらも、いつの間にかすっかりノリノリでその無茶な計画に参加している。「でも、準備の時間はある程度考えておきたいところですね。見回りの時間が解れば、その間にある程度準備は出来るでしょう。とにかく、内部に侵入なんて無茶苦茶なことは無しですよ。ただでさえ力を封印されているというのに、多勢に無勢過ぎます」
「無茶とは何だ、無茶とは」竜王は凄艶な、としか他に例えようの無い笑みを敷く。畏怖と魅了が混在する、何とも不可思議な笑みだった。どうも、あの目で見られるのは苦手だ。「ククク、久々に血が疼くわ」
「あ、あの、あのあの…」
「ん、どうしたオルフェとやら」
「どうしました?」私達の答えが余りにも見事にハモっていたので、オルフェは刹那言い淀む。
「あ、あ……その、火ぃ、つけちゃうの?」
半泣きのオルフェに向かって、私達はさも当たり前のように答えた。
「やらないのか?」
「やらないんですか?」
「やらないんですか…」
オルフェは半泣きの侭、情けない顔を何度も縦に振った。
決行の朝。
とはいえ、この世界には昼と夜の区別は無い。太陽もなければ星もなく、空は唯陰鬱で薄暗い雲に覆われるのみ。
竜王は前の日に森で引っこ抜いて来た木――と言っても、瑪瑙の塊なのだが――を叩き折って作った丸太を脇に抱えている。その出で立ちはお世辞にも、美しいとは言い難い。
「はちまきでもしたら似合いそうですね」オルフェががちがちに緊張しているのを見取って、私は彼を安心させようと軽口を叩いた。
「何だ、そんなにおかしいかこの格好が。確かにこいつは不格好だし重たいし、便の良い武器とは言えん。だが、これしかないのだから仕方が無かろう。こら、貴様笑うな」
「ご、ゴメン…」
私は怖じ気づくオルフェの背を軽く叩いた。「そんなにびくびくする必要はありませんよ、取って喰うって訳じゃないんだから。くれぐれも、気を付けて下さいね」
「う、うん。アリガト」オルフェは小さく頷く。励ます位しかしてやれないのが、今の無力な己には、辛い。
「いいか、ユークァル。こ奴のお守り、しかと任せるからな」竜王がユークァルの肩をぽんと叩く。ユークァルは礼によって何の疑問も抱くでなく、首肯して主人に返す。
「な、なんで私が彼女にお守りされなくてはいけないんですか…」
「当たり前だろう、今の貴様が、この娘ほど戦えるとでも言うのか?」
その通りだったので、私は口を噤むしかなかった。
「絶対に離ればなれになるんじゃないぞ。いいな」
ユークァルは素直に頷いて、小さな手で私の手を握った。
「あたしが護りますから、ちゃんと付いて来て下さいね」
私は力無く微笑んで、その手を握り返した。
我々は城門前に立ち尽くし、針の城を見上げていた。圧倒的な存在感を持ってそびえ立つ紫紺の城は 精緻な細工を施された門の奥にその姿を垣間見せる。辺りはどことなく退廃的で、気怠げな空気に満ちている。
「やっぱ、何時見てもすげぇや……」
「凄い、ですね…」感嘆の声を発するしか無く、馬鹿みたいに門を見上げている私達を、竜王は鼻で笑った。
「ふん、妖魔公とやらは門というものを自分の城の飾りにしか思っておらぬらしい。なら都合が良いわ。良いか、見ておれ。門という物はな…」
言うや、数歩下がると瑪瑙の丸太ん棒を振り上げる。その足が、砂埃を撒き散らしながら地を蹴って駆出した。
「え、あ、ちょちょちょちょっと? え、待って? いや、やめてえぇ〜っ!!」絶叫するオルフェ。
「何でですか?」ボケるユークァル。
「無駄ですよ…」悟る私。
「こうするためにあるんだーっ!」
竜王は丸太ん棒を袈裟懸けに振り下ろすと、華奢な作りの鉄格子の扉をぶち破って突っ込んだ! けたたましい金属の悲鳴が辺りに響き渡り、宣戦布告の角笛代わりとなる。
「ぐうぅうぉーりゃあぁーっ!!」
「な、何だあいつは? …わあっ!」
「グハッ!」
瑪瑙の丸太ん棒を振り回し、寄ってきた雑魚妖魔どもを吹っ飛ばす。吹き飛ばされた妖魔達は針の城の壁一面に叩き付けられ、豪快に内臓を振りまいた。騒々しい物音を聞きつけ、直ぐに妖魔騎士達が駆けつける。
「貴様等は先刻の、森への侵入者、がはああああああっ!」言い終わるか終わらないかのうちに、銀の鎧が壁に叩き付けられてめり込み、生身の浮き彫り一丁あがり。
「アホウどもめ、真の美しさが何か、貴様等のその身を以て示してくれよう!」
「ほざけ、邪妖が!」
「邪妖とは!」
妖魔騎士達が細身の剣を抜き放ったのを横目に見て取り、口角が吊り上がる。爛々と光を放つ黄金。面に浮かぶはあの凄絶な、笑み。
「誉め言葉と受け取っておこうぞ!」
言うが早いか、竜王は無骨な丸太ん棒を振り下ろして妖魔騎士の頭上に叩き付ける。妖魔騎士達は次々に頭を砕かれ、青い血に混じって脳漿を撒き散らした。
「貴様等はそうしている方が余程美しい。……だがやはり、血は赤くなくてはそそらんな」
飛び散った妖魔達の血は、鉄の匂いの代わりに、花の仄かな芳香を辺りに漂わせた。頬に付いた青い血を拭って、口に含む。
「ふん、芥子の香りがする。反吐が出るわ」
竜王は唾ごと青い血を吐き捨てると、素足で妖魔達の脳管を踏み躙った。
「たくもう…人には散々、離ればなれになるんじゃないぞ、な〜んて言っておきながら、自分はさっさと奥に行ってしまってるじゃないか」
偉そうに説教をたれていた当の本人が勝手に敵地深く突っ込んでいってしまっては、我々が離れ離れにならぬ方がおかしい、というのが道理である。歩く先々で妖魔達の潰れた死体が辺りを蒼く染めていて、それは残虐かつグロテスク極まりない光景の筈、なのだが、青い血の色や非常識なまでの死体の数が現実味を失わせた所為なのか、奇妙に幻想的な眺めと映っていた。私はユークァルの手を引いて、とぼとぼと潰れた遺体を目印にの後を辿って行った。
「それにしても、何処まで行ってしまったのでしょうね…ひっ!」
目の前を、サーベルの刃が遮った。後から追いかけてきた妖魔の一群が、私達を待ち伏せていたのだ。再び振りかぶられたサーベルを躱し、後じさる。杖の一つもあれば話は別だが、素手ではどうしようもない。
逃げようと、踵を返した時だった。
生暖かい液体が足下を濡らし、足を取られる。
体制を立て直して足下を見下ろすと、先程までサーベルを振り回していた妖魔騎士が、ユークァルの手で肉の塊と化していた。
「ユー、クァル…」
頬とその手をを妖魔の血に染めるユークァルは、凡百の妖魔達より妖艶で、美しかった。
この娘は、私が仕える魔族の王と同質の生き物なのだ。
私は、改めて、己が恐るべき領域に踏み込んでいたのを悟って戦いた。
ユークァルは草でも刈っていくように、次々と妖魔達を屠って行った。その身は返り血にまみれ、頬には血に濡れた髪がまとわりつく。
殺す為に生まれて来た、否、殺す為に造り替えられた、存在。私は彼女に圧倒されていた。何と美しくも怖ろしいのだろう。そうとしか、形容し難い。私は、甘美な戦慄に打たれていた。私は唯彼女を見ているだけ、追うだけが精一杯だった。嗚呼、幾星霜積み重ねて会得した知識も、知恵も、こんな聖なる単純さの中においては何と無力なのだろう。魔力のない己など、唯のひょろりと細く理屈っぽいだけの役立たずではないか。蒼が踊る。散る。花開いてはまた、散る。散華。命散り逝く残酷なまでの、美。何一つ無駄の無い、完璧な所作。殺人の為にのみ造り替えられた、美しい自動人形。
機械人形の動きが、奇妙に歪んだ。半身に掛かる不意の圧力に蹌踉めく。
眼前で迸る朱。そして、蒼。膝を付く少女。
完璧が、完璧でなくなった瞬間。
「ユークァル!」駆け寄る私を制するようにユークァルが壁に手を付き、起き上がる。ナイフの先には蒼い血、そして、頭髪を振り乱せし、毒の牙持てる妖魔の屍。
私を庇ったユークァルが怪我を負ってしまったのだ。
危険だ。
これで我々の生存確率は、また数%落ちた。
歯痒い。自分の無力さが歯痒い。
ユークァルの傷口から毒を適当に吸い出し、囚人服を適当に引き裂いて傷口を塞いでやる。ユークァルは痛みを訴えなかったが、やはり僅かに傷ついた足がいざっている。
行く手の通路からまた足音が響いて来た。これ以上は無理だ。戦えぬ。
だがユークァルは、あのナイフを身構えていた。
「だめです、引き返しましょう!」
私はユークァルの腕を強く引いた。
一瞬、彼女の腕が抗うように引かれた。私の中を、或る怖れが揺さぶる。彼女が、このまま私の腕を振り解いて勝ち目無き戦いに身を投じるのではないか、否、私には到底理解する事の出来ない、遠い世界へ、手の届かない所へ行ってしまうのではないかと。私の腕は、彼女を引き留めるには余りにもか細く、力無い。
だが、すぐに彼女は無抵抗に、私に手を引かれていった。
行った道を引き返す。走って、走って、階段を飛び降り、廊下を滑り、広間を駆け抜ける。死への怖れが、迫り来る足音が、私達を急き立てていた。死と隣り合わせの生を歩んで来たが故に、死ぬのが怖いとは昔から思っていなかったつもりだった。だが、死ぬ事そのものよりも、再び与えられた可能性を失う怖れが、私を駆り立てた。初めて、何かを失いたくないとそう思わせた。
ユークァルの足下が危うげになっているのに私は気付いた。
「大丈夫ですか? 足は、痛くないですか?」
「平気です。ところで…痛いって、何ですか?」
私は愚かな質問をしたのを悔やんだ。彼女に痛覚はないのだ。平気だと言い張る彼女を無理矢理負ぶって、私は針の城を縦横に駆けた。息を切らせ、追っ手から、高鳴る跫音から逃れようと。
「ここ…どこですか?」
ユークァルに問われて、初めて辺りを見回して、私は愕然とした。道に迷っていたのだ。恥ずかしくて、私は彼女に答えてやる事が出来なかった。一体今の今まで、私は何をやっていたのだろう? まったくもって私の方が足手まといだ。私は死にたいのか? いや、そもそも、どうしたいのだ?
私達は途方に暮れてしまった。だが、死神達は、確実に我々を死の淵へと追い詰めていた。妖魔達の気配がひたひたと、一歩、また一歩と近付きつつある。ああ、神よ、私にもう一時の、猶予を賜りとう御座います。
追い詰められて左の角を曲がると、道の途中に古びた扉が視界に入った。
「あ、あれだ!」倉庫らしき扉を見付けて、駆け寄る。
「開きません。鍵がかかってます」背後からは既に、足音が聞こえてくる。
「あ、開けられませんか?」
「やってみます」
こういう時に彼女はうってつけの人材だった。如何なる時にも決して動揺する事無く、すべき事を確実にこなしていく。足音がかなり反響するようになった頃、ユークァルは私に南京錠を手渡した。「開きました」
「よし、入ろう!」
「倉庫の鍵が開いています」
「愚かな連中が、せっぱ詰まったか。よし、手分けして倉庫を探せ」
確かに、愚かな選択ではあった。私達は自ら袋小路にはまりに行ったようなものだった。
金属がぶつかり合い、蝶番が軋む音が辺りに響く。殆ど出ない唾を飲む。呼吸が、荒くなる。祈ろうとして、事の無意味さに気付く。祈ったところで何が出来よう。私は棄教者だ。私は組んだ手を解き、暗闇の一角に手を伸ばした。まだ、ここで、こんな所で死ぬわけにはいかない。二人して倉庫の棚の中に身を潜める。だが、跫音は着実に、こちらへと近付いてくる死神の到来を報せている。
ああ、どうか来ないでくれ。神よ…貴方に慈悲あらば、どうか私を、否、ユークァルだけでも妖魔の手からお守り下さい。
だが、世界は無情であった。僅かな隙間から漏れ出る光は、私の姿を余すところ無く映し出して行く。妖魔達の忌々しげに舌を打つ様。こんな時、人はどうするのだろう。私は苦笑いするのが精一杯だった。 無論、笑ったところで許してくれる訳はない。私は手首を掴まれて引きずり出され、袈裟懸けの一閃に打ち倒される――筈だった。
本能とは、実に怖ろしいものだ。
無意識の内に振り上げていた腕に走る、激しい衝撃。耳を劈く金属音、眩い光。不意を打たれたらしく呻く妖魔。恐る恐る振り上げた腕を降ろすと、手錠に一筋、刻まれた溝から、甲高い金属音を残して、手錠は抜け落ちた。軽く手首を振ってみる。無事だ。片方の枷が完全に抜け落ちたのに呼応して、もう片方の手錠も魔力を失い、床に転がり落ちる。
我が魔力を縛る枷は、遂に砕け散った。
「…ちぃっ! おのれ…今度こそ、死ねぇ!」
四肢に封じられていた力が漲る。力を抑えようにも、霊気となって抑え切れぬ程に端から溢れ出る。魔力が尾てい骨から脊髄を通じて螺旋を描きながら頭の芯から天に突き抜けて迸り、焼け付く様な熱と光と快楽がこの身を支配する。
かつてこの様な感覚が私を突き動かした事があっただろうか?
心地好い震えが止まらない。
今ここでなら、抑える必要も無い。
解き放て! 解き放つのだ!
全てを!
全部だ!
「イオナズゥーンッ!!」
属を持たない光と熱の奔流に、妖魔の肉片は形を留める事もなく、四散した。
理性のたがを自らの手で外し、私はおそらく、初めて、破壊の快楽というものを知った。
ようやく力を取り戻せた、という安堵が、そして、無力でなくなった自分を許せた余裕が、私を元気づけてくれた。
「ユークァル、足を出して」
キアリーとベホマの呪文で傷を治してやる。ユークァルの足は傷が塞がり、以前の様に自然に動くようになった。不思議そうに足を振るユークァルの頭を、緩く撫ぜてやる。
今度は、私がユークァルの手を取って歩く番だった。
そのころ。
針の城外周ではオルフェが城に火を放つ準備を着々とこなしていた。枯れ枝や布切れなど、燃えそうなものを片っ端から木の節に詰め、油を針の城にかける。襲撃をかける前にも、一同半日仕事でこっそり根元周辺に枯れ枝をつんだり、あちこちから油やら薪やら枯れ枝やらをかき集めておいたりして、この時の為に備えていたのだ。
遠くから話し声が聞こえてきたので、オルフェは身を竦ませた。
「たく、何が妖魔公だ! こちとら、魔王級の脱獄者2人組を追っかけてるってのによ…」
「美しくないから城には通さん、用件だけ伝えておくと 12時間も門の前で待たされて、挙げ句の果てに『この世界には例え誰であろうが余所者は一切立ち入らせぬ。貴殿等も同様、さっさと立ち去られるが良い』だとさ! こんな城、奴らにでも潰されちまえばいい! 全く、竜王様々だぜ!」
「あぁ、ホントだぜけったくそわりぃ!」
ヨソモノだ。オルフェは彼等を観察する。
羽根飾り付の真鍮性の兜、鎧もきっと真鍮に違いない。オルフェが見慣れて来た妖魔騎士達のそれの様には、煌びやかでもなければ精緻な細工も施されてはいない。異邦者の腰にぶら下がる幅広の剣は、華奢な細身の剣を見慣れたオルフェには無骨に思えた。
「奴ら、自分達の城が心配じゃないのかね?」片割れが、肩を竦めた。
「そんだけ自分達に自信があるってこったろ?」もう一方が鼻息荒く上腕二頭筋を盛り上げた。「自信があるなら代わりにやっつけて欲しいもんだ。あのモヤシ共に出来るもんならな!」
「あの…」オルフェはひょっこり顔を出す。
「何だ?」
「その、何とかって言う囚人のことなんだけど…」
「やあ! 何だ、この世界にも友好的な妖魔が居るんじゃないか! 俺の名はニュロン、天空人で根の国の看守だ。ヨロシク! キミの名は何て言うんだい?」
強く握手を求められて、未だ余所者に慣れないオルフェはたじろいた。「あ、お、オイラはオルフェ。ヨロシク」
「俺はツァディ。ヨロシクな!」上腕二頭筋もりもりの方がオルフェの手を上下に激しく振った。オルフェは相手の馬鹿力に釣られて身体ごと握手させられた。端から見たらオモチャの握手人形みたいだったに違いない。「ところで、オルフェ君はこいつらのことについて何か知らないか?」
オルフェは痺れる手を振り解くと、ツァディから羊皮紙を受け取って確認する。間違いない、人相書き。だがオルフェは思いっきりすっとぼけてみせた。「変な顔だね…あ、待って。思い出すから」
「ほう」ニュロンが反応した。「何でも良い、何か知っていたら教えてくれたまえ」
オルフェは天空人達の高飛車な口振りに反感を覚えたが、おくびにも出さずに人相書きを丸めてベルトに挟み込む。「…何か役に立つこと、もしかしたら教えられなくもないけど」
「何でも良いんだ、些細な事でも」
「オルフェ君、思い当たる事があるのか?」
「でもその前に、オイラやらなきゃいけないことが一杯あってさ」オルフェは値踏みするように2人の顔と瓦礫を見比べた。「こいつをほったらかしにして油を売ってると、他の上級妖魔達にお仕置きされちゃうんだ」
「やれやれ、同情するよ」ニュロンが頷く。
「奴らならやりかねんな」ツァディが腕組みした。「よし、じゃあ俺達が手伝ってやろう!」
そらきた、しめしめ。心の中で舌を出す。
「実はさあ、この枯れ草と枯れ枝を、そことそこと下のうろの中に放り込んで欲しいんだ…まだあそこに一杯積んであるんだけど、いいかなあ?」
天空人達は、山と積まれた柴と枯れ草の山をしげしげと眺めた。
「奴ら…これを全部片付けろってキミに言ったのか?」
「まあね」オルフェは軽く柴の山を叩いた。「さすがに、ここまで運ぶのに時間がかかっちゃってさあ」
「こりゃ大変だな、手分けするか…、ニュロン、そっち持ってくれ」
「あいよ」天空人達が手伝うのを見下ろしながら、オルフェは、もし何故この枯れ草やら薪やらを城のあちこちに詰め込んでいるのかを知ったら、こいつらは果たして驚くだろうか、それとも喜ぶだろうかと考えていた。
オルフェの手が疎かになりかけていた時だった。
針の城が、生まれて初めて揺らいだ。
耳をつんざく爆音、そして振動がこの世界中に鳴り響いた。爆風と共に城の一角が抉られ、煙が吹き出す。きな臭い匂いが辺りに広がり、やがて煙が収っていくと、そこには、端から見ても解るほどの妖気をまとった魔が、自ら招いた破壊の余韻に酔いしれている様があった。オルフェは半ば好奇心、半分は妖気に引き付けられる魔族特有の本能に突き動かされて覗き込んだ。
魔族が頭をゆっくりと上に向け、オルフェと偶然、目があった。
心底までの戦慄がオルフェを捉えた。あれが、嘗て同じ火を囲み、自分に同情を寄せてくれたかの人と、同じ人物だと言うのか。あれこそ、天空人達が魔王と呼んだそのものではないか。
魔族の男はゆっくりと頭を巡らし、その眼で天空人達2人組を捉えた。
「ほ、本物だ! ヤ、ヤベエ!」
「ヒエーッ! マ、マ、マジだーっ!」天空人達は怖れ戦き、一目散に逃げ出した!
オルフェだって、逃げ出したかった。逃げ出したかったが、かいなが、肢が震えて言うことを聞かなかった。オルフェは必死に針の城にしがみつき、呪い言のように自らに言い聞かせながら藁の山に油をぶちまけた。
「この世界から抜け出るんだ! 勇気を出せオルフェ。びびり虫のダメ妖魔で一生終わっていいのかよ! どんなにガンバッても一生報われないのに、あきらめながら生きていけるのかよオレ! 今さら引き返してもどうにもならないじゃんオレ!」
そう、今更臆病風に吹かれたって、もう帰る場所はないのだ。
オルフェは、この時ようやく自分がもはや引き返せない所まで来ている事を悟った。オルフェは作業を続けるしかなかった。それが例え、もはや己の望みでなかったのだとしても。
オルフェが臆病風に吹かれている遥か足下で、見られているのにも気付かぬ侭私は破壊活動に明け暮れていた。堅固な城の粉々に砕ける様を愉しみ、己の力に酔った。妖魔達は我が魔力の下に砕け散り、肉塊となって吹き飛んだ。笑いが止まらなかった。
辺りを吹き飛ばしながら、私は城の最も広いバルコニーの一角に出た。澱んでいた筈の大気は掻き乱され、血と芥子の匂いを辺りに散らす。その向こうに、蒼い血にまみれた竜王の姿を見付けて近付いていく。
「おお、貴様か。どうした?」
「どうしたじゃありませんよ! 勝手にどんどん奥に行ってしまって、追いかけるの大変だったんですよ」
竜王は暫し、私の変化に気を取られていたが、やがて突然火を噴くが如くに怒りだした。
「? 貴様一人か? 待て、ユークァルはどうした! まさか貴様、あのバカ娘を一人にしたのではあるまいな! 何処を見ていた! この抜け作めが!」
「何ですって! 貴方はどうなんです! 人の事言える立場ですか?! いいえ、貴方こそ裸の王様ですっ! 無茶な作戦を立て、無茶に突っ込んで!」いつもなら恥ずかしそうに俯いて失敗を恥じるところだろうが、高揚感が抜けきらぬ所為なのか、ムキになって言い返す。
「やかましいわっ! いっつもいっつもいっつもいっつもぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐち小言を言いおって。キサマはヨメいじめの姑かっ! とっととユークァルを探してこい!」
「貴男に命令される筋合いはありません! しかも貴男みたいな我が儘で乱暴者で自己中なヨメはこちらから願い下げです!」
ぎしり。地面が重みで僅かに撓む。
「そこにいたか、貴様等下等妖魔めらが! よくもまあ、此処までぶち壊してくれたな!」振動をもたらした方角に一瞥をくれると、妖魔騎士の団長が妖魔騎士達を引き連れて踊り場に降り立った所だった。
「黙れ! 貴様の主人はこの私だ。主人に命令する気か!」
「誰が貴男の僕ですか!」が、頭に血が上っているおかげで私は雑魚共にくれてやる一瞥も惜しんでケンカモードに頭を切り換えるのであった。足下が揺れようが知ったことではない。
「貴様だっ! 他に誰がおる!」
「こらーっ! そこの二人、無視するなぁー! 人の言うことを聞けーっ! 聞かんかーっ!」
「断固として拒否します!」
「貴様がこの私に意見できる身分だと思うな!」
「無視するなと言ってるだろうがー! 聞いておれば、下等妖魔の分際で偉そうなことをほざきおって!」
「勝手に決めないで戴きたい! 私は貴男を主と認めた憶えはありません!」
「何だと? 貴様如きにそんな事を言われる筋合いは…」
「キイイィッ! 行け、ブロンズプリマ!」
妖魔騎士の団長は無視されたのがよっぽど腹ただしかったらしく、ヒステリックに喚き散らして魔術棒を振り回す。見れば、身の丈6メートルはありそうな巨大な青銅製の乙女の像が、片足でくるくる回りながらこちらに近付いて来るではないか。私は後ろを指差して、注意を引こうとした。
「あ、あれ、あれあれ!」
「何があれだ。そんなもので誤魔化されると想うな! う、ぐわああ、何じゃこれは!」
人の警告を聞かないからだ、なんて言うのはよしにしよう。とにかく、巨大な青銅製の乙女が竜王をつかみ上げ、暴れるのも何のその、有無を言わさず両手で抱きかかえる!
「くそっ、放せっ! 無機物と抱き合う趣味はないわ! 妖魔どもめ、こんなものが美しいというのか。悪趣味の極みだ! 放せ! 放さんか!」ブロンズプリマの肩を拳でガシガシと殴りつけるが、この程度ではうんともすんとも言うわけがない。
「ふははは、ブロンズプリマに握り潰されて無様に死…うぐっ」
妖魔騎士の首に白い手が忍び寄り、不自然に曲がってどうと倒れる。その後ろには、ユークァルが立っていた。周りの妖魔騎士達は年端もいかぬ少女に隊長の首をへし折られたのを見て、大人げもなくユークァルに斬りかかる!
「イオナズンっ!」
一度呪句を唱えれば爆風があたりを包み、ユークァルに襲いかかる妖魔達をはじき飛ばす。が、衝撃で再び地面が揺れる。ほんの少しだが、片足で立っているブロンズプリマが傾ぐ。
好機!
私は迷う事無く、ブロンズプリマの足下にイオナズンを叩き込んだ!
再び、地面が揺れた。大きく。
叩き込んだイオナズンの御陰で、城の踊り場がちょうど半分ほど、ガクンと欠けた。だが流石は妖魔達の美意識の結晶、ブロンズのプリマ像は術の衝撃に見事耐え、怨敵をしっかと抱き留めて離そうとしなかった。その片足がゆっくりと、何もない空間に向けて傾いでいく。
「う、うわぁーっ!」
「し、しまった!」
二階建ての一軒家ほどもあるブロンズプリマにベア・ハッグで脚を極められ、抱き留められた侭、竜王はまっ逆さまに針の城を落下して行く! 私はすぐさま後を追って飛び降りた。
「うっくそ、振り解けん! こんな奴と心中するのは真っ平だ!」
「そこからパロ・スペシャルに技をスイッチするのです!」
「待たんかっ! メディアが違うわ!」
「そこで脚と腕を決めて阿修羅バスターにっ!」
「出来ん事を言うなあーっ!」
私は無我夢中で、真っ逆様に墜ちて行くブロンズプリマに飛びついた!
「アストロンッ!」
大地の口付けを受ける前に、我々の肉体は鉄の塊となって衝撃を逃がしてくれた。ようやく身体が元に戻ったので起き上がってみるとさあ大変、起きあがった真後ろで、ブロンズプリマが巨大な両腕を振り上げている。このタイミングからでは、声をかけて振り返った所でちょうどドラゴンのミンチが出来あがる計算だ。私は素早く、深く息を吸った。
「ん? どうした?」竜王は背後の危機にも気付かぬ侭、呑気に土埃を払っている。
「バシルーラッ!」
私は彼を少しばかり見くびっていた様に思う。竜王は全力で放った魔風の圧力に文字通り何処吹く風と言った風情だったが、ブロンズプリマはまともに風圧を受けて、嵐の日の看板よろしく物凄い勢いでどこかに吹っ飛んでしまった。
「おお、貴様無事であったか…それにしても何だ? いきなり。目に埃が入ったではないか」
「ええ、何とか」ブロンズプリマが巻き上げた埃で泥だらけになった顔を擦る。説明はしないでおく事にした。
「…貴様、ユークァルは?」
はっと、上を見上げる。
「上です、早く戻らないと!」
「すぐ行くぞ!」
竜王に連れられて踊り場に戻ると、彼女は黙々と、入り口付近で何某かの作業をしているところであった。
「そこ、気を付けて下さいね」
作業を終えると、ユークァルはわざわざ通路から這い蹲って出て来た。
「気を付けろだと?」
「はい、罠を仕掛けておきました」ユークァルが答えてまもなく、通路の奥から追っ手が猛然と飛び出してきた。顔、腕、足。剥き出しの部分に、一筋二筋薄い剃刀の刃で付けたような傷痕が浮かび上がって、妖魔達は顔をしかめる。
「うっ! 何だこれは」
「糸…? う、うぐぅっっ…」
肌を傷付けた妖魔達は途端に藻掻き苦しみ、次々目の前で斃れていった。
「毒を…塗ったんですか…」
ユークァルは無言で頷いた。自分を棚に上げる気は毛頭無いが、揃いも揃ってまともな連中じゃない。
殺戮は留まるところを知らなかった。
塔の周りを廻る螺旋を駆け巡り、並み居る妖魔達をなぎ祓い、叩きのめす。我らの前に妖魔無し、我らの後に妖魔無し、後の世に語り継がれるであろう凄まじい闘いであったことは疑いない。魔力迸り、丸太が宙を薙げは紫紺を蒼で染め上げる。
生命の形になぞらえた螺旋を登り切り、私達は塔の屋上へと通じる扉を開け放った!
塔の屋上で私達が見たのは、異様な光景だった。
そこだけ空気が、他の世界と違っていた。我々がさんざ掻き乱したにもかかわらず、塔の上だけは、隔絶された緩やかな時が流れていた。否、止まっていたのかもしれない。
私達は、異物なのだ。そう、知らしむるが如き、穏やかな、嫋やかな大気の流れ。
妖魔達の血を吸い上げた木の幹、咲き乱れる花々は、虫食いの痕さえない完璧なまでの容姿を誇っていた。その花畑も直ぐに我々に踏みにじられ、柔らな花弁とより一層甘くも蠱惑的な香りを辺りに放つ。
塔のテラスでは、妖魔が独り、窓の下を眺めていた。緩やかな風が吹き抜け、妖魔の長い髪を撫で、遅れて彼の甘やかな残り香を我々に運んだ。彼は我々に気付いていないようにも、気付いていても無視しているようにも見えた。
私は彼が切り出すのを待ち構えていたのだが、何時までもその様子がないのを見て取ると、しびれを切らして一歩前に進み出ようとした。
「ここは、汝ら下賤の輩の立ち入る場所ではない、去るが良い」
妖魔公が振り向きもせずに言い放ったので、竜王はかちんと来たようだった。
「シカトを決め込んでおったとは、良い根性しておるわ。貴様の命運今にも尽きなんとしておるというのに」
妖魔公は我々の様子を意にも介さず、唯風に靡く長い髪を掻き上げた。さらさらと、指先から掬われては零れ落ちる白。色素が抜け落ちた白髪とは違う、艶やかな髪だった。己は生まれながらの君主であり、己の世界に置いては全ての者が平伏すが法であると、出で立ちが、佇まいの全てが物語る。
だが、我々“ヨソモノ”は、法の外に在る。
「おい、サル山のボスザル。いいか、貴様はサル山じゃあ一番かもしれんが、お前の住むサル山の外では、でかい狼が牙を剥いているのだと嫌と言うほど思い知らせてくれるわ」
竜王は巨大な瑪瑙の棒切れを構え、睨め据えた。
「思い知った後では遅いだろうがな!」
上段に構えて大きく飛び上がるや、真っ直ぐに、妖魔公の脳天目がけて瑪瑙の丸太ん棒を振り下ろす!
だが瑪瑙の幹は、脳天を潰すどころか白髪を揺らすことさえ出来無かった。空気が張り詰め振動し、震えたのは、石の丸太と魔力の障壁がぶつかり合った所為だった。
「ぬぐぐぐ……っ!」
妖魔公は唯薄く笑うのみ。振り返りさえしない。ぎしぎしと軋む障壁はしかし、やはり微動だにしない。魔法の障壁は術者の精神力――何物にも侵されぬ、と自らを信じられる精神力に基づいている。ここは敵のテリトリーのど真ん中、明らかに私達には不利だ。相手を如何に動揺させるか、揺さぶるか。其れが、鍵になる筈。
「…?!」
其れを伝えようとする前に妖魔公が指を鳴らす。と、床を割って現れる蔓草。棘に表皮を覆われた荊の蔓は、私達の身体に巻き付き四肢を絡め取る。瑪瑙の丸太は吹き飛ばされて、真っ二つに折れた。
「うわっ!」
「何じゃ、この蔓は! くそっ、引き剥がせんっ!」
藻掻けば藻掻くほど、棘が己が身を引き裂く。蔓を引き千切ろうにも、怪我を負う覚悟で棘だらけの蔓から引き抜かなくてはならなかった。そして蔓は執拗に、益々質量を増して絡み付く。
そんな中、いち早く棘の蔓から逃れたのはユークァルだった。ユークァルは己の身にも一切構うことなく無造作に蔓を引き剥がし、手にナイフを構えて妖魔公に踊りかかった! が、その身は妖魔公の手から溢れた衝撃波にあっさり弾かれ、ゴムボールの様に二、三度弾んで、転がった。すぐ構え直すユークァル。
「こら、待て! ……無茶苦茶しおるなあの娘は! いくら痛みを感じぬからと言って…」
「…痛く、ない?」
痛くない? 確かに、彼女は痛みを感じない。ならば、どうだろう? 痛みを殺す事が出来れば。
意識を閉ざす。視覚、聴覚、嗅覚……匂い? そうだ。この部屋を満たす甘やかな香り、気怠い空気。私には思い当たるところがあった。
「これは、まやかしです! 幻術です! この匂いが、元凶です!」
「幻だと?」茨の蔓に巻き付かれながら、竜王は叫んだ。「幻だったら血なんか流すか? くそっ、この蔓取れん!」
「まったく、仕方有りませんね。それは、自分で自分を傷付けてるんです」私は嘆息すると、己の手に気を込めて、手を振りかざして見せた。「バギクロス!」
辺りに突風が巻き起こり、気怠い空気が吹き飛ばされる。辺りに見えない真空の刃が生まれ、茨の蔓はばらばらと音を立てて落ちるや、そのまま床に溶けて消えた。
「消えた…」竜王はきょとんとしていたが、すぐ立ち上がった。「ああ、本当だ、自分で掻きむしった後がある…くそっ、こんな幻術に引っかかるとは…」竜王は忌々しげに舌打ちすると、そのまま「思い知らせてくれる!」と叫ぶや否や、口を挟む間も与えず疵痕も顧みず、獲物目がけて飛びかかって行った。
「ああっ待って、ベホ…」
やれやれ、貴男だって、ユークァルのことは言えないでしょうに。私は飛びかかって行く我が主の背中を目で追うのが精一杯。
無手で襲い掛かる侵入者への妖魔公の態度は実に、冷徹にして冷淡極まりないものであった。細く骨張った指を差し上げて、白皙を歪めさえもせずに薄く、唇を開き吐息と共に呪力を噴き出す。我々一行を、身を切り刻むかの冷気、突風が襲った。身体は風に薙ぎ倒され、どうと地面に打ち付けられる。透き通った、水晶めいた氷の結晶が突風と共に飛来し、刃と化しては次々と身を切り刻み食い込んで紅い血を溢れさす。その血さえも滴り落ちる前に凍り付き、氷の結晶は熱を奪おうと冷気を体内にじわじわと送り込み、侵食して行く。見目の美しさより遥かに、危険な凍気の毒。この侭では――喰われてしまう。易々と、させはせぬ。奥歯をぎり、と強く噛み締める。
「ベギラゴン!」
言霊放たれれば紅蓮の炎、眩き舌となりて渦を巻き、気怠い空間を煌々と舐めていく。熱に煽られた花弁が舞い上がり、萎れ、焼け焦げて灰と化す。炎の舌は妖魔公を傷付ける為の物ではない、恐らくは、届くまい。だが、芥子の甘い幻惑を焼き払うには、身体に染み込み行く氷の毒を中和するには足るであろう、との読み故に放たれた、乾にして熱たる力の迸り。読みは十二分に当たっていたらしく、あの甘ったるい匂いは熱で揮発して殆ど消え失せていた。竜王が傍らに転がる無骨な武器を抱えると、火焔の舌に身を投じ、風の勢い借りて狙い違わず妖魔公の腕を捉える。壁に叩き付けた肉の引き裂かれ、躙られる様。迸る、インクにも似た色合いの蒼が床を濡らし、伝っていく。
妖魔公の美貌が、憤怒に燃えた。怒り。長い白い髪が蒼に染まり、雫を滴らせる。無事な方の手を正面に差し伸べ、血の色にも似た青紫の爪が向けられる。
赤が、迸った。
はだけた胸元から散る朱。傷は浅い。肉を抉って朱に染まった爪は直ぐに引かれ、再び呪力が迸って竜王の体を弾き飛ばす。ゴムまりのように弾んで一度床に叩き付けられた身体は、しかし宙で一回転して着地を決める。先程まで腕に食い込んでいた瑪瑙の塊を、妖魔王は疎ましげに呪の一撃で砕いて吹き飛ばした。粉々になった破片が弾き飛ばされ、風圧に乗って我々を傷付ける。私には、ユークァルを庇うのが精一杯だった。
膝ががくんと、沈み込んだ。
「!」駆け寄ると、胸元がどす黒く染まっている。苦しそうに胸元を掻きむしった所為で、爪痕が幾つも刻まれている。
「掻きむしっては行けません」胸元掻きむしる手をそっと押し退け、傷口に癒しの気を集めて注ぎ込む。息が荒い。顔色が悪い。額に汗を滲ませている処から察するに、見た目以上のダメージになっているのだろう。
「くそっ、あの野郎…闇を、注ぎ込みおった……」
目の前には、圧倒的な闇の膨張が迫っていた。闇が有効だと知って、呑込もうというのか。闇はじりじりと辺りの生命を奪っていく。舞い上がった花弁は萎れて、風に舞い粉となり辺りに飛散する。闇は又、砕ける花々の撒き散らす甘く気怠い死の匂いをも吸い込んでいく。闇は爆発的に膨れあがると、その腕を広げて我々を呑込もうとした!
光、光、光………。光在るところに又影もあり。が、影を打ち消すもまた光。一時でも、影を打ち消すほどの強い光を産み出すことが出来れば…しかし、例え力を取り戻せたとして、私に、妖魔公に対抗し得る程の強い光を生み出せようか?
「光…ですか?」
ユークァルの問い掛けに、私は言葉に詰まりかけた。ユークァルは心が読めるのか? が、闇は目前に迫っている。私がユークァルの視線の先に視線を重ねると、そこには砕けた瑪瑙の破片が散らばっていた。私は頷いた。ユークァルも黒曜石のナイフを翳す。
闇が我々を包み込もうと広がる瞬間、私は呪文を唱えた!
「ニフラム!」
闇の中生まれた、か細い柔らかい光。其れはやがて加速度的に空間に占める領域を広げて行く。闇は尚も我々を包み込むが、光を拾った欠片が光を反射して、闇より決して強くはない光を助けてくれる。
突如、身を屈めていた竜王が、光の欠片の一つを握り締めて闇の中に飛び込んだ! 光を発し切り、弱まりつつはあるが未だ失われていない光の源を、私は欠片の一つに急いで向けた。闇の中、尖った瑪瑙の欠片は三日月の如く煌めいて、闇を裂く。
「な…あ、り得ぬ!」
「くたばれ、ヴィジュアル系〜!」
「ちょっと、今の、ひがみ入ってましたよね…」
「やかまし!」尖った瑪瑙の欠片を肩口に叩き込めば、蒼い血が辺りに迸り、闇が薄れた。苦悶に貌を歪める妖魔公が蹌踉めきながら後じさるのを追って、竜王は容赦なく体当たり気味にエルボーを叩き込んだ!
べこ。
…べこ?
「あ、穴が開きましたね」
「うわぁー! またかい!」
タックルの衝撃で木の壁がぶち抜かれ、二人は宙に投げ出されてしまった。そのまま妖魔公は真っ逆様に塔を落ちていった。所々で木の幹にバウンドして、落ちながら。竜王は翼を広げ、バサバサ羽ばたきながら舞い戻って来る。
「偉そうにしおって、空も飛べないのかふふんふん♪ 一件落着だな、ざまあみやがれコンコンチキが」
「コンコンチキって一体……げほ、げほっ………それにしても、脆かったですね…そう言えば」
「何、ニヴルヘイムと同じさ」木の幹を軽く叩く。鈍い音だ。「魔族の血なんぞ吸っていたからおかしくなったのだろうよ」
「そういうものなんですかねぇ」議論しても答えは出そうにない。結果良ければ全て良し、といったところだろうか。ふと、私はユークァルに向き直る。「ユークァル、何故私の考えていることが解ったんですか?」
ユークァルは不思議そうに首を傾げ、相変わらずの無表情で私に答えた。「唇を動かしていたんです。あたし、読唇術できるから」
「あ、そう……」
「さ、火を付けるぞ!」
「楽しそうに言うことですか」別段窘めるでもないのだが、半ば癖になっている。私は窓の外に目をやった。「それより、オルフェを早く迎えに行かないと」
「その為にも、急がんとな。この状態なら、油なぞ無くともさぞかし良く燃えるだろう」
空に爆炎が上がり、陰鬱な灰色の空が煌々と輝くのを、そして、針の塔が勢い良く燃え上がり、火の粉を辺りに撒き散らすのを、オルフェは呆然と眺めていた。
「ほへぇ…」
本当になってしまったんだなあ、というのが、オルフェ最初の実感であった。やれやれ、これから大変だぞ、と何処か他人事めいた感想を抱きつつ、いそいそと作業の仕上げに取りかかる。
オルフェが火矢に火を付けようと、懐から火打ち石を取り出した時だった。
「手を止めろ」
「い、ぎ、ぎ、ぎ……」
いきなり背筋に氷を突っ込まれたように身を竦め、ぎこちない仕草でオルフェは振り返った。こんな気分は何時でも嫌と言うほど味わわされて来た。だから、振り返らなくても知っている。
そこには、上級妖魔達が立っていた。
オイラはもう逃れられないんだ。
『もしもお前が本当の自由を手に入れたいと願うのならば、自らの血で贖え。自らの力で妖魔の掟とやらを克服してみるが良い』
逃げられないんだ。だから……。
オルフェは震える手で弓を番え、矢を向けた。力による階級が絶対の、妖魔の世界では通常、考えられぬ行動であった。
妖魔騎士の一人が、僅かに眉根を寄せた。
「気でも狂ったのか? 下級妖魔の分際で…」
蔑みの視線に、オルフェは胸が痛んだ。
上級妖魔に見られて、オルフェは弓を引く手を下ろしてしまった。弓を降ろしていなかったとしても同じだろう、照準を見定める事が出来無いほど、オルフェの腕は震えていた。
「ダメだ…オイラには、上級妖魔に手を出すなんて出来っこないよ…」
下級妖魔の彼に、生まれた時から半端者のオルフェには、妖魔の世界に生まれ、掟を受け入れるべく運命付けられた彼には、自由など望むべくも無かったのだ。身に過ぎた望みだったのだ。そう思うと、オルフェは何だか涙が止まらなくなった。怖いからでは無く、情けなさの故に。
かちゃり。鎧を着た騎士が、鞘から剣を抜いた音。
オルフェに信仰が在れば、神に祈ったであろう。だが、縋るものも信ずるものもなく、寄る辺無きちっぽけな下級妖魔に許されるは、精々が上級妖魔の裁きを待つ事位であった。身をちぢこめて死への瞬間に未だ背を向けることも出来ただろうが、オルフェは何となくそうしなかった。硬く、目を瞑った位は、彼の勇気に免じて許されるだろう。
刃が振り下ろされると思った瞬間、妖魔の騎士の上半身が、風にもぎ取られて、消えた。
「へ?」
「お待たせしました――間に合って、本当に良かった」
「おお、遅くなって済まんな。妖魔公に手間取ってな。大きな口を叩いた以上、最後まできっちり片を付けねばならんからな。それに」
竜王は蜘蛛の子散らすように逃げていく妖魔達など一顧だにくれずオルフェに近付くと、思いっきりデコピンを喰らわせた。
「針の城をぶち壊したはいいが、貴様が死んでは何にもならんからな。…鼻水拭け、汚いから。…って、こらー! 人の袖で鼻噛むなっ! タタキにして喰うぞ!」
一同は、針の城より遥か遠くで地上の様子を見守っていた。
妖魔達は上級妖魔も下級妖魔もなくパニック状態。混沌の中人の動きは、不思議と一定の動きを描いて何処か曼陀羅の文様を思わせた。紅蓮の炎に包まれし紫紺は、燃え尽き、やがて少しずつ、崩れて辺りに火の粉を散らしながらその形を失っていった。
「…良く、やりましたねオルフェ」
「うん…」オルフェの頬は、すっかり涙の後も乾き切っていた。「焼けちゃったね、針の城…皆、どうするんだろう」
「自らの運命を省みぬ者達など放って置けば良い。運命に抗わぬ者が悪いのだ」
「でもきっと、二度とここへは帰れないな」地上を見下ろし、妖魔の少年は何処か寂しそうに呟く。
「そうだな。だが、こんな虫みたいな連中しか住んでない国に戻りたいか?」
「ううん」オルフェは愛想良く答えた。「二度と戻って来ないから、良く目に焼き付けておくんだ」