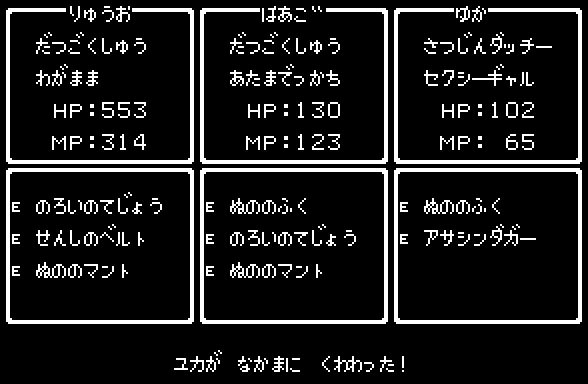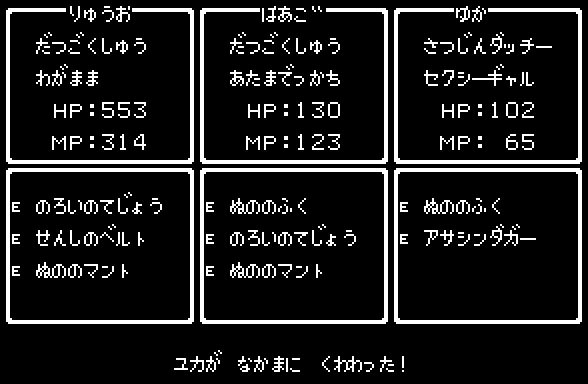第II章 Sodom et Gomora(背徳の街)
根の国から逃げ出して来た私達を襲った最初の困難は、何と言っても空腹であった。
「おい、何か喰う物はないのか。ああ、今だったらあの残飯だって喰ってやる!」
食うや食わずの今となっては、受け付けなかった筈の、あの臭いを放つ萎びたキャベツの芯が懐かしく思える。露に濡れた草むらを分け入る際に発せられる独特の青臭さが、貧弱な筈のニヴルヘイムでの食卓を思い出させた。
「そんな事言われたってないものはないです」
「くそ、貴様でも喰ってやろうか!」
「やや、やめて下さいっ! 私はおいしくないですっ!」竜王に胸ぐらをつかまれ、飢えに血走った目に捉えられ、つい声が上擦ってしまう。空腹なのはこっちだって同じだ、と内心毒突く。
「畜生、もっと食えそうな奴を連れて来れば良かった」気紛れな主人の腕から解き放たれて、私は生まれて初めて自分の貧弱な肉体に感謝した。
しかし。改めて思う。何故私は彼に付いて行く気になったのだろう? 自分勝手で、気紛れで時に残酷ですらある、我が儘な神竜の御落胤に。
あの魔眼に魅入られてしまったからだ。ダマされた。
あの当時は、本気でそんな風に思っていた。
追っ手の目を避けつつ、幾つもの山を駈け昇り、幾つもの森を抜けると、私達は眼下に広大な畑の跡と小さな農家が点在する村を一望する、小さな丘の上に出た。何処までも続く茫漠たる平原と、うって変わって開放感の無い空の重さに圧倒されて、私は暫しその場に立ち尽くした。
「よし、農家を襲うぞ」
「え?! ちょ、ちょっと! 貴男、何て事を言うんですか!」
「ん? 何かおかしな事でも言ったか?」幾ら空腹とはいえ、略奪がさも当然と言わんばかりの態度には呆れて開いた口が塞がらなかった。が、無理にでも塞がなくてはこのまま私達は略奪者になってしまう。
「食べ物を恵んでもらうんですっ!」
「あん? 何でそんな七面倒臭い事をせねばならんのだ?」
「見たら解りませんか?」私は一つ一つの農家を指差した。「どこの家からも、煙突の煙が上がってないでしょう。あれだけ広大な農地を持っていながら、どの家も藁葺き屋根の貧しい家です。おそらく、土地が貧しいか、全部借地なのでしょう」
「んな事は知った事か。…何なら奴らが飢えて死なないように、私が皆食らってやろうか? 人間の肉は雑食だから大して旨くはないが、まあ腹の足しには…」
「馬鹿っ!」とうとう堪忍袋の尾が切れて、私は喚いた。
「もし本気でそんな事をするつもりでしたら、私一人でも根の国に帰りますからね!」
竜王はしばらくの間黙りこくっていたが、さぞ不満げに口を尖らせた。
「うるさい奴だな、ったく、貴様など連れて来なければ良かった」
「結構です。請われて付いて来た身ですから」
「う、ううむ…こうまで貴様が煮ても焼いても食えん奴とは思わなかったわ。ふん、仕方ない。解った。言う通りにしようではないか」
竜王がしぶしぶ従ってくれたのを見て、私はようやく一息ついた。だが、今後を考えるととても悠長な事を言ってはいられないのだが。こんな事がこれからも続くのだと思うとうんざりする。
適当な農家の扉を叩くと、中から老夫婦が顔を出した。
「すみません、私達は旅の者なのですが、どうか、路銀かいくばくかの食べ物を恵んでは戴けないでしょうか?」
老夫婦は舐め回す様に我々を眺める。二人はすぐ顔を見合わせ、怪訝な表情を作った。が、すぐに我々を奥に通すと、「ちょ、ちょっと待っておくんなさいね、見ての通りの貧乏百姓なものですから」と言うなり裏に引っ込んでしまった。我々は随分待たされたが、二人は戻って来るなり、村長の家であんた達をもてなすことになったから是非来てくれ、などと言い出したので、今度は我々が顔を見合わせる番となった。老夫婦は我々を、見るからに貧しい村落の中でも、一番それらしい造りの屋敷に連れて行った。
客間に通されてしばらくすると、村長とおぼしき男が挨拶にやって来た。村長がにやけた笑みを浮かべながら合図を送ると、奥から先ほどの老夫婦と村長の妻らしき人物が食事を持って現れる。幾つもの皿が、恐らくは今しがたどこかから発掘されたばかりの薄汚れたテーブルクロスを敷き詰めた食卓の上に並べられ、手厚いもてなしの証を示していた。私達に振舞われた料理は彼らの貧しい生活の中でも間違いなくほぼ精一杯のものに違いない。我々は感謝の言葉を述べて、食卓についた。
「なあ、ハーゴン、おかしいと思わぬか?」
聞こえるか聞こえないか位の呟きで食事の前の祈りを中断されて、私は首を傾げた。「? どうしてですか?」
「貴様…以外と鈍いのだな。気付かなんだのか?」
真意を量りかねて小首を傾げる私に、竜王は誰にいうでもなしに呟いた。
「何処の誰が、どこの馬の骨とも知れぬ旅人二人組をもてなすのに、わざわざ村長の家にまで連れて行って、こんな、連中にとっては間違いなく最大限の料理を振る舞うのだ?」
「巡礼の旅では、こんな事は別段珍しい事ではありませんでしたよ」
竜王は再び眉根を寄せて、何げなげに呟いて返した。
「……なあ。我々、巡礼に見えるか?」
私達はお互いの姿格好を見合った。
「……見えません、ね」よくよく見ると、今まで気付かなかったのが不思議なくらい村人達の笑顔が強張っている。
「ああ」
我々が、椅子から腰を僅かに浮かせたその時、天空人達の追っ手が扉から雪崩れ込んできた。
「やはりここにいたか! お前達二人を、根の国からの脱獄容疑で逮捕する!」
「やはり面が割れておったか!」
「裏に逃げましょう裏!」椅子を蹴飛ばし、村長を押し退けて裏口の扉を開けると、やはりそこから武装した天空人達が世界樹の湧き水の如くに侵入してくる。
「完全に囲まれてしまいましたね」
「くそう! 連中、賞金をあてにしてタレコミおったな! ……良いかハーゴン、またやるからな。よーくつかまっておけよ!」
竜王は言うが早いか、床をを蹴って梁につかまると、反動を付けた勢いで藁葺きの天井をぶち抜いて飛び出した。
村中をひっくり返す大捕物の末にやっとの事で追っ手を振り切り、私達は街中に逃げ込んだ。
街は活気づいてはいたが、どことなくいかがわしい、アルコールと紫煙の匂いが似合いな背徳的な空気を漂わせていた。辺りでは行商人が武器を売り、その脇の路地では娼婦が男達を誘っている。麻薬の売人らしき男がたむろし、酒場では流れの傭兵達が昼間から酒をあおって、酔った勢いで暴れては殴りあう。そんな場所であるから、人間でない我々がそこらをうろちょろしていようが誰も注意を払ったりはしない。どうやら人相書きもこの辺りまでは出回っていない様である。
「路銀を作らんと話にならんな……ちっ、仕方ない。キューリは泣くだろうが、そんな事は知ったこっちゃ無い。な、ハーゴン貴様これ売って来い」
「武器、無くて大丈夫なんですか?」値踏みするべく件の剣を鞘から抜いて、刃渡り両手一杯に余る青々と光る刀身を睨み据える。特に刃こぼれもなく、実に良く手入れされている。かほどの業物、今後そうは手に入るまい。店で売っているかどうかは別として、これクラスの武器なら20000ゴールドを下らないだろう。
「何とかなるだろ。それよりメシだメシ。剣がいくらあっても腹が減っては戦はできんからな」
武器屋で剣を相当安く買い叩かれた後(それでも5000ゴールドは出させた)身を隠す為のマントと当分の食料その他雑貨、それらを持ち運ぶ為の背負い袋を買って街の通りを歩いていると、早速身につけたばかりのマントを引っ張る者がある。こんな所に知人の当てはないので、不審に思って懐に手を入れる。スリかもしれないと思ったのだ。全財産をスリに掏られたとなったら、どんな目にあわされるか解ったものではない。しかし、財布の中身は無事だった。振り返る。
「…すみません、あの…あたしを、買って下さい」
「え?」
「あたしを買って下さい」
見れば、そこにいるのは12〜3くらいの少女である。裸足で、膝上丈の袖なしの麻のぼろ着をまとい、この背徳の街には場違いな風情で、私の傍らに寄り添う様に佇んでいた。栗色の髪が頬を撫で、肩までを覆っている。少女の瞳は、私を見ていながら実は何も映してはいないのではないかと思われる様な不可思議な色味を帯びている。私は以前、こんな眼で見据えられた事があったのをふと思い出した。
「どうした、貴様幼女趣味でもあったのか、坊主は大変だな」
「だ、誰が幼女趣味ですか!」
裾をつかむ少女を振り切って、私は少女に諭した。
「こんな所に居ちゃいけない、家に帰りなさい。いいかい、もっと自分を大事にするんだよ」
街から大分離れた所で、私達は今夜の野宿の準備を進めていた。
「今頃、もう街にも追っ手は来ているんでしょうね」
「ああ。だが、それまでに我々がこの世界から脱出すれば済む話だ。どうだ、旅の扉はどの辺にあるか解るか?」
「旅の扉というのは、世界樹の振動で発生する時空の歪みなんです」私は街で買ってきた地図を広げた。「一般的傾向として、世界と世界を繋ぐ様な旅の扉は、川の源流とか磁鉄鋼の取れる山など、山間部に限られてるようです。ですから…?」
すぐに私は、注意が自分の話に向けられていないのに気付く。
「…?誰かいるのかそこに?」
気配を感じて、竜王は素早く身構えた。武器を売り払ってしまったのは早計に過ぎたかも知れぬ。
だが、草むらを掻き分けて現れたのは、天空人達の追っ手ではなかった。
木の影から出てきたのは、昼間私のマントを引っ張って自分を買ってくれとせがんだ、あの少女だった。
「ほお、貴様もすみにおけんな。何時の間に約束してたんだ。何だ、やっぱり幼女趣味か」
「だああっ! ち・が・い・ま・す!」愉快そうな口振りは昼間の嫌がらせに違いない。
「もっと自分の欲望に素直になればいいのに、なあ娘?」
「その娘に同意を求めるのはやめなさい! ああああああああああああ! 貴男なんかに付いてくるんじゃなかった! もういいです! やっぱり私は根の国に戻りますから一人で勝手になさい!」
少女の影が火元に一歩近付いた。
「…ごめんなさい……勝手についてきました…」
「どうして……私達に付いて来られても、私達はこの通り、ただの通りすがりの旅人。何もしてあげられませんよ。お嬢さん、家にお帰りなさい」
「あの……あたし、家、無いんです」
「……そう、だったのですか…」
「…あの…付いてってもいいですか?」
少女の左目は動かなかった。私はその時、少女の左目が義眼である事に気付いた。
「…かまいませんか?」
「おいおい、その娘を本気で連れて行く気か? 足手まといを連れて行ける余裕は無いのだぞ?」
「私が連れて行きます」私は宣言した。この少女を、あの背徳の街に帰したくなかった。義眼を嵌めさせ、生きる為に身体を売る事を教えたあの街に。
真夜中。
私達はようやく、まともな眠りに付く事が出来そうだった。
根の国から抜け出して、何日が過ぎただろう、あそこを抜け出してからは殆ど一睡もしていない。私は夢見であり、元々眠りの浅い体質だが、木の上だの薮の中だので微かに微睡む事しか許されぬこの数日間は、流石に気の遠くなる程永く、辛く感じられた。意識が朦朧とする事もしばしばで、農村の一件であんな間抜けた事をしでかしても気付かなかったのはその所為だろう。
眠りの神
が微睡む私を夢幻境へ誘わんと枕元に降り立った。意識が、溶けて行く。
意識の隅っこが、外界の変化を告げた。起きろ、と呼ぶ本能と、眠ってしまえ、と囁く誘惑が残り僅かな意識を苛む。
誘惑を振り切って重い瞼を開けると、今まで眠りの囁きによって遮断されていたあらゆる情報が、五感を通じて押し寄せて来た。私は戸惑った。
草むらが風に舐められて
慄
きざわめく様。
消えかかった炎が爆ぜてぱちぱちと最後の命を放つ様。
そして。その炎に照らされる、少女のシルエット。
「あの…」影が少し、深くなる。
「ん? どうした娘」竜王の方は半分寝に入っている様で、大して関心も無さそうに少女の方を見やった。
「あたしを…抱いて下さい……」
「馬鹿ぬかせ。私にはそっちの趣味はない。そういうのは…」
少女は反論を聞く間も無く、麻のぼろ着を脱ぎ捨てた。
「御奉仕します…」
「………?!」
少女の左胸は大きく欠け、乳房がもぎ取られた痕が残されていた。
竜王が一歩、飛びすさる。はね除けられた毛布が足下に落ちて広がった。
ぼろ着を脱ぎ捨てた筈の少女の手に、鈍くきらめく黒曜石のナイフが握りしめられていた。
「こ奴、暗殺者だ!」
竜王は少女の腕を跳ね上げる。少女は軽く身を捻ると、すぐに体勢を建て直してナイフを突き込んで来る。竜王が片手で少女を突き飛ばすと、少女は転がりながら立ち上がり、踵を返して再び襲いかかる。
「ど、どう言う事なんですか?!」
「言った通りだ。恐らく、我らが根の国から脱走した事は予想以上に早く伝わっているらしい」
言いながら、少女の足をなぎ払う。少女はくるっととんぼ返りし、再び黒い刃のナイフを振り翳す。その刃の輝きが、妙な色味を帯びているのに私は気付いた。
「刃に毒が!」
「なるほど」竜王が剣を振り翳した少女の手首を軽くつかんでひねると、少女の体は受け流される様にして横転した。少女はナイフを取り落とし、ナイフは足下に転がる。終わった。と思った。
「あいだだだだだ! このバカガキ! 噛み付きおったな!」
噛み付かれた竜王に振り払われたその隙に、少女は屈んで黒曜石のナイフを拾い上げた。が、脇腹を軽く蹴り飛ばされて玩具の様に簡単に転がされる。彼女はもう飛びかからなかった。己の力量では、到底かなわない相手だと悟ったのだろう。
彼女と視線があった。
無表情に変わりはなかったが、その目に、僅かな輝きを私は見出した。彼女は攻撃目標を切り替えたのだ。私は彼女が一瞬、凄絶な笑みを浮かべた幻想に囚われた。
少女は無防備な私の懐に飛び込んだ!
「ぐうっ!」
脇から強烈な体当たりを食らって、私は無様に転がった。
「バカたれ、ぼんやりしてるんじゃない」
竜王に罵倒されてゆっくり身を起こした私の前に、裸のまま片方の足首を逆さに吊られた少女の身体がぶら下がっていた。その様子は、子供の手で逆さまに引きずられたセルロイド人形の様に、私の目に映った。
信じられぬ事に、目が合った途端、少女の目に再び生気が宿った。
少女の手が、逆さに吊られたまま私の顔面目掛けて下から振り上げられたのだ。手がそのまま空を切ったかと思いきや、彼女は驚くべき柔軟さと強靭さでもって腹筋の力だけで起き上がり、竜王に襲いかかった。だが振り翳したナイフは標的に届く前にもぎ取られ、あっさり地面に叩き落されてしまった。
「そのナイフ拾っておけ」竜王は地面に転がった黒曜石のナイフを蹴って寄越した。私はナイフを拾い上げて、丁寧に布切れに包んでバックパックにしまい込んでおいた。竜王は足を引っつかんだまま少女を持て余し気味にしていたが、ふと何かに気付いたのか少女の肢体に関心を示し出し、例によって玩具を扱うみたいにひっくり返したり押したり引いたりして彼女を観察し始めた。「なるほどな、そういう事か」
「何をなさってるんですか。人を散々おちょくった割には、貴方にもそっちの趣味がおありですか?」私としては散々言われたお返しに皮肉ったつもりだったのだが、竜王は私を無視すると、少女の足首を相変わらず逆さに持ったまま私に少女の鼠蹊部を指し示した。「これを見てみろ」
「そんなもの見る趣味はありません」顔を背ける。
「ふん、何を勘違いしておる、そうじゃない。いいかよーく見ろ。この体には、何人もの男達を相手にした痕がある。男どもの相手をさせて、相手が油断した所で殺す、そういう用途で作り上げられた、殺人ダッチワイフという訳だ。人形に自我は必要ないからな、悪趣味だが、良くできたシロモノだ」
少女は無表情のまま、足首をつかまれて逆さに吊られている。
痛いとも苦しいとも口にせず、命乞いもせず悪態も吐かず。
乳房をもぎ取られ、目を抉られ、慰み物にされて。
あれから何も世界は変わってはいないのか。
「…酷い…事を……」ようやっと、そう口に出すのが精一杯だった。少女の義眼の訳はそんな事だったのだ。憤りに、知らず身を震わせる。
「心配するな、すぐに楽にしてやる」
竜王はあの魅入るような瞳で、少女に囁いた。「情けと思え。本来なら、我に逆らいし者を簡単に死なせる程慈悲深くはないからな」
私はかつて、こんな光景を見ていた時があった。私は無力だった。誰も救えない、誰一人にも手を差し伸べることすらかなわない、あの時の自分。
救えないのなら滅ぼしてしまえと、焦燥に駆られていた頃を。滅びの後の創造、その、見届ける事すらかなわぬ、今にして思えば有りや無しやも解らぬ未来の為に、己の全てを捧げ尽くしたあの頃の記憶が、今ここで、現実の物として再現されていた。
「止めて下さい、お願いです」
止めなければ。
「ん? どうした?」
止められるものならば!
「お願いです、この子を殺さないで下さい!」
ほんの数秒の沈黙が、私には気が遠くなる程永く感じられた。
竜王は素に戻ると、数度瞬きした後、宇宙人でも見るかにまじまじと目を見開いて私を見た。
「何故だ? 下らん情けをかけた所で、この娘には通じんぞ。この娘には、そういう感情を理解出来る心は無い。ならば、いっその事、早く生まれ変わった方が幸せになれるというものだ」
「私に……私に、彼女を任せてもらえませんか?」
「…どうして貴様はそう甘ちゃんなんだ? 一度は殺されかけたのだぞ?」竜王は、駄々をこねる子供に言い聞かせでもするように噛んで言い含めた。「良いか、情けをかけるのは勝手だが、それは己の身を守れる力のある者がする事。今の貴様にそんな力がどこにあると言うのだ? あん?」竜王は私の手枷をつかむと、私の目の前に手首ごと突き付けた。
「それとも、貴様まだ償いとやらに拘っておるのか? 世界を滅ぼそうとした罪の」
彼の指摘は当たっていた。私は何処かで勝手に思い込んでいるのだ。――もしもこの少女を救う事が出来たならば、私は自分自身の罪をも許せるかもしれない、と。
その為なら、一度失った命などどうして惜しかろう。
「…そうか、勝手にしろ。だがな、私はこんな所で小娘にぶすっとやられてニヴルヘイムに送り返されてハイさようなら、なんてのは真っ平御免だからな。今の貴様の主人は私だ。この娘を連れて行くなら私の流儀でやらせてもらう。良いな?」
竜王は一つ大きなあくびをすると、あっさり私の提案を受け入れた。良くて罵倒されるか、事によると、目の前で少女の首をへし折られるくらいは覚悟しておかねばならぬという私の予想は、以外な位に良い意味で覆されたのだった。
「さて、と…流石に…眠らねばならんな」竜王が娘の顔を厄介そうに見やっている。「寝首をかかれては困る。はて、どうするか…」
「自分で縛れます」そう言って、少女は自らの身体をロープで縛り付け始めた。
「馬鹿者やめんか!」少女の手からロープを取り上げる。「そんなもの、自分で縛ったのなら簡単に抜けられるではないか。そもそも縛った所で、どうせ関節の一つや二つ外す訓練くらい受けておるだろうが。そんなので安心して眠れるかバカモン! なめくさるのもいい加減にしろ」
「だめですか…」大して残念でもなさそうに、少女は一人ごちた。
竜王はしばらくの間、せいぜい12、3の少女相手ににらめっこしていたが、一大決心を固めたらしく、深々と溜め息の大きなのをついて、言った。
「仕方あるまい、抱いて寝るか」
「抱いてって貴男…」
「貴様じゃないんだ、幼女に欲情する趣味はないわ! ほれ、服を着ろ。……、ちょっと待った」竜王は少女から麻のぼろ着を取り上げると、ひっくり返してばたばたと上下に振った。と、ぼろ着の中からは毒針やら針金やらの暗殺用の道具が面白い様に落ちて来る。
竜王は深々ともう一つ、あくび混じりにため息をついて、それから、娘に服を手渡し、私の顔をちらっと見やった。
「なあ、この娘、本当に連れて行くのか? 過ぎた情けは身を滅ぼすぞ」
翌朝、起きてみると、二人はすっかり疲れ果てて寝入っていた。
「……ハーゴン、貴様、この娘を、まだ連れて行く気か…?」揺すぶって起こすと、竜王はだるそうにようやっと身を起こした。「貴様の誠意はこれっぽっちも通じてはおらんぞ。一晩中、うつらうつらする度に娘の殺気で目が覚めた」
「お互い様のようですね」私はまだ寝入っている少女の頭を撫ぜる。
「解っているのならもう少し寝かせろ」
「そうも行かない様ですよ」
「くっ、また追っ手か。どの辺まで来ておる?」
「いえ、見た訳ではありません。が、夢を見ました。私は夢見なので…そろそろ我々の動きが感付かれた様です」
「全くしつこい連中だ。仕方ない、抱えて行くか…」
竜王が抱え上げようと脇に手を入れると、少女は息でも吹き込んだかのようにすっと目覚めた。
「ふん、相当仕込まれておるようだな…やれやれ」
険しい山道を、休み一つ取らずに、我々は獣道を、道無き道を踏みしだき、歩みを進めていた。追っ手の気配はまだなかったが、時間のロスは避けねばならなかった。戦わずして済むのならそれがいいと私は思っていたし、竜王は竜王で、武器もなく、2人のお荷物を抱えて(しかもその内の1人は自分を暗殺しようとしているのだ!)追っ手とやり合うのは何としても避けたいところだったのだろう。口に出さずとも互いに解っていたのか、それとも、疲れ果てていて口を利く余裕がなかったのか、私達は行者の様にひたすらに、黙々と山道を歩んだ。
「…休もうか」
ふと、そんな沈黙の時に終止符が打たれた。
「そうですね。足が傷だらけですよ。薬草でも塗り込みましょうか」
「全員裸足か似たようなもんだから仕方なかろう。おい、休むぞ娘。…貴様、名前は?」
そう言えば、彼女の名前をまだ聞いていなかった。
「ユークァル。ユークァル=ムォノーです」
「ふん、ユークァルか。良いか、良く聞けガキ。貴様の主人は今日からこの私だ。今までの主人がどうかは知らんが、私は私流の流儀で行かせてもらうから良く憶えておくが良い。ふむ……もしだな、貴様がまだ前の主人の下した命令を忘れていなかったとしても、生きて帰りたくば私から殺れ。この事が何を意味するか解るな?」
私には何の事だかさっぱり解らなかったが、ユークァルと呼ばれた少女は即応して頷いた。私が怪訝そうにしているのを見て、竜王は早速昨夜の仕返しとばかりに毒を吐く。
「はっ、鈍い奴だな!お前の命の保証をしてやったのではないか。良いか、もしこの娘…ユークァルがお前を先に手にかける事があればだな、私はこの娘を生かしてはおかんだろうからな。その逆であれば、この娘も安心してお前を殺すことが出来るだろう。だが、まあそんな事は万が一にもあり得ん事だからな。解ったか? このとんちきが。象牙の塔で屁理屈ばっかりこねくり回して世界を滅ぼそうとした頭でっかちの貴様より、このダッチワイフの方がよっぽどか賢いわ。なあ? ユークァル。いいか、貴様の主人はこ奴じゃない、私なのだからな」
竜王は適当に頭を撫でくり回していたが、突然顔をしかめてなで回していた方の指をくわえた。「痛! …この娘…髪にまで…暗器を隠しておったのか…!」
無造作に頭を撫で回され、髪をくしゃくしゃにされながら、ユークァル=ムォノーは何度か瞬きして、それから応えた。
「解りました、御主人様」
「御主人様はやめろ御主人様は。そういう趣味があると思われるではないか」
「またそう言う事を。しつこいですよ」
ユークァルは少し考えてから、再び口を開いた。
「…解りました、マスター」
刹那、訳もなく鳥肌が立った。竜王は眉間に一筋深く皺を刻むと、ユークァルの胸ぐらをつかんで引き寄せた。
「マスターだけは絶対許さん。良いか、今度その名前で呼んだら、八つ裂きにして魔物のエサにしてやるから憶えておけ!」
「…では、どうお呼びしましょう」だが、ユークァルの義眼は、恫喝にも色を変える様子はない。
「ふむ、呼び捨てでかまわん。変に様付けされるのも落ち着かんしな。ハーゴン、貴様はどうだ」
「別に、構いませんよ。さん付けでもいいですし」
「こんなガキにさん付けされたくはない」
「……陛下って言うのはどうですか?」
「くわっ、それは勘弁してくれ……ふむ、待てよ」その時、私は竜王の瞳が意地悪く輝いたのを見逃さなかった。
「よし、これからハーゴンの事を猊下と呼ぶ事にしよう。いいか、猊下だぞ猊下。いや、聖下だったかな。聖下にしよう聖下。森永聖下」
「はい」
「やめてえぇ、それだけはやめてえぇぇ…」
この呼び名は、この世界を離れて、竜王が飽きるまでの間しばらく続いた。