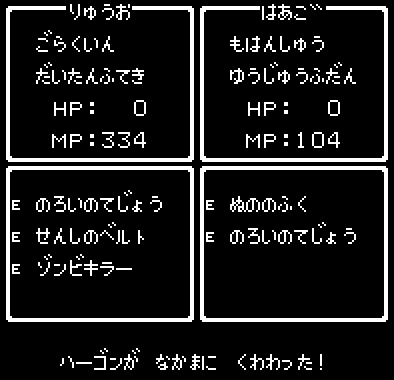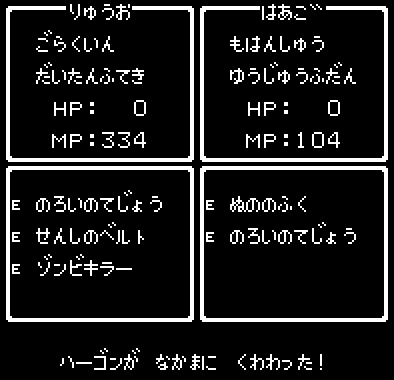第I章 根の国(ニヴルヘイム) 〜死んだ魚の目を拒め!〜
今日は朝から夜だった。
どんより曇った日本晴れ
昔々のついさっき
昨日生まれたばあさんが
九十五六の孫連れて
黒い白馬に跨がられ
前へ前へとバックした。
今日も朝から夜だった。
日の当たらないこの世界に、朝というものがあるかどうかは知らない。此処に幽閉されてからというもの、最初の内こそ今日が何月何日かなんて指折り数えていたものだが、今となってはあれから何年経ったかももうはっきりしない。それでも大体百年は経っていると思う。が、此処を出る機会が万が一あるとして、実はあの日から1日も経っていなかった、なんて事も有りそうな気がする。そんなぞっとしない可能性については考えたくもないがな。
私が地上で死んだ日。
そう、あの日から私は罪人として、このつまらん世界の根源である世界樹の、さらに根源たる根っこの世界"ニヴルヘイム"の、世界樹に設えられた特別製の牢獄の中で、この上もなく無為で、退屈な日々を過ごす羽目になっている。
此処に来てすぐの頃は他の罪人共同様に強制労働に就かされていたが、奴ら私をナメていたのか他の囚人と同じ枷を着けさせていたものだから、簡単に鎖を引きちぎっては本来の姿を現して随分と暴れ回ったものだ。他の囚人と同じ物とはいえ、この枷は魔法を封印する上、ものによっては着けられた者の能力を何分の1かに押えるというスグレモノだ。が、私に言わせれば、天空人の一人や二人、たかが力が2分の1や3分の1になった所でやられる気はしない。
そんなものだから、看守の命令にことごとく逆らっては、罪人共を統率し、ストをやったり機械を壊したりとメチャクチャやったので、今ではその手に、何と能力が16分の1に制限される特別製の鎖付き手枷をはめられ、他の全ての罪人共からも隔離され、平穏で変化のない、しかし退屈極まりない日々を、邪魔っけな鎖を着けながら寝て暮らしている。暮らしながら寝ているのやも知れぬ。囚人共と来たら、ストをやっている時にはさんざ人をもてはやした癖に、いざ特別製の牢に押し込められるや、掌を返した様に後指を差して人を笑い者にするようになりおった。まったく卑屈で愚かなクズ共ばかりだ。
一方、看守の天空人はと言うと、根の国の連中を光の側の裏切り者として蛇蝎の如く忌み嫌い、出来る事なら近付かぬ様近付けぬ様にと避け、任期を終えて天空に帰る日を指折り数えながら日々を過ごしているどっちもどっちな連中ばかりだ。だから、この国をもっと面白可笑しく変えてやろうだのもっと住み良い世界にしようなどとはつゆとも思っちゃあいない。そもそも奴らが此処へ来るのは、あくまでもそれが天空人としての義務だからであり、試験の結果によって勤務地にふり分けられ、それぞれの場所に配属されて2年か3年かの任期を全うする仕組みになっているからなのだと聞く。でもって、根の国の管理なぞは重要な仕事とは見做されていないらしく、大抵優秀な連中は送り込まれて来ない。連中はそれを判っているから――つまり、此処に来た者にとっては、根の国への配属は災難以外の何物でもなく、ありていに言ってしまえば、自らの無能の証明なので――欝屈をため込んだ連中は故に、必要以上に囚人達に酷く当たるのである。人材の有効利用にはもってこいという訳だ。まったく、誰がこんな下らんシステムを作り上げたものか。
んな事は今更分かり切っているのだが。
そ奴のお陰で、肉体的にも精神的にも物理的にも、私は天空人達の不当な八つ当りから免れているのだから。が、そんな特典は別に有り難くも何ともない。見捨てられているか、さもなくば服従を強いられている点では変わりない。
自分の父親、世界の支配者マスタードラゴンに。
と、話が逸れたが、とにかく、此処は朝から晩まで何も代わり映えのない、心底つまらぬ場所である。そんな世界で唯独り、百年二百年を、愉しくとは行かぬまでも過ごしていくのは並大抵の努力では勤まらない。私の様に一生の時間を何千、何万年というペースで捉えられれば未だしも、そうでない者ならとうに気が狂ってしまっているのだろう。それでも、最初の内は暇潰しの為に随分色々な事を試みたものだ。壁に爪でスライムのレリーフを掘ってみたり、自分の血で絵を描いてみたり。スライムの方は数年で塞がってしまったし、絵の方は看守に後で全部消されたので馬鹿馬鹿しくなってやめた。そもそも自分には絵心が無い上、どうせ消されてしまうのにそんな事に血を流すのは馬鹿げている。今にして思えば何故そんな事を思い付いたのかさっぱり解らぬ。恐らく、余程キていたのだろう。
看守が比較的マシな奴なら、地上の情勢を聞きだしてみたり世間話をして時を過ごす事もある。尤も、大抵はロクでもない連中ばかり、マシな奴でもしばしば我慢のならん事がある。だから、起きていて手持ち無沙汰な時には、いつか此処から脱出し、そしてこの私を陰気な世界に百年以上も幽閉したクソ親父に何としても一矢報いてやらんが為とばかり、ひたすら体を鍛える事に決めている。体を動かしていると余計な事を考えずに済むので気が楽だ。
とはいえ、此処で体を鍛え続けるのもまた一苦労。場所が狭いからだとか、機械がないなんて事じゃない。まず、鎖だ。手枷から伸びた、枷同士を繋ぐ太い鎖。何度も引きちぎろうと引っ張ってはみたが、やはり16分の1はこういう処に出ているらしい。そうそう、こいつが特別製である事は先に述べた通りだが、この手枷というのがこの上なく厄介な代物で、枷の上に堂々と、ぶっとい文字で『1/16』と書かれているのだ。いや実際、他の囚人達も似たり寄ったりなのだが、他の連中は大体、まあ強そうな奴で1/2か1/3くらいである。あまりにみっともなくて、これには閉口した。
そして、何より、とにかく食事が酷い。こんなもの、地上の犬でさえ跨いで避けるというものだ。本気で囚人達はこれを喰ってあの労働をさせられているのか、良く暴動を起こさぬものだ。内訳はこうだ。かびの生えたパンの耳一枚分。虫喰ったキャベツの萎びた芯、しかも臭いのするのが2〜3本。どぶ水の臭いがするぬるいスープがコップに半分。ごくたまに、腐りかけた臭いのするゆで卵が半切れ付く事がある。これが一日一回だぞ! どうも天空人達は、自分達の残飯を囚人に与えているらしい節がある。サディズム此処に極まれりだ。
無論こんな食い物は願い下げだから、盆にも触れずに放っておく事にしている。性格のねじ曲がった奴が残飯担当だった頃、そ奴は残飯の上にさらに新しい残飯を積んで放っておくという実におぞましい事をやってのけた。酷い時には残飯の山が腐臭を放って山盛りになっていたっけか。余りに残飯が悪臭を放つお陰で、匂いを嗅ぎ付けたはえおとこ共が牢の前に大量に群がってニヴルヘイム中に大繁殖する事件が起った。駆除には相当苦労したらしいが、それこそ因果応報自業自得、ざまあみろと言うものだ。流石にその件があってからは盆を下げるようにはなったが、それでも、食べもしない残飯を持って来ては一々置いていく習慣は一向になくならない。儀式のつもりだろうか?
で、どうやって飢えを凌いでいるかというと、こればかりは本当に腹立たしい限りだが、また例の父上の御慈悲に縋っているという次第なのだ。此処でミソなのは、この独房が世界樹の根っこの中にあるという点だ。この牢獄の奥には、
この世界
でただ一ヶ所だけ日の光が差し込む場所がある。それはもう、実に極々僅かな光にすぎないが、それでも、その隙間からたまに植物の種が舞い込んで来ては、運良くこの牢の中で芽を出す事がある。そんな生命を、此又極たまに口にさせて戴くという寸法だ。無論こんなもので飢えが凌げる訳はないから、此処でもう一度例の御慈悲に登場願う事になる。その日の光の差し込む僅かな隙間からは、やはりごく僅かながら、夜の内に――と言っても、夜も昼も大して代わりはないのだが――世界樹の葉に降りた露が雫となって滴り落ちる。これを錆びの浮いたコップに集めて飲む。腹は膨れないが体には良い。
腹が減ってどうしようもないが、雑草の芽も喉を潤す世界樹の雫も当てに出来ぬ時には、仕方ないので窓の外から囚人達を眺めているか、そんな気力もない時には天井を眺めてあれこれと身の振り方について考える。言っておくが、親父に頭を下げて此処から出してもらおうなんざ、一度たりとて思った事はない。寝ながら考えるのは、親父を前にしたらどうするか、ぶん殴って頭を下げさせるか、なんてたわいもない事ばかりだ。
流石にもう、私もあの時の様なガキじゃない。魔王と称して魔物達の軍勢を率いて暴れたところで、何の意味もないのは判ってる。今にして思うに、やはりあの頃の私には、どこかで甘えがあったのだ。己れの被造物が我が子の手で傷付けられる様を見れば、少しは我が子をほっぽっておいた己れの所行を悔やみもするだろう、己れの非を認めて頭の一つも下げにくるだろう、と。
結果か? 此処まで言ってもまだ気付かないのか?
裏切られたのさ。見事にな。
私は、親父殿の送り込んできた刺客の手で、世界を統べる神の後継者としてではなく、世界を恐怖に陥れた悪の化身として闇に葬られたのだ。皆は刺客の事を"伝説の勇者"と呼ぶがな。奴にとっては、血の繋がった子の苦悩の叫びより、虫螻共の命の方が大事だったって訳だ。
当時は、そんな事すら判らぬ程追い詰められていた。一息付いて考えよう、と考える余裕が無かった。ようやく一息付く余裕が出来た頃には死んでいるんだからな。ああ、これは逆だな。死んだから余裕が出来たのか。
当時はがつがつしていて、いつも何物かに急き立てられていた。魔界では回り四方敵ばかりで、生きていくのが精一杯だった。恐怖を憎悪に変える事、やられる前にやる、それが、私が幼少時魔界で学んだ事の全てであったように思う。 だが、現実はどうだ? 憎悪の力などたかが知れているではないか。
憎悪を抱き続けて生きるには、余りにも大きな緊張を自らに強いねばならぬ。あの頃はともかく、今の私にはもうそれを自らに強いる気は失せている。此処では誰も本気で殺しにも来なければ助けにも来ない。全身全霊を賭けて生きてる奴なんて一人もいやしない。私も含めて。
全霊を傾けて生きたところで、何にもなりゃしないがな。
――では、死ねば良かったのか? 生きる事しか考えていなかった、癖に。
今までの人生は何だったのか。
何の為に、この世に生を享けたのか。
いつもの答えの無い問いに結論が出なくなった所で、考えるのをやめた。
あ、そうそう、変わり映えのしないこの世界に、有難い事に最近ちょっとした変化が訪れた。大した事ではないのだが、それでも何も起こらぬより遥かにマシだ。
地上から新しい囚人が送り込まれてきたのだ。
あの腐った魚みたいな目をした連中の仲間が増えただけなら特別何とも思わないのだが、こいつはちょっとばかり違ってた。
その囚人は、名前をハーゴンと言った。
「ええい、また残したか愚か者めが! 貴様、神の血を引く身でありながら、無辜の民草を苦しめた悪業の数々、未だつゆとも悔いておらぬのか! この選ばれし神の子ワルキューリ様が天に立ち代わりて成敗してくれる!」
「何だ、キューリまた貴様か。相変わらずうるさい女だな。たく、こんな所をうろうろしてないでとっととヨメに行ってしまえ。そもそもこんなものどうせ喰わんのだから持ってくるな!」
特別独房担当の看守がやってきて、また残飯の新しいのを持ってきた。この独房担当の看守というのがまた変わった奴で、名前を確か……ええっとワルキューリ=ド=……とか何とか言うらしいのだが、本名があまりに長くて憶えられないので、今後は勝手にこの女をキューリと呼ぶ事にする。で、この女がどう変わっているかというと、とにかく剣の腕は立つわ、魔法も一通り使いこなすわ、古代語は完璧に判読できる上、悟りの書をそらで暗唱できるほどの才女なのだが、にもかかわらず動く石像とゴーレムの区別が付かないというどうしようもない間抜けなのである。知恵が無いだけならともかく、短気な上に冗談が全く通じず、プライドだけは雲より高い性格破綻者と来ている。しかも、試験の成績がほとんどトップだったにもかかわらず、自ら志願してこの根の国の警備にやってきたのだと聞く。
勿論、そんな女と一緒に仕事をするのは卑屈な落ちこぼれ共にとって甚だ惨め且つ迷惑であり、結果としてこの女は天空人の看守達の鼻つまみものとなって、奴らにとってはどうでも良い、誰もが嫌がるような任務に就かされている。驚くべき事にこの女は、特別独房付近の掃き掃除だとか私の飯の管理だとか、そういう何の足しにもならんくだらぬ仕事を、本気でくそ真面目に一つ一つ丁寧に、完璧にこなしているのだった。その様があまりに哀れなので指摘してやったら、「何、かくの如き任務も、誰もやらねば困る者がおるではないか。あのどこにもつながっておらぬ無為な機械を毎日回し続けねばならぬ囚人達に比ぶれば遥かに有意義な事よ」と胸を張っていたのには驚かされた。この女のお陰で、初めて私は囚人達の強制労働が本当にただの罰の為の罰としてしか機能していない代物である事を知ったのだった。
と、かくの如き変人であるが故に、また私があ奴の学を理解できる根の国で殆ど唯一の者であったが為に、奴とはそれなりに地上の情勢など色々世間話をする事もある。看守としては比較的マシな部類に入ると言えようか。とは言え、初めの内はこのバカにうつけ呼ばわりされるのに我慢ならなくて、そりゃあ随分とやりあったものだ。今まであれを縊り殺さなかったのが不思議と言えば不思議なのだが、バカで高飛車でどうしようもないこの女も、そのバカさ加減故に本気になるのがアホらしくて何処かでセーブしていたのやも知れぬ。兎に角、この女はその度に、持っているほうきの柄で牢の外から人の頭をぽかぽか叩いてくる。ある時なぞあんまり腹が立ったものだから、キューリのほうきを取り上げて目の前で叩き折ってやったら、あの女、顔を真っ赤にして涙を流しながら、独房の中に躍り込んで剣を振り回して襲いかかって来おった。大概の事に動じない自信はあったが、その時の奴の目が完璧にイッてしまっていたのを見て、こいつだけは怒らせまいと心に誓ったものだ。
「なあキューリ」
「ん、何じゃ?」
「貴様、
根の国
に自ら志願してきたそうだな」
「うむ、その通り」キューリは例によって誇らしげに胸を張った。
「何故、こんな所に?」
「それは、ひょっとすると、天空人の落ちこぼれ共が来るような所に、何故成績優秀な妾が配属を希望したか、という事か?」まぬけのキューリもこういう所の飲み込みは流石に早い。
「だからそう言っておるだろうが」
「ふーむ」
キューリは独房の外に座り込んだ。天空人共からハブられているキューリの事、どうせ帰った所でヒマなので、話し込んでいく気分になったらしい。
「木にとって最も重要な部分は、養分を大地から吸い上げる根っ子であろう?」
「そうだな」
「それと同じ様に、世界樹を支えている最も重要な部分は、実は根の国なのではないかと思うたのじゃ」
「なるほど。貴様、中々のインテリゲンチャだな。…………ぃったー!」
キューリの奴、ほうきの柄で額を突きおった。叩くとかわされる上、ダメージも大した事がないのが解って戦法を変えて来たという訳か。とんまでマヌケでもこの程度の学習能力はあったらしい。それにしても眉間を思い切り突きおって、死んだらどうするつもりだ。ってもう死んでるか。
「この愚か者が! 囚人の分際でまたもや妾を愚弄する気か! 貴様の様な極悪非道の輩は、このワルキューリ=ド=ブリュンヒルト=シュトレマイヤーII世=ベイゲン=フォン=テヅルモヅル……………………」
「ああ、もういいもういい悪かった、謝る。だから話の続きをしてくれ」この女に名乗りをあげさせると、全部の名前を名乗るまで1分30秒かかってしまう。前にフルネームを名乗っていた時、こっそり秒数を数えて教えてやったら、えらく怒ってしばらく口を利こうとしなかった。誰がこ奴の名前を付けたのかは知らんが、こ奴の一族は皆が皆揃って長い名前なのだろうか。こんな家には婿入りしたく無いものだ。
「……ふん、今日はこの辺りで勘弁しておいてくれるわ。話を戻すぞよ」
「そうしてくれ」
「しかし、天空においてはその重要性は全くといって良い程認識されておらぬ。根腐れが起これば木が倒れてしまうように、世界樹も、根の国が滅びれば滅びてしまうのが道理というもの」
「ふむ、それで貴様、この根の国の実態を調査しにきたという訳か」
「そうじゃ」
キューリは柵にもたれかかり、ため息をついた。
「思うておったよりずっと悪い」
「そんなに酷いか?」
「ああ、少しの間待っておれ」
「時有り余る身分だ、付き合ってや………………あれ、行っちまった」
此方の返事を聞こうともせず、キューリはマントをはためかせてぴゅーっと飛んでいってしまった。
ほんのしばらくすると、キューリは手のひらに一杯の木屑を抱えて戻ってきた。差し出すので、摘み上げると、虫に食われてぼろぼろに朽ちている。
「これを見よ。虫が喰っておるであろう」
「ふむ、確かに。しかも腐っておるな」摘み上げた木屑はじっとりと湿って柔らかく、半ば溶けかかっている。ほんの少し匂いを嗅いで、木屑を払い除ける。
「根の国のゴミ廃棄場の辺りの根じゃ」キューリは溜め息を付いた。「日が当たらぬ上に綺麗に掃除をしておらぬ故、毒虫やらマタンゴやらクサレタケやらが辺り一杯に生えておる」
「そりゃ酷い」普通マタンゴやクサレタケは、綺麗な水のある所には生えてこない。
「此処だけではない。例えば貴様の独房の近くに世界樹の水脈があるであろう」
「うむ」
大抵の植物は根を通じて大地から水と養分を吸い上げる。世界樹も無論例外ではない。キューリの話によれば、世界樹程の巨木にもなると、その水脈たるや小さな川くらいの水量はあるのだそうだ。
「その辺りも随分と木の表層が軟らかくなっておる。虫が喰っているのではないかと思うのじゃ。が、調査するよう妾が主張しても、誰も耳を傾けようとせぬ。全く腹立たしい事じゃ! 囚人をいたぶる事と早く天空に帰ることしか頭に無い阿呆共が!」
キューリはそこまで一気にまくしたてると、ぽつりとつぶやいた。
「滅びの時は近いのかも知れぬな」
「おいおい、貴様がそんな事を言ってどうする」正直、こんな弱気な様子はキューリに似付かわしくない。こいつは芝居がかった口調で訳のわからん死語を叫びながら、ほうきを振り回して暴れている方がずっと、らしい。
「あの様な若者が現われて、世界を滅ぼそうなどと企むのも、時代の性なのであろうか」
そう言って立ち上がると、キューリは足元の無意味な機械を廻している囚人達を見下ろした。
「余程思い詰めていたのであろうな」
「ああ、だろうな」
二人の視線の先では、どう見ても肉体労働に不向きな体型の竜人族の若い男が、他の囚人と一緒に巨大歯車を懸命に廻していた。
「……あまり、いじめてやるでないぞよ」
「ちょっと待てキューリ、どういう事だ。私が何時あ奴をいじめた? おい!」
「この間貴様、仕事中に此処から大声で呼び止めたであろう。あの男、あれから看守の憶えが良くなくてな。模範囚であるにもかかわらず色々と不便を被っているように見受けられたが? この間など、夜見回りに行った帰り、看守達の袋叩きにあっているのを見かけたぞ?」
げ、だから奴、あれから声をかけても無視するようになったのか。
悪い事をしてしまったかな。
あの囚人に少しだけ後ろめたさ――後からそれが、世間でそう呼ばれる感情と知ったのだが――を覚えつつ、仕事を片付ける為に飛び立ったキューリの背中を見送る。キューリが去ったのを見届けると、私はこれからも繰り返されるであろう退屈な日常に埋没する己の運命に溜め息をついた。
私が己の世界での生を失い、この罪ある死者の世界ニヴルヘイムに送り込まれてからはや8年が経とうとしていた。
此処の囚人として罪を償う生活は、時の流れを忘れさせてしまうかに規則正しく、私の罪が償われるその日、永遠に訪れぬかも知れぬその日まで、倦まず弛まず続いて行く。
罪が償われる時、私が罪を許されんが為に償いの日を生きる事を忘れる時まで。
私は粗末な食事の前の瞑想に入っていた。
誰に聞かせるともなく祈りを捧げた後、ちょっとばかりカビの生えたパンの耳にかぶりつきながら、今日の出来事を思い出す。今日は比較的平穏な日だった。肉体労働は相変わらずだが、あの特別製独房からまたぞろ声をかけられないかと、此処の所少しばかり神経質になっていたからだ。以前、竜王にあの独房から仕事中に大声で話しかけられたおかげで、他の囚人達の笑い者にはなるわ、すっかり看守の覚えが悪くなるわ、挙げ句看守に言われもなく袋叩きにされるわと散々な目に遭ってしまった。何でも、竜王も以前は他の囚人たちと同じく労働に従事していたらしいのだが、看守の命令に全く従わず、何度も軛を絶っては囚人達を率いて根の国をメチャメチャにした為に、今ではあの独房に封印付きで閉じ込められているのだそうな。何故私が彼に気に入られたかは皆目見当が付かないが、これも我が身の罪深さ故の天罰と思えば詮無き事ではあるとはいえ、やはり良い迷惑というものだ。
だが、此処に来てからどうしても、不思議な事に思い出せずにいる事がある。
何故私が己れの過ちを悔やんでいるのか。
何をして自らの過ちと為しているのかを。
何処の忘却の河の水を口にしたのであろうか、とても大事な事だったのかもしれないのに、まるでそれが取るに足らぬ事であったかのように、私の記憶はそこだけが欠落していた。
己れの犯した罪を鑑みれば、やはり、それすらも取るに足らぬ事かもしれないが。
「よ、新入り」
食堂で、私の隣に見かけぬ男が座り込んで声を掛けてきた。一口に死者の世界と言っても、善行を為した者だけが赴く事を許される世界もあれば、此処の様に、光の世界の住人として創造されながら、悪業を為した者達が罪を償う為に送り込まれる場所もある。光の世界の住人とは言え、全ての者が善良で、一点の曇りも無き心を持っているとは行かないので、此処ニヴルヘイムに送られてくる罪人が皆顔見知りと言える程少なかったという事はない。私がこの世界に来てから8年余りになるが、他の囚人達に大して関心を払っていなかった所為で、顔と名前が一致するのはカンダタ一味を筆頭に数える程しかいない。私の事を知らない囚人がいたとしても、おかしくはない。
「アンタ、この世界短いんだろ」
「それでも、もう8年近くなります」
「ハァハハ、短い短い! オレなんかもう500年は此処にいらぁ! まぁ、竜人族の兄さん、今後ともよろしくな!」この囚人、声をかけるのも初めてなら顔を合わすのも初めてだというのにやけに馴れ馴れしい。恐れられ、崇められる事はあっても馴れ馴れしくされた事は無く、正直、どうしたものやら戸惑いを隠せない。
「はあ、どうも。ところで、どなた様でしょうか」
「おうおう、名乗るのを忘れてたな。オレの名はバコタ。盗賊バコタといやぁアリアハンでその名を知らぬ者はないって言う大盗賊だ」
「アリアハン……ねぇ」
アリアハンなどという国は聞いた事が無い、とは言わぬが花なので黙っておく事にする。
「アンタは?」
「私ですか、私の名はハーゴン」
「ふうん、ハーゴンてぇのか。そういや看守がアンタの事ウワサしてたな。てこたぁよっぽどヒドイことしてココに来たんだろ。何したんだい? 泥棒? 人さらい? いや、アンタ賢そうだから違うな……サギ師かい?」
「いや」
「へえ」バコタはいやにしつこく聞いて来る。「じゃあ何をやらかしたんだい?」
言いたくはなかったが、無視しているとさらにしつこく聞かれそうなので仕方無しに答える。
「私は…………世界を……滅ぼそうとしたのです」
「ふぇえ。頭良さそうな奴のやる事はやっぱり違うねぇ。たいそうなこった」
バコタはそういうと、私が食べ残した萎びたキャベツの芯を口の中に放り込んで旨そうに噛み砕いた。この世界に来て、酷い食事も罰と思って口にしてきたが、これだけはどうしても口が受けつけない。
「アンタに比べりゃカンダタ一味なんて可愛いもんだねえ。こっちじゃズイブンエラそうな顔してやがるけどさ。ま、此処じゃシャバで何やったかはあんまり関係ねえけどな。そうそう、アンタ、看守だけじゃなくてカンダタの野郎にも目ぇ付けられてるから注意した方がいいぜ、じゃ!」
バコタが去った後で、私はまた一つため息をついた。竜王の次はカンダタ一味か。
食事が終わった後、囚人達は思い思いに食器を片付け、担当の者が食堂の掃除を始めた。食事の後の時間は、囚人達にとっては眠りの時と並んで数少ない憩いの時間だ。
私はこの貴重な時間を、瞑想するか本を読む時間に充てている。場所柄そうそう本が入手できる訳ではないが、キューリさんと言う看守が私に優しくしてくれるので、たまに彼女の本を貸してもらう事にしている。彼女は気難しいがなかなか知的な女性で、こんな所では到底手に入りそうにない研究書や聖典を沢山此処に持ち込んでいるのだ。
読んでいる本が影で暗くなった。顔を上げる。
「よ!」
うわ、来たな。ウワサのカンダタ一味だ。
「お前が模範囚のハーゴンだってな」
「世界を滅ぼそうとしたんだって? その割には意外と大人しそうな奴じゃねーか。あぁん?」
「バカ、そういう奴がキレると後が怖いんだよ!」カンダタ親分がすかさず子分その1をどつく。目を付けられている、とバコタに言われたのを思い出して、少しだけ拳に力が入る。
「いや何、兄さんよ、取って食おうってんじゃないぜ」カンダタ一家の総帥、カンダタ親分が私の肩を軽くつかんだ。マスクの下から覗く口元が奇妙な形に歪み、肩に乗せられた手からは、血の通う生ぬるい感触が威圧感と共に伝わって来る。魔物や高位の悪魔神官達を従えてきた私には、別段この程度の気は恐ろしくも何とも無かった。が、此処で騒ぎを起こしてまた色々と面倒な事になるのだけが厭わしく思えて、少しばかり眉根を寄せる。
「オレ達のちょっとした忠告って奴よ」
「は、はあ…………」
「看守に媚びて、刑期を短くしてもらおったってムダだぜ」
カンダタの意外な言葉に、私はつい目を真ん丸くしてしまった。心臓の鼓動がいつもの調子に戻り、緊張が切れた糸のように行き場を無くしてだらんと緩んだ。
「そんな事は思っていません」
カンダタ親分とその一味は顔を見合わせた。彼らには解らないらしい。
「じゃあ何かい? この汚い世界で、せめてもうちょっといい生活がしたいのかい? もうちょっとましな飯が食いたいとか、少しだけ楽な労働がしたいとかよ」
「いいえ」やはり彼らの理解はこの程度なのだろう。彼らに、罪を償うという発想は無いのだ。「そんな事が無駄である事は解っています。現に却って私は看守の方々に疎まれてますから」
「アッハッハァ! あの事件だな! あいつはおかしかったぜ兄さんよ! あんたも災難だな!」カンダタが笑ったのを受けて、子分どもがつられて一緒に笑った。カンダタが酷く私の肩を打ったので、私はよろけて椅子から転がり落ちそうになった。
「アンタ、あのワガママ息子に気に入られちまったたぁ可愛そうにナァ! これじゃあ看守に嫌われるわけだァ! はっはははは! 竜王のダンナもあんな所で日がな一日寝ッ転がって退屈なのさ。ま、天災と思って諦めな。どうせそのうち飽きるだろうしよ。これから長いんだ、あんまり最初から力みすぎんなよ新入りさん! お互いせいぜい仲良くしようぜ。じゃあな、あばよ」
言うだけいって出て行くカンダタ一家の背中を見ながら、これから続いて行く長い長い償いの日々の事を思って、私は手元の分厚い本を閉じた。
* * *
キューリが残飯の後片付けを終えて去った後、今日はゆっくり寝る事にした。しゃべり過ぎて疲れた訳でもないが、腹が減って仕方がない。世界樹の雫は三日前に飲み干してしまってもうない。寝転がると、牢屋の埃とキャベツの据えた臭いが鼻腔を僅かにくすぐる。私は世界樹に頭をもたせかけ、目を閉じた。
世界樹の内側から水の流れる音が聞こえてくる。この独房は水脈に近い為、横たわると水脈の流れる音が自然と耳に入る。この水音に耳を傾けていると、どんなに腹が減っていても不思議と心地好い眠りに誘われる。
だが、今日に限ってちっとも眠りは誘いに来ない。
水流がぎゅるぎゅると不協和音を奏でている。今までこんな事はなかった筈だ。布団代わりに下に敷いたござや藁を取り払い、世界樹に耳を押し付ける。此処の食事を初めて口にした金持ちのボンボンが腹を下した時のような、そんな音。
出たかな、と思った瞬間、水圧によって体が持ち上がった。水流はこの身を天井に叩き付けると、壁に向かって逆流し、柵の間から外へと溢れ出て行った。お陰でしこたま頭を打ち付ける。水流に弾き飛ばされたおかげで何とか水の柱から脱出したが、頭がくらくらする。
一息ついて、柵の外を見下ろす。と、シロナガスクジラの潮の如き水流が世界樹のあちこちから吹き出しているではないか。キューリの危惧は正しかった様だ。
「お、そうだ」
此処3日ほど何も口にしていなかったのを思いだし、水脈から溢れ出る水を飲んだ。雫ほどではないが、量が違う分腹の足しには充分だ。私はほぼ百年ぶりの腹を満たす行為に夢中になっていた。
が、ふと我に返ると、独房から噴き出した水流が、腐った世界樹の表皮を削り落としている。
水圧に削れて行く独房の壁を見て、我が身に雷の落ちたような、甘美な痺れが襲った。
千載一遇のチャンス!
終わりなき日常などクソ食らえだ!
溢れる感慨が身体を満たし、圧されて百年以上ぶりのげっぷが飛び出した。
ともかくも此処から出なくてはなるまいと、鉄格子に足をかけ、水流に手伝ってもらいながら力をかける。鉄格子は思った以上に脆く、からんからん言いながら水流と共に落ちて行った。身体を何とかねじ込めるくらいの隙間が出来たので、息を深く吸い込むと鉄格子の一本を捕まえて身体を隙間に押し入れる。水流が手助けしてくれたおかげで、思ったより楽にすり抜ける事が出来た。水圧に弾き出されて下に落ちない様、体を開いて巧く圧力を逃がしてやる。
ずぶ濡れになった身体を震わせると、辺りに雫が飛び散る。その先に、キューリがいた。
「おおどうしたキューリ。ずぶ濡れになっておるではないか」
「貴様が雫を飛ばしたからではないかー! このうつけ者がーッ!」
何ヶ月かぶりに頭に湯気を立てるキューリと、百年ぶりの開放と、久しぶりの満腹のお陰で、久しぶりに愉快な気分になれて、私は噴き出した。こんな気分になったのは、生まれて初めてだった。「ぷっ、くくくく貴様にうつけ者と呼ばれる程阿呆ではないぞ。ところでキューリ、何の用だ?」
「何の用だではないわ!」キューリは手錠に手を伸ばした。「とうとう世界樹がだめになってしまった。囚人を避難させる為に来たのじゃ。行くぞよ」が、キューリの手は空を切った。
「いやいや、それには及ばんよ」錠に手を伸ばしたキューリの手を、足が宙に浮くまでつかみ上げる。キューリは地に足付けようと、必死でじたばたもがいた。「それくらいの事は自分で出来るのでな」
「は、放さんかこの下郎があ! 馬鹿者ーッ! 妾を手篭めにする気かーっ」
「ったく、すぐ放してやるようるさい女だなお前は。誰も貴様なんぞ取って食いやしない」私はキューリの腰から素早く剣を抜き取ると、ぱっとキューリの手を放した。突然手を放され、キューリはバランスを失って転がり落ちる。起き上がろうとするキューリの喉元に、いつぞやに家宝と見せびらかされた剣を突きつける。
「ううう、おのれおのれえぇ! その剣は、我ら一族に伝わる至宝なるぞ!」
「悪いな、キューリ。至宝序でにそのベルトも借りるぞ」
剣を突き付けられ動けないキューリの脇から素早くベルトを外して引っ張ると、キューリはその勢いで、悪代官に帯を外される村娘の様にくるくる回ってすっ転んだ。キューリは私を親の敵の如くねめつけると、すぐに片膝付いて起き上がって来た。
「あーれー! って言わんのか。つまらんなあ」
「うぬぬぬぬ……よくもこのワルキューリ=ド=ブリュ……」
「さらに悪いな、お前の名乗りに付き合えなくて」
言うが早いか、私はキューリを宙に向けて思いっきり突き飛ばした。キューリの体は宙に浮き、奴はそのまま、数々の恨み言を列ねながら、世界樹から真っ逆さまに落ちていった。
「心配すんな、その下にはヤドリギが生えてるからなー、聞こえてるかー、おーい。…………まあ、あ奴は殺しても死ぬタマではなかろうがな」
遥か地上を眺むれば、下は世界樹のあちこちから吹き出す水のおかげで大混乱に陥っていた。行く先を失った愚か者共が彷徨き、おたおたと狼狽え、呆然と佇む様はなかなかの壮観であった。が、何時までもこんな光景を眺めてせせら笑っているつもりはない。こんな物は、腐った世界の死んだ眼こそ相応しい。我々生者の瞳に映すべき世界は、もっと他にある筈だ。
待っておれ。今、私が貴様を、その生命ある瞳に相応しい世界へと誘おう。
そして、この世界を、我らの色に塗り変えてしまおうぞ!
キューリの返事がなかったのを確認し、私は宙を見据えた。
「第1ラウンド開始だな」
* * *
その日。
いつもの様に、私は他の囚人達と共に巨大な歯車を回し続けていた。
異変に気付いたのは昼の休憩が済んでからすぐの事であった。囚人の一人が何やら世界樹の様子がおかしいと看守に報告しに来たのだが、看守は例によってこの報告を無視した。が、やがて、どうっという激しい音がして世界樹から滝の如き水流が幾筋も迸るのを見て、天空人達は慌てて世界樹の方に駆けて行った。
労働は中断してしまった。
最低限の看守しか仕事場に残らなかったので、囚人達が、突然仕事をしなくなってしまったのだ。
そんな訳で、看守達は初めの内こそ無理矢理仕事をさせようと彼等を鞭打ったのだが、言うことを聞かぬ囚人達に看守も匙を投げ、囚人達を牢に帰してしまう事に決めた。
囚人達がぞろぞろと自分の牢に戻り始めたその時だった。
世界樹のど真ん中から特別どでかい水流が噴き出した。
水はちょうど作業場の近くに降り注ぎ、辺りを水浸しにしてなおも溢れ出した。降り注ぐ、と言ったが、その様子と来たら、寧ろ叩き付ける、と言った言葉が相応しいように思われる程で、囚人達は水を避けようと慌てて建物の中に雪崩れ込み、辺りを泥だらけにした。こうなるともう看守も手が付けられない。
その時、どこかで誰かが叫んだ。
「暴れろ! 今がチャンスだ、暴れてやれよ! どうした、連中に去勢されちまったのか? どうせ出られないのだ、メチャクチャにしてやれ!」
囚人達の中で、何かが弾けたようだった。
囚人達は、看守が必死に止めるのも空しく、外に向かって逆流した。
世界樹の放水騒ぎで手薄になっていた為に、一旦暴徒と化した囚人達はもはや看守達の手には負えなくなっていた。囚人達は騒ぎ、暴れだし、設備を壊し、詰所を占拠し、見せ掛けの秩序をぶち壊しにした。
そんな中で、私は、どの潮流にも乗れずに、人の波に押し潰され、渦の狭間に弾き出されてただうろうろしているだけという案配であった。こんな様子では、例え自分の身に何かあったとしても、身を守るどころかただ情け無く「たすけてくれえ」とでも叫ぶしかないだろう。叫んだところで、誰も私なんかに注意を払いっこないだろうが。
背後から、不意に首根っこを引っつかまれた。
助けてのたの一言を言う前に、誰かが既に口を塞いでいた。私を通路に引っぱり込んだのはこの人物に間違いない。私はふと、以前倉庫の裏手に引きずり込まれて看守達に袋叩きにされたのを思い出した。
その人物がゆっくりと口を塞いでいた手を外したので、私は相手の正体を見定めようと振り返った。
「よ、久しぶり。以前は悪い事をしてしまったな」
「え…………えええっ?!」
特別製独房に放り込まれている筈の竜王が、そこにいた。
「まだ自己紹介しておらぬな。それとも、もう知っておるか?」
「ええ。良く存じ上げておりますとも」
良く知っている。良く知っておりますとも!
100年あまりの昔、勇者ロトより託されアレフガルド王家に伝わりし光の玉を奪い、魔物達を率いて世界を支配しようとした魔竜。邪悪の化身。大魔王。
世界の支配者マスタードラゴンの御曹司にして問題児。
根の国始まって以来の最強の、そして最悪の囚人。
「そうかそうか。いやすっかり有名人だな。どうせ色々他の囚人達から吹き込まれたのだろう? あいつらは、自分達では何もせん癖に、人がへまをするとあげつらってせせら笑うだけしか能の無いクズ共だ。気にするな。……ん? どうした聞いてないのか。…………ははあ、貴様、模範囚だそうだな。連中に相手にされておらんのだな。まあ良い」
「あの…………貴男の方が私について、余程御存じなのでは?」私がこの世界に来た時には既に独房に幽閉されていた為、実はまともに口を聞いた事すらない筈なのに、此処まで己を知られているという事実に私は少なからず驚いていた。いや、バコタの話によれば私は看守達の話の種になっていたそうだから、それも頷ける話ではあるが。
「おお、気分を悪くしたか、すまんな。仮にも信徒を率いて人を導いて来た者に聞く口では無かったか。許せよ」
「その事は、もう言わないで下さい」過去を取り沙汰されるのは仕方ないにせよ、かくの如き評価を受けるのは、今の私には到底我慢ならない事だった。だが、竜王はその意図を計りかねたのか、僅かに首を傾げた。
「何を言うか。やり方はともかくにせよ、貴様の、世界を変えてしまおうという滅びをも怖れぬその覚悟、中々出来たものではない。どう思っておるかは知らぬが、私は貴様を買っておるのだぞ?」
「やめろと言っている!]耳を塞ぎ、私は吐き捨てた。それは、私が捨てねばならぬ過去なのだ!
「何故!」
しばし、私達は睨み合った。
「後悔するくらいなら、最初からやるな!」
「己れの過ちを認められず、エゴの為だけにただ回りを巻き込んで傷付けるだけよりは遥かにましだ」
「過ちなど犯してはおらぬ。私は、己れのした事を恥じた事はない。手段はいただけなかったがな」
「!! 何と……何ですと!」
当然と言えばあまりにも当然の答えだった。彼に己の悪を見つめる真摯さなど望むべくもないのだ。そうでなければ、どうしてこんな無茶苦茶な事が出来るのだ。その有り様と言ったら、全てをぶち壊しにして、混乱と破壊をもたらす台風の目だ。もううんざりだ。どこかに消えてくれ! 私の償いの日々を邪魔をしないでくれ!
だが、天の意思はそれを許してはくれなかった。
「貴様はまだ、己れの為した悪を受け止められるに足る程充分に強くなかっただけだ。そして、貴様になら、新たな悪と、そして善とを産み出すその素質がある」
「買い被り過ぎです」皮肉のつもりだった。
「ものを見る目には自信がある。伊達に長くは生きておらぬ心算だぞ? それとも、我が目を節穴というか?」
「貴男の目は欲望と復讐、憎しみとに曇っていて、真実が見えないのだ」
「はっ、言ってくれるわ。私を盲いているというか。面白い、それでなくては落としがいがないというものだ。だが貴様は誤っている。私が盲いているというのなら、貴様はあきめくらだ! 何が償いだ、阿呆者が。お前がそう信じてやっている事、それにどんな意味があるというのだ? 貴様は変態か?」
余程私が変な顔をしていたのだろう、竜王は訝しげに私の顔を見回した。
「まさか…………まさか、本当に貴様、知らなかったと言うか?」
「どういう……事、ですか?」
「いいか、良く聞け」竜王は、両の腕を、捕まえておかなければ逃げてしまうとでも言わんばかりに強く握り締め、一言一言を、世界の秘密を打ち明ける隠者の様に、真の名を伝える名付け親の様に言い含めた。
「貴様が他の連中と一緒に回し続けているあの機械、あれはな、何処にも繋がっておらんのだ。あの機械は、この世界を作った奴が囚人達をすり減らし、従順で無気力な阿呆共を量産する為に作った拷問機械なんだ」
「嘘だ」私は殆ど驚きの余りに叫んだ。「そんな事があるのか」
「貴様以外の囚人は皆知っている」
「やめろ」
「だから奴らは無気力で、目の前の損得しか考えられぬ阿呆共なんだ」
「やめてくれ!」
「嘘じゃない、目を覚ませ! 目を開けるんだようく見ろ!」引っ張られて行った。私は目を背けた。
「見ないというのか。貴様また同じ過ちを繰り返すというのか!」
そうまで言われて見ない訳には行かなかった。恐る恐る目を開くと、囚人達は自らを縛り付けていた例の巨大歯車を水の浮力に任せて皆で根こそぎひっくり返し、殆ど職人の様に丁寧に、それこそ元が何だったのか解らなくなる程完膚なきまでに、打ち壊していた。
その機械は、どこにも繋がっていなかった。
「此処に来る奴は誰も償いの事なんか考えちゃいない。その意思すらも粉々に打ち砕く石臼だ、あれは」
私はただ呆然とその場に立ち尽くすしかなかった。私は、以前こんな光景を見た事があったような気がした。
「我に忠誠を誓え」
「な、何と!」
「何故貴様に声を掛けたか、まだ解らぬか。貴様の眼はまだ死んでおらぬ。このままこの腐った世界で駄目にしてしまうには惜し過ぎる。世界を滅ぼそうとする程、貴様はまだ、世界を見捨てられぬのであろう。ならば」
竜王は私の手を握り締めた。鼓動が伝わってしまいそうな程動悸が激しく打ち、畏れと恥じらいの余り息が止まりそうになる。こんな感覚に捉われたのは何年ぶりの事だろう。
「世界をこの手で塗り変えてしまおうぞ! そして、我と共に来るが良い、地獄の底までな!」
金色の瞳。その輝きが、私の心を深く、捉えて離そうとしなかった。
私の目を見ていながら、私の目を見ていない。その奥にある私の心を、見透かしてしまっている。それでいながら、私の事など見ていないのではないかとも思わせる。
記憶の隅に埋もれさせていたあの想い、世界への"想い"を。
私は、理性に逆らって無我夢中で首を縦に振っていた。
「よろしい、決定だ」
竜王は私の手をひっつかむと、私の手を繋いでいた手錠の鎖を易々と引きちぎった。
「しかし、この世界からどうやって……」
「あてはある。おぶってやる。落ちるなよ」
竜王は私をおぶって助走を数歩つけると、世界樹の上方に向かって猛然と駆け上がった。幹に剣を杖代わりに次々に突き立て、素晴らしい脚力で駆け登っていく。此処だけの話、あまりの素晴らしさに、背負われながらも彼の筋肉の動き一つ一つに見惚れていたのだ。神の創り給いし生命の美しさよ!
上半身が、がくんとのめり込んだ。
木の中に剣が突き通ってしまったのだと解った途端、剣が突き通った僅かな隙間から、世界樹を傷付けた二人を振り落とすように大量の水が噴き出した。
「どわーっ!」
「やっぱりぃーっ!」
天に唾する罰当たり2人組は、天則に従って真っ逆さまに落ちていった。
私達の身体は、世界樹のあちこちにバウンドし、上手い具合に衝撃を和らげられながら落ちていった。とはいえ、地面に激突した時の衝撃が軽かった訳では決してない。不時着地点にあった子供向けの空気トランポリンの様なものが衝撃を受けとめてくれなければ、おそらく五体満足ではいられなかっただろう。
意識を取り戻すと、真っ暗な中に、互いの輪郭がぼんやりとヒカリゴケの様に浮かび上がった。あたりに粉が舞って、再びゆっくりと積もって行った。
「おお、貴様大丈夫か?」
「ええ……何とか……」
「この鎖がある限り魔法は使えんからな、怪我せぬようにしてくれよ。……ぷっ! はははは!」
「何ですか。いきなり人を指差して」いきなり笑われたので、私は竜王を睨み付けた。
「ははは、見てみろ! 貴様全身ヒカリゴケの様だぞ!」
「そういう貴男こそ」
そう言って私達は大笑いした。そして、黙り込んだ。
「粉?」
「ああ、粉だな」竜王は服に付いた粉を払い落とした。「待て、何の粉だ?」
身体の下で、地面が蠢いた気がした。
「今、地面が動きませんでしたか?」
「地面……この地面、ふかふかするから何だかおかしいとは思っておったのだが。ちょっと待てよ……うっ」
「こ、これは……」
竜王が地面から引っ張りだしてきたのは、潰れたマタンゴの死体だった。と、いう事は、このふかふかした地面は皆マタンゴのかさで、この暗闇でぼんやり発光する謎の粉の正体は…………。
私達はしこたま嘔吐した。といってもどうせまともなものは口にしていないから、必然的に出てくるのはきらきら光るものの交じった胃液だけだ。
「おい、ハーゴン、胞子はちゃんと払い落とせよっ! マタンゴが身体に入ったら胃の中で繁殖して貴様もマタンゴになっちまうんだぞっ」
「何かの見過ぎですっ! そんな訳ないでしょ!」
吐き過ぎて涙目になった目をこすると、ようやく闇に目が馴染んできた。辺りの輪郭がはっきりしてくる。私は恐ろしい事に気付いた。
「あ、あの、あれ、あれあれあれれ……」
「ん? 何だ? ………………う、ま、ま、マ、マタンゴ!」
指差した先にそそり立つはマタンゴで出来た壁。足下にもびっしりとマタンゴがひしめいて、地面をも埋め尽くしている。
私達に反応して、何百、何千のマタンゴ達が一斉に私達を睨み付けた。
私達は、マタンゴの群生地に落ちてきてしまったのだ。
「う、だめ。腰が抜けて立てない」
マタンゴの崖が、僅かに斜めに傾いた気がした。
私が竜王に腕をひっつかまれたのと、マタンゴの壁が崩れたのがほぼ同時だった。
「そこの二人、止まれぇーっ! 止まりなさぁぁーいッ!」
運の悪い事に、マタンゴの大群から逃げ出して来た我々の目の前に天空人達が、貧弱なバリケードを張って立ち塞がっていた。
「止まってられるか、いいなハーゴン、強行突破だ。行くぞっ!」
「止まれーっ! 止まれ、止まれってば! うっ、ぎゃああああ!」
私達がバリケードを無理遣り蹴倒して突入すると、後に残された天空人達はマタンゴの大群に押し潰されて全身蛍光色になっていた。
「うぷっ、ふはは、はーっはっはっはっ! ざまあみやがれ天空人共め! 威張りくさりおって、いい気味だ!」
「フフフ、アハハハハ!」
ザマアミロ、と思っていた訳では必ずしもなかったが、マタンゴ相手に格闘している天空人達の様子が、仏頂面で囚人達を従えるいつもの姿からは想像も付かなくて余りに可笑しかったものだから、竜王につられてつい一緒に笑いだしてしまった。私達はおおいに笑った。此処に来て忘れてしまった分を取り返すように。
「ストップ! ストーップ!」
「何だどうした、今度は貴様か? う、わっ!」
私が止めたので、竜王はつんのめって、真っ逆さまに崖から墜落する寸前で立ち止まった。
「チッ、行き止まりか!」
振り返ると、後から追っ手が迫り来る。前の崖は高さ数百メートルはあろうかという断崖絶壁、落ちれば即死は免れまい。
「もう、諦めるしかないのでしょうか」
「馬鹿言え、これしきの事でへこたれてどうするか! しっかり捕まれよ!」
脇から抱え上げられた時、私は此処で見捨てられるのかと本気で覚悟を決めていた。と、突如二人の身体を暗い影が覆い尽くし、羽音と共にこの身が宙に舞い上がった。
「翼……」
「空など飛ぶのは何年ぶりかな。うおっとと、慣れるまでバランス悪いかもしれんが我慢しろ」
雲の切れ目より眺むれば、地上の喧騒も、パノラマの如く鏤められる泡沫の祭りの後に過ぎない。世界樹のあちこちから吹き出す水流が、太陽に煌めいて虹を描いていた。
太陽の光に触れるなど、既に諦めていた事なのに。
罪人の私には、ただひたすら贈り与えるだけの太陽の豊かさは、余りに大き過ぎた。恩恵を受けるに値しない程に、私は弱い。
「強くなれば良いのだ」
想いを見透かす様な呟きだった。私は、僅かに首を上げた。
「強く、なれるでしょうか」
「なれるさ」竜王は頷いた。「そう私の直感が働いたのだ。だから大船に乗った気でいるがいい」
「泥の大船ですね」
「かもしれんな」竜王は愉快そうに言った。「だが良いではないか。泥舟でも火で固めれば水に浮くだろう」